Works 192号 特集 2026年-2035年 次の10年 雇用の未来を描く
国際競争力で低迷する日本 存在感取り戻すために道州制の導入など抜本的な改革を
私が北東アジア代表を務めるスイスのビジネススクールIMDでは、毎年「世界競争力ランキング」を発表しています。これは「企業が持続的な価値創造を行う環境」を各国・地域がどの程度提供できているかを測定する指標として、世界で高く評価されています。
日本の競争力ランキング 出所:『IMD World Competitiveness Yearbook 2025 Competitiveness profile JAPAN』をもとに編集部作成
出所:『IMD World Competitiveness Yearbook 2025 Competitiveness profile JAPAN』をもとに編集部作成
このランキングが始まった1989年から数年間、日本の総合順位は1位でしたが、2025年版では、世界69カ国・地域中で35位。前年の38位から若干改善したものの、この30年間、低落の一途をたどっています。
ランキングは、経済・ビジネス・政府・インフラという4つのカテゴリーで構成されます。このうちインフラは例年20位前後で、とりわけ「科学インフラ」「健康と環境」などの指標では世界トップ10に入っています。「国内経済」「国際貿易」「雇用」などを指標とする経済パフォーマンスも、コロナ禍で一時的な落ち込みはあったものの、やはり20位前後にランクインしています。
日本の競争力低下の大きな要因となっているのは、この20年間、40位前後で低迷している政府の効率性(指標は「公財政」「税制」「企業関連法」など)と、2014年以降大きく下降し、現在は50位前後で推移するビジネスの効率性です。ビジネスの効率性の指標の1つが「労働市場」です。「労働市場」は49位と、「経営慣行」の65位、「生産性と効率性」の56位などと並び、ビジネスの効率性のランクを押し下げる要因になっているといえそうです。
また、データ全体を横断して見たとき、日本のジェンダー平等に関する課題も浮かび上がってきます。「女性の経営への参画(上級管理職、中間管理職に占める女性割合)」は60位、「取締役会における女性(取締役に占める女性割合)」は40位、「女性の労働力(労働人口全体のなかでの女性比率)」は40位、「議会での女性(議席数に占める女性の割合)」は65位、「可処分所得(女性/男性比率)」は56位と、ランクが著しく低い傾向にあります。対して、「学位を持つ女性(25~65歳の学位保有者のうちの女性割合)」は6位です。女性の社会における地位が低いのは、教育を受けているにもかかわらず、企業組織での昇進、昇給、活躍の機会が限られていることにありそうです。
道州単位での競争力向上策を 日本も希求すべき
興味深いのは、ランキング上位国の変遷です。以前はアメリカや日本など、いわゆる大国が上位にランクインする傾向がありましたが、近年ではスイスやシンガポールなど、人口や面積の比較的小さな国が目立ちます。
かつては人口(=労働力)と競争力には強い相関性がありましたが、社会の複雑性や予測不能性が増すなかで、ルールが根本的に変わりつつあるのではないか。国としての選択と集中が勝敗を分けるようになれば、人口数百万人程度の国が持つ機敏性こそが競争優位性につながるという仮説が成り立ちます。
たとえばエストニアのデジタル国家戦略は有名ですが、電子政府の実現や紙の公文書廃止など、思い切った施策に踏み切れたのは、約137万人という人口規模も一因だったのではないでしょうか。
一方、日本は少子化が進行しているとはいえ、いまだ人口1億2000万人を超える大国で、産業構造も巨大で複雑です。このため産業や教育において、一点集中型の政策を取りづらい面があります。
もちろん日本でも福岡市のように、国家戦略特区「グローバル創業・雇用創出特区」として、官民協働型のスタートアップ支援などの産業支援、アジアのハブとなる経済活動拠点の形成に取り組むなど先進的な自治体もあります。ただ国家間の競争においては、市町村や都道府県単位での取り組みだけでは限界があるのではないでしょうか。
スイスでは、連邦政府がイノベーション支援プログラムを立ち上げ、ライフサイエンスやナノテクノロジーなどのクラスター強化を図ることで、国内外から優秀な人材や投資マネーを集めています。スイス(人口約900万人、面積4.1万平方キロメートル)一国は、九州(人口約1300万人、面積約4.2万平方キロメートル)と同規模です。今後国際競争力を高めるうえでは、たとえば九州全体が広域連携し、特定領域におけるイノベーション創出に取り組むといった施策も必要でしょう。これまでのように都道府県単位で行政を区切り、中央官庁が監督する枠組みだけでなく、道州制の導入なども選択肢の1つになるかもしれません。
Text=渡辺裕子 Photo=曽川拓哉
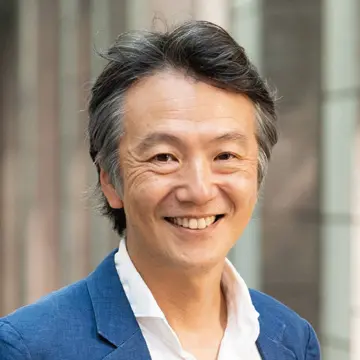
高津尚志氏
IMD 北東アジア代表。
日本興業銀行、ボストン コンサルティング グループ、リクルートを経て現職。近著に『世界の経営幹部はなぜ日本に感化されるのか―伝統文化の叡智に学ぶビジネスの未来』(日本経済新聞出版)。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ