Works 192号 特集 2026年-2035年 次の10年 雇用の未来を描く
AI時代、人々の働く意味や役割、幸福感はどう変わっていくのか

個人に目を向けたとき、仕事や働く環境の変化は何をもたらすのか。
時代の転換点を迎え、古屋は、「幸せの追求を問い直す必要がある」と投げかける。
「技術が進化してもブルシット・ジョブは増え続け、仕事と生活の両立を迫られ、人々はますます忙しくなっています。世界的に見れば、娯楽を提供する企業が莫大な利益を上げており、あらゆる企業が人々の時間を奪い合っている状況です。これからは、むしろ時間の余裕をつくり、自由に使える可処分時間を増やすことが、幸福感や生活満足度につながるでしょう」(古屋)
汎用AIが普及して多くの仕事を代替するようになれば、人間は労働から解放され、創造的な活動に専念できるといわれてきた。しかし現実はそうなっていない。人々はブルシット・ジョブに追われている。
一方で大量のデータを学習したAIを使えば、たとえば誰もが簡単に「○○風イラスト」を生成できる時代になり、「プロフェッショナル」の定義は曖昧になりつつある。そのなかで人間は何をすべきか、朱氏はこう語る。
「著作権料を払うことなく、学習データとして利用されるということは、クリエイターが努力して培ってきたスキルが、AIによって簒奪されているのと同じことです。アメリカの動きを見ても、この流れは加速していきそうです。一方で、AIが19世紀の絵画をすべて学習しても、印象派やキュビズムなどのまったく新しい潮流を生み出すことはできないだろうといわれます。ゼロから新しいものを生み出す創造性は、やはり人間しか持たないのかもしれません。重要なのは、AIをうまく使えるかどうか。これからはAIにどういう指示を出すか、どういうデータを学習させるかが重要になります。そのときに求められるのが倫理(エシックス)だと思います」(朱氏)
直感的なヒヤリハットが システムエラーを食い止める
倫理というと、日本では「やったほうがよいこと」という努力目標のように理解されがちだが、西洋文化圏では「何をしないか、何をやってはならないか」を定めるものと捉えられている。
たとえば欧米では、顔認証技術の開発を抑制する傾向にある。過去のデータに人種差別的な偏りが含まれ、それが差別を再生産してしまう恐れがあるからだ。
AIは学習するデータ(インプット)と回答(アウトプット)の関係がブラックボックス化していることが指摘されており、運用にあたっては、その過程で何が起きているのかを推測し、問題がないか吟味する必要がある。AIが出した答えを解釈するのは、人間の役割だ。「何でもできるからやろう」ではなく、「できるが本当にやってよいのか」という葛藤が生じたとき、自らの理念や規範に照らして自ら判断しなければならない。
朱氏は「倫理を考えることは難しい話ではない」と言う。誰でも仕事をしていると、「これは少し気持ち悪い」「これを怖いと思う人がいるかもしれない」といった違和感を持つことはあるだろう。多くの人が持つ、ごく当たり前の直感こそが重要ということだ。
システムエラーは一度起きると大きな事故につながりかねず、その前段階で小さな違和感に気づけるかどうかが重要になる。AIの高速な処理のなかに、あえて非効率な人間を置くことで、ヒヤリハットを察知するゲートキーパーになり得るのだ。
生身の人間から生まれる 多様な言葉を守っていく
人間が機械のように振る舞うのではなく、むしろ自分の直感や身体的な感覚をどれだけ表現できるかが問われる時代になると、朱氏は指摘する。直感をどう鍛え、言葉にしていくかが、ビジネス価値を生み出す源泉になり得るという。
「これからの人間の役割とは、ナラティブ(物語)を紡ぐことではないでしょうか。自分たちが何を目指し、何をしていくのか、そのなかで仕事をどう意味付けるかを言語化し続けることです。私は、そのツールとして哲学の言葉が役に立つと考えています」(朱氏)
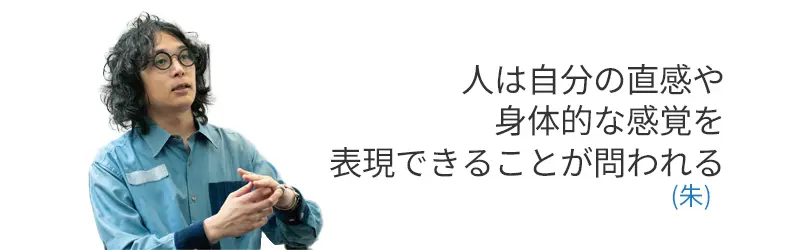
哲学者のリチャード・ローティは、会話を重視し、「人類の会話を守ることが哲学の使命だ」と述べている。ローティを研究する朱氏は、ここでいう「会話(conversation)」とは、意味を伝達するためのものではなく、必ずしも言葉を交わさなくても、身体を持つ他者とその場を共有することだと考えている。
SNSで誰とでもつながることができ、AIが悩みの相談に乗ってくれる時代になった一方で、ローティが重視した親密な「会話」は失われつつある。インターネット上の話題が広く共有され、皆が同じようなネットスラングを使うようになり、言葉の多様性が奪われている。
「私たちは言葉なしに考えることはできません。言葉が貧しくなれば、発想も貧しくなってしまうでしょう。インターネットで流行する強く侵略的な言葉から、繊細で弱い在来種の言葉をいかに守っていくか。自分の人生に裏打ちされた言葉をどう紡いでいくか。これは、生身の人間が取り組むべき重要な課題だと考えています」(朱氏)
 コロナ禍では人々の動きが一斉に止まり、一気に親密な「会話」が失われた。
コロナ禍では人々の動きが一斉に止まり、一気に親密な「会話」が失われた。
Photo=今村拓馬
Text=瀬戸友子 Photo= 今村拓馬(井上氏、古屋、矢田氏)、刑部友康(山田氏)、MIKIKO(朱氏)
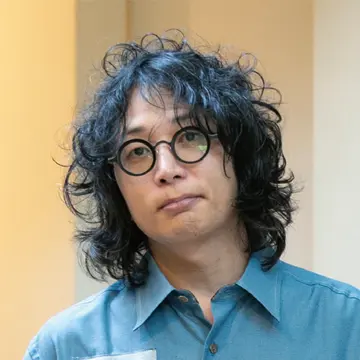
朱 喜哲氏
大阪大学 社会技術共創研究センター招へい准教授 兼大学院文学研究科招へい研究員
大阪大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。専門はプラグマティズム言語哲学とその思想史。研究活動と並行して、企業において各種データを活用したビジネス開発に従事。ビジネスと哲学・倫理学・社会科学分野の架橋や共同研究を推進。

古屋 星斗
2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。
2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ