Works 192号 特集 2026年-2035年 次の10年 雇用の未来を描く
不足するエッセンシャルワーカー。リスキリングと労働移動でいかに増やせるか

私たちの社会に、ホワイトカラーの余剰とエッセンシャルワーカーの不足という未来が待ち受けているのだとしたら、いかに現場の仕事に携わる人を増やせるかが重要になる。しかし、賃金水準の高いホワイトカラーからエッセンシャル領域への労働移動を促すことは現実的に可能なのか。
古屋は、ホワイトカラーとエッセンシャルワーカーの賃金差について、次のような見解を示している。
「ホワイトカラーの賃金が高いのは技能習熟が必要だからなどといわれますが、私は単に情報の非対称性の問題だと思っています。つまり、研究者やコンサルタントといった仕事は、どんな仕事なのか端からはわかりにくい。だから何となく『すごそう』だと思われがちです。一方、現場の仕事は、農業でも介護でも点検でも、仕事の様子が見えるためわかったつもりになってしまう。その勘違いが、賃金差の根底にあるのでは。ところが実際にそれらの仕事を体験すると、技術も専門知識も必要ですし、非常に頭を使う難しい仕事であることがわかります」(古屋)
エッセンシャル領域での 高度人材を育成
山田氏は、この複雑な仕事を高度に遂行する「現場の力」こそ日本の強みだと指摘する。
「海外では考えるのはホワイトカラー、実行するのはブルーカラーという役割分担になっていましたが、日本では現場が自ら考え、改善活動や品質管理に取り組んできました。いわばブルーカラーがホワイトカラー化することによって、日々変化する現場に対応し、高い生産性を実現して世界と戦ってきたのです。エッセンシャルワーカー不足という課題解決を図るにも、現場労働にAIやロボットを導入して自動化・省力化を図りつつ、日本の強みである現場の力を活かす方向で考えていくべきでしょう。私は『アドバンスト・エッセンシャルワーカー』という新しい役割を確立する必要があると考えています」(山田氏)
アドバンスト・エッセンシャルワーカーは、人手不足の現場を裏から支える存在である。たとえば、多くの手作業が残っている介護の現場でも、ロボットやデジタル技術を導入して生産性を大幅に向上させた事例が出てきている。このように介護の現場に入って既存の業務のやり方を改善したり、新しい技術を取り入れて顧客のニーズに応えるサービスを実現したりと、現場に根ざして介護のあり方を再設計していくのがアドバンスト・エッセンシャルワーカーの仕事だ。これは一度で終わるものではなく、環境変化や技術革新を踏まえて、現場は絶えず改善を続ける必要がある。アドバンスト・エッセンシャルワーカーは常に作業が円滑に進むようサポートしていく高度な役割を担い、賃金水準も高い。
「給料は需給だけで決まるわけではなく、その仕事に対する社会的な価値観も反映されます。賃金を上げるには、アドバンスト・エッセンシャルワーカーが『意義のある仕事』『かっこいい仕事』であるという価値観を社会全体で共有することが重要です。そうしたメッセージを積極的に打ち出し、議論に乗せていく社会運動が必要だと思います」(山田氏)
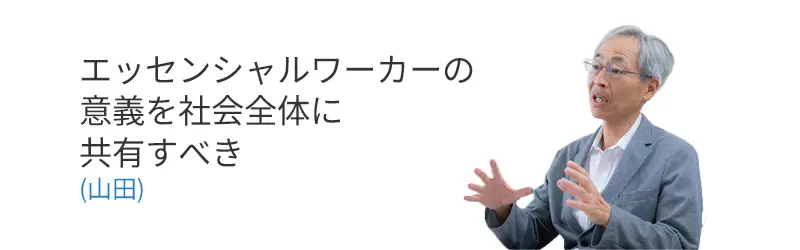
エッセンシャル領域の仕事でも、テーマパークのキャストや「カリスマ清掃員」など、仕事をクリエイティブに捉え、プロフェッショナルとしての誇りを持って取り組んでいる例はいくつもある。働き手が自らの仕事を再定義することで、モチベーションを高め、パフォーマンス向上につなげるジョブ・クラフティングの好例としてもよく知られている。
学びの楽しさを教え 学び続ける仕組みを整備する
井上氏も、主体的に学ぶことの楽しさを広く教えていくべきだという。
「日本人は勉強が嫌いなんです。国際調査でも、学力は世界トップクラスなのに、勉強は嫌いだと答える子どもが多い。学生たちを見ても、勉強を何かの修行としか思っていないのではないかと感じることがあります。勉強して大学に行ってホワイトカラーの仕事に就いても、これからはAIに仕事を奪われるので、ブルーカラーになりましょうと言われたら、もはや勉強もしない、大学にも行かなくていいとなってしまうのではないか。それは、近代化の否定にほかなりません。技術革新が世の中を変えていくスピードはますます速くなっており、どんな仕事に就いても、ずっと学び続けていくことが必要です。また、自分の興味・関心に基づく学びは楽しく、人生を豊かにしてくれます。子どもたちには学ぶことの楽しさを教えていかなくては、二重三重の意味でこれからの時代を乗り切れないと思います」(井上氏)
人々の意識を変えると同時に、制度的支援も不可欠だ。ドイツのマイスターのような資格制度を整備し、それぞれの職業の価値を担保するとともに、政府、使用者団体、労働組合が密に連携し、個々のスキルアップや学び直しの仕組みを確立する必要がある。
また、賃金を上げる原資として、山田氏は「ファンドを活用する」というアイデアを挙げている。
「ヨーロッパでは一定の要件を満たす大規模な農家には、不安定な農産物価格に左右されないよう、価格調整ではなく所得補償で直接支払いが行われています。エッセンシャルワークはまさに社会に不可欠なものですから、価格を上げるのが難しい場合には、公的ファンドをつくって賃金に上乗せするのはどうでしょうか。財源は税金以外にも篤志家からの寄付を募ったり、法人税減免などのインセンティブを設けて、大幅に利益を伸ばしている大手企業からの拠出を促したりするのもよいでしょう。方法はいろいろと考えられるはずです」(山田氏)
Text=瀬戸友子 Photo= 今村拓馬(井上氏、古屋、矢田氏)、刑部友康(山田氏)、MIKIKO(朱氏)

山田 久氏
法政大学経営大学院(イノベーション・マネジメント研究科)教授 兼日本総合研究所客員研究員
京都大学経済学部卒業後、住友銀行(現三井住友銀行)入行。1993年4月より日本総合研究所に出向。調査部長/チーフエコノミスト、理事、副理事長を経て、2023年4月から現職。2015年京都大学博士(経済学)。

井上智洋氏
駒澤大学経済学部 准教授
慶應義塾大学環境情報学部卒業。2011年に早稲田大学大学院経済学研究科で博士号を取得。早稲田大学政治経済学部助教、駒澤大学経済学部講師を経て、2017年より現職。専門はマクロ経済学。

古屋 星斗
2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。
2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ