Works 192号 特集 2026年-2035年 次の10年 雇用の未来を描く
汎用AIとロボットは登場するのか。そのとき、仕事は、組織は。可能性と課題に迫る

深刻な労働力不足への対策として、真っ先に考えるべきはテクノロジーの活用だろう。しかし歴史を振り返っても、大きな技術革新は労働のあり方を根本から変えてしまう。近年、急速に普及している生成AIも、さらなる進化に伴い、技術的失業をもたらすともいわれている。
井上氏は、人間のようにさまざまなタスクを自律的に実行できる「汎用AI」の実現は間近に迫っていると指摘する。
「現在の生成AIが汎用AIの原型のようなものと考えられ、一説には2027年頃には本格的な汎用AIが登場するといわれています。それが急速に進化して『人工超知能』と呼ばれるようなものに発展していくという説が、特にアメリカで有力視されています。そうなればホワイトカラーの仕事のかなりの部分を、AIが担うようになるでしょう」(井上氏)
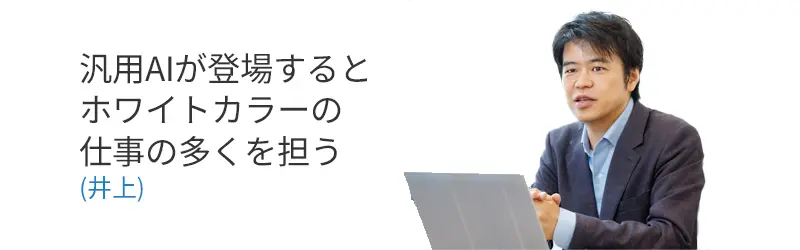
既にIT業界では、エンジニアの育成に影響が出始めている。ここ1年ほどで、AIコーディングエージェントと呼ばれるプログラミングを実行するソフトウェアが爆発的に進化し、ユーザーの指示通りにコードを生成できるようになった。現状ではまだ人間がプロトタイプをつくる必要があるが、多くの部分で自律的にタスクを実行できるようになっている。
「ある企業では、エンジニアの新人研修において、前半では従来通りプログラミングの基礎を教え込み、後半では徹底的にコーディングエージェント(プログラムをつくるAI)を使いこなすよう指導しています。自分でコーディングするよりもAIを多く活用するほうを、高く評価しているそうです。エンジニアの世界では、実は中途採用が減っているそうです。経験豊富なエンジニアは、生成AIを使わずに自分でコーディングしがちなのですが、遠くない将来、それでは太刀打ちできなくなると考えているからです。熟練のエンジニアがAIを使いこなす新人に負けてしまうようになれば、企業は新卒を採用してAIネイティブのエンジニアを育て、AIになじめないベテランは職を失うことになるかもしれません」(井上氏)
現場労働を担う汎用ロボットは 2030年頃に登場
一方、建設現場や工場労働、介護サービスなど、より人手に頼っている現場の仕事では、汎用AIよりも汎用ロボットの登場が期待されている。先行するAIに対して、ロボットの進化にはもう少し時間がかかると井上氏は言う。
農業では、自動運転トラクターやドローンによる自動農薬散布、ロボット除草機など特化型のロボットが既に登場しているが、まだ汎用性は低く、価格も高価なものが多い。技術的には、テスラの人型ロボット「オプティマス」など、汎用ロボットの原型になりそうなものは生まれてきている。井上氏は、「2030年頃には汎用ロボットと呼べるものが登場して、2030年代前半には人とロボットのコストが逆転していき、現場の仕事に汎用ロボットが漸次導入されていく」と予想する。
ただし技術的に可能になっても、実際に広く普及するまでには、さらに10年から20年かかると見られている。ネックとなるのは専門家の不在だ。現場からは、「相談できる人がいない」という声がよく聞かれる。
建設現場では、大手ゼネコンが主導して自動化や機械化が進められているが、特に地方で農業を営む個人事業主などは、何から手を付けていいのかわからず、専門家によるサポートを求める声が少なくない。汎用ロボットの普及には、技術的な知識を持ち、業務の自動化・機械化を進めていけるプロフェッショナルが、各産業の現場に入って具体的なアドバイスをしていくことも必要だろう。
労働力不足の解消にAIやロボットの活用は欠かせないが、それが普及した未来には新たな課題も生じる。多くの人が仕事を失い、賃金の低い仕事に移らざるを得なくなり、収入が不安定になることが予想される。井上氏は格差や貧困の解消のために、社会保障制度を見直し、生活に必要な最低限のお金をすべての人に給付する「ユニバーサルベーシックインカム」の導入を提言している。
権利保護やAI依存など 新たなリスクも生まれる
大阪大学の朱喜哲氏は、「公共の担い手が、国家から企業に変わりつつある」ことに注意を喚起する。現代では個人の日常の行動がデータ化され、個人情報を含む膨大なデータをプラットフォーマーが握っている。国家よりもはるかに大きな規模で、はるかに頻繁に一人ひとりの生活者のデータを取得している民間の企業が、市民のプライバシーを保護し、権利を守る主体になりつつある。このような時代に、市民の権利をいかに守っていくのかは新たな課題となりつつある。
また、AIの能力が高まるほど、人間がAIに依存するリスクも無視できない。
「学生に聞くと、当たり前のようにChatGPTに相談をしています。親や親友よりも、AIのほうが安心して話せると感じるようです。看護や介護の現場でも、新しいケアの担い手としてAIが活用できると期待されています。しかし、家族にも言えないような話を民間企業に明け渡してしまってよいのか、という問題があります。さらにいえば、AIへの過度な依存は、逆に人間の孤立を深めてしまうかもしれません。他人に頼る能力を奪い、複数の依存先をつくって自律する道を奪うことにもなりかねない。そうしたリスクにも目を向ける必要があるでしょう」(朱氏)
Text=瀬戸友子 Photo= 今村拓馬(井上氏、古屋、矢田氏)、刑部友康(山田氏)、MIKIKO(朱氏)

井上智洋氏
駒澤大学経済学部 准教授
慶應義塾大学環境情報学部卒業。2011年に早稲田大学大学院経済学研究科で博士号を取得。早稲田大学政治経済学部助教、駒澤大学経済学部講師を経て、2017年より現職。専門はマクロ経済学。
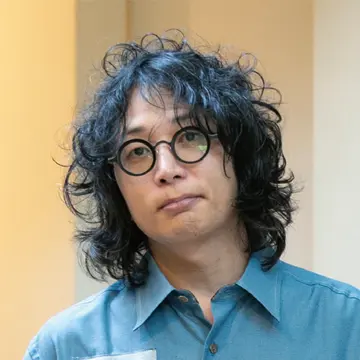
朱 喜哲氏
大阪大学 社会技術共創研究センター招へい准教授 兼大学院文学研究科招へい研究員
大阪大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。専門はプラグマティズム言語哲学とその思想史。研究活動と並行して、企業において各種データを活用したビジネス開発に従事。ビジネスと哲学・倫理学・社会科学分野の架橋や共同研究を推進。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ