Works 190号 特集 本気の 女性リーダー育成
現役女性管理職本音座談会 どうしたら女性管理職は増える?
女性活躍推進を掲げる企業は増えているが、多くの企業では遅々として女性の管理職登用は進んでいない。さまざまな業界で管理職として働く4人の女性に、それぞれの職場の実態と課題、女性の登用には何が必要かを話し合ってもらった。

管理職にはなりたかった? 躊躇していた?
Aさん:前職はいわゆるJTC(伝統的な日本企業)です。20代のころは、全力で働いて成果を出せば海外駐在、管理職昇進といった「王道」のキャリアが拓ける、と思っていました。しかし私は出産によるブランクの影響か、海外勤務もできず管理職にもなれませんでした。仕事に物足りなさを感じて、現在の勤務先に転職しました。今は初級管理職として事業企画に関わり、毎日が充実しています。
Bさん:私は当初管理職になりたいとはあまり思えず、登用試験の受験資格を得てからも数年試験を受けませんでした。当時は会社が女性登用に力を入れ始め、先輩の女性が相次いで昇進していました。しかし私がいた営業では、まだ管理職は男性ばかりで自分に務まる自信がなかった。周囲でも「女性は受かりやすいからね」といった決めつける声を耳にするなど、仕事ぶりではなく「女性」という部分だけを判断されたようで違和感がありました。
ただ人事に異動し、組織を俯瞰して見るようになって視野が広がり、自分のようなタイプの人間が管理職になることで後輩女性の背中を押せるかもしれない、と思うようになりました。異動先の上司が、管理職の仕事のおもしろさを伝えてくれたことも、チャレンジしようと思えた大きなきっかけでした。
Cさん:今の会社に転職後、30代半ばに管理職の打診を受けましたが、実務にやりがいを感じていたため一度は断りました。しかし次第に自分が人事でやりたいことが、経営課題に直結するとわかってきたのです。社外のキャリアカウンセリングで「経営課題を解決したいなら意思決定の場に入ったほうが早い」とアドバイスを受けて視界が開け、登用試験を受けました。
管理職になって、意思決定に関与できるやりがいは感じています。一方で、一部の経営層のジェンダーに関する考えが想像以上に古く、無邪気な発言をすることに驚かされています。
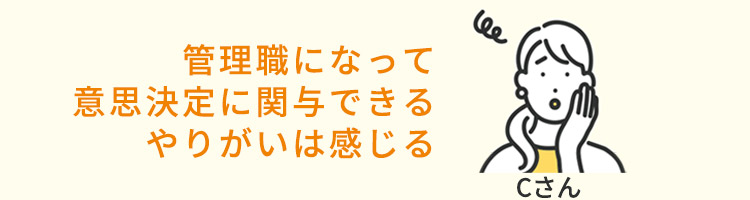
Dさん:3年ほど前に管理職になりました。男性デスクが圧倒的に多いなか、多様なコンテンツを発信するためにも、自分がデスクになることで同僚たちを支える側に回ろう、と思ったのです。
管理職になると同時に約1年半、地方転勤になり、子どもを夫に任せて単身赴任も経験しました。それ以前には夫の単身赴任期間が長く、実家の助けを借りながら私がワンオペで子どもを育てていたこともありました。
男女で偏る配属。 何が女性の昇進を阻むのか
Dさん:メディアの環境が厳しくなるなか、記者の数も減ってきています。そうなると時間的な制約のない男性を、重要な持ち場に置きがちです。人材を戦略的に育成するというより、目先の「職場の回しやすさ」が重視されていると感じることもありました。
私は管理職になり、部内の女性記者を一覧表にし、そこに同期の男性の配属先も加え、女性のキャリア形成を考えて配属を決めてほしいと上司に訴えました。その後、これまで男性しか担当しなかった持ち場に女性が置かれるようになりました。
Aさん:配属と昇進には大きな関係があると、私も前職で身をもって感じました。ある仕事でトラブルが起きたとき、力不足に加えて育児もあってフルコミットできず、上司に助けてもらいました。彼が冷静に対処する様子を見て、過去の「修羅場」経験の差が能力差になることを痛感したのです。女性社員には子育てなどで働き方に制約が生じる前に、中核的でタフな仕事の経験を積ませてほしいです。
前職では子どものいる女性の多くは管理部門に配属されていました。本人の希望や周りの配慮もあると思います。一方で製造業の本丸である「作って売る」部署で経験を積めないことが、経営層に女性が少ない要因の1つだと感じています。日本の基幹産業の製造業が変われなければ、優秀な人材は外資系などに流出してしまうと思います。
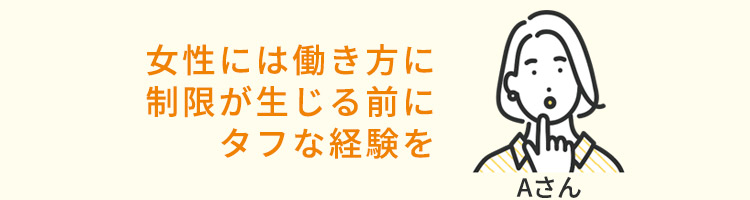
Bさん:当社は社員の3割が女性ですが、管理職登用試験の受験者に占める女性は10%前後で、管理職を目指す女性の少なさが課題でした。
そこで、女性たちが登用試験を受けなかった理由を調査したところ、「自信がない」「育児や介護で試験勉強の時間を確保できない」という答えが多かったのです。このため試験内容を軽量化するとともに、女性リーダーの経験談を聞ける座談会を実施しました。女性だけを対象とした研修も設け、女性同士のネットワークづくりや経営課題を考える機会を与えた結果、登用試験受験者の女性比率も約25%にまで上昇してきました。
Cさん:社内調査の結果、女性管理職の7割がオールドボーイズクラブ(男性中心の特有な文化や慣習、仕事の進め方など)を感じていました。また上司である部長たちは、女性に管理職試験の受験を一度打診して断られるとそれ以上は勧めず、なかには「育児で大変だろう」と配慮し、打診すらしない人もいました。一方、時間をかけて後押しした女性たちは自信を深めて試験を受け、結果として合格率も100%と男性の約6割に比べ高かったのです。
何の手も打たなかった場合、女性管理職比率が現在の10%強から30%に上昇するには、約20年かかることがわかりました。しかし経営層に積極的な対策を取るよう訴えても、「男性同様、休日にゴルフをさせていいのか」「男性が3人育休を取ったら仕事が回らない」など本質から外れた意見をされ、業務外のゴルフを問題視しないのはなぜか、育休を取るのが女性なら仕事は回るのかとモヤモヤした気持ちになりました。
経営層に女性登用の必要性を 理解してもらうには?
Cさん:身をもって体験することです。ある役員がDEIの必要性に目覚めたきっかけは、女性管理職の集まりに男性1人で参加し、マイノリティ側の気持ちに気づいたことでした。
役員へDEIの重要性を訴える際、営業担当には顧客企業のサステナビリティ重視の姿勢を挙げて、「現状のままでは将来的に取引中止になるリスクがある」と話すなど、相手によって説明を変えました。こうした結果、女性管理職が一気に1人から7人に増えました。いい意味でオールドボーイズクラブの「お作法」を知らない女性たちが「忖度しない」発言をすることで、多様な意見が意思決定層に生まれると期待しています。女性管理職を役員がメンタリングする「スポンサー制度」も導入しようと考えています。
Dさん:多様なニュースを届けるには組織の多様性が大事だと、経営トップの認識もここ数年で大きく変わりました。とはいえ、中堅女性社員が数カ月間役員について回る「シャドーイング」をすると、まだまだ会議には男性が多く、がっかりする女性参加者もいます。
Bさん:おそらくDEIの必要性は頭では理解しているものの、結局経営層は専業主婦の妻を持つ生え抜きの男性ばかりなのが現状で、経営層のコミットメントはまだまだ課題であると感じています。Cさんのお話の通り、当事者として体験しないと気づかないので、経営陣や部門の意思決定層に女性やキャリア入社者など多様な人材を入れて意見を言ってもらい、気づかせるしかないと思います。
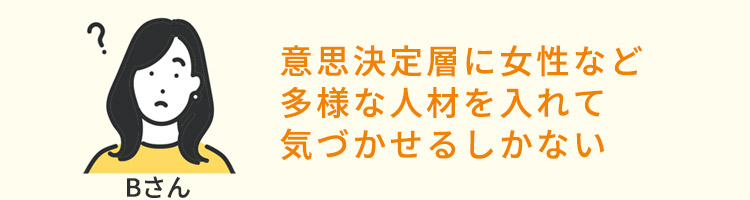
女性が管理職に 前向きになるためには?
Aさん:管理職が、やりがいを持って仕事をする姿を部下の女性に見せることではないでしょうか。私は今、マネジメント層の仕事ぶりを間近で見ていますが、動かせる予算も部下の数も非常に大きく、とてもおもしろそうです。もちろん横につく上司次第、という属人性はあるかもしれませんが、少なくとも今は、彼らから学べるものは全部学びたいです。
現場の一社員という「自転車」と、管理職・役員という「スポーツカー」があったとき、女性は自ら「自転車が分相応だ」と考えがちかもしれません。しかし1度スポーツカーに乗ってみてから決めてもいいのではないでしょうか。
Dさん:女性がキャリアを志向するには夫と、その勤め先であるJTCの意識を変えることが絶対に必要です。我が家でもJTCに勤める夫は、私の単身赴任に大反対しました。彼の言い分では、自分はやむなく転勤させられたが、私は自分の意思なのだから断れと。私だって会社の命令で異動するのに……。
彼の勤務先は専業主婦の妻を持つ社員が多く、夫が子育てすることへの理解がまったくなかった。夫はそのつらさをすべて私にぶつけた形で、あのときのしこりは今も残っています。
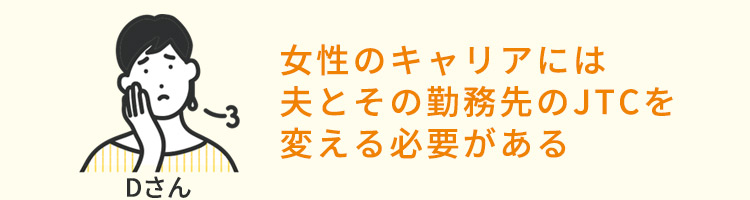
Cさん:若手男性のなかには、転居を伴う異動を命じられると「自分のせいで妻のキャリアを阻害したくない」と言って転職する人もいる時代です。10年後に今の若手が主力になったら職場の景色が変わるだろうし、そうなったときに備えて、今のうちにダイバーシティの一丁目一番地である女性の環境を整えておくこと、ジェンダー間で生じる阻害要因をなくしておくことは、企業や組織としての最低ラインだと思います。
Text=有馬知子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ