Works 193号 特集 採用のジレンマ
リーダー採用は「対話」で決まる。企業の軸を明らかにし、人格を見極めよ

幹部層の採用では、候補者のパフォーマンスや経験が重要な指標になる。しかし、リーダーともなると「人格」も見極めなければ組織にいずれ悪影響を及ぼす。現代的な優れたリーダーの条件を、リーダーシップ理論の第一人者、滋賀大学経済学部・大学院教授の小野善生氏に聞いた。
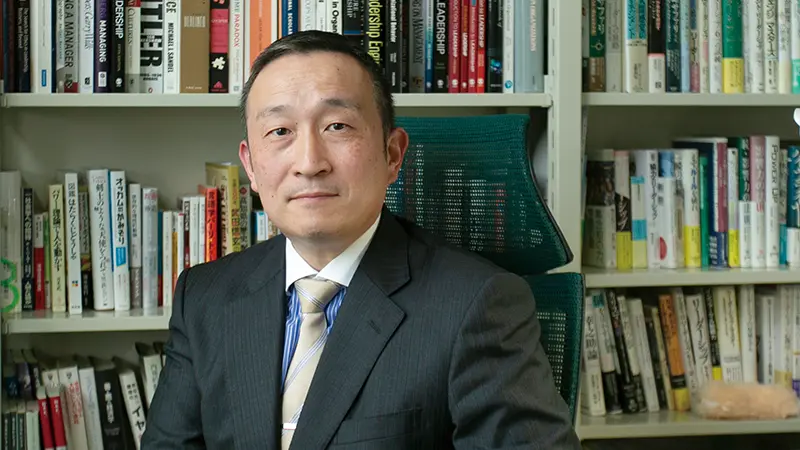
滋賀大学経済学部・大学院教授
小野善生氏神戸大学経営学研究科で博士(経営学)取得。20170年より現職。フォロワーの視点を重視したリーダーシップ研0究を行っている。著書に『最強の「リーダーシップ理論」0集中講義』(日本実業出版社)、『フォロワーが語るリーダー0シップ』(有斐閣)など。
「リーダーシップのあり方は、社会や経済の状況の変化に寄り添い、時代ごとに形を変えてきました」と、小野善生氏は説明する。
リーダーシップ研究の中心地アメリカの理論は、戦前の「資質アプローチ」(リーダーの資質のある者がリーダーシップを発揮できる)に始まった。その後、1950~1970年代には、的確に部下に指示し、人間関係を構築できる「行動型」のリーダーが理想とされてきたという。「当時、アメリカは安定成長期で、企業の方向性やビジョンも安定的で、成果の出し方にも一定のセオリーがあったのです」
その後の1970年代から1980年代にかけては、不安定な時代に突入する。ベトナム戦争やオイルショックなどにより、アメリカの国力は低下に向かう。こういう時代に求められたのが、GEのCEOを務めたジャック・ウェルチ氏やレーガン大統領など、強いビジョンを掲げて組織をリードする「トップダウン型」のリーダーシップだった。
1980年代後半以降は、シリコンバレーを中心にIT企業が次々と勃興した。「処理する情報量が爆発的に増え、情報の専門化や多様化が進展し、ビジネスの変化のスピードも加速度的に上がりました。強いリーダーであっても、1人で“百発百中”の意思決定を下すのは難しい。むしろメンバーを上手に巻き込み、その知識や意欲を引き出すリーダーが求められるようになったのです。こうしたなかで、サーバントリーダーシップやシェアドリーダーシップなど、リーダーとフォロワーの関係性を重視するリーダーシップスタイルが登場しました」
近年、政治分野ではアメリカのトランプ大統領をはじめとするトップダウン型の強いリーダーの復権が、1つの潮流のようになっている。「しかし、ビジネスの環境は複雑化するばかりです。産業界ではますます他者の力も借りて組織の成果を上げるスタイルが重視されていくはずです」
リーダーを見極めるための 面接とは、“対話”である
そうしたリーダーシップの有無を見極めるには、まず「何」を見極めるのかを明確にする必要がある。小野氏は、現代のリーダーに求められる力を2つに整理する。
1つは、異なる価値観を持つ人々の間で共通の認識を作り出す力だ。現代の組織には多様なバックグラウンドや価値観を持つ人が集まっており、そのなかで互いの考えを理解し合い、新しい意味を紡ぎ出し、「誰もが同じ方向を向ける基盤」を築く力こそが本質的なリーダーシップだというのだ。「自分と異なる意見に出合ったときこそ、リーダーの成熟度が問われます」
もう1つは、学び続ける力だ。過去の成功体験をもとに答えを授けるトップダウン型のリーダーでは、変化の時代には通用しない。「異なる考えを受け入れ、他者から学び、自らを更新し続ける。状況の変化に応じて柔軟に考え方を進化させる学習する存在であるべきです」
小野氏は、そうした学びの出発点には「人をどう捉えるか」という前提があると指摘する。
人は単純な報酬や地位だけで動く存在ではない。心理学者エドガー・シャインの複雑人モデルが示すように、複数の欲求や目標を内包し、状況や関係性によって行動の動機が変化する「複雑な存在」である。だからこそ、リーダーは他者を一面的に判断せず、多様な内面や文脈を理解しようとする姿勢を持たなければならない。その前提に立ち、ともに働く人々の言葉に耳を傾けることで、違いのなかから新しい学びを得ることができる。
では、これらをどのように見極めるのか。「ワンショットの面接では、リーダーシップは見えません」と小野氏は言い切る。形式的なやりとりでは、候補者の意図や動機、そして学びの姿勢は浮かび上がらない。「面接とは対話であり、質問に答えさせるのではなく、ともに考える場です。問いと答えを交わすうちに、相手がどんな価値観に立ち、どのように世界を見ているのかが見えてくる。そこに、“この人となら新しいことができるか”という感触が生まれるのです」
小野氏によれば、対話とは「知識の交換」ではなく、「関係の生成」である。面接を短い儀式として終わらせるのではなく、時間をかけて意見を交わし、互いの経験や立場、置かれた状況を学び合う。その過程でこそ、言葉の背後にある思考の質や、学び続ける意志が浮かび上がる。
「特にキャリア採用では、一定の知識や経験を持った完成品を求め、面接はどれだけ完成品に近いかを見極める場になりがちです。そうではなく、面接を判断の場から関係を築く場へと捉え直す必要があるのです」
組織の「軸」を明確にすること それが採用の成否を分ける
だが、その対話を真に機能させるためには、もう1つ欠かせない前提がある。それは、対話の土台となる組織としての「軸」を採用する側が持っているかどうかだ。「共通認識の出発点となる価値観や方向性が、採用する側のなかで定まっていなければ、どんな候補者であっても自社に適切な人材であるかを判断することができません」
採用の現場では、しばしば「優秀な人を採りたい」「変革を担うリーダーを求めたい」といった言葉が独り歩きする。だが、「何をもって優秀とするのか」「どんな変革を目指すのか」という問いに明確に答えられるかどうか、まずは自問自答すべきだ。「採用は組織の人格、つまり存在理由をつまびらかにする行為です。どんな人を、どんな理由で迎えたいのか。抽象的な理念やビジョンにとどまらず、それを基盤とした現実的な課題や未来の姿、候補者にそこで何をしてほしいのかを、自分たちの言葉でストーリーとして語る力が、採用の成否を分けるといっても過言ではありません」
採用の現場では、採られる側ばかりが評価されがちだ。「実際には採る側の姿勢が問われています。採用は組織の成熟度を映す鏡なのです」
そして実は、この軸を整理しておくことの重要性は、採用の段階にとどまらない。
たとえば変革人材やDX人材を採用する場合、まずは自社が今どの段階にあり、今後数年間で何を達成したいのか、その達成のためにどんなギャップがあり、そこにどんな役割を担う人を求めているのか。そしてDXが組織のパフォーマンスにどのような恩恵をもたらすのか。その一連の青写真を描き、経営層にわかりやすく伝え、組織全体に意義を浸透させておかなければ、優れたリーダーが1人採用できても変革の実現は危うい。「軸を明確にするとは、採用のための準備であると同時に、採用した人が組織のなかで力を発揮できる土壌を作る営みでもあるのです」
Text=川口敦子 Photo=MIKIKO


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ