 石川治江氏 特定非営利活動法人ケア・センターやわらぎ 代表理事、社会福祉法人にんじんの会 理事長
石川治江氏 特定非営利活動法人ケア・センターやわらぎ 代表理事、社会福祉法人にんじんの会 理事長

外資系の組織に勤めた後、居酒屋や喫茶店などを経営し、ビジネスに手腕を発揮していた石川治江氏が、それまで無縁だった福祉の世界に飛び込んだのは約35年前のこと。その原点には「怒り」があった。何かをしなければならない――在宅ケアのボランティアからスタートした石川氏の活動と情熱は、一貫して「困っている人が当たり前に暮らすための仕組みづくり」に注がれてきた。介護保険制度の原形ともいわれる仕組みを構築するなど福祉業界に幾多のインパクトを与えてきた彼女の発想、そして行動は、社会に「本来の福祉のありよう」を問い続けている。
上司と仕事に恵まれ、
「眠っていた脳」が開花
何事にも直截的で、バイタリティあふれる現在の石川氏からは想像もできないが、聞けば、子ども時分はとても病弱だったそうだ。食事制限はあり、運動も自由にできない。学校にいる時間より、家で過ごす時間のほうがはるかに多かった。
友だちは「活字」だけ。家では本ばかり読んでいて、昔あった貸本屋さんの本を全部読破しちゃったほど。あとは絵を描いたり、お習字したり、家の中でできることってそれぐらいですから。欠席が多いと同級生とは話が合わないし、偉そうにしている気に入らない先生もいたものだから、とにかく学校には行きたくなかった。今でいう不登校児ですよ。
勉強のべの字もしない子どもだったけれど、母が教師だったので、要所で勉強を見てくれたものです。あと、「学校なんか行かなくても大丈夫よ」と、まるで専属ナースのように病弱な私の世話をしてくれた祖母の存在も大きいですね。母も祖母も実におおらかな女性で、私はそのおかげで、何の負い目も感じることなく真っ直ぐに育った気がします。下着から洋服まで、大半の衣類は彼女たちが手づくりしてくれたし、親類縁者もしょっちゅう泊まりに来るような家でしたから、愛があって楽しくて......私は"いい大人たち"に囲まれていたんでしょうね。
「50歳まで生きられるかどうかわからない」。医師の叔父からはそう言われていたそうです。それを聞いた時、「そうか、50過ぎたらおまけだな」と思いました。それが不思議なもので、出産を機にすごく元気になった。体質が変わったのかもしれないし、何より、育児や仕事で甘ったれていられないから、その緊張感のおかげかな。人間、なまじ時間があると、ろくなことにならないものですよ(笑)。
高校卒業後、知人から勧められた勤め口があった。外資系の非営利組織・IWS国際羊毛事務局(当時)である。この頃、石川氏は本格的に始めた油絵に夢中になっていたから、「働く気はなかった」そうだが、結果、彼女はここで仕事の面白さに目覚めることになる。「眠っていた脳みそが開花したの」――今日までを紡ぐビジネススキルを培った時代だ。
紹介してくれた知人への義理があったので、仕方なく出向いた面接でした。私は正直に、英語もタイプも何もできないと伝えたのに、どういうわけか受かっちゃった。でも縁ですよねぇ、この時に出会ったボスこそが私に強い影響を与え、師匠となるのです。なかなかの変わり者なんですが、とにかく頭脳明晰で。「世の中なんてつまらない」と斜に構えていた私に、仕事の面白さ、素晴らしさを教えてくれました。
最初は秘書をやっていたので、いつも側にいるわけです。ボスの仕事の進め方、物事の捉え方、メンバーを"本来の目的"に導くマネジメント力、これらを間近に見てきて得たものは大きい。波長が合ったのでしょう、生意気な私を可愛がり、機会も与えてくださった。「二人分の仕事をしているのだから昇給してほしい」と言えば聞き入れてくれ、「商品企画の仕事をしたい」と言えば環境を与えてくれ、億単位の商売も経験させてもらった。もうめちゃくちゃ仕事が楽しくなって、「私は仕事で生きていくぞ!」という勢いで働いていました。
カルチャーショックと怒り。
無縁だった福祉の世界に飛び込む
 その後、結婚と「命からがらの出産」を経て、石川氏は飲食店業を始める。自ら「飽きっぽい」と言うだけあって、従前とは畑違いの居酒屋や喫茶店経営に乗り出したのである。それでも、IWS時代に培ったビジネススキルと持ち前の独創性で、商売は大繁盛。「めちゃ儲かっていたのよ(笑)」。大きな転機が訪れたのは、80年代に入ってすぐの頃だった。友人に誘われて訪問した授産施設で知った現実。それが、石川氏を福祉の世界へと導いた。
その後、結婚と「命からがらの出産」を経て、石川氏は飲食店業を始める。自ら「飽きっぽい」と言うだけあって、従前とは畑違いの居酒屋や喫茶店経営に乗り出したのである。それでも、IWS時代に培ったビジネススキルと持ち前の独創性で、商売は大繁盛。「めちゃ儲かっていたのよ(笑)」。大きな転機が訪れたのは、80年代に入ってすぐの頃だった。友人に誘われて訪問した授産施設で知った現実。それが、石川氏を福祉の世界へと導いた。
授産施設は初めてで、ほんと何気なく友人について行ったのです。そこで目に飛び込んできたのは、作業場で、脳性麻痺などの障がいを持つ人たちが並んでタイピングをしている光景。大変そうだとか、そういうのじゃない。とにかく生まれて初めて見る光景だったから、私は頭が真っ白になるほどのカルチャーショックを受けたのです。
加えて、今はだいぶ違うでしょうが、あの頃は施設での生活は様々な行動規制がされていて、例えば髪すら自由に伸ばせない。外出もままならず、国鉄(当時)に乗るには2日前に申請しなければいけないとか、現実を知るたび、私には「何で? 何で?」ですよ。そして「これは何ということだ」という怒りも湧いてきた。やはり原点はここですね。
やがて私は、彼らと共に、駅にエレベーターの設置を要求する運動を始めました。東京都の立川駅でそれが実現したのは97年。16年の歳月を経て、5基のエレベーターが設置されました。時間はかかったけれど、この運動は全国に波及し、日本の移動運動(移動の権利を保障する運動)のきっかけになったと思います。
エレベーター設置運動と並行して、石川氏は、「施設を出て地域で暮らしたい」という障がい者の要望、生活を支えるボランティア活動にも勤しんだ。その過程で「命のすごさに圧倒された」石川氏は、営んでいた商売を手じまいし、持てる力をすべて福祉の世界に注ぐようになる。非営利の民間福祉団体「ケア・センターやわらぎ」(2000年にNPO法人格取得)を立ち上げたのは87年、40歳の時だった。
人が自分の意思で生活していくのは当たり前でも、障がい者にとっては極めて大変なこと。彼らのためにアパートを借り、生活用品をそろえても、暮らすためには常に人の手が必要になります。当初は、私みたいな元気なおばちゃんたちが頑張っていたんだけれど、安定的な人手確保はすごく困難で、やはりボランティアでは限界がある。活動は全部自腹を切ってやっていたから、年々、清く正しく貧乏になっていくし(笑)、すってんてんにもなった。
在宅ケアを継続保証するにはどうすればいいか。誰でも、いつでもどこでも、必要な時に当たり前にサービスを受け取れるような社会的な仕組み。それを構築したくて、暗中模索のなか立ち上げたのが「やわらぎ」です。
運営費は、利用者の会費と行政の助成金、活動賛同者からの寄付金などで賄い、利用者が支払う介助料はすべてワーカーや看護師に支払う。つまり私たちの立場は、サービスの利用者と提供者をつなぐ非営利の仲介者。24時間365 日のニーズに応えるためには、これ以外の方法は考えられなかった。
当時は、そんな発想がなかったから「有償のサービスは障がい者の生きる権利を侵略するものだ」と、様々な活動家から責め立てられたものです。でも、違うでしょう。我々と同じように、障がいを持つ人たちが地域で生活すること、これは当然の権利として保証されるべきだし、その機能を継続させる社会的システムは必要なのです。手助けのニーズがあれば、社会に張り巡らされた"網の目"のどこかに引っかかり、必要なサービスを受けられる――私はそんな仕組みをつくりたいのです。
介護の本質と向き合いながら、
「仕組みづくり」に奔走する
 介護と看護を両輪とした在宅ケア、そして、24時間365日のサービスを打ち出したのは日本初である。以降も石川氏は、サービスの利用者・提供者間に契約の概念を導入したり、業務の安定性、効率化を図るためにケアを百数十種類に分けマニュアル化するなど、次々に新手を編み出してきた。それら独自のシステムは、介護保険制度の骨組みに大きなインパクトを与えたとされる。
介護と看護を両輪とした在宅ケア、そして、24時間365日のサービスを打ち出したのは日本初である。以降も石川氏は、サービスの利用者・提供者間に契約の概念を導入したり、業務の安定性、効率化を図るためにケアを百数十種類に分けマニュアル化するなど、次々に新手を編み出してきた。それら独自のシステムは、介護保険制度の骨組みに大きなインパクトを与えたとされる。
うちのような在宅福祉サービスを行うところはどこにもなかったから、マスコミに取り上げられたり、全国から視察者が訪れたり。理解者が増えるのはうれしかったけれど......時には招かざる客もいました。
介護保険が売り出された頃の話。大手の損保会社がやって来てね、「支援として資金提供をします」と言うわけ。こっちは寄付だと思って喜んでいたら、代わりに利用者さんの名簿を寄越せと。その頃、31市区町村をカバーしていたから、確かに相当の名簿数ではあったけれど、それが目的だなんてアタマに来るじゃない。みんなで塩まいて追い返した、なんていう一件もありましたねぇ。
重度障がいや寝たきり、難病や痴呆といったほかの団体では受けきれないケースを多く請け負ったこともあり、「やわらぎ」は繁盛しました。換言すれば、それだけサービスを必要とする人が大勢いたということです。障がい者だけでなく、介護を担うたくさんの家族の方々と出会うなか、苦悩することも様々あったけれど、そのたびに知恵をしぼり、サービスの手直しを重ねてきました。プロとして、どんなニーズにも的確に応えられなければならない――常にそう思いながら走り続けてきたように思います。
活動は大きくなり、「やわらぎ」を始めた10年後には「社会福祉法人にんじんの会」を設立。現在では、東京都と山梨県において、特別養護老人ホーム、グループホーム、訪問介護・看護などといった介護保険事業や障害者総合支援法事業を幅広く展開している。陣容が拡大しても、石川氏らには変節なき考え方がある。自著のタイトルにもなっている『介護はプロに、家族は愛を。』だ。
この世界で出会う人たちの多くは、日々の介護と「家族なんだから」という重圧に苦しめられている。だからこそ、私たちは家族と介護を別々に置いて見つめ、排泄、入浴、食事などといった介護は「行為」であると位置づけたのです。
医療も同じじゃないですか。私たちは病気やケガをした時、「思い」より「医療行為」を求めて病院に行くわけでしょ。同様に介護の領域を明確にし、必要な時、いつでもサービスが受けられる仕組みがあれば、家族は重圧から抜け出すことができる。維持すべきは、家族だからこその精神的な支えであって、負担や重圧ではない。だから「介護はプロに、家族は愛を」なのです。
ただ、介護は単体の商品ではなく、関係性があって初めて成り立つんですね。これも医療と同じですが、信頼関係がなければ本当の意味でいい行為はできない。「やれないから、やってあげる」という概念だけだと上から目線になってしまう。やれないことができるようになった時には、「寄り添う」態度が必要なんです。それができるのがプロだと思います。では、「プロとして、いいケアって何?」。この答えはねぇ......すごく難しい。生涯の宿題のような気がしているけれど、でも、わからない部分や未知の領域がいっぱいあるから、私には面白いんです。それが、人との出会いや経験を通じて、少しずつわかっていく楽しさ。この仕事を続けているエネルギー源の一つかもしれません。
レールの引かれていない未開の地にこそ、
楽しみと喜びがある
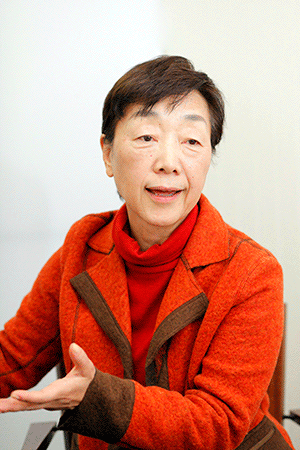 本人が語っているように、石川氏は未開の地を好む。先陣に立って切り開きながら、そこで仕事をつくることを楽しんでいる。そして、彼女が福祉の世界に飛び込むきっかけとなった「怒り」、これもまた変わらぬ大きな原動力として存在し続けている。
本人が語っているように、石川氏は未開の地を好む。先陣に立って切り開きながら、そこで仕事をつくることを楽しんでいる。そして、彼女が福祉の世界に飛び込むきっかけとなった「怒り」、これもまた変わらぬ大きな原動力として存在し続けている。
飽きっぽい私がこんなに長く続けている大本には、やはり怒りがあると思いますが、変容はしてきています。少しキザに言えば、怒りや疑問を解決する戦略が考えられるようになったということです。最初のエレベーター設置運動では、厚労省のフロアに座り込んで「エレベーターつけろ!」と拳を上げる直接的な要求運動をしていたわけですが、それが仕組み化というか、システムを構築する機能運動に変化してきた。戦略を持って勝ち取っていこうと。こちらのカードと相手のカードを出し合い、「何ができるか」を探っていく。顕著なものとしては、介護保険制度をつくる時がそうでしたね。
今、広めようとしている認知症予防プログラム「だんだんダンス」もそう。認知症って、1対1のケアがなかなか成り立たなくて、どうしても家族を巻き込んでしまう。認知症の親を抱えて勤めを辞めざるをえない、さらには「施設に入れるお金もない」で、これは家族だけでなく日本経済にも影響を与える深刻な問題なわけですよ。それで「よし、認知症予防をやるぞ」と始めたのが、脳を活性化するダンス。私、思いついたらどんどんやりたくなる(笑)。企業も触手を動かしてきているし、これは大きな動きになると思います。
ほかにもいろんなことをやっているので、とにかく忙しい(笑)。でも、ボランティアにしてもNPOにしても、花火をズドン、ズドンと上げる人がいないと、組織ってもたないんですよ。みんなが疲れて、モチベーションが下がりますから。「理事長が、また何か始めるぞ」――それが私の役割だと思っています。実際、アイデアはどんどんわいてくるし、知恵を出してやってみたら単純に面白い。金のないところに知恵があるんです。
人生ってYの字じゃないですか。複数の選択肢があってどっちかの道を選ばなくてはならない。その岐路に立った時、私が自分に課していることは「しんどいほうを選ぶ」、そのうえで「レールが敷かれていて、つまらなそうな匂いがしたら動かない」。結局のところ、私は、誰も行ったことのない道が好きなんですよ(笑)。
TEXT=内田丘子 PHOTO=刑部友康
プロフィール
- 石川治江
- 特定非営利活動法人ケア・センターやわらぎ 代表理事 / 社会福祉法人にんじんの会 理事長
- 1947年東京都生まれ。
外資系組織で秘書を務めた後、喫茶店、居酒屋、手紡ぎ工房などを経営する傍ら、障がい者との出会いから介護・福祉分野に問題意識を持ち、78年に生活支援ボランティア組織を発足させる。その後、87年に非営利の民間福祉団体としてケア・センターやわらぎを設立。日本初の24時間365日の在宅福祉サービスを打ち出す。2000年、NPO法人化。現在、同団体代表理事、社会福祉法人にんじんの会理事長、立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科客員教授、21世紀社会デザイン研究学会副会長、一般社団法人ダイアログ・イン・ザ・ダーク理事。
