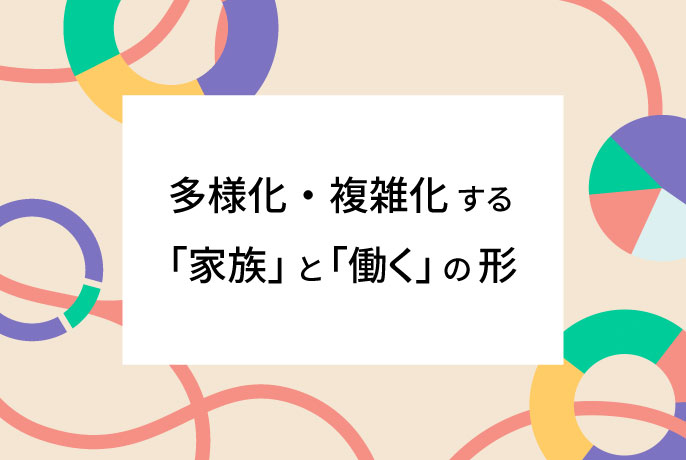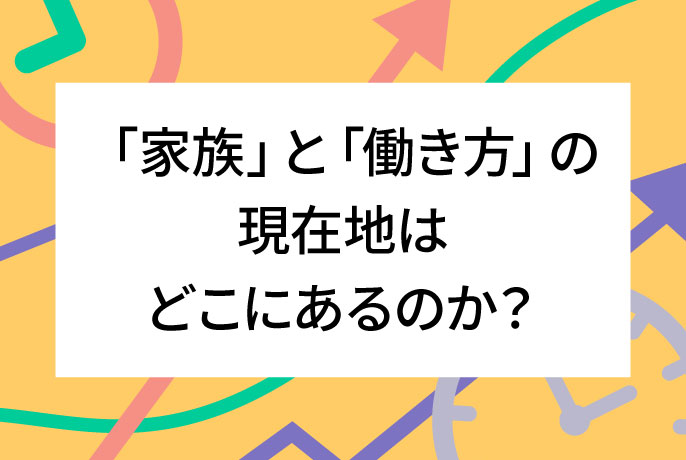「弱いロボット」がつむぐ自立共生的な関係
筑紫女学園大学副学長・現代社会学部教授、豊橋技術科学大学名誉教授の岡田美智男氏に、「弱いロボット」やコミュニケーションロボットと人との関係をテーマにお話を伺いました。
「弱いロボット」研究の始まり

岡田美智男氏とロボットたち
――「弱いロボット」の研究をするに至った経緯を教えてくださいますか。
音声科学や音声言語処理といった、今でいう〈Siri〉や〈ChatGPT〉のようなものを研究していました。それから40年近くコンピューターと会話するという研究をしています。そうしたなかで、人工知能の「冬の時代」といいますか、自然に応答したり発話したりする研究を扱うのが大変な時期がありました。そうした時期に、「コミュニケーションは、同じような身体を持っているからこそできているのではないか」といったことを考え始めました。相手が自分と同じように身体を持っていて、お腹が空くという感覚を持っているから、相手の表情を見て、あ、お腹が空いているかもしれないと想像がつく、といったことは少なくありません。
加えて、言葉だけのやりとりだとリアリティが伴わないと感じることもありまして、コミュニケーションにおける身体性、身体役割の研究を始めました。そんななかで、当時そんなにロボットの知識があったわけではないのですが、ロボットを作ってみたのです。そのロボットはポンコツだったのですが、ロボットの近くで様子をうかがっていたお子さんが見かねてロボットの世話を焼いてくれた。この経験が、弱さや不完全さに意味があると思い始めたきっかけであり、現在の「弱いロボット」の研究につながっています。
不完全さの持つ力
――一般的にロボットは能力が高く、できることが多い方が良いと考えられがちな気がします。先生が「弱いロボット」の研究で大事にしていることは何ですか。
確かに、研究者や開発者は、ロボットは能力が高い方がいい、できることが多い方がいい、と考えて開発をしがちです。一方で、私たちが作ってきたロボットは、不完全だったり、へこみがあったりすることで、相手の優しさや強みを引き出すことができています。喜びを引き出すこともできているのです。私や一緒に研究している学生が大切にしているのは、ブリコラージュ(Bricolage)、つまり、その場のありあわせのものや、寄せ集めたものから何かを作り上げていくという考え方です。予算や人員が足らないという部分を大事にしています。予定調和ではつまらないのです。
例えば、「弱いロボット」の一つである〈ゴミ箱ロボット〉も、ゴミ箱にゴミを拾い上げるロボットアームをつければロボットが自分でゴミを拾うことはできるのですが、その予算がなかったこともあって、あえてロボットアームはつけず、ゴミを拾ってゴミ箱ロボットに入れてもらうところは、人に手助けしてもらうことにしたのです。
――「弱いロボット」の「弱い」という言葉にはどのような意味が込められているのでしょうか。
「弱いロボット」という名前は、書籍を出版する際に担当の編集者さんが名付けてくれたもので、その後、「弱いロボット」という言葉で研究を認知してもらえることが増えました。一方で、「弱い」という言葉は誤解を生じやすいと感じています。弱さをデザインするとあざとさになってしまいます。私たちが目指しているのは、完璧なものを目指すという「強さ」というベクトルと対極にあるものであり、その意味で「弱さ」と呼んでいます。
隣の人の身体を見ると何も不自由なく完全に見えることがあります。しかし、自分の身体を見てみると、不完全なところやできないことがあることを皆知っています。それを人は隠して生きていて、自分ひとりでやろうとしがちですが、実際は周囲の環境からの支えのなかで生活したり、目的を実現したりしています。言葉にしても、挨拶にしても、それを繰り出す際には不完全なものですが、相手が返してくれるから成立します。ある意味、相手の反応や行動に「賭けてみる」という点では、そこに脆弱性や勇気を伴うのです。
つまり、支えがあって初めて成立する、相手の反応や行動に賭けてみるという「不完結なもの」という意味での「弱い」であって、能力的に弱いという意味ではありません。周りとの関係性のなかで作られていくものには、しなやかさを感じますし、出てきたアイデアは素晴らしいことがあります。関係性のなかで生み出すものならではの良さがありますね。
コミュニケーションロボットがもたらす程よい距離感
――先生は企業と共同でコミュニケーションロボットを開発されています。これは、どのような点に注目して開発を進められたのでしょうか。
私が企業と開発しているロボットはペットロボットと呼ばれることも多いですが、ペットロボットや癒やしという言葉は、私自身はあまり好きではありません。ロボットと一緒に生活することについても、まだまだ研究途上にあるのかなと思いますが、一つの「ポップカルチャー」を生み出していくという点では、とてもスケールの大きな社会実験になっているのかもしれません。この開発では、「家庭のなかで使えるコミュニケーションロボットを作りたい」という話を、企業からいただき、お手伝いすることになりました。
同様のロボットをかわいがっている人は世の中にたくさんいて、オーナー会やファンミーティングも盛り上がっています。こうしたロボットと一緒に出歩いたりするという関わり方は、欧米ではなかなかないものです。
コミュニケーションロボットとの関わりを考える上では、「程よい距離感」を大事にしています。人には人の世界があって、ロボットにはロボットの世界があって、自律的にいられる距離感を作ることが大切だと考えました。それぞれのロボットにはそのロボットだけの世界観があります。かまってほしいと近づいてくるタイプのペットロボットは、どちらかといえば犬に近いですが、私たちが開発したロボットは、時には甘えて、時には適度に距離をとっており、それがうまくいっているのだと思います。また、このロボットは成長していく過程で新しい言葉を覚えますが、きちんとした言語を使ってしまうと関係性が堅くなってしまうことにも注意しています。
共感し合う関係性の構築
――コミュニケーションロボットならではの関係性とは、どのようなものでしょうか。
以前、スマートスピーカーが出てきて流行った時期がありましたが、今少し下火になっているように感じます。スマートスピーカーとの間では、関係性やつながりを作れなかったからです。しかし、共感性を持ってくれたり、少しだけこちらを慮ったりしてくれたりすること、そして、そこに身体がついてくると、人はロボットに共感します。実際には、まだまだ人間側の片思いだとは思いますが、情報をやり取りしたり、適切な情報をくれたりするだけではなく、関係性を生み出すことが上手なロボットが増えています。共感し合う関係性を作るのは大きなテーマです。現時点では、ロボット側が人に共感的にふるまうところがまだ弱いです。最近は、生成AIの高度化によって、身体をベースにした基盤モデルの研究が進みつつあるので、それも進んでくるでしょう。
会話を交わしたり、気持ちを返してくれる存在が大切
――日本では単身世帯が増えています。日本社会において、ロボットが補完すべき役割について、先生はどのようにお考えでしょうか。どのような存在としてロボットがあるべきでしょうか。
私自身は、結婚していますが半分の期間は単身赴任での生活です。この程よい距離感が心地よいと感じています。よって、私自身は一人でいるときにロボットにそばにいてほしいかと言われると、あまりそうでもありません。ただ、相手にほんのちょっと気持ちを返してくれたり、少し顔を向けてくれたりする関係性がある状態は自然であり、それをロボットは担えると思います。
コロナ禍で、家で過ごすことを余儀なくされたときに、誰も頼れないことに加えて、誰かに頼ってもらえることがないというのは辛い感じがしました。心理的な安定、グラウンディングのためには、ちょっと落ち着かないときに少し気持ちを返してくれたり、会話を交わしたりする存在が大事であり、その役割はロボットもできると思います。雑談は情報交換ではなく、相手とのつながりを確かめるための手段であり、一言二言でもつながりを感じられるものです。
家庭における自立共生的な関係づくりへのロボットの貢献
――ロボットと人の関係性は、家庭との関係性や家族のあり方とも通じる部分があるのでしょうか。
ロボットであっても不完全なところがあって、人間には強いところも弱いところもある。それが関係性基礎になっています。補い合うことで関係性を作ることは、共依存を生むこともあります。共依存だと少しずれると関係性が崩れてしまうので、緩く支え合う要素が大事です。
私は、コンヴィヴィアリティ(自立共生的な関係)という言葉に注目しています。家族でも母親があまり子供のことをやりすぎると、子供の主体性を削いでしまうことがあります。それはなんでもできるロボットも一緒です。緩くつながっている関係性が理想で、程よい距離感を作ることが大事だと思います。
会社などは能力主義で、自己完結することが求められたり、全方位的に強さを見せたりしないといけない社会や職場になっています。だから、息切れしてしまう。家族のなかで 自分が弱いところを出せたり、ロボットが程よい距離感や緩さでそこにいてくれるのが良いのではないかと思います。
私たちが最近大事にしているのは、複数のロボットがいる状態です。ロボットと1対1だと、「何か話さなきゃ」といったように人にプレッシャーを与えてしまうことがあります。ロボットが複数いて、ロボット同士で会話をしてもらうと、人間側は楽になったり、少し考える時間を持てたりするので良いのです。複数のロボットがコミュニティになっていると、そのコミュニティのなかで人も会話も楽しめます。
家族との会話も1対1だと、対峙している感じになりやすく、時に緊張感を感じたり制約を感じたりすることがあります。ロボットも家族も、コミュニティがあって、そのなかにたまに自分も参加する形がいいのかもしれません。何もしゃべらなくても関係性が成り立つ、対峙ではなくて並んだ関係、並んでごはんを食べたり、テレビを見たり、注意を向けたり、向けなかったり。そんな、緩くつながっている関係性が理想だと思います。
■お話を伺った人
岡田 美智男(おかだ・みちお) 氏
筑紫女学園大学副学長・現代社会学部教授/豊橋技術科学大学名誉教授
1960年生まれ。1987年、東北大学大学院工学研究科博士後期課程修了。NTT基礎研究所、国際電気通信基礎技術研究所、豊橋技術科学大学を経て、現在、筑紫女学園大学副学長・現代社会学部教授。コミュニケーションの認知科学、社会的ロボティクス、ヒューマン・ロボットインタラクションの研究に従事している。著書に『〈弱いロボット〉から考える 人・社会・生きること』(岩波書店)などがある。

武藤 久美子
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ エグゼクティブコンサルタント(現職)。2005年同社に入社し、組織・人事のコンサルタントとしてこれまで150社以上を担当。「個と組織を生かす」風土・しくみづくりを手掛ける。専門領域は、働き方改革、ダイバーシティ&インクルージョン、評価・報酬制度、組織開発、小売・サービス業の人材の活躍など。働き方改革やリモートワークなどのコンサルティングにおいて、クライアントの業界の先進事例をつくりだしている。2022年よりリクルートワークス研究所に参画。早稲田大学大学院修了(経営学)。社会保険労務士。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ