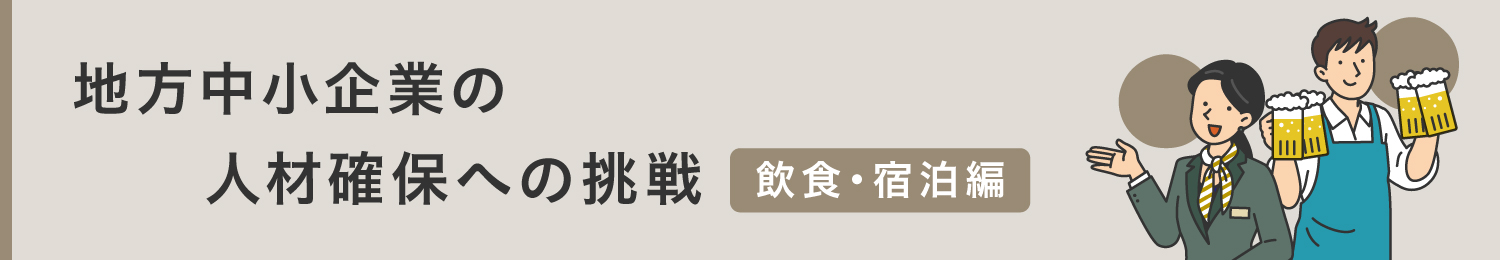
全部をやらないことが、企業価値を守る 業務工程の分業と信頼できる外部連携で生まれる現場改革――株式会社ORihon
東京・神楽坂、趣ある旧・折本(おりほん)工場を改装した一軒の喫茶店から始まった「株式会社ORihon」は、イートイン、テイクアウト、卸売、オンライン販売と着実に事業領域を広げ、コロナ禍という予測不能な社会変化の中でも、“変わらぬ美味しさ”と“ほっとひと息つける非日常”を届けたいという想いを貫いてきた。その根底には、「人がいないなら、仕組みとコミュニケーション、信頼できる外部連携で支える」という、柔軟で明確な戦略がある。代表取締役・熊木啓悟氏に詳細を聞いた。 株式会社ORihon
株式会社ORihon
代表取締役 熊木啓悟氏
「喫茶店」というあこがれから始まった、手づくりの原点
――株式会社ORihonは、もともと喫茶店から始まったとお聞きしました。
2011年、地元の神楽坂にあった折本(おりほん)工場を改装し、大人の世界の入り口のようでずっとあこがれていた喫茶店を始めました。しかも冷凍食品を使わず丁寧に料理を作る、昔ながらの喫茶店をやりたいと思ったのが飲食業に進むきっかけでした。 ――その後はどのように事業を展開されたのでしょうか。
――その後はどのように事業を展開されたのでしょうか。
最初は平日にランチ営業をしていましたが、お客様から「夜にも洋食を食べたい」という声が増えて。そこで、夜は「洋食バル・オリホン」として営業を開始。さらにイベント出店で人気だったホットケーキを週末限定で提供する『熊木ホットケーキ店』もスタートし、週末と平日、昼夜で業態を切り替える、いわゆる“二毛作”スタイルの営業となりました。
2019年にはクラウドファンディングで180%の支援が集まり工房を整備。その後は商品開発や製造も本格化し、現在は商業施設での展開も含め、ミートパイやタルトなどの販売も行っています。
「店舗休業と新しい事業形態」──コロナ禍がもたらした柔軟な事業戦略
――順調に事業を拡大されていたなか、新型コロナウイルスの影響はどのようなものでしたか。
ようやくホットケーキ店に行列ができるほど人気が出てきた頃、緊急事態宣言が出ました。店舗は高齢の方が多く住むエリアにあるので、万一何かあったらと考え、翌日には店舗の営業を一旦止めました。当初は短期間のつもりだったのですが、気づけば2年半も休業していました。
先が見えないなか、店舗以外の商売を模索し、お弁当とフランスの古典菓子をメインにしたテイクアウトを始めました。従業員はわたしたち夫婦のほかに工房スタッフが2名と店舗アルバイトが3〜4名。店舗スタッフには、出勤は控えてもらうが給与は休業中も払い続けるという、厳しい運営状況が続きました。
――その期間に、その後の主力商品「ミートパイ」が誕生したのですね。
コロナ禍においては店舗に頼らず収益を生み出す必要があり、テイクアウトの強化を推進しました。商品は試行錯誤の末、誰もが知っているが提供している場所が少ない、“ありそうでなかった”ミートパイに着目。生地はパティシエである妻が担当、フィリング(※お菓子やパン、料理などに使われる詰め物や具材のこと)は僕が担当して、「ミートリオン」というブランドを作り、マルシェや商業施設での販売をスタートしました。2023年には法人化して、現在は株式会社ORihonとして事業展開を進めています。
人材不足を乗り越える。工程の分解で「できることから始める」仕組みと、低離職率の秘訣とは
――事業を展開していくなか、人材についてどのようなご苦労がありましたか。
いつも一番難しいと思うのは人材の確保と定着、そして従業員教育です。新しいことを始めようと人材を募集・採用し、実際に仕事を覚えてもらうまで、弊社の形態ではアルバイトの方でも半年はかかります。
たとえば商業施設内にあるミートパイの店舗はたった4坪ですが、現場で包んで焼く必要があるため、本来1人で回せる規模でも2人いないと回らない。夜は社員が1人なので、仕込みも新しい試みもできない。商業施設の営業時間に合わせるため、残業などもコントロールできないなか、限られた人員の中で、業務を効率化する必要がありました。
――人材不足のため、できていないことはありますか。
人手が足りていないためにあきらめていることは多々あります。ホットケーキは仕込みと焼きに手間がかかるため、4種類中2種類に絞って提供しています。ドリンク展開も紅茶とコーヒーだけにしている状態で。ミートパイ専門店でも、オペレーション的に人手が足りず、飲み物とのセット提供を断念しました。
――人材不足の解決策が「工程の分解」だったんですね。
従来は正社員やフルタイムで働くアルバイトですべての工程を行う形で進めてきましたが、多くの商品を少数の人員で製造するには限界がありました。フルタイムですべての工程ができる職人採用は難度が高く、スポットワークサービスも試してみましたが、弊社が求める作業は一定の訓練が必要なものが多く、マッチングが難しい状況だったのです。
そこで、製造工程を分解して、未経験の人でもできる仕事と外注でもできる仕事に分けました。たとえばパイは「練る」「寝かす」「フィリングを作る」「包む」「焼く」の5つの工程があり、今までは、それをひとり一気通貫でこなすのが当たり前でした。しかしそれでは作業を覚えるまで時間もかかり未経験者にはハードルが高い。こうした作業のすべてができる人を採用することは困難です。
まずは各工程を細かく分け、業務分解をしたうえで、短時間で働くパート・アルバイト社員を雇い、それぞれの業務に特化した人材を育成することにしました。そうすれば未経験者でも、まずは「生地を練る」といったシンプルな作業からスタートできるので、採用のハードルは大きく下がります。最初からすべてできなくてもよいため、教育のハードルも下がりました。
さらに、一つの業務に慣れてきたら徐々に他の工程も覚えてもらい、複数の業務ができるように育成します。こうしてそれぞれの業務について時間ごとにローテーションを組むことで、全体の作業を分担しながら遂行する体制を整えました。結果として、採用面でも定着面でもプラスになっています。
「全部をやらない」ことで守れるもの。“手仕事”の価値から見出す未来の希望
――製造工程で業務分業を進めた以外に工夫されている取り組みはありますか。
業務分解した結果、外注できる業務もあることに気づきました。創業当初から“手づくりであること”を大切にしています。でも、人手不足の中で全部を自分たちでやるには限界がある。起源になる喫茶店は自分たちの味を大切にしたいからこそ、既製品は使わない、製造工程では外注はしないのが前提でした。一方で、出店したことにより、このままでは製造が追いつかないことはわかっていたので、何とかしなければならない。自分たちの味を実現できる信頼できる職人さんを探していました。その職人さんがいる加工工場と出会えたのが、飲食店やフード提供事業者が仕込みを外注できるプラットフォームです。
はじめはたぶん自分たちの味にはならないだろうと少し思っていましたが、レシピを忠実に再現してくれました。今は安心して仕込み工程の一部をお願いしています。全部を抱え込まず、だけど大事なところは譲らない。このバランスが、私たちの価値を守るための手段です。
――今後の展望についてお聞かせください。
私たちが届けたいのは、「味」だけではありません。そのひと皿を通じて生まれる空気、会話、空間、そして思い出――「どこで、誰と、何を食べ、どんな時間を過ごしたか」という体験そのものが、お客様の心に残る価値だと信じています。美味しさの先にある、忘れられない時間を提供したい。それが、創業から今も変わらぬ私たちの想いです。
これからは接客により比重を置いた、バル業態のような新しいチャレンジも構想しています。人材不足という課題は簡単には消えないけれど、「守るべきことは何か」「採用と定着と教育の工夫をどうするか」「どれを外部に頼るべきか」を見極めながら、これからも、お客様に心に残る時間を届けていきたいと思います。
聞き手:岩出朋子
執筆:村上綾子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

