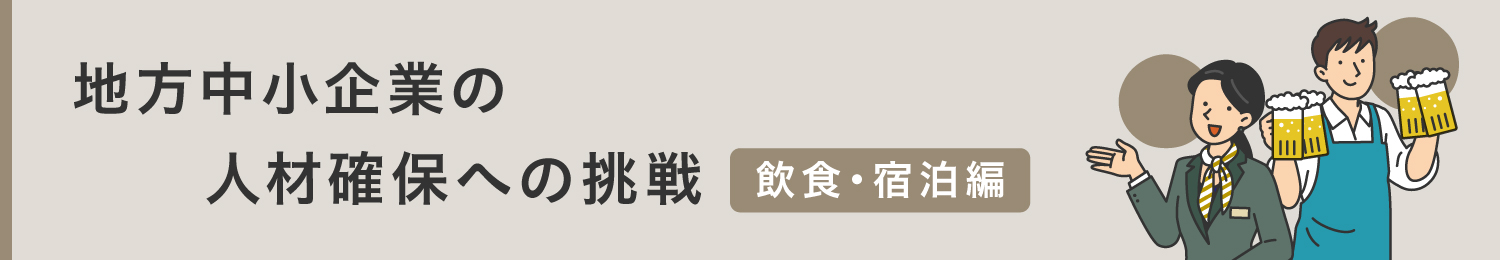
採用単価100万円時代への挑戦 「アルバイトからの正社員登用」「セカンドキャリアの用意」「出戻り歓迎」――株式会社スマイルリンクル
人材獲得競争が激化し、飲食業界では一人あたりの採用単価が100万円を超えようとしている。中小企業にとっては厳しい金額だ。この状況を打破すべく、東京でお好み焼き「Big-Pig」やしゃぶしゃぶ専門店「春夏秋豚」などの飲食店を経営する株式会社スマイルリンクルは、アルバイトからの正社員登用など、すでにつながりのある人材の育成・獲得・プールに取り組んでいる。代表取締役社長の須藤剛氏に訊いた。
 株式会社スマイルリンクル
株式会社スマイルリンクル
代表取締役社長 須藤 剛氏
一見、反時代的な原則“強制参加”の全社ミーティングを復活させた理由
――現在の飲食業界における採用市場の現状と、その中で中小企業が直面している課題から教えてください。
求人媒体に100万円の掲載料を払っても新卒も中途も正社員雇用では一人も採用できない、という厳しい状況です。採用単価が倍々ゲームで高騰してきています。こうした状況で潤沢な資金を持つ大手企業と真っ向から勝負するのは、私たち中小にとっては難しい。では、どうすれば生き残っていけるのか。私たちはその答えが既存のスタッフ、特にアルバイトからの正社員登用にあると考え、採用方針の舵を大きく切りました。採用の7割を目標に取り組んでいます。
実はかつて私が現場の店長だった時代には、アルバイトスタッフの中から「社員になりたい」という声が自然と年に2、3名はあがっていました。しかし組織が大きくなり、現場との距離が生まれるにつれて、そうした声が聞こえなくなってしまっていました。なぜ声が出ないのかを考えるうちに「引き上げる人がいないんだ」と気づきました。それならば、会社として意図的にその機会を創出しよう、と。
――御社ではいったんやめていた「全社ミーティング」を復活させたそうですね。どのようなねらいからですか?
「働き方改革」で労働時間の短縮が求められ、そのしわ寄せが「教育」の時間に及んでいます。弊社でもここ数年は教育やミーティングに十分な時間を割くことから目を背けてしまっていました。しかし、それでは人は育たないし、よい組織風土も生まれない。
そこで、全社員・全アルバイトスタッフを対象とした月1回の「全体ミーティング」を、給与が発生する労働時間として復活させました。「このミーティングに出られない方は、申し訳ないですがうちの会社には合いません」と、これから入社する方にもはっきりと伝えています。
――そこまで徹底される理由は?
組織としての一体感やよい風土を確立するためです。全員が会社の目指す方向を共有し、当たり前の基準をそろえることが、組織を強くすると確信しています。
ミーティングでは会社のビジョンや目指す世界観を伝え、参加者自身のスキルアップにつながる「問題解決能力」を養うワークショップに力を入れています。たとえば覆面調査(ミステリーショッパー)の結果から自店舗の課題を抽出し、「なぜ目標スコアに届かなかったのか」「どうすれば改善できるのか」を全員で考えます。
自分たちの店の課題を、自分たちで発見し、改善策を考え、実行する。この経験は、将来彼らがどんな道に進むとしても必ず役立つスキルになる。もし採用面接で「私はアルバイト時代に、主体的に店舗の問題解決に取り組んできました」と語れる人材がいたら、私なら絶対に採用したいですからね。
振られる覚悟で内定を通知
――全社ミーティングを通じて、参加スタッフにはどのような変化が見られますか?
全社ミーティングを始めた当初の参加率は60%程度でしたが、回を重ねるごとに徐々に上がってきています。今の若い世代にも「なぜこれをやる必要があるのか」という目的や背景を丁寧に伝えれば、理解し、行動してくれるのだという実感があります。
ミーティングでは各店の取り組みシートを発表します。アルバイトであっても自分たちのアイデアが店の運営に反映され、実際にスコアが改善されたらその成果がミーティングの場で共有され、賞賛される。このサイクルをくりかえすことで「やらされ仕事」が「自分ごと」になり、「楽しい」に変わっていく。それがさらなる主体性を引き出します。店が好きになれば、自然と会社にもよい感情を抱いてくれるようになると期待しています。そうしたエンゲージメントの高い状態のアルバイトスタッフから、正社員への道筋をつけていきたいと思っています。
――社長自らがアルバイトスタッフと食事に行く会も実施されているそうですね。
これまで、スタッフの教育は部長やマネジャーに任せていました。しかし、会社の想いや熱量は、どうしても伝言ゲームになるなかで薄まってしまう。特に会社の未来を担ってほしい人材には、トップの口から直接、想いを届けなければならないと感じ、この会を始めました。
月に1度、選ばれたアルバイトスタッフと私で食事に行きます。これは、私からの「根回し」の場でもあるんです。会社の魅力や将来性を伝え、その場で「いつでもうちの社員になれるよ」と、いわば合格通知を出してしまう。断られてもいいんです。アクションを起こさなければ何も始まりませんから。100人に声をかけて、3人でも振り向いてくれたら大成功。常に「振られる覚悟」でアプローチしています。
――すでに社員である方向けにはどんなことをされていますか?
月に1度、会社が費用を負担しての全体食事会や全社表彰式、社員旅行、バーベキューなど頻繁にイベントをして社内のタテ、ヨコ、ナナメのコミュニケーションを深めています。積極的な取り組みを始めてから、現場の空気感に変化を感じています。そこで私は参加者の表情を見ているのですが、うまくいっているチームは、やはり雰囲気が明るく、スタッフの表情も生き生きしている。逆に、雰囲気が悪い店舗はすぐにわかります。これらのイベントは組織の状態を確認する「答え合わせ」の場です。何か問題の兆候があれば、すぐにマネジャーと連携して介入できる体制を整えています。
ES(従業員満足度)アンケートも力を入れています。ESのような定量的な仕組みと、こうした定性的な観察を組み合わせることで、組織のコンディションを常に把握するようにしています。
セカンドキャリアを当たり前に。誰もが長く輝けるステージを創る
――社員が長く安心して働ける環境づくりとして、セカンドキャリアの構築にも力を入れているとうかがいました。
私は2代目ですが、創業者が築き上げた土台の上に、社員が安心して長く働けるためのインフラを整備するのが私の役目だと考えています。たとえば20年勤続してくれた功労者が50歳、60歳となったときに、あと20年現場の最前線に立ち続けるのは体力的に現実的ではありません。
そこで、現場を退いた後も輝けるステージとして、セントラルキッチンを設けました。現場での立ち仕事は難しくなっても、仕込みなどのクローズキッチンでの業務であれば、年齢を重ねても十分に活躍できます。また、結婚や出産でフルタイム勤務が難しくなった女性社員にとっても、働き続ける選択肢になります。
弊社では労働時間が長くなるためランチ営業は敬遠していたのですが、新たにセントラルキッチンを活用したハンバーグ業態でチャレンジを始めました。これが軌道に乗れば、「ランチタイムのみ」という新しい働き方も生まれます。社員一人ひとりのライフステージに合わせて、多様なキャリアパスを選べる会社にしていきたいです。 ――一度退職されたOB・OGの方々との関係構築も始められたとか。
――一度退職されたOB・OGの方々との関係構築も始められたとか。
退職して3カ月後、1年後といったタイミングで、OB・OGを招いて集まる機会を設けています。いわゆる「アルムナイ」ですね。
一度外の世界を見た上で、「やっぱりスマイルリンクルがよかった」と戻ってきてくれるケースがあれば、これほど嬉しいことはありません。彼らは私たちの会社の文化やオペレーションを熟知していますから、まさに即戦力です。一度は離れても、つながりを大切にし、いつでも戻ってこられる関係性を築いていきたいと考えています。
聞き手:坂本貴志・岩出朋子
執筆:飯田一史


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

