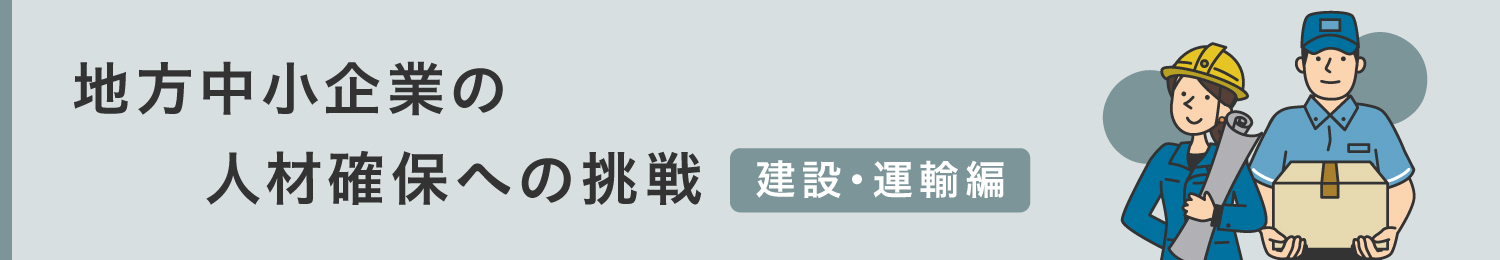
従業員第一で業界の悪しき慣習を変え、それでも変えづらい部分は隠さず伝える――株式会社長崎地研
どの業界にも長く「当たり前」とされてきた慣習がある。だがそれが従業員の長時間労働や心理的な負荷につながり、離職の要因になっていることも少なくない。長崎県佐世保市に本社を置く地質調査、ボーリング工事を行う株式会社長崎地研は、現場に根付いた“当たり前”を見直し、従業員第一で業務慣行を刷新している。2024年4月に代表に就任する以前は自らも雇われ社員だったという村山泰治社長は「自分が社員だったらイヤだと思うようなことをしない」。この方針のもとで、勤務時間の扱い、案件の選別と発注者との交渉、そしてクラウドツールを使った業務効率化を進めてきた。
 株式会社長崎地研
株式会社長崎地研
代表取締役社長 村山 泰治氏
従業員が不満を抱く業界の慣習を見直し、正当な対価を支払う
――多くの企業が人手不足に直面しています。採用・定着、属人的な要素に過度に依存しない業務づくりという観点からの取り組みを教えてください。
当社では従業員が働きやすい制度を地道に整えています。たとえば建設業では当時まだ珍しかった完全週休2日制を2020年ごろには導入し、残業時間はできる限り正確にカウントし、支払っています。特に労働時間管理に関しては、長距離移動を伴う現場出勤が多い地域事情を考慮し、移動時間を労働時間として扱い、手当として反映するなど徹底しています。この業界では「現場に朝8時に集合するには移動に1時間かかるのに、その分は労働時間にノーカウント」という慣習があったのですが、弊社ではそこを抜本的に見直したのです。
――導入の経緯は?
当時、現場への早出出勤に対して疑問を持った社員からの提案を、幹部である部長陣、当時の先代の社長が受け入れ導入されました。今は長距離現場の場合は出発から勤務扱いにする運用を整え、申請すれば時間外として手当を付与できるよう社内ルールを明文化しています。
私は今の会社で経営に携わる前、ある住宅系の大手メーカーに10年ほど在籍していました。その間に働く環境がよい方向に激変していく様子を目の当たりにしてきました。大手企業が働き方を抜本的に変えているのですから、採用力の劣る中小はもっとドラスティックに改革しなければ従業員は定着しません。こういった経験が、経営者として「組織は変えることができる」「旧来の『当たり前』だと思われていた慣習であっても変えられる」という感覚にもつながっていると思います。
敬遠されそうな情報もオープンにしてミスマッチを減らし、定着率を高める
――「働く側にうれしい制度」は、実際に働いてみる前の段階の採用広報では伝わりづらい面があると思います。どのように外部へ伝えていますか。
高卒採用の機会は地元の金融機関やハローワーク、地元の採用媒体主催のものなどいくつかありますので、それをキャッチしてまずは学校の先生や生徒に会ってお伝えしています。
また、求人媒体にはできるだけ細かく書き込みます。高卒採用ならハローワークの求人票を丁寧に作り込みますし、大卒向けには民間の求人広告の媒体に詳細を記載します。高卒採用では学校の先生の紹介力も非常に大きいです。ですから、必ずお会いして制度や実態を説明し、ご理解をいただくようにしています。
それから、採用プロセスの一環として職場見学というかたちで、オフィスだけでなく、実際の作業現場等を必ず見てもらうようにしています。

――よい点は伝えやすいですが、厳しい点・デメリットはどうされていますか。
代表である私が面談・面接に出席し、よいことだけでなく厳しい側面も事前に必ず話しています。入社後のミスマッチを避けるためです。たとえば、山間部などの厳しい条件の現場があることや、稀に不規則な勤務時間になることが発生することなど、考え得るマイナス要素を率直に伝えます。
正直に話すと「思っていたのと違う」と辞退されることもあります。ただ、それはそれでいいと思っています。知らずに入社して、思っていたのと違ったと早期に辞められると企業と従業員の双方にとってマイナスですから。現状を正しく理解した上で応募・入社してくれた人たちの定着はよく、そちらのほうが重要です。
私は4代目ですが、かつては時代背景もあり「とにかく採用できればいい」と、会社のよいところだけを強調する傾向がありました。その頃は入社後にギャップを感じたことが理由での離職もままあったと聞いています。
採用人数自体はそこまで多くはないですが、3年以内の離職率に限ればここ5~6年ほぼゼロで推移しています。ここからも、透明性の高いコミュニケーションの効果はあると見ています。こうした効果もあって、現在弊社は従業員数が30名弱ですが、10~20代が約10名と若い人材を十分に採れています。
――業界的には「若い人が来ない」「すぐ辞める」と語られているなか、御社は若手の比率が比較的高く、定着していると。若い従業員が長く働くことを選びたくなる職場にするために意識している点を教えてください。
くりかえしになりますが「自分が社員だったらイヤだと思うようなことをしない」。ほかの事例としては、弊社では長らく、掃除などを目的に「定時」より30分から1時間程度前倒しされた出社が習慣化していました。しかしこれも「極端な早出は不要で各自のペースで定時までに出社すればよい」と伝えています。
あるいは原則的に完全週休2日とはいえ、現場の事情で休日出勤が必要になる場合があります。その際は振替休日を取らせ、休める体制を組むため余剰人員を確保できるよう意識と体制を改革中です。また、同時に無駄な残業や休日出勤が発生しないよう、生産性を上げたり、作業工程を適正化することも部長陣と共に意識を高く持つよう言い続けています。逆に、必要な残業や休日出勤はきちんと申告してもらった上で認めるようにしています。必ず休まないといけないということもストレスになりかねませんから。

従業員の負荷軽減の必要性を説明することで、クライアントから解決策の提案も
――従業員第一の実現のために、案件の選別や発注者との交渉も見直しているそうですね。
当社は地質調査や鑿井(さくせい)工事等のボーリング、特に大深度のボーリングの技術で評価いただいています。温泉掘削やワイヤーラインといわれる工法を伴う案件では全国から引き合いがあります。ただしこうした案件は労務負荷が極端に大きく、長期出張や長時間労働が発生するケースがあります。以前は主力事業として積極的に受注してきましたが、従業員の負荷を考えると再考が必要と感じ、社員負荷が大きい案件は額が大きくとも、基本的に慎重対応、場合によっては見送りとする方針を打ち出しました。
――売り上げが立っても受けない場合がある、と。発注者側の反応は?
意外と理解していただいており、ありがたく思っています。弊社の考えや事情を率直に説明すると、「ではこういう条件ならどうか」と代替案を考えてくださる発注者さんもいらっしゃいます。こういった反応は弊社にとっても目からウロコが落ちる体験でした。そうか、包み隠さずこちらの考え方と具体的な人員計算を共有することによって、発注者側も現実的な調整を検討してくれることがあるんだな、と。対話を通じて単純に「請ける/請けない」の二択ではない、第三の解が見えることを実感しています。
「新しいものに触る」を当たり前にすることで、時代に取り残されない組織を作る
――建設業の中小企業では昔ながらの紙とエンピツで事務処理を続けているところも少なくない印象がありますが、御社のIT・デジタル化、クラウドツールの活用について教えてください。
全従業員に会社支給スマホを配布し、勤怠はスマホで打刻できるようにしました。情報共有はGoogle WorkspaceやLINE WORKSを併用しています。紙中心だった稟議はスプレッドシートで運用し、購入希望品目・金額等を入力、関連見積もりはクラウドストレージ(ドライブ)に格納、決裁欄に承認印(丸)で発注可としています。私もクラウド上で定期的にチェックしていますから、確認次第すぐチェックを入れて進めてしまいます。最近は簡単なRPA(ロボットによる業務自動化:Robotics Process Automation)の利用も試みています。シンプルですがこういったちょっとしたツールでも、仕事のスピードは劇的に上がりました。履歴もしっかり残りますし、業務効率化に大きくつながっています。
また、ツールの導入自体も重要ですが、「新しいものを触ることに慣れる」という意識改革も大事だと考えています。そこから新しい効率化の糸口が生まれますし、「よくわからない」とか「うちは古い業界だから」で済ませていると、世の中が激変したときに振り落とされかねないからです。そういうことは社内で常々言っています。これからもその時々の新しい技術を活用しながら生産性高く仕事を行う体制作りを進めていきます。
聞き手:坂本貴志・岩出朋子
執筆:飯田一史


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

