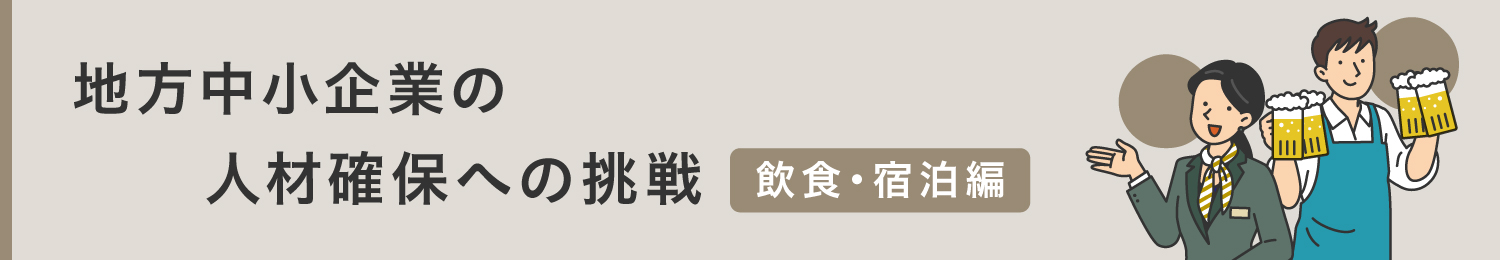
離職率4.2%を実現した「総支配人が1年間直接指導を行う」新人育成法――株式会社当間高原リゾート・ベルナティオ
ホテル業界では多くの企業が採用や定着の難しさに直面している。そんななか、新潟県十日町市のリゾートホテル「ベルナティオ」は、業界平均を大幅に下回る離職率4.2%を実現、毎年12名前後の新卒採用を継続している。かつては縦割り組織で業績も低迷していたホテルを、いかにして従業員が輝き、顧客から愛される場所に変えたのか。新入社員は全員1年間総支配人室に席を置き、総支配人が直接指導するといった独自の人材育成法とその背景にある考え方を、前総支配人で現在T-BOX代表の佐野智之氏に訊いた。 T-BOX代表 佐野智之氏
T-BOX代表 佐野智之氏
(前・株式会社当間高原リゾート ベルナティオ 統括総支配人)
縦割り意識を解体するために「部長の全シャッフル」を行う
――ベルナティオに着任された当時の状況から教えてください。
私は2014年にベルナティオの総支配人として着任しましたが、着任当時のベルナティオは稼働率43%と低迷し、組織は典型的な縦割り構造でした。従業員のあいだには自分の部署が最優先であるという空気感もあり、部署間の連携がとれていませんでした。さらに、特定の経験豊富な社員が「自分にしかできない仕事」を抱え込み、業務がブラックボックス化していました。
――そこからどのように改革を?
着任してすぐに行ったのが、部長職の全員シャッフルです。長年同じ部署にいた部長たちを、経験のない部署へ異動させました。当然、大きな反発がありましたが、このくらいドラスティックなことをしないと染みついた縦割り意識は解消できないと判断しました。
結果として組織の風通しは劇的に改善され、部署間の連携も生まれ始めました。この改革を皮切りに、お客様に提供する価値の向上と単価アップに取り組み、2年半で稼働率を77%まで引き上げることができました。
新入社員は1年間、総支配人の直属の部下
――力を入れられているという人材育成に関して教えてください。
人手不足が叫ばれるなかで多くのホテルが陥っているのが、「早く戦力にしたい」という思いからスキルばかりを優先的に教えてしまうことです。しかし、仕事への向き合い方、マインドが整っていなければ、いくらスキルを身につけても職場の人間関係の悩みなどがあるとすぐに辞めてしまいます。
私が着任するまでのベルナティオもそうした課題を抱えており、育成の仕組みを根本から変えることにしました。
――具体的には?
最大の特徴は、新入社員が入社から1年間、総支配人である私の直属の部下になることです。現場の上長に任せるのではなく、組織のトップが責任を持って、社会人としての土台となるマインドを教え込みます。
もちろん、ずっと総支配人室にいるわけではありません。普段は各部署で研修を行いますが、あくまで籍は総支配人室にあり、私が直属の上司として彼ら一人ひとりと向き合います。他社さんでは「総支配人と話したことがない」という若手や、支配人が管理職としか話さないことも少なくないようですが、弊社では私から積極的に現場の若手の話をよく聞くようにしています。また四半期に一度は必ず全ての新入社員と1on1面談を実施し、悩みや困っていることに耳を傾けています。
――総支配人が直接、新入社員全員と向き合うのは大変な労力だと思います。
毎年12名スタッフを採用していますから、全員と面談するのに2日はかかります。「よくそんな時間がとれますね」と言われますが、私は逆に「新入社員をないがしろにして大丈夫なのか」と問いたいです。PCとにらめっこして目先の売り上げや利益といった数字を追うよりも、人と対話し、コミュニケーションをとることにこそ、より多くの時間を投じるべきだと思っています。総支配人が現場の若手と直接対話することで、彼らの小さな変化にも気づけますし、研修を受け入れる各部署の管理職にもよい緊張感が生まれます。「総支配人が見ている」となれば、いい加減な指導はできませんから。
2年生が1年生を指導。「教えない」コーチングと「指導者向けマニュアル」
――入社1年目の研修や育成の具体的な流れは?
入社後の最初の3週間は、徹底的に理念についての教育を行います。担当するのは、専門のトレーナー資格を持ち、研修経験やセミナー講師としての実践が豊富な私の秘書です。ここでは、挨拶のお辞儀の角度といった形式的なマナーよりも、「なぜ感謝の気持ちが大切なのか」といった心の部分を重視します。
また、若手を見ていると、できる同期と自分を比べて落ち込んでしまうことがよくあるんですね。ですが「同期はライバルではなく仲間なんだから、劣等感を抱く必要はない。お互い得意なところで支え合おう。誰かが困っていたら助けよう」と伝え、チームワークを育んでいます。
この3週間が終わると、レストランやフロント、客室清掃など、ホテル内のさまざまな部署をローテーションで回り、実地研修に入ります。
――現場での指導体制は?
現場での新人の直属の上司には、入社2年目の先輩を付けています。一番年齢が近く、1年前の自分の悩みや不安を理解できる2年目の人間が指導役(レポートライン)となります。
新人は毎日研修レポートを提出し、1週間分がたまると、2年目の社員がそれに具体的なフィードバックを書き込みます。そのレポート全てに私が目を通し、必要に応じて私や秘書が1年生、2年生双方にアドバイスをします。この仕組みによって、現場任せにせず、育成の質を担保しています。
――指導する側の2年目のスタッフも大変そうですが、うまく機能しているのでしょうか。
私たちは「指導者向けの業務マニュアル」を非常に細かく作り込んでいます。このマニュアルは教える側が誰であっても指導内容がブレないようにするためのものです。
ただし指導の基本スタンスは「教える(ティーチング)」ではなく、「本人に考えさせる(コーチング)」を徹底しています。「あなたならどうする?」と問いかけ、本人の気づきを促す。そのやり方自体をマニュアルに落とし込んでいます。しっかりとした型(基準)を身につけた上であれば、自分のオリジナリティを発揮してもらっていいと伝えています。でも、「型なし」で好きにふるまうのはダメだよ、と。この順番が大切です。
離職率4.2%の秘密は、人を育てる文化への信頼
――手厚い育成が、低い離職率や継続的な採用成功につながっている?
そうですね。人を大切に育てる文化が定着したことで、全体の離職率も現在では4.2%まで下がっています。
採用面でもよい循環が生まれています。特別な採用活動をしているわけではありませんが、地元の専門学校などの先生方が「ベルナティオに行けば、大切に育ててもらえるから」と理解してくださり、優秀な学生さんを推薦してくれるようになりました。評判が評判を呼び、人が集まる好循環が生まれています。
――人材育成に悩む多くの経営者へメッセージをお願いします。
多くの企業が、うまくいっている会社の「やり方」や「仕組み」だけを真似しようとしますが、それではうまくいきません。大切なのは、それらを運用する人間の「あり方」、つまりマインドです。
まず取り組むべきは、従業員満足度の向上だと思っています。「サービス・プロフィット・チェーン」という考え方がありますよね。従業員が幸せで、誇りを持って働ける環境があれば、おのずとお客様へのホスピタリティは高まる。その結果として顧客満足度が上がり、最終的に売り上げや利益につながっていく。この考え方が全ての基本です。
目先の利益を追うのではなく、まずは一番身近な従業員と向き合い、彼らの成長に投資し、従業員が満足して働ける環境を作る。遠回りに見えるかもしれませんが、それが持続的に成長できる組織を作る方法だと考えています。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

