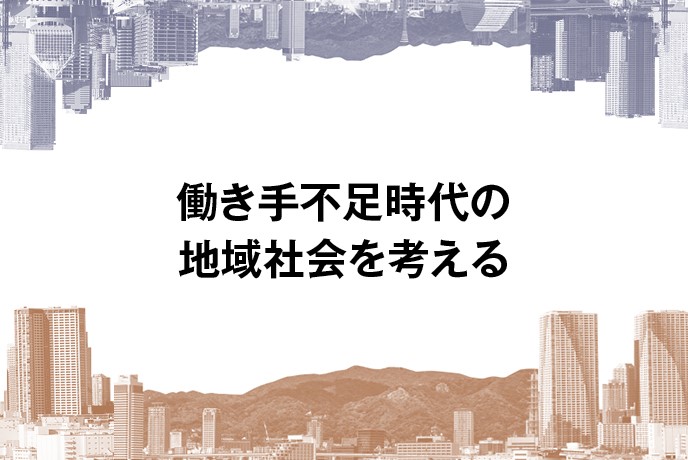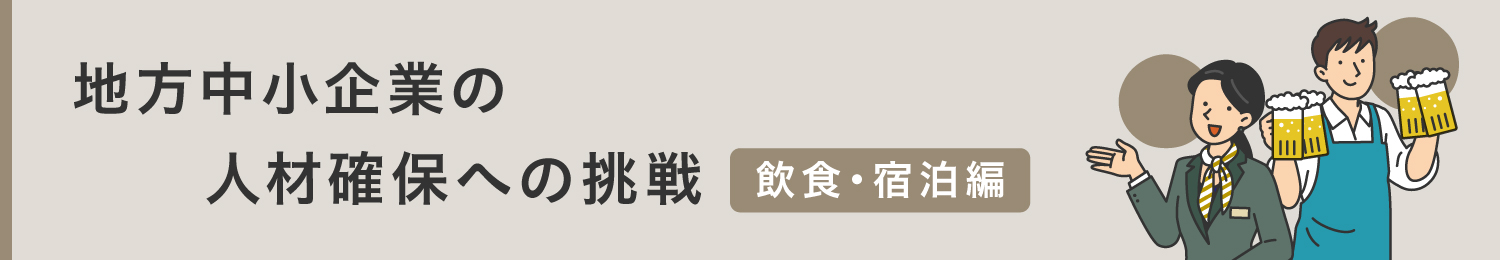
事業の選択と集中で労働環境が改善 新卒採用者の3年離職率は1割を切るまでに低下――志戸平温泉株式会社
岩手県花巻市で老舗ホテルを運営する志戸平温泉株式会社は、2018年に戦略を転換。宴会・婚礼など複数あった事業を個人客の宿泊に絞る再編を行った。その結果、資源の集中によって利益率が改善、業務に余裕が生まれ従業員の働きやすい環境が実現したという。人材育成のためブラザー・シスター制度なども積極的に取り入れる代表取締役社長の久保田剛平氏に話を聞いた。
 志戸平温泉株式会社 代表取締役社長 久保田剛平氏
志戸平温泉株式会社 代表取締役社長 久保田剛平氏
バブル期の拡大路線を引きずり現場が慢性的な人手不足に陥っていた
――志戸平温泉株式会社の事業について教えてください。
志戸平温泉は1830年創業、今年で195年を迎える中小企業です。事業内容はホテル旅館業で、客室173室の大型リゾート「湯の杜ホテル志戸平」と客室26室の「游泉志だて」の2施設を運営しています。私は実家の事業を継いで2022年に社長に就任しました。従業員は正社員154名、パート28名の計182名(2025年7月現在)。正社員中心の雇用形態は昔からになります。
 湯の杜ホテル志戸平
湯の杜ホテル志戸平
――2018年に事業転換された背景と経緯を教えてください。
当時、大型ホテルの「湯の杜ホテル志戸平」に課題がありました。大型ホテルのため、昔から売り上げ重視の経営を行っており、バブル期から本格的に拡大路線に入ったのですが、団体客、宴会、婚礼、法要、日帰り客、個人客と多角的な顧客を相手に事業を行っていたため、現場が慢性的な人手不足に陥っていました。中抜けシフト(1日の勤務時間中に一時的に業務を抜けるシフト)もとり入れ対応していたものの、変則的なシフトで休みも取りづらい環境では接客の質が上がりませんし、従業員の定着率も上がりません。それでも稼働率を上げるために価格を引き下げて量をとろうとしていましたが、数をこなすことに精いっぱいで、それが原因で長時間労働になったり、サービスの質が下がったりと、悪循環に陥っていました。過去の負債、世相とのずれによって経営状況も厳しくなっていため、拡大路線を改め、今ある施設を使って経営のクオリティーを上げる必要があると考えました。
「事業の選択と集中」から、婚礼、宴会、団体利用などの事業をやめ、粗利率の高い個人のお客様の宿泊に特化させる戦略転換を行いました。結果として、売り上げは若干シュリンクしましたが、利益率が改善しました。従業員数は維持し、外注していた清掃業務も内製化するなどしてコストを減らし、利幅を増やすことができています。
事業再編により労働環境が大幅に改善
――近年のコスト増もある中で利益率を改善できたのはすばらしいですね。従業員の働く環境はどう変化しましたか。
固定残業を廃止し、労働時間に対する意識も上がったことで、サービススタッフの残業時間はほぼなくなりました。調理スタッフの残業はまだどうしても出てしまいますが、全スタッフの平均で月5~6時間と以前に比べ大幅に改善されています。また、中抜けシフトもなくし、通しのシフトに変えました。休みも以前は週休2日をとってもらえないこともありましたが、年間105日とれるようになり、年間20日の有給休暇消化率も50%超えと向上してきています。設備投資をし客単価を上げたことで、給与とボーナスもここ2〜3年で少しずつ上げることができています。
労働環境が改善できたのは、事業を絞ったことで現場に余裕が生まれたことが一番大きいです。働きやすい環境になったことでサービスの質も上がり、お客様からのアンケート結果も如実によくなっています。お客様に体験価値を感じていただくことで単価を維持できる、そして増えた利益を従業員に還元する。いいサイクルができてきていると実感しています。
――単価を上げるためにはどんな付加価値をつけたのでしょうか。
従来の「低価格で勝負する老舗の総合ホテル」から「渓流リゾート」へとコンセプトを変え、設備投資として2020年から全館リフォームを行いました。最初に着手したのは宴会場です。それまでのメイン宴会場を、ビュッフェ会場に改装し、食事場所をそこに集約することにしました。個人のお客様のペルソナとして定めた「7歳と3歳のお子さんを持つ仙台在住の35歳の女性」に喜ばれる体験を考え、森をイメージした空間で、解体ショーや時間限定のデザートイベント、お子様へのワゴンサービスを行うなど、テーマパークのようなエンターテインメント性の高い食体験の提供を目指しています。ただ綺麗にするのではなく、ターゲットとコンセプトの入れ替えを図ったわけです。期間限定のイベントなどはその都度ひと手間がかかりますが、事業を絞ったことでリソースをさくことができています。
その後ロビー、ラウンジ、客室と順にリフォームを行い、渓流リゾートというコンセプトを体現するデザインに刷新しました。
 改装したビュッフェ会場
改装したビュッフェ会場
直近3年の新卒採用者の離職は10%を切るまでに
――経営戦略を抜本的に変えるには、従業員への説明などプロセス面で難しいこともあったのではないでしょうか。
宴会や婚礼の営業を頑張ってくれていた従業員たちにとっては、反発を覚えることも当然あったと思います。今後のビジョンやその目的も説明しましたが、正直納得できない部分は残っていたと思いますし、それは当然とも思います。一方で、「新しいことにわくわくする」というマインドで引っ張っていってくれる従業員もいました。婚礼をやりたくて入社した従業員も、人を喜ばせたり感動させることは、違う形でも提供できると発想を変えてくれて。特に若い従業員は思考が柔軟な人が多かったですね。とても心強かったです。
――従業員の平均年齢は40代とお若いですよね。
毎年10名ほど新卒採用を行っていて、今は定着率も高いので若い人の割合が増えて平均年齢が下がってきている状況です。2024年の新卒の定着率が88.9%、2023年は100%でした。ここ3年の平均定着率は90%を超えています。
――新卒の採用や定着率に悩む企業が多い中、とても高い数字ですね。コロナ禍でも新卒採用を継続されていました。
旅行割引キャンペーンなどで客足に波があり、人手は必要でした。また採用は何より継続が大事で、ストップするとあとあと響いてくるものです。人数の調整はあっても採用は途切れず行うのが基本的な方針ですね。
新入社員が入ることで、若手社員が仕事を教える側の立場になり、それが貴重な成長機会になるという側面もあります。わが社ではブラザー・シスター制度を取り入れていて、若手社員がトレーナーチームを組み新入社員の定期的なフォローアップと育成を行っています。新入社員の不安を解消することはもちろんですが、若手が成長すること、仕事の楽しさややりがいを感じてもらうこともねらいの一つです。
――新卒の採用状況改善のためにしていることはありますか?
弊社は地元のお客様が多く、ここ数年は実際に泊まって楽しかったから応募した、という学生も増えています。高校・大学を卒業して地元で就職を考える際に、「あのときの体験がよかった」と思い出してもらえるようです。今は、たくさんのお客様を喜ばせる中で、我々の未来の仲間になる人がいるかもしれない、という意識を従業員全体で共有しています。
社長に就任したときに、従業員が同じ方向を向けるように「従業員ハピネス」という理念を制定しました。ビジョンを共有し、みんなでベクトルを合わせることで仕事に意義ややりがいを感じられる。私の肌感覚としても、働く環境づくりにつながっていると感じています。
195年の歴史を振り返ってみると、廃業の危機も何度かありましたが、その都度、その時々で働いていた従業員や、地域の皆様に支えられて困難を乗り越えてきました。それは今も変わらず、従業員があってこそ会社が成り立っているので、一番近くの人が幸せに働く会社にしたい、それを理念として言葉にしています。
――今後の経営戦略や方向性は。
戦略を転換させてサイクルが回り始めたところなので、まさに次のビジョンを考えているところです。今は、ホテルを地域のメディアにして、ここに来ると土地の魅力や人の魅力が感じられる場所にしたいと考えています。人手不足の時代で、地元の人が県外に多く出て行ってしまう中、地域の人と一緒にエリア全体、業界全体のイメージを高めていきたいですね。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ