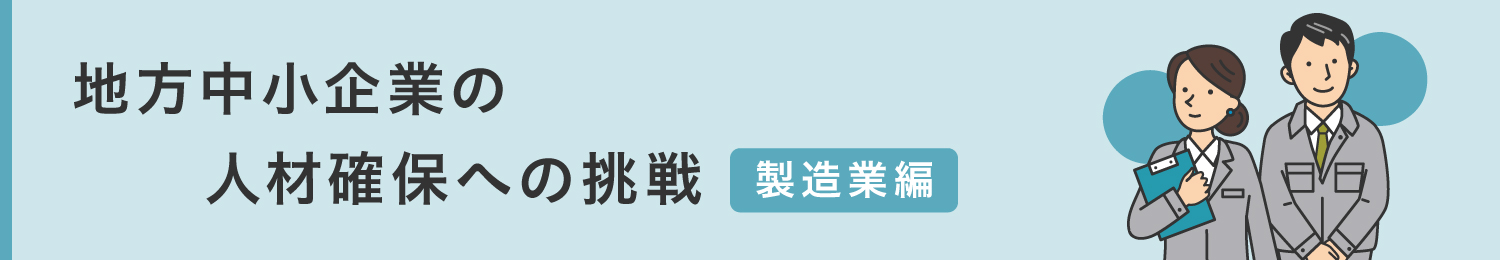
“休みが多い会社”で選ばれる。町工場の採用を変えた「年間休日137日」――株式会社フジイ金型
人材確保や定着に悩む製造業の現場で、年間休日を大幅に増やす取り組みが注目を集めている。「休みを増やして生産性を上げる」「多能工化で従業員のキャリアアップにつなげる」。愛知県の金型メーカー「フジイ金型」のそんな挑戦が、若手人材の応募増や従業員の成長や定着を促している。コロナ禍に一時帰休を実施した逆境を逆手にとり、年間休日137日でも売り上げや給与水準を維持できる画期的な勤務体制を敷いた藤井寛達社長に話を聞いた。
 株式会社フジイ金型
株式会社フジイ金型
代表取締役社長 藤井寛達氏
「年間休日137日」が若手応募の決め手に
――年間休日を137日に増やした取り組みを教えてください。
2022年5月から年間休日137日に移行しました。それまでは年間休日119日でしたが、休みを18日増やして週休2日が週休2.5日ほどになりました。営業部門は土日休みに加え、平日も半休がとれます。工場部門は「6稼4勤(ろっかよんきん)」といって、月〜土曜日の6稼働日のうち4日勤務するシフトを隔週で組んでいます。週4日出勤、週5日出勤が交互にくる勤務体制です。法律に従って年次有給休暇も最低5日間は取得してもらうので、年間で最低でも142日が休日です。有休を10日間取得し年間147日休んでいる従業員ももちろんいます。
――取り組みのきっかけは。
一つの理由は2020年のコロナショックです。受注が前年比約20%減、一時的には半減近くになり、一時帰休を実施せざるを得なくなったときに課題が発生しました。製造業の現場では毎日の経験の積み重ねによって手が早くなります。そのペースが崩れると気持ちの面でも取り戻すのが難しく、生産性が下がってしまうのです。2009年にリーマン・ショックの影響で受注が激減したときも、一度落ちてしまった生産ペースを戻すのに苦労した経験があります。その反省から、休みが増えても通常時の生産性を維持する働き方を模索した結果、一斉に休むのではなく、月〜土で出勤日をずらす「6稼4勤」にたどりつきました。それまで休みだった土曜日もシフトに入れることで稼働日が増え、1日あたりの出勤者数が少なくなるため、1人が複数の業務を行う「多能工」で生産性を上げる。それを仕掛けました。
――従業員からは土曜に勤務することや、多能工化への抵抗はありませんでしたか?
工場部門は月2回ほど土曜日が出勤になるので、反対する従業員もいました。「休みは増えなくていいから、今まで通りに土日休みを維持してほしい」と。一方、休みが増えることや平日休めることを喜ぶ従業員もいて、さまざまでした。勤務体制の変更については、私自らが各部署を回って丁寧に説明しました。休みが増えること、結果的に単位時間あたりの給料が増えること、あとは多能工とセットにして「新しい仕事を覚えるチャンスでもある」とポジティブな側面を伝えていきました。同時に人事制度も多くのポジションをこなせる人を重宝する方向性で、評価シートを改訂するなど評価制度を変更しています。
――時間数に関してはいかがでしょうか。休みを増やしたことで、残業時間が増えたりしなかったのでしょうか。
所定は1日8時間勤務のままで、休日数の増加に応じて勤務時間の合計も減っています。残業時間も当初は増えることを予想していましたが、意外に変化はありませんでした。元々残業しない従業員は新体制になっても残業せず、毎月30時間申請する従業員は30時間申請のままです。残業時間に関しては仕事量との連動というよりも、時間を増やして給料を増やしたいのかそうではないのかなど個人の志向やライフスタイルが反映されている面が大きいと感じます。
――休日数を増やしてから、採用に変化はありましたか?
採用が難しくなる中、休みの多さはアピールできると考えて、募集要項にも「年間休日137日」と明記しました。実際、最近は「休日が多い会社だから」と応募してくる若者が増えています。多能工については採用のネックになっていると感じることはありません。未経験者の場合、まず一つ業務を教え、数カ月から1年様子を見ながら次の業務を教えるといったステップを踏むので、自然と受け入れられるようです。
省力化と人材育成で「1日あたり30分」の効率化を実現
――今後の方向性として、週4日勤務を増やす予定はありますか?
意識としてはありますね。ただ各部門のリーダーにこれ以上休みが増えると現場が回らないと言われていますから、ハードルはあります。
年間休日を119日から137日に増やすとき、月単位、時間単位とスケールを変えながら検討しました。月単位では「20.5日勤務」を「19日勤務」に1.5日減らす。時間単位では12時間、週あたりだと3時間、1日にならすと約30分の短縮です。「1日30分くらいなら効率化できる」と考えました。無駄な打ち合わせはしないとかそういうことでできることはいくらでもあります。人間は時間があると思うと無駄な仕事もしてしまう側面があります。だから私は無理やり働く時間を奪ったのです。そうすると自然と効率化が行われますよね。
ただ、人間の努力だけでは限界があるので、省力化のための設備投資もセットです。そうした取り組みの中で、さらにあと1日30分減らすことができるかどうか、検討の余地はあります。
――省力化に効果のある設備とは、どのようなものでしょうか。
徐々に設備を大きくしています。大きなサイズの金型は需要があり、それを製作する大きな機械を買うと、小さい材料なども一度に乗せられるので生産性向上、省力化にもつながります。新しい機械を導入するときは多角的に検討しますが、少ない人数で生産できるような省力化はよく見るポイントです。
あとはマネジャーたちの能力が大事なので、町工場としてはめずらしいかもしれませんが、教育にかなりお金をかけています。小さなゴール目標を設定して、目標とのギャップがあれば現場とコミュニケーションをとって課題を解決する。そういう能力は現場に欠かせません。
――OJT以外では、どのようにマネジメントの訓練をされているのでしょうか?
OJTも大事だと思っていますが、50歳前後の幹部層5名と、30代前半〜40代前半のヤングマネジャー層10名に対しては、それぞれ毎月3時間ほど外部講師を招いて研修を行っています。必ず課題を出してどう解決するかをひたすら繰り返す。毎月それだけではつまらないので、読書会を開いたりして人間力を向上させるような取り組みをしています。マネジメント研修に年間1000万円近くかかっていますが、人材育成はそれだけ大事だと思っています。最初は私自身が経営大学院で学んだことを直接教えていたのですが、素人ですし、社長が社員に教えるのでは関係性がフラットではないので難しい。自分と目指すところや感性が似ている講師に任せました。教育の効果はしっかり出ています。実際に、研修を始めて従業員と私に共通言語ができ、意思疎通が非常に楽になりましたので。
「多能工化」で休日増と売り上げ維持を両立
――従業員数については、過去から少しずつ増えていますか?
2020年のコロナショックのときが約80人で、いつか受注数も戻るだろうと80人前後をキープしてきたのですが、ここ最近はやや減っています。退職者が出たらその都度中途採用をして補填してきましたが、ここ半年は退職者がいても人を増やしていません。新卒採用は継続して行っていて、私自身がいろいろな大学とパイプを作って採用できる道筋をつけています。
――売り上げの変化は長期的に見ていかがでしょうか。
コロナ前が最高売り上げの16億円で、現在はその前年あたりの14億〜15億円を維持しています。労働時間を減らし、従業員も少しずつ減る中で売り上げが横ばいなので、生産性は上がっていると言えます。多能工化したことや設備投資の効果が大きいですね。多能工は言葉の響きは難しく聞こえるかもしれませんが、以前から「単能工で1つの仕事しかできないと、仕事量が減ったときに『ここ1週間暇でやることがなかった』という状態になって無駄が出る」と思っていました。星野リゾートさんも、1人の従業員がフロント業務も調理補助もベッドメイキングもするマルチタスク運営ですよね。そうしたことで人件費抑制をされているのを参考にした部分もあります。
省力化などを通じて、女性・高齢者の採用に注力したい
――今後はどういった方向に舵を切っていかれる予定でしょうか。
女性従業員を増やしたいと思っています。現在の女性従業員は14人で、工場部門の配置は2人。町工場は油仕事、力仕事のイメージで応募者がほとんど男性ですが、女性が応募してくれればターゲット層が2倍になります。どうしても筋力・腕力が足りない面は、補助できるような設備や道具を準備すればいいと思っています。また女性が働きたいと思えるような清潔感のある職場にする努力も必要です。一番はトイレが大事だと思い、女性社員にヒアリングして女性用トイレを全てきれいにして、全個室に鍵をかけられるプライベートボックスも設置しました。あとは平均寿命が伸びているので、高齢者が働きやすい環境を整え、今後はシニアの採用も増やしていきたいですね。
聞き手:坂本貴志・岩出朋子
執筆:杉本透子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ