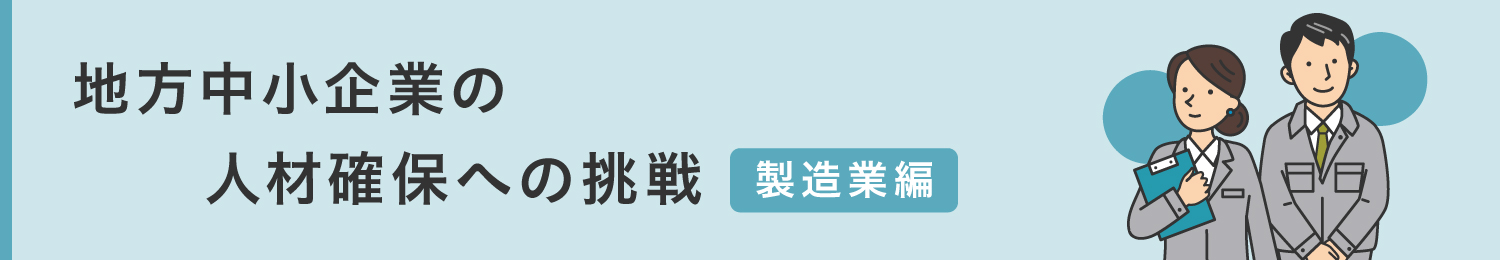
給与レベルを大幅にアップ。待遇面の大胆な改善で人材確保を図る――有限会社榮真
製造における「マザーツール」とも呼ばれる金型は、自動車や半導体、電子部品、医療機器、玩具、建築などの大量生産において欠かせない存在だ。この金型で量産品を作り上げるのがプレス加工である。金型を扱う板金業界は、近年自動車産業をはじめ各種産業の需要増に伴い、業績は堅調に推移している。一方で、深刻なのが人手不足だ。板金業界において板金技術の熟練度は非常に重要であるが、その技術を持った人材が減少しており、需要に対して供給が追い付かない状況が続いている。人材確保に向けて有効な施策を進めている有限会社榮真取締役の野田雅也氏にその取り組みを聞いた。
有限会社榮真 取締役 野田雅也氏
成長企業からの受注増で売り上げが堅調に推移するも、人手不足で全ての受注に対応できない現状
――最初に事業の概要や従業員の体制についてお聞かせください。
当社は、熊本県和水(なごみ)に拠点を置く製造工場です。金型・プレス・溶接加工の事業を展開する、いわゆる板金業を営んでおり、金型から製品製造まで一貫して行えるのが強みです。バイクや農機具などのパーツの金型作製から製造、溶接、加工、一部カーポート、門扉レールなど建材の部品加工なども行っています。大手企業との取引も多く、製品の品質の高さも当社の優位性となっています。従業員数は40名(内パート2名)、管理職が4名、残りが現場の作業員ということになります。当社の定年は63歳ですが、定年を超えて働いている従業員が14人で35%が高齢の方になります。
――受注の動向や人材の過不足感についてお聞かせください。
おかげさまで、受注に関して言えば順調に推移している状況です。しかし、業務量に対して人が足りない、生産能力が追い付かないというのが現状で、全ての注文に対応できていません。肌感覚として4~5年前からそのような状態になっています。売り上げベースで、3年前と比較して20%以上向上していますが、人員は40名前後でずっと推移しており、変化がありません。受注が増えてもモノを作らなければお客様から対価を得られませんから、人材の確保をいろいろ検討・模索しながら進めているところです。
――売り上げが増えてきている背景にはどのような要因がありますか。
20~30年前ぐらいは板金メーカー、加工メーカーがひしめき合っていましたが、だいぶ数が減って、競合の仕事が流れてきている状況はあると思います。また、当社と取引させていただいている主要なお客様が大変好調で、成長を続けています。元々は小規模なメーカーでしたが、次第に規模を拡大されている状況です。当社がビジネスモデルで何か大きな変化を遂げたというわけではなく、お客様が成長していくに伴って、当社に多くの発注をいただいているということです。
――人材獲得の難易度という観点では、ここ数年の変化はありますか。
人材の獲得はかなり厳しいものになっています。スキルがある人や若い人たちを、当社のような小規模な会社で確保していくのは、かなり苦しいところがありますね。最近もあるメーカーに勤める溶接のスキルを持つ人をスカウトしたのですが、結局勤務中の会社から条件面で上回る提示をされたということで断られました。ある程度経験がある中途の人材は市場にもう出てこないのが現状です。
そこで最近始めたのが高卒者の採用です。業務の特性上、危険な作業を伴うため、作業に慣れている経験者を採用するというのが以前から会社の基本的な考え方としてありました。昔は人材が多かったのでなんとか採用できていましたが、今はそのような環境ではありません。ですから高卒の人材を採用して育てていく方向に舵を切ったわけです。
不要な支出を徹底して精査し経費を圧縮したことで、月18万円から月28万円へ給与を大幅アップ
――人材確保に向けてどのような施策を進めていますか。
大胆な待遇改善に踏み出しました。休日に関しては設備の稼働率も考えなくてはなりませんから大きく増やすのが難しい状況です。したがって、待遇改善は給与に焦点を当てました。近年の売り上げ増によるもののほか、社内の経費管理の一斉見直しを実施して不要と思われる支出を圧縮し、そのぶん、従業員に還元しようと考えたのです。その結果、たとえばスキルのある正社員で月収18万円だったのを、28万~30万円に引き上げました。管理職では倍以上になっていると思います。 ――大幅な給与アップに踏み切った背景にあるお考えをお聞かせください。
――大幅な給与アップに踏み切った背景にあるお考えをお聞かせください。
中途の応募者を容易に獲得できない状況の中で、今いる従業員に転職されるのは避けたいわけです。当社は人の入れ替わりが激しいわけではなく、昔からいる人がコアになって、長く勤めていただいている比率が高い会社です。かつては給与といえば「最低賃金を少し上回る水準」が基本という発想があったのですが、今の時代、それでは通用しません。機械を扱う専門的なスキルを持っていて、お客様に提供する製品の知識も蓄積している人たちを正当に評価して、当社から離れないように給与を上げようと決め、ベースを抜本的に上げたような形ですね。2024年度の労務費が 1億400万円(平均月収18.5万円/1人)だったのが今期は1億9200万円(平均月収34.2万円/1人)で 上昇率が約185%になります。大幅な給与アップになりましたが、元々それぐらいに相当する従業員のパフォーマンスはあったと思います。
――月18万円から28万円というのは、大きな決断だったと思いますが。
この給与アップを考えていた時点で、すでに高卒採用の構想がありました。高卒を採用するためにそれなりの金額を提示しなければならないなかで、それが今いる従業員のレベルよりも高いと顰蹙を買ってしまいますよね。月18万円から28万円のアップというのはスキルがあり長く勤めている人が対象です。入社したばかりでスキルが低い従業員であれば、18万円を21万円にアップするといった感じになります。管理職に関しては、今まで20万円だった人を40万~60万円にしました。月給60万円の場合、ボーナス込みで年収840万円になります。昼休憩にコンビニに行くと求人が出ていたりするのですが、以前の給与では、「これだったらコンビニで働いたほうがいいのではないか」となりかねません。そんな危機感もあって大幅給与アップに踏み切りました。
ロボット導入による生産性向上、工程短縮化の取り組み。多能工化や工程平準化、ノウハウの共有を推進
――売り上げが伸びている以上、同じ人員で現場を回すには負荷も高くなっていると思います。新たな取り組みがあれば教えてください。
そこは日々検討している課題です。特に設備関係ですね。工場にはプレスのロボットや溶接のロボットを導入していますが、さらに省人化を図るため生産能力の向上に向けて協働ロボットの導入を検討しています。ただ協働ロボットは部品をセットしたりという形で人の作業の一部を代替するもので、必ずしも即省人化にはつながりませんが、全体の生産能力を増やすという点では有効だと思います。また工程の短縮は、常に追求しているテーマの一つ。たとえばある製品を作るのに7個金型があるとします。それぞれを1つのプレス機に乗せて加工していかないといけませんが、工程を見直すことにより、2つの金型を1つに集約することが可能な場合があります。これによって、プレス機のワンストロークで2個加工できることになります。そうなればプレス機を6台に減らすことができるので、仮にそれを1000個作るのであれば7000回プレス機を作動しないといけなかったものが6000回でできます。このような取り組みを、以前からずっと続けています。
また、受注の考え方も少し変えています。これまでは受注をいただければある程度低い金額でも請けようという考えでしたが、近年では利益が出るものに絞って受注するようにしています。たとえば新しい発注があった場合は、人件費等の高騰分はしっかりと見積もりに反映させ、ある程度高めのコストを提示するようなケースも増えました。結果として取引につながらないことがあっても、それはそれでよいと考えています。 ――人の活用という点では、どのような取り組みを進めていくお考えですか。
――人の活用という点では、どのような取り組みを進めていくお考えですか。
当社の業態は、プレスならプレスだけとか、溶接なら溶接だけというように、専門分野に特化している人たちが多いのが特徴です。しかし最近は、対応できる幅を増やす多能工化や工程の平準化を進めています。工程の平準化というのは「この人しかできない」という属人化を潰していって、誰でもできるようにするということです。もちろん、ベテランとしては自分の仕事が奪われるという危機感もあるので、衝突することもあります。そんなときは、「もしあなたが病気で倒れたらどうするのですか?」「もしその業務が止まったら誰に迷惑がかかるのでしょう?」と説得し、納得していただくしかありません。
加えて重要なのがノウハウの共有ですね。何か現場で不具合が起きた際や困りごとがあるときなど、解決ノウハウを持っている人に話を聞くのが一番早いですよね。現状ではそうした知見が、その人たちしかわからないような状態になってしまっている。そういう状況をなるべく潰していきたい。みんなが対応できるように言語化するとか、データ化してすぐ見られるようにするとか、いろいろ方法はあると思っています。
――そうなると、従業員間のコミュニケーションが大切になりますね。
それに尽きると思います。お互い言葉の使い方一つ間違えただけで信頼関係なんて簡単に崩れてしまいます。こまやかな気配りだったり気遣いだったり、お互いの関係が大切ですよね。日頃からコミュニケーションを密にして関係性を築くことで、相手の受け取り方も変わってくると思います。私たちはロボットじゃなく、お互い人間同士です。単に業績がよければいいというものではない。私自身、ベテランに修理のやり方を教えてもらってそのコツを身をもって体得した上で、他の従業員に伝えるといったこともやっています。経営側と従業員や現場とのコミュニケーション、人間同士の信頼関係、それは非常に重要と考えています。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

