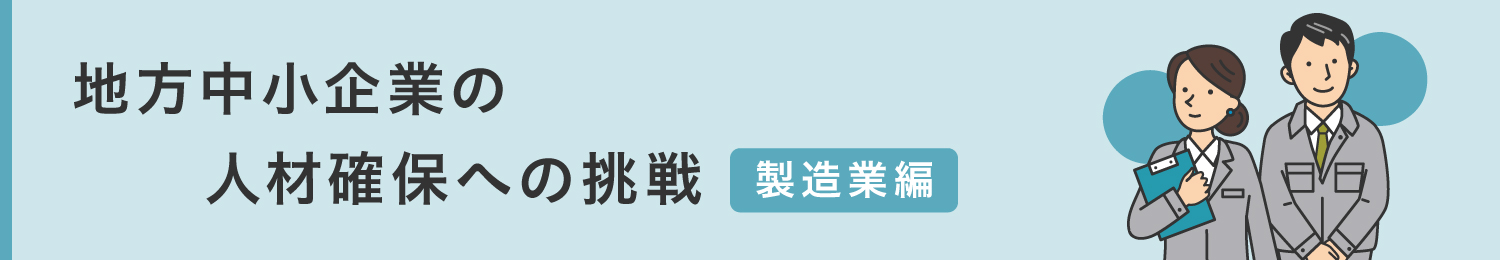
インライン検査とAIカメラで生産性140%へ ――地方企業が挑む「脱・属人化」と「見える工場」の実現 ――株式会社サニー・シーリング
宮崎県都城市(みやこのじょうし)で人材確保の挑戦を進めるのは、シール・ラベル印刷や精密スリット加工など幅広い事業を自社設備によって展開する株式会社サニー・シーリングだ。新卒採用向けのインターンシップのスピード実施、年間休日129日の挑戦、職人不足に対応するための「スマート工場」化。あらゆる方面で新しい施策を続ける社風は、社員一人一台以上のPCを、製造主要ラインの担当者にはタブレットを支給し、管理職にはスマートウォッチを配備するなどデジタルデバイスの徹底活用を土壌に育まれてきた。30年近くデジタル化を主導してきたという専務取締役の久野康之氏と、この5年ほど製造現場のDXを推進する製造部部長の外村陽一氏に話を聞いた。
 株式会社サニー・シーリング
株式会社サニー・シーリング専務取締役 経営企画室 室長 久野康之氏
製造部 部長/工場長 外村陽一氏
シール・ラベル印刷から特殊ラベル開発まで自社で完結
――創業から今までの事業の移り変わりを教えてください。
久野:創業は1982年で、小さな菓子店や惣菜店に並ぶ商品のラベルなど、ごく身近で小ロットのラベル印刷から始めたと聞いています。現社長・窪田祐一の父親である創業社長(故窪田次生氏)と、後に2代目となる創業社長の義理の弟(現会長の冨吉博文氏)、従業員2人の計4人でスタートしました。創業社長は「事業の将来性」や「地方での競合の少なさ」を重視して起業したようで、一般的な商業印刷ではなく特殊な加工をするシール・ラベル印刷を選んだのも、拠点として創業社長の妻の出身地である都城市を選んだのも、競合他社が少なかったことが理由の一つだったようです。ただ、それでも確たる勝算があったわけではなく、とにかく「やってみせる!」という意気込みだけで起業したようなもの……と、後に創業社長は笑いながら語っていました。
町の小さな印刷会社が事業拡大したきっかけは、80年代後半に大手電子部品メーカーとの直取引が始まったことです。シール印刷に使う凸版の製版技術を、電子基板へのシリアルナンバー刻印用途として提案したところ、採用されました。そこから直接の取引口座が開き、本業のラベル製品も徐々に取引が増えていきました。商業用のラベル印刷は価格競争が厳しいので、根幹事業として残しながらも、徐々に精密部品やエレクトロニクス系など工業系の仕事を増やしていきました。90年代後半には徹底して異物を排除できるクリーンルームを構え、2000年代には当時爆発的に普及していた携帯電話の液晶部材加工に参入、売上も従業員数も増え続けます。精密スリット事業、光学部材、リチウムイオン電池関連部材、医療分野向けの超低温ラベルの開発など、現在手掛ける事業は多岐にわたり、全部門にクリーンルームを配備して一貫加工できるのが強みです。今は従業員数が100人規模になっています。
起案から3カ月のスピード実施 新卒採用向けのインターンシップ
――人材採用に向けてどんな取り組みをされていますか?
久野:弊社は中途採用が8割、新卒採用は高卒者が多く、相対的に大卒の新人が少ないという社員構成になっていました。そこで、今年8月に大学・短大・専門・高専生を対象とした5日間のインターンシップを初めて実施しました。5月に宮崎大学でインターンシッププログラムを開発している先生のセミナーに参加し、「これはぜひやるべきだ」とすぐに起案。過去にも、小中高生向けの短期インターンシップやオープンカンパニーでは、「ラベルづくり体験」などをやってはいましたが、手ごたえとしては今一つと感じていました。そこで、地元のお客様で、全国に製品を販売されている南酪さん(南日本酪農協同株式会社)とのコラボレーションを思いつきました。南酪さんと日々リアルに行っている商品企画の打ち合わせに学生が参加できれば、「次こんな商品を考えている」「パッケージはこんな色で」「文字は」「サイズは」など、実際のものづくりのプロセスと、その楽しさを味わってもらえます。さらに、「デーリィ牛乳」や「スコール」「ヨーグルッペ」などで全国的に知られる南酪さんのブランド力は絶大で、学生にも知名度があり親しみやすい。また、B to C商品開発のプロである同社に、マーケティング要素も含めた講義をしていただければ、必ず学生に“響く”はず……と思いました。6月初旬に同社にご説明と打診に伺ったところ、先方から「ぜひやりましょう」と快諾いただき、話がトントン拍子に進んだ結果、6月下旬には募集開始となりました。
――BtoBの会社で学生の認知度が低い弱みを、誰もが知っているBtoCの取引先と協働することで補いながら御社の仕事をわかりやすく説明する機会にしたのですね。
久野:そうですね。弊社に対する学生の「クリーン服を着て、精密な機械を使って」といった“理系に寄ったイメージ”を払拭したいというねらいもありました。実際には一部専門職を除けば、文理関係なく遂行できる業務が大半ですが、どうしてもイメージから文系の方に敬遠されてしまうこともあるようです。インターンシップの募集パンフレットも、ミーティングやデスクワーク中の写真を採用するなど、文理にかかわらず応募いただけるように工夫しました。
――宮崎大学の調査によると、大学生の約6割が就職活動においてインターンシップを「活用したいもの」として挙げています。一方で、宮崎県内の企業ではインターンシップを実施している割合は4割未満にとどまっています。(※1)。今や人材獲得競争で欠かせないインターンシップですが、やはりコンテンツをゼロから作るのは難しいでしょうか。
久野:そうですね。やはり一定の企画力は必要ですし、簡単ではないかもしれません。ただ、当社はこれまでいろいろな新規事業やプロジェクト、展示会への出展などを、全て社内で企画し、形にしてきました。ですので、今回はテーマが「インターンシップ」というだけで、企画立案はそこまで苦ではなかったですね。ただ、担当の若手は日々の業務と並行しながら準備をしたので大変な面はあったと思います。幹部から全社的に大事なプロジェクトだということを発信したこともあり、関係者が皆、「やり切るぞ」という思いでスピーディに動いてくれました。担当者は自分のインターンシップ参加経験も参考にしながら、学生が楽しく業務体験できるよう、商品のデザインワークショップを軸とした5日のプログラムを作ってくれました。告知開始当初は思うように応募人数が集まりませんでしたが、パンフレットを持参し大学に営業に赴くなどPRに注力しました。最終的には定員を超える応募が集まるなど、非常にいい反応をいただき、無事開催の運びとなりました。今回は若手中心の推進メンバーでしたが、素晴らしい仕事をしてくれたと思っています。
全従業員にPCを、管理職にスマートウォッチやタブレット支給──徹底したデジタルデバイスの活用
――人材不足を受けた処遇改善や生産性向上に向けた取り組みを教えてください。
福利厚生はここ10年で手厚く整えてきました。完全週休2日に加え、リフレッシュ休暇を設けて年間休日は129日になっています。導入前は私たちも含め幹部社員は「生産量が落ちるのでは」と不安でしたが、振り返ってみると当時決断してよかったと思います。
――年間休日129日は多いですね。休みを増やすために生産性向上で取り組んだことはありますか?
久野:基本的にはデジタル化と自動化です。本格的なデジタル化の取り組みは20年前からで、現在、弊社はパート社員を含め全従業員がPowerPointを使えます。当番制で毎月2回、全社員の前でスピーチをする「NJ(Nice Job)スピーチ」という2005年から続く取り組みがあり、好きなフレーズやチャレンジしていることをPowerPointで作ったスライドを用いて発表するんですね。アプリの操作がわからない人がいても、周りにいくらでも教えてくれる人がいます。この長年の取り組みもあって、全従業員がPCを操作できる土壌ができました。
ここ最近はDXという名前を掲げてやっていますが、5年ほど前に「DX」という言葉を聞いたときは「これだったんだ、私がやりたかったのは」と思いました。20数年の下積みがありましたし、社長も積極推進を掲げましたので、当社にとってDXのスタートは比較的容易でした。現在は社内の全ての部屋にPC画面をワイヤレスで投影できる大型モニタがありますし、従業員100名に対して200台以上のPCがあり、工程には数十台のタブレットも支給しています。管理職以上の役職者には全員スマートフォン、スマートウォッチを貸与しています。IP電話で、世界中どこにいても内線・外線がつながります。4年前にはLINE WORKSを導入し、内線通話自体が大幅削減され、部署を超えたスピーディな情報共有ができるようになりました。個人的には、このビジネスチャットを活用した社内コミュニケーションは、その導入以前とは比較にならないスピードと生産性をもたらしたと感じています。
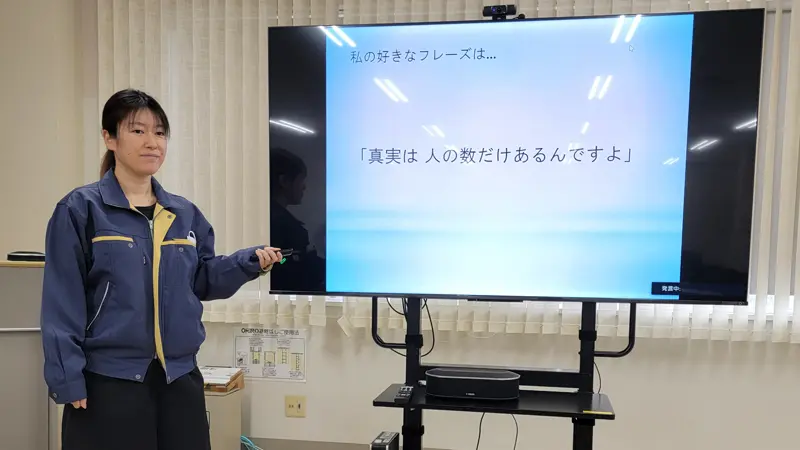 写真:20年前から始まった従業員の NJ(Nice Job)スピーチ
写真:20年前から始まった従業員の NJ(Nice Job)スピーチ
――生産性向上の取り組みで多くの企業がデジタル化を進めますが、デジタルデバイスが従業員全員には配られなかったり、アクセスできる環境がなかったりして、進まないケースは多いです。デバイスの貸与に対してとことんこだわり進める原動力はなんですか?
久野:生産性を上げるためにデバイスを増やすのは、最もコストパフォーマンスが高い方法だと思います。たとえばラベル製造を今の倍のスピードで実現しようと思うと大変なコストがかかりますが、PC作業の際に同時に2画面使って仕事をすれば、それだけで2倍の仕事ができます。もちろん、設備投資や工程改善も重要ですが、「まずは、目の前の自分の仕事の生産性を大幅に上げる」ことを、一人ひとりに実感してほしいのです。PCで、開いているウィンドウを閉じて、開いてという無駄な時間をなくせるなら、デバイス1台の値段なんて安いものです。とはいえ、200台以上となると経費を抑える工夫は必要で、うちでは状態のいいデバイスを中古で買って自分たちでメンテナンスをしています。社内でSSD(Solid State Drive:ソリッドステートドライブ)から何から全て入れ替えもできるので。ITに限らずですが、当社は「自前主義」を大事にしていて、業務効率化のアプリ制作も社内で積極的に行っています。今では、200個以上の自社アプリが稼働しています。
――ペーパーレス化も進んでいますか?
外村:2年がかりで基幹システムのクラウド化を進め、作業伝票は紙を廃止しました。これまでは何かあったときに指示書を探すのが非常に手間でしたが、クラウド上でいつでも見られるようになり、業務効率化につながっています。検索も早く、ロットナンバーを見れば生産記録がすぐにトレースできます。紙だと整理、保管の手間もあり、検索も大変です。また修正指示があれば、都度現場に伝えて、伝票の原本に手書きで修正を加える必要がありましたが、全て解消されました。ほかには、お客様からのFAX発注もデジタル化を進めています。KINTONEやクラウド系ECアプリを活用し、お客様から簡単に発注できるシステムを構築して、既存のお客様はもとより、新規の客先にも展開しています。
AIを活用し生産性を向上させる「スマート工場」化
――自動化についてはどのような取り組みがありますか?
外村:ここ3〜4年で進めているのは、インライン検査とスキルレスを核とした、DXベースの「スマート工場」化です。労働人口が大きく減る中、製造の生産性を上げていくのは、当社だけでなく製造業の必須課題です。当社は早期からDXに取り組んでいますので、このスマート工場化においてもアドバンテージがあると思っています。
インライン検査とは、生産ラインをリアルタイムチェックし、不良品を検知する方法です。これまで人による目視では、速度を上げると対応が難しく、生産スピードに限界がありましたが、検査機に切り替えたことで、その制約がなくなりました。結果として印刷機の稼働速度を高めることができ、生産性が1.4倍に向上しました。
スキルレスとは、いわば脱・属人化です。性能が高い印刷機を導入し、ベテラン職人がいなくても生産可能な環境を整える。従来の印刷機は手作業やカン・コツに頼る部分も多く、新人が完全にオペレーションを習得するのに2〜3年はかかっていました。一方、当社が選定した高性能印刷機であれば1週間で認定試験が受けられるレベルになり、3カ月あれば独り立ちができます。段取り工数も少なく済むため、1台で生産できる量も倍近くなりました。もちろん、設備を入れるだけではだめで、運用方法や仕組み含めて構築にはそれなりに時間がかかりましたが、ようやく一つの形が見えてきたように思います。
工場内の現場管理も自動化・リモート化を進めています。天井にAIカメラを設置し、10数台ある設備には報知機能のある「パトライト」というライトを取り付け、設備の稼働状況をリアルタイムでPCに知らせるようになっています。さらに作業帽を人として学習させ、23人の従業員の稼働状況もリモートで正確に把握できるようになりました。これまでは従業員が日報で作業にかかった時間を報告していましたが、誤差が出ていた課題をパトライトで解決することができました。また現場でトラブルが起きたとき、作業者が助けを求めにくい場合でも、30分を超えると自動で工場長に連絡がいく仕組みになっています。
 写真:インライン画像検査システム
写真:インライン画像検査システム
DX実装により売上が110%に増加 生産時間は減少
――スマート工場化による成果は出ていますか?
外村:効果はかなり出ていて、シール製造課では1年間で売上が110%に増加した一方、生産時間は減少しました。製造人員は1名異動のマイナス1名ながら、男性社員の育児休業を延べ126日取得の実績ができました。ここ数年間、男性の育休休暇取得率は100%となっています。生産性の改善により、想定よりも残業時間の増加幅を抑えられ、総生産時間は1年で2226時間削減しています。
――今後の戦略についてはいかがでしょうか。
久野:この2年間、オリジナルの基幹システムの刷新に取り組んできまして、今年7月から運用がスタートしました。まだ改修や運用ルールの整備と並行しての運用ですが、効果は実感しています。基幹システムは新しくなりましたが、社内にはまだまだ手作業でやっている業務も残っています。引き続き、全社的にDXを強化・推進し、経営理念である「なくてはならない企業」を目指して頑張っていきたいと思います。
(※1)宮崎大学が実施した「若者の県外流出要因等調査(令和6年3月)」によると、就職活動において活用している、または活用したいものとして「インターンシップ」を挙げた割合は、県内大学生で59.5%、県外大学生で61.6%である。一方で、宮崎県内の企業におけるインターンシップの実施状況は、「実施している」が38.6%である。
聞き手:岩出朋子
執筆:杉本透子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ