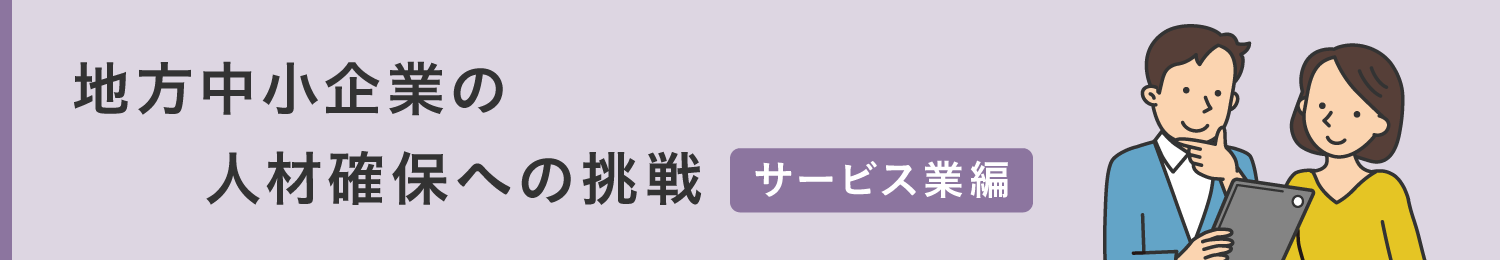
「快適に働ける環境づくり」「動画によるノウハウ継承」で長期的な勝ち筋を作る――株式会社エイコー商事
創業40周年を迎え、中古車販売を主軸に新車販売、レンタカー、鈑金・整備、保険までをワンストップで提供するエイコー商事は営業や整備人員の不足、特にベテランが退職することによる熟練整備士が足りないという課題に直面していた。これに対し、業界内では異例の「工場の冷暖房完備」や「マニュアル動画の作成・蓄積による育成の強化と省力化」など積極投資による労働環境改善と作業ノウハウの非言語的な継承という2本柱で取り組んでいる。近く2代目の代表取締役に就任予定の富川宗一郎氏に訊いた。 株式会社エイコー商事
株式会社エイコー商事
取締役 富川宗一郎氏
従業員構成と人材確保の課題
――まず、現在の従業員構成から教えてください。
当社の従業員は約80名、うち外国人技能実習生が5人ですが、今年インドネシアとベトナムから7~8名を追加採用する予定です。男女比は女性が25%、男性が約75%、平均年齢は34~35歳。職種別では営業が約20名、サポート部門・フロントを含めると30名、鈑金が10名、整備が30名、事務が10名という構成です。平均年齢は30代半ばと若いのですが、定着がなかなか難しいというのが課題でした。特に営業と整備については、相対的に人数は多いのですがスキル面を考慮するとまだまだ手は足りていないのが現状です。
――採用の状況は?
高校生を積極的に採用しています。例年、約17校にパンフレットを配り、人事担当者や店長が学校を訪問して先生方や生徒の皆さんに対して会社説明を行い、短期インターンシップも積極的に実施しています。平均すると毎年3名程度ですが、安定的に入社いただいています。
近年は外国人採用も進めています。こちらは採用前も採用後も言語の壁が大きく、定着も課題と感じています。
「楽しそうな職場だ」と感じてもらい、そこで働く姿を想像してもらうための工夫
――採用のための工夫について教えてください。
当社ではベンツGクラスを模したジムニーやレトロテイストのモデルなど、他社にはないカスタムカーを提供しています。今では絶対に買えないクラシックカーを現代のクルマで再現したものなど、「ここでしか買えないクルマ」をお客様にご案内しています。こうした事業に取り組むことは、顧客に対しては会社の存在感を高め、また、価格以外の付加価値を中古車に感じていただくことにつながります。
整備や営業人材の採用に対しては「ここで働けば、こういうものを自分で作れるんだ」「クルマを買いに来た人たちが見て驚いたり、かっこいいと言ってくれるようなクルマを売ることができるんだ」と意欲を持ち、楽しそうな会社だと思ってもらうという、2つのねらいがあります。
当社でも採用プロセスの一環としてインターンシップを実施していますが、達成感を抱いてもらえるように、参加した生徒さんにできそうな業務を自ら選んでもらい、たとえば洗車作業を体験してもらうといった工夫はしています。しかし、一般的なインターンシップの期間内では高度な鈑金・カスタム作業まで教えることは難しい。カスタム化には時間がかかるからです。
それでもインターンシップの期間内に実際にできあがった完成品を見せる、あるいは作ったり、販売したりしているプロセスを見てもらうことによって「こんな仕事ができるんだ」というイメージを持ってもらえるようにしています。
現場の仕事だからこそ、快適な環境づくりを推進して整備士を守る
――整備士の離職率低減のための環境整備について教えてください。
整備士は中途採用が多いです。当社の整備工場内は冷暖房完備、工場中央の通路を中心に工程が流れるレイアウトが特徴です。おもいきって設備投資を行い、導入しました。業界では多くの整備工場が今でも夏は暑く冬は寒い環境のままです。酷暑が常態化しているなか、エアコンすらないとなると体調を崩しますし、今ではご家族からその仕事を続けることへの理解も得られなくなってきています。このような従業員の労働環境を重視した当社の取り組みは、大きな差別化になっていると感じています。
――負荷の軽減は、今の時代には明確に求められるポイントですね。
冷暖房完備の工場には数億円単位の投資が必要ですし、ランニングコストもかかります。短期的な目線で捉えると整備・鈑金事業単体ではすぐには回収できません。ですが、そこは営業で得た利益を他部門にも還元する仕組みで負担を吸収し、また、従来は「無料サービス」としていたことにも正当な対価をいただく方向に見直しを進めています。中長期的にはこれが効いてくると確信しています。
実は中古車販売業界では近年、倒産件数が多いんです。ディーラーさんが整備士不足に直面して他社に外注するケースも増えています。そうした状況下で当社は整備士が長く働きたいと思える環境を作り、よい人材を集めて・育てていきたい。
日本では、人口は減り始めていますが、クルマの保有台数は意外と減っていません。人口1人あたりのクルマの保有台数で見れば、むしろ微増しています。今後も整備需要、中古車需要が急にシュリンクするとは考えにくい。今は負担が大きくても、将来こうした市場環境の中で生き残り、高まる整備需要を吸収できる体制を戦略的に作っています。
従業員のためにも、無料サービスや過度な値引き競争は見直していく
――客単価は上がっているのでしょうか。
部品・人件費など、物価の高騰に伴い価格転嫁を行っています。たとえば以前は車検や整備料金も激しい値引き競争が当たり前でした。しかし当社では「どこもやっているからうちも」という考えを改め、5年10年先を見据えた持続可能なサービスを目指して「正当なサービスを提供し、適正な対価をいただく」方針へ転換しています。添加剤やタイヤの性能一つとってもお客様に丁寧に説明をし、納得を得て適正単価の商品を提案することによって収益を確保しています。
ほかにも、長年実施してきたオイル交換無料サービスも、人手不足の現状では広告宣伝費と割り切るのも難しいため、見直しをしました。実はこれは年間約900万円の損失と負担が重いサービスでした。オイル交換するにも当然人手がかかるわけですが、「無料でウェルカムです」と言ってどんどん引き受けていくと、業務量が重くのしかかって目に見えてスタッフが疲弊していくんですね。これはもう厳しいな、と。
ですから従業員を守るために、できる範囲で負荷を減らし、単価を上げる。そして得られた収益を先ほど言った空調や工場内の環境整備といった従業員の環境づくりへの投資に回しています。
マニュアル動画で技術継承と外国人対応を効率化
――業務改善の一環としてマニュアルの動画化を予定しているそうですが、これはどういうねらいですか。
外国人採用を進めるなかで、日本語をある程度は理解していても細かなニュアンスを言葉だけで伝えるのは難しく、身振り手振りや擬音語を用いて補足せざるを得ないという課題がありました。そうなると、既存の従業員も教える業務に時間がとられてしまって疲弊してしまいます。熟練技術者の高齢化が進み、こうした職人が退職していくと長年蓄積してきた技術が失われてしまうという危機感もありました。そこで整備工程を映像化してノウハウを残していくことにしたのです。すでに整備や鈑金で3分程度の動画を作成していますが、まだまだ作成が追いついておらず、10本程度になっています。
――動画マニュアルの運用方法は?
当社ではノウハウ動画共有サービスを使っています。制作・編集作業には、撮影した動画をアップロードすると、その映像を自動でカットして分割し、字幕を付け、多言語に翻訳するツールを導入予定です。少しやってみてわかったのですが、人力で動画を制作するのは非常に時間がかかります。これが仕事になって業務負荷が増えては本末転倒ですから、使い勝手のよいツールとプラットフォームを選びました。
――マニュアルを動画にすることには、具体的にどんなメリットがありますか。
これまで現場では、同じ工程でも熟練者ごとにやり方が異なり、新人はどれを採用すべきか迷うことがありました。動画で標準的な手順を共有すれば、教育のブレをなくすことができます。また、紙のマニュアルは欲しい情報がどこにあるか探すのに時間がかかり、現場で参照すると汚れやすいという難点があります。動画は一元化して1つのプラットフォームに置いておけば検索しやすくなったことも利点です。外国人や若い世代は文字よりも動画で学ぶほうが理解しやすく、多言語の字幕があることで言語の壁も乗り越えやすいです。
それから、営業や整備士がお客様に車両の「ここの部分はこうなっています」とご説明するときにも役に立つなと実感しています。
――業界に風穴をあける取り組みですね。
本当に何かを成功させるためには、捨てなければならない部分があります。そこに挑むのは誰しもリスクに感じるでしょうが、当社が成功させることで、業界をよい方向に変えていけたらと考えています。 聞き手:坂本貴志・岩出朋子
聞き手:坂本貴志・岩出朋子
執筆:飯田一史


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

