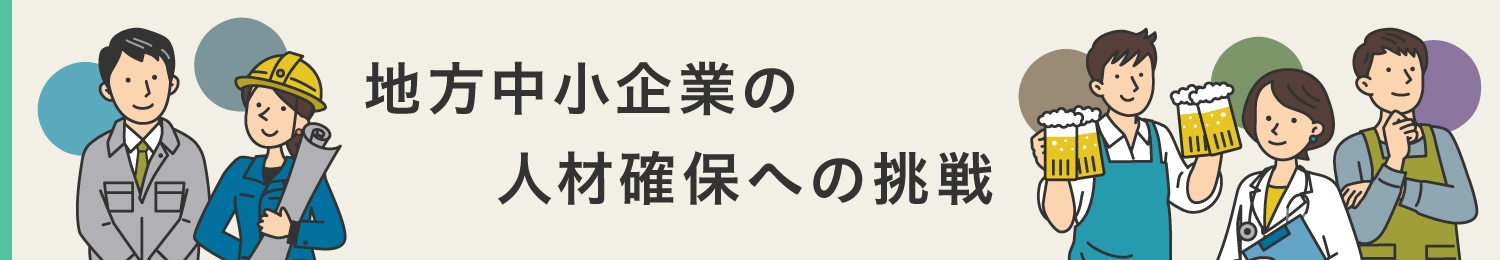
中小企業による人手不足への具体的な対応策とは(採用編)
ここまで、中小企業の取り巻く環境や人手不足への対応策についてデータを中心に概説してきた。
改めて企業は具体的に人手不足の問題に対してどのように対応しているのだろうか。リクルートが過去に行った「中小・中堅企業の事業課題・人材課題に関する調査」では、中小・中堅企業の事業責任者4,072人を対象に、事業課題・人材課題をテーマとしたアンケート調査を実施している。本調査では、「ご自身が管轄されている事業における人手不足緩和への取り組みと、その結果起きた変化について、具体的な取り組み・変化がございましたら教えてください」という設問を用意しており、自由記述形式で回答を回収している。
本回答では、企業が自ら記述した改善提案や取り組み内容がわかる。そこには現場のリアルな声と工夫が凝縮されている。これらの記述を分類・整理することで、企業が直面する課題とその対応策の全体像を明らかにし、人手不足時代に企業がとりうる人材に関する戦略を明らかにしていこう。
企業が実際に取り組んでいる採用活動の強化策は
ここではまず、企業が行っている採用に関する取り組みをまとめていこう。
採用活動の強化は、人手不足の直接的な対応策として、最も多く見られた取り組みのひとつである。採用活動を行う場合、その方法は新卒・中途採用ということになる。中小企業では新卒採用の難しさは特に深刻になっている。実際に、全国の中小企業からは「応募者が来ない」「人材確保にコストがかかる」「定着しない」といった声が並んだ。
・「新卒採用の強化に取り組んではいるものの、学生の絶対数の減少は否めない状況」
・「新卒及び中途とも求人を出しているが、求める人材は質&量とも確保できていない」
・「教育に時間を割かなければいけない状況になっている」
・「新卒対応を毎年ではなく単年度単位で実施していたために、採用活動がバラバラになって、相手先、特に高卒採用で不利に」
・「新卒、中途採用ともに採用基準を拡げたり下げたりした結果、定着率が低下した時期がある」
・「紹介企業を検討実行してみたが、適正な人材が得られる結果と費用が見合っていない」
・「エキスパート人材の採用、確保が難しく、結局他社の人材を採用した。コストもかなり上がり、業界内で批判を受けた」
・「キャリア採用を増やしたが、期待するスキルを持つ人がいない」
新卒、中途における採用チャネルの総合的な活用
このように採用活動が思うように進まない企業が増えている一方で、着実に成果を上げている企業も存在する。そのために必要な取り組みがまず「様々な採用チャネルの総合的な活用」である。
新卒採用に成功している中小企業の傾向として、継続的な高卒採用を行っていること、ハローワーク、大学や高校等との関係を強化する取り組み、インターンシップ導入などが効果を発揮したという事例があった。採用活動の継続性や地域・学校との連携など計画的な採用戦略が重要になると見られる。
・「新卒採用、主に高校卒の採用を強化し、今年度の採用数が増加した」
・「新卒採用方法に関して、ハローワーク等、待ちのスタンスから、アプローチ型の採用手法を取り入れた結果、採用成功率が上がった」
・「関連学校への積極的な訪問や新卒者の定着率等を随時報告し、新卒者の採用に成功している」
・「従業員の専門学校出身校への協力要請で応募増加」
・「新卒採用を積極的に取り組むためのインターンシップを実施 その結果希望者が増加した」
中途採用においても、採用チャネルの総合的な活用によって成果が上がったという声があった。採用成功企業は、従来のハローワークや民間の求人媒体への広告掲載に加え、人材紹介サービスの活用、リファラル採用、SNS経由の採用など多様なチャネルを活用している。
・「採用手法の多角化によって、計画通りの人数を採用することが出来た」
・「積極的な人材広告の活用をおこないました。それにより採用が活性化しました」
・「中途採用求人募集サイトを従来の業者から他社に変更したところ、短期間で人員が確保できた」
・「ハローワークの人材募集・採用に加え、人材紹介会社を通した募集・採用も行い始めている。」
・「ダイレクトスカウトの活用による中途採用の強化と給与制度の見直しを実施した、中途採用の実績は増えた」
・「社員・従業員へ声かけを行いリファラル採用を推進したところ、良い人材が集まるようになった」
・「リファラル採用とスカウト採用を強化して専門人材が徐々に採用できるようになってきている」
・「知り合いを紹介し、その人が採用試験に受かった場合紹介者は幾らかの報酬を受け取る。その結果、優秀な人材を複数人雇うことができた」
・「Uターン者の募集サイトへの登録、スカウトによる人材確保」
多様な人材の活用(女性、中高年、高齢者、障がい者、外国人、副業人材等の活用)
人材確保にあたっては、従来の新卒一括採用を中心にした採用計画のみでは対応が困難になっている。この点、従来の採用枠にとらわれない多様な人材の活用について、言及している企業も多くあった。
実際に、女性、中高年、高齢者、外国人など、背景や働き方の異なる人材を受け入れることで、採用に成功したと回答した企業は多い。かつては取り組む企業が少なかった副業についても、貴重な即戦力として受け入れを行っているという回答も散見された。あるいは国内人材の確保が難しい状況が続くなか、外国人の採用によって人材確保を図っているという企業も多数見受けられた。
・「女性活用に幅を持たせる事で可能性が広がってきた」
・「派遣会社を通じて、中途採用を行っている。定着率が高い中高年から選考しており、65歳まで継続して勤務することが期待できる」
・「副業人材の活用を始めた」
・「海外スタッフの雇用で事業拡大に繋がっている」
・「外国人研修生の活用」
・「事業拡大に伴う売上高拡大・新規事業立ち上げに中途採用の強化を押し進めたところ、既存事業部門の若手社員の離職が顕著になってきており、外国人従業員採用に舵を切ることとなった」
・「門戸を広げて外国人の雇用をしている」
人手不足の対応策としてとりわけ回答が目立ったのが外国人材の採用であった。外国人材の活用は、深刻な人手不足に直面する日本企業にとって重要な選択肢となっている。しかし、採用に成功した企業であっても、現場では様々な課題に直面している。文化的背景の違いによるコミュニケーションや価値観のギャップ、生活支援、ビザ管理、キャリアパスの提示など、採用後のフォロー体制が整っていない企業では採用しても定着しないといった課題も挙げられた。
・「外国人人材を増やした結果、社内のコミュニケーションが複雑になった」
・「技能実習制度を活用して外国人に就労してもらっているが、仕事を覚え、さあこれからという頃に、特定技能の職種のいずれかに転職するという事態が多発している」
・「国内での人材の確保が年々厳しくなっているのを肌で感じる。外国人労働者の採用と育成を行っているが、どうしても、文化の壁というのが一定数存在していて、その溝を埋めるのに四苦八苦している状態」
人材採用のためのPR強化(採用HP、SNS、動画メディア等の利用)
求職者と企業とのより良いマッチングのためには、企業と求職者とのコミュニケーションも重要である。
外部から見た企業イメージは採用力に直結する。就職希望者は企業口コミサイトやSNSで評判を調べているため、取り組み内容は隠さず公開すべきだ。先進的な働き方改革を実践し、その成果を示せば、地方の学生や女性、ベテラン技術者など多様な人材を引きつける有力な材料となる。逆に、表向きだけ改善して実態が伴わないとわかれば、SNSで瞬く間にネガティブ情報が拡散しかねない。企業は本気度を示す施策とともに、現場の声も正直に伝える見える化を心がける必要がある。
人材獲得競争が激しさを増すなか、採用ホームページ、オウンドメディア、SNS、動画メディアなどの広報手段を強化する企業が注目を集めている。以下は、自由記述から読み取れる採用広報で成果を上げた企業の声である。
・「ネットで答えがすぐ見つかる時代だからこそ、考え抜いて答えを出す経験が社会を生き抜く力になる。そうした企業姿勢を自社HPなどで丁寧に発信している」
・「人手不足解消のために自社HPによるブランディングを強化している」
・「オウンドメディアの立ち上げによる採用活動。これからの変化に期待している」
・「Instagramの活用を勧められて始めた」
・「業界全体が採用しにくい状況なので、特色を強くだしている。その結果、会社の知名度、認識度はやや右肩上がりになっている」
・「HPをリニューアルしブランド力、技術力、求心力をアピールした。 入社応募が増えた」
・「ハローワークでの求人状況で、現状の整備しないといけない HPの開設と、その他のリクルート関係を利用するにしても必要なHPの開設を早急に行う。HPがない事で求人に対しての活性化がはかれないことが分かった」
採用フェア・イベントへの積極的参加
最後に、全国の中小・中堅企業が人材難に直面するなか、採用フェアや就職イベントへの積極的な参加を通じて、打開の糸口を掴んでいる企業も見られる。採用イベントに出展するだけではなく、採用広報(Web・パンフ)の見直しとのセットでの取り組みが重要になるとの回答もあった。また、適切な広報のためには外部人材やプロの力を借りることも考える必要があるだろう。通年型・長期的視点の採用体制整備が問われることからも、地道な取り組みが必要になりそうだ。
・「就職フェア参加 採用パンフレットの見直し ホームページの改善」
・「首都圏のUターン就職セミナーへ参加させていただくようになって、優秀な人材が少し確保できるようになりました。今後も機会があれば積極的に参加したい」
・「採用活動や人事研修が出来る人材を外部から採用し、私からの指示のもと、その方に人事全般を任せている」
・「現場に業務効率化を担う社員がいないため、新規でキャリア採用活動を行なっている。内定辞退などで苦戦するも、採用広報に力を入れ始めたことで応募者数が増えてきた」

坂本 貴志
一橋大学国際公共政策大学院公共経済専攻修了後、厚生労働省入省。社会保障制度の企画立案業務などに従事した後、内閣府にて官庁エコノミストとして「月例経済報告」の作成や「経済財政白書」の執筆に取り組む。三菱総合研究所にて海外経済担当のエコノミストを務めた後、2017年10月よりリクルートワークス研究所に参画。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

