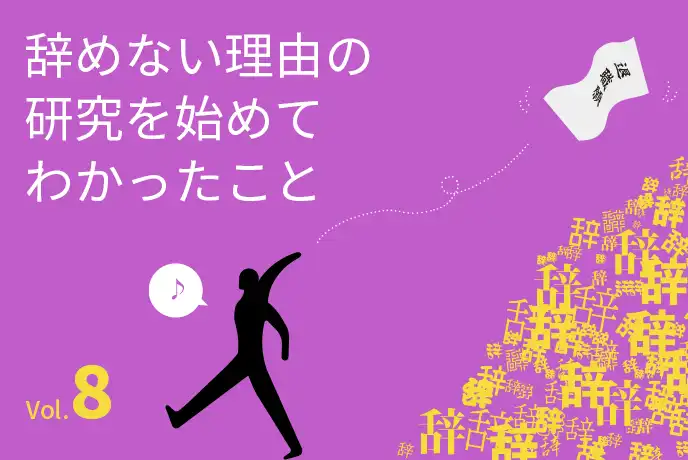「意気に感じて働く」 優秀な人材が辞めない、組織の魅力
「辞めない理由」の研究【インタビュー編】②ボストン コンサルティング グループ
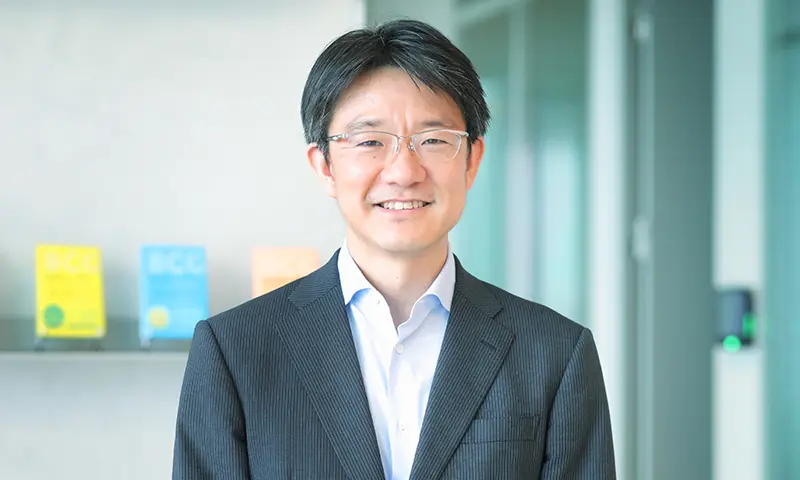 竹内 達也 氏
竹内 達也 氏
ボストン コンサルティング グループ マネージング・ディレクター&パートナー
東京大学教養学部卒業。同大学大学院総合文化研究科修士。ドイツ銀行を経て、2004年ボストン コンサルティング グループ(BCG)に入社。BCG金融グループの日本リーダー。組織・人材グループの日本リーダーを務めた経験もある。
戦略立案やトランスフォーメーションと融合した組織・人材変革の支援経験が豊富。人材戦略、カルチャー改革、イノベーション組織、パーパス(企業の存在意義)などに関する支援も数多く行っている。
経営をサポートするコンサルティングファームの立場から、人材や組織をめぐる現代企業の課題はどのように映っているのか。ボストン コンサルティング グループで金融グループ日本リーダーを務めるマネージング・ディレクター&パートナー、竹内達也氏が提示する「3層構造」の特性を掘り下げ、優秀な人材をひきつける企業が持つ強みと差別化のポイントを探った。 (聞き手:リクルートワークス研究所・古屋星斗主任研究員)
人材の過剰と不足をめぐる二極化
―大手企業を中心に、人材戦略が古くて新しい課題になっています。企業が抱える現下の組織課題についてどのように見ておられますか。
竹内:人材をめぐる不確実性や複雑性が増し、先が読めない状態にあると感じています。エッセンシャルワーカーだけでなく、高度専門人材も足りないという声を聞く一方、人材が過剰だという課題も耳にします。果たしていまは、人が足りないのか、それとも余っているのか。これは単純に言い切れる状況ではありません。組織全体としてはもちろん、部署やチームごとに人員のアンマッチが生じ、至る所で「過剰」と「不足」の問題が複雑に絡み合うなかでのマネジメントが求められています。このため、人材ポートフォリオに沿った従来の経営サポートでは対応が難しくなっています。この相反する問題をどう解消するか、悩ましい状況に直面しています。
人材をめぐっては量的な問題だけでなく、質的なスキルの面でも「経営側と社員のギャップ」が浮き彫りになっています。例えば、社員が学びたいスキルと、経営側が求めるスキルにギャップがあるケースは少なくありません。キャリア志向についても同様です。管理職は「罰ゲーム」と揶揄されるようになって久しいですが、経営側が白羽の矢を立てた社員が昇進に応じてくれないケースも珍しくありません。「働き方」をめぐるギャップもあります。自分の成長のためにハードワークをいとわない人もいれば、プライベートを重視する人もいます。個人によって求める働き方に幅があり、経営側の意向とずれが生じやすくなっています。
―こうした流れのなかで、人材マネジメントに関するウエートが増し、現場だけでは解決できず、経営課題として対処しなければいけない分野が増えている、というわけですね。
竹内:加えて、これから注視しなければならないのは「業務におけるAI活用が進むことの影響」です。5~8割の人員削減ビジョンを提示する企業もあり、社員の定性的な役割やオペレーション、あるいは組織構造やビジネスモデルも一変すると予想しています。極論すれば、人材とAIエージェントの管理の境界がなくなりつつある、とも言えます。それぞれのAIエージェントがどのような役割や権限を持ち、得意・不得意な分野は何か、といったことまで把握し、あたかも人材を管理するようなシステムの構築がすでに始まっています。つまり、AIエージェント時代の到来に伴い、組織の概念そのものががらりと変わる、というわけです。
「定着」の再定義と社内外の需給にマッチングさせる「育成」
―組織と人の新しい関係はどうあるべきなのかを考えるうえで、大変示唆に富んだお話です。こうしたなか、人材の「定着」や「育成」をめぐる組織の課題はどのように変化していると感じておられますか。

竹内:少しマクロな視点からお話ししたいと思います。弊社は昨年度、「海外投資家は日本企業の人的資本開示をどう見ているか」というテーマで調査・分析を行いました。その結果、海外の大手投資家が人的資本を非常に重視していることがわかりました。ネガティブ、ポジティブの両面からチェックし、投資判断に影響を与えています。「定着」の観点では、海外投資家は企業のリテンション(顧客や従業員をつなぎ留めるための施策や戦略)やエンゲージメント(働きがい)を重視する傾向があります。組織として蓄積した経験則や分析力が長期的な経営パフォーマンスや企業価値に大きな影響を及ぼすという判断があるからです。「育成」に関しても、企業がラーニング&デベロップメントにどれだけ投資しているのかが、投資家の長期投資の判断材料のひとつになっています。
ここから先は私の見解になりますが、従来型のリテンションからもう少し視点を広げた方が良いと思っています。「定着」という言葉からは、新卒一括採用した社員を終身雇用で囲い込もうとする旧来型の思考も透けて見えます。中途採用やアルムナイ採用など人事の多様性が進み、外注や業務提携など外部との協業も増えています。そうしたいまの時代に合う形で組織の垣根を柔軟に捉え直し、「定着」を再定義した方が良いと考えています。
もうひとつ指摘したいのが、「育成も複雑化している」という現実です。かつては5年、10年先を見据えた計画を立て、必要なスキルを持った人材を育てるのが常道でした。しかし今は、テクノロジーや地政学的な面で変化のスピードが速く、先が読めません。また、企業と個人も従来の上下関係から対等な関係へとシフトしており、会社の意向や方針に沿ってキャリアを歩む人も減っています。こうした潮流もふまえ、「育成」は組織が個人に一方的に押し付けるものではないという認識のもと、市場メカニズムを機能させつつ、外部市場のニーズと組み合わせたり、社内の各部署の需給にマッチングさせたりする方向に転換していく必要があると考えています。
―外部との協業に関しては、近年はアルムナイや内定を辞退した若者など、その会社に魅力を感じ、コミットした経験がある人たちも取り込んで「人材力」として活用していく企業が増えていますね。
竹内:そうですね。「定着」に関しては、もちろん長期在職のプロパー社員がコア人材であるという認識は維持すべきだと思います。一方で、個人に求めるスキルもどんどん変わる時代に、「定着」することにどれだけの価値があるのか疑う視点も必要な気がします。
―そこは日本の企業が乗り越えるべき視座のひとつだと思います。定着率を上げ、離職率を下げるKPI自体、機能不全に陥りつつあるようにも感じます。その文脈でいま注目されているのが、「静かな退職」です。日本はもともと、欧米の労働市場と比べてエンゲージメントが低く、「静かな退職」を選択する人はおそらく昭和の時代にも多かったと思うのですが、なぜかいま、米国から逆輸入するような形で課題視されています。日米の人材課題の相違点について、どのようにお考えですか。
竹内:たしかに、最低限しか働かない、というスタイルは以前からあったと思います。「サボる」という言葉がまさにそうです。ただ、「静かな退職」という言葉で再定義された背景には、ワークライフバランスの概念や多様な働き方が広がるなか、「仕事以外」の部分に重きを置く文化に日本がうまく適応できていない点も挙げられると思います。米国はもともと、労働市場の流動性が非常に高いため「嫌だったら辞めればいい」という価値観の素地がある。一方、日本は流動性が低く、働き方の選択肢がまだ限られているため、「静かな退職」が新たな動きとして注目されるようになっているのではないでしょうか。
ペルソナを設定せず個別性を重視する
―米国の場合、コロナ禍を経て、「静かな退職」という新たな選択肢も出てきたという流れだと思いますが、日本は違いますね。一方で、日本企業はこれまで「静かな退職者」にどう対応してきたのか。その打ち手はこれからも有効なのか。このあたりいかがでしょう。
竹内:日本企業の人事が打つ施策は全社員に通じる総合的な施策が主で、個別性はほとんどありません。つまり、典型的な社員像に基づく「ペルソナ」を設定しているのだと思います。今の若手に対しても、ワークライフバランスを重視して自律的にキャリアを磨き、転職志向が強い、といったステレオタイプ的な見方もありますが、当然ながら全員がそういうタイプではない。明確な志向や目標を持たずとも、与えられた仕事に取り組む方が働きやすく、成長も速い、というタイプの若手はとりわけ高度専門人材が集まる組織に多いという現実もあります。申し上げたいのは、個別性を重視する必要がある、ということです。
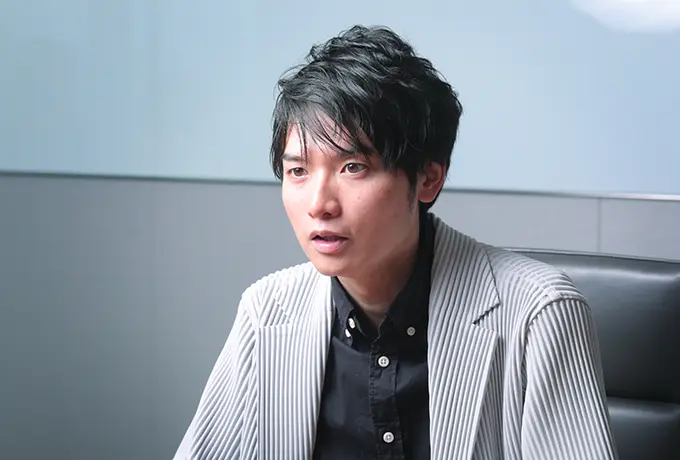
―バックグラウンドの異なる多様な人材を育てる機運が日本企業でも広がってきたことにより、個別性が極めて重要になってきていると。冒頭で言及していただいた働き方やキャリア観のギャップにも通じますね。個別性をふまえた有効な対応策を導入している企業の事例をご紹介いただくことは可能ですか。
竹内:私が知る限りそんなに多くありません。なので、弊社の例になってしまいますが……。
―ぜひお願いします。
竹内:BCGでは、一人ひとりのコンサルタントにキャリアアドバイザーをつけています。プロジェクトとは関連のない「斜め上の先輩」がつく形で、私のようなパートナー(幹部職)クラスも含め、ほぼ全員にキャリアアドバイザーがついています。コンサルタントは能力だけでなく、キャリア志向なども個別性が非常に高いので、それぞれの過去の丁寧な考慮も含め長期のキャリアをかなり時間をかけてサポートしています。
―若手に対しては「斜め上の先輩」やコーチングパートナーをつける事例は一般的ですが、竹内さんのようなパートナーも含め、アドバイザーがつくのは大変ユニークですね。
竹内:その理由はシンプルで、BCGにおけるキャリアには完成形がなく、各段階で成長が求められるため、どの社員も常にキャリアの悩みを抱えながら働いているからです。
―非常に興味深いお話です。キャリアアドバイザーは固定メンバーが務めるのでしょうかか、それとも随時入れ替わるのですか。
竹内:昇進のたびに入れ替わります。段階的にステップを上がる過程で、キャリアアドバイザーもよりシニアなコンサルタントになります。一人ひとりのキャリアをしっかり見つめ、信頼関係を築いて、その人の価値観を含めて理解し、共感し合うなかで対話を重ねていく環境が重要です。
―ヒアリングやアンケートでは意外と本音を伝えられていなかったり、正確に言語化できていなかったりしている部分もありますから、本音や真意をうまく引き出してくれるコーチやメンターの存在は大きいですね。傾聴力や共感力というソフトなスキルは重要です。竹内さんご自身もキャリアアドバイザー役を務めておられるのですか。
竹内:はい。私は今片手を超える数のマネジャーのキャリアアドバイザーを担当しています。
―負担ではないですか。
竹内:全くそんなことはありません。これは経営戦略の一環と捉え、誰もが躊躇せず時間を割きます。コンサルティング会社はとりわけ、競争力の源泉は人だけである、といっても過言ではないですから。
―日本社会全体も、「競争力の源泉は人だけ」という気構えが必要だと思います。そのうえで、若手人材を育てるために、企業にはどのような組織戦略が求められているとお考えでしょう。企業に新卒採用を続ける理由を尋ねた厚生労働省の調査では、経営の中核を担う基幹人材(コア人材)を確保するため、という回答が増えています。企業のなかでコア人材の採用が意識されている状況をどのように見ておられますか。
竹内:新卒採用でコア人材を求めるのは肌感覚として納得できます。人口減少が進み、生成AIやロボットの導入が広がるなか、定型の仕事を担う労働力や専門人材のニーズは明らかに減っています。一方、マネジャー職には組織の文化やビジネス特性に精通した人材が必要で、それは新卒採用した社員のなかからも選抜したい。このため、新卒採用した人材のなかからいかにしてコア人材を確保し、どう育てていくかは、どの企業でも必ず議論になります。
―入社後かなり早い時期から労働時間が長い若手と、全く残業しない若手の二極化も生じています。前者がマネジャー職以上になる確率は3倍ほど高く、年収もその分高くなるのですが、7年間の経年変化を追うと、年収の上昇幅は前者と後者で全く同じでした。こうした側面は、均等性や公平性を過剰に重視する日本企業の特徴が出ているようにも感じます。
竹内:その弊害は、日本企業の経営層と対話しているとよく聞く話です。個々の社員のパフォーマンスや役割に応じて待遇にメリハリをつけ、人件費を最適化したいという経営者は増えていますが、制度も運用も追いついていません。社員の心情や組織の調和を優先し、不公平感を払拭する運用に踏み切れないのが実情です。
―そうした状況はどうすれば打開できるのでしょう。
竹内:高い成果を出す人やそのポテンシャルがある人には特別に処遇することが必要です。そうしないと、外資系企業や国外、別の産業に人材が流出していくばかりになります。
社会的インパクトの強さと過剰なほどの成長機会
―人材力の高い企業の「辞めない理由」はどうなっていくとお考えですか。

竹内:とある業界で高い成果を上げる人材を対象に集中ヒアリングを実施したことがあります。そこから浮かんだのは、「辞めない理由」につながる3層構造の企業特性でした。第1層は適正な報酬水準や公正な評価システム、ワークライフバランスへの配慮、パワハラなどのハラスメントがない、といった衛生要因。第2層は職場環境の良さです。良好な人間関係、裁量・意思決定の柔軟性、豊富な成長機会、周囲に優秀な人材が多く学びの場がたくさんあるなどの要素に加え、本人の意思に応じて柔軟に働き方を調整できる、といった職場の風土も含まれます。
第2層までを全て満たす企業は数多くありますから、特に優秀な高度専門人材の獲得に向け、差別化を図るうえで重要なのは第3層になります。それは一言でいうと、「社会的インパクト」のある企業です。パーパスや長期ビジョン、あるいはきわめて魅力的かつ強力なビジネスモデルとイノベーションの方針、そしてこれらを裏付ける投資実績……。ポイントはこうした環境そのものではなく、働く側がそれらを「意気に感じる」ことにあります。これからの経営者は3層目に踏み込むべきでしょう。競争優位も加味した社員の提供価値をしっかり考える時代になっていくでしょう。
―「意気に感じる」という表現、非常に説得力がありました。ちなみに、私がいま行っている「辞めない理由」の研究では「第ゼロ層」とも言うべき現実も浮かんでいます。
竹内:ぜひ教えてください。
―日本の大企業に勤務する20~30代の正社員を対象に辞めない理由を問うと、「特に理由はない」を挙げた人が4割近くを占めました。さらに、複数回答で約3割が「転職するのが面倒だから」や「転職のコストが高いから」といった理由を選択しています。
竹内:なるほど、分かります。今は国際的に「エンゲージメント万能時代」になっていると感じていますが、いわゆるエンゲージメントの高低が業務の成果と必ずしもリンクしない人もいます。仕事は仕事と割り切りながら、非常に高い成果を上げる人は存在します。
これにはエンゲージメントの定義のブレがあると思います。規律と動機付けの両方の軸が備わった、企業の業績に寄与するコミットメントの高さが、BCGが定義する「エンゲージメント」です。そう考えると、「面倒だから転職しない」という人たちは、モチベーションはないが規律はあるタイプか、逆にモチベーションはあるが規律に欠けるタイプなのだと思います。つまり、規律と動機付けのいずれかが欠けている。弊社は規律と動機付けの両方の軸を高めることを「エンゲージメント」≒「企業のパフォーマンスを上げる」という概念として捉え、組織開発しています。
―では、御社の社員が「辞めない理由」は何だとお考えですか。
竹内:いろいろありますね。まずは先述の第3層で指摘した「社会的インパクトが大きい」こと。大企業・グローバル企業をご支援して社会を変えようと仕事に取り組んでいますから、その意義はとても大きいと感じているはずです。加えて、非常に多様かつ魅力的な成長機会は過剰なほどあります。やりがいと成長機会が大きいことによって、「その先のキャリア」もより広がり、期待がもてます。また、一人ひとりも強い個人であることが求められますが、集団としても「カルチャーの良さ」が魅力になっていると思います。
―竹内さんご自身の「辞めない理由」は何でしょう。
竹内:先の3層構造で言うと、私が大事にしているのは3層目です。第1層の制度や、第2層の職場環境も当然魅力的ですが、やりがいやパーパスを大事にしており、これまでずっと働いてきた中でクライアントを含めお世話になった人たちから様々なことを学ばせていただきました。その恩義をクライアント、社会、次世代に返したい、という思いが一番強いですね。特に、次世代の育成が今の私のモチベーションになっています。
―ありがとうございました。
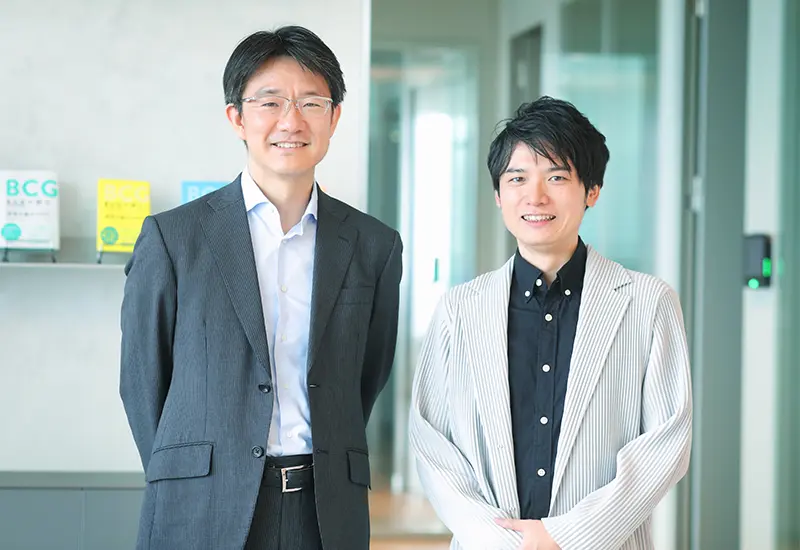 執筆:渡辺 豪
執筆:渡辺 豪
撮影:平山 諭


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ