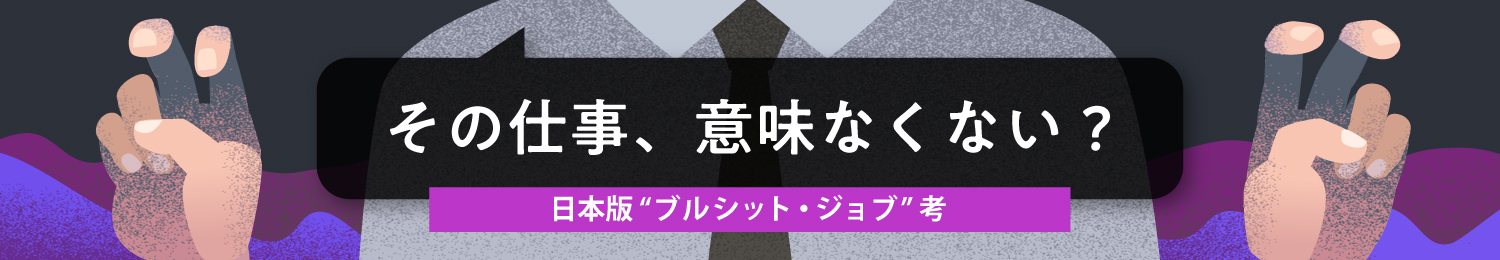
大企業のホワイトカラーに聞きました。「あなたの会社、職場には、どんなブルシット・ジョブがありますか?」
仕事に手応えが得られず、後ろ向きになっている人が多い理由。日本のエンゲージメントスコアが、世界に比して著しく低い理由。それは、“無意味な仕事”に蝕まれているからではないか? 書籍『ブルシット・ジョブ』にインスパイアされ、その実態を解明しようと、研究プロジェクトを発足。まず手始めに、私たちプロジェクトメンバーは、その実態の感触をつかむために、それぞれのつながりを活かして機縁法でのインタビューを試みた。
筆者は、自身が携わっているいくつかの事業を通じて深く交流させていただいている大手企業の執行役員、部課長クラスの方5名にお声がけし、日本の大企業ホワイトカラーの実態の聞き込みをしてみた。「あなたの会社、職場には、どんなブルシット・ジョブ=無意味な仕事がありますか?」というストレートな質問に、それぞれがそれぞれの想いを持って、問わず語りで様々な話をしてくださった。
増殖している報連相の場
「パワポ職人、エクセル職人、と呼ばれる人がいるんです」
超大手メーカーのグループ会社に長く働くAさんの話は、こんなフレーズから始まった。“無意味な仕事”と言われて、真っ先に浮かんだのが、会社内に蔓延している会議や打ち合わせだらけの実態。その象徴といえるような存在として、会議、打ち合わせ用の膨大な資料を専ら作っている人たちが思い浮かんだのだという。
「役員や事業部長クラスの人たちの予定は、ほとんどすべて会議で占められていますよね。スケジュールをオープンにしていることもあって、どんどん予定が埋まっていくんです。その大半は、報連相(報告、連絡、相談)の場。その中に必要なものがどれだけあるのか……」
なぜそのように会議、打ち合わせだらけになってしまうのか。Aさんの見立てはこうだ。「役割が分担されていて、全員がそれぞれの状況が見えない状況になっていることがベースにあると思います。大企業ですからピラミッドがかなり縦長になっていますし、エリアごとに事業を展開しているので、横長にもなっているわけです。そうした構造がどんどん複雑になっていく中で、報連相の場もどんどん増えているように思います」
日本企業には「報連相はビジネスの基本」という規範がある。報連相が個人の成長を促したり、事業創造を生み出したりするインフラになっている会社、職場が今もきっとあるだろう。しかし、本来の意味を失った報連相もたくさん生まれている。
「権限委譲ができていない、ということもあると思いますが、報連相するのが大事だ、そうしておくものだ、という規範のようなものもあると思います。私が進めていた全社プロジェクトは、社長直轄で、かなり自由にやらせてもらってはいるんですが、『あの人には話したか?』『あの人に報告しておいたほうがいい』という意見が周囲から入ってきて……こんな人に話す必要あるの?と思うケースはたくさんありました」
Aさんのコメントに類する話は、これまでにもよく聞かれたものだ。過度な報告・連絡・相談、そこに臨むためだけに量産される膨大な資料……「日本企業あるある」の最たるものだが、かねてから指摘されている「無駄な仕事」の範疇のものであり、目新しさはないように思える。しかし、話を聞いていくと、その度合いが加速度的に増しているという印象を受けた。
役員、部長クラスのスケジュールの大半がミーティングで埋められている、というエピソードは、コロナ禍でオンラインでのミーティングが中心になる中で、いたるところで聞かれるようになった。変化の度合いの激しさは増し、複雑化する案件への対処のために役割分担の細分化が進み、対面機会の減少、オンラインコミュニケーションの増加により、情報伝達の劣化が進む……話をお聞きする中で、Aさんが放った「管理職は、不安でしょうがないんでしょうね」というコメントが、ことの深刻さ、根深さを表していると感じた。
リスク回避型規範が生み出す“無意味な仕事”
膨大な資料の話は、別の方の話の中にも出てきた。日系金融機関の執行役員であるBさんは、以前働いていた外資系金融機関との対比もしながら、資料作りに関してこんな話を聞かせてくれた。
「全部の質問に答えられるように、全部入れちゃってるんですよね。たくさん何かを用意するほうが、答えられるとか安心だみたいなカルチャーがあるんです。そんなものを作らされる側は、非常にやりがいを感じない。作って終わりですから」
「複数の案やシナリオが提示されているんですが、提示する側が判断しないようにしてる。レコメンドしないし選ばない。責任回避のために膨大な資料が作られています」
Aさんの話と大きく重なるが、さらに根深さを感じさせる話だ。こうしたリスク回避型の規範や行動は、「失われた30年」を通して日本企業に深く根付いてしまっている。野田稔氏(明治大学大学院グローバルビジネス研究科教授/リクルートワークス研究所特任研究顧問)は、それを「緊急避難の常態化」と指摘する。
リスク回避型の規範は、コンプライアンスの文脈にも通じている。Bさんの発言だ。
「コンプラ部門からの要請がハードルになるんです。邪魔しているんじゃないかって感じるぐらいの保守的な見解が提示される。提案できる人がいないので、何でもかんでも『これ駄目』みたいな対応になる。この折衝には相当の労力がかかるわけですが、これも意味があるかというと……」
書籍『ブルシット・ジョブ』の著者グレーバーが「管理部門の膨張」と指摘した文脈に当たる話だ。コンプラ部門のように新たな社内勢力が生まれているケースもあるが、既存の部門からの要請が増えているケースもある。Bさんは、その典型として人事部門を挙げた。
「今、1 on 1推進月間なんですよ。全部署で一斉に実施が呼びかけられているんです。部長を兼務しているしフラットなチームなのでメンバー全員が対象なんですが、正直、やる意味を感じない」
Bさんが在籍する会社が1 on 1を推進している起点は、システム障害にあったという。その主因としてインナーコミュニケーションの劣化がクローズアップされ、社内プロジェクトで対策についての議論がなされ、その一環として1 on 1を推進することが決議された。しかし、Bさんは1 on 1を推進することがその課題解決にも、一人ひとりのモチベーションアップにもつながらないと、これまでの経験を通して実感している。
「人材開発会議に向けて、部長が、膨大なエクセルシートを作らなくちゃいけなかったり、部署の人材に必要なスキルセットの詳細なチェックシートを作らなくちゃいけなかったりするんですが、こうしたことも本当に意味があるといえるのか。こうした具体的な施策や制度ではなく、ビジョンレベルのものを共有し、浸透させていくことが必要ではないか」
数値化の危うさ
人事部門の業務への言及は、別の方の口からも聞かれた。ご自身も人事部門の部長職にあるCさんは、人的資本経営を俎上に載せて話してくれた。
「開示ですから、ポイントは数値化なわけですが、多分そういう数値を出すためだけの仕事が、日本中の人事メンバーを圧迫してるんだろうなと思っていて」
ご自身が在籍する会社では、ISO30414において掲げられている「人的資本に関する情報開示のガイドライン」のフレームを踏まえて独自のフレームを創造し、自社が業績を高め、新たなものを生み出していく上でキーとなる人的資本指標を定めて、数値化していくというオリジナルストーリーが確立されているという。しかし、多くの会社では、そのようなオリジナルストーリーが描かれてはいないのではないか、と危惧する。
Cさんは、数値化の危うさについて、ご自身が前任の部署で担当した別テーマでの取り組みも例に出してくれた。
「生産性の議論ですね。限られたリソースをどこにどう配置して生産性を高めていくか。可視化、数値化が求められるわけです。なので、みんなの工数取って、行動を書き出してもらってそれを集めて、モデルを作って……その仕事がまったくの無駄だったとは思わないんですけど、でも、それ本質的じゃないよなとは思いつつも、それ以外の方法で、われわれの業務の妥当性を示す方法がなかったんです」
「生産性も、あるいは品質の話もそうなんですが、経営からの要請が『難しすぎる』んですよ。でも、『それ数値化、構造化するのは無理だと思います』なんて言えない。これやっても意味ないよと思いつつも、それは口が裂けても言えない」
「開発部門の中で話をする分には数値なんていらない。でも、そういった共通理解を得ている人との間の会話ではなく、そうじゃない人との会話になると、数値が必要になってくる。ビジネスがクリティカルになればなるほど、勘とか『えいや』で投資をしたりゴーをかけるわけにはいかなくなるので、それを保証する心の安全性のために数字を求めるんです。疑念とか不信が根底にあって、それを払拭しようとすると、ほとんどのケースでは無駄でしかない仕事をやらざるを得なくなるんです」
野中郁次郎氏が指摘していたオーバープランニング・オーバーアナリシス・オーバーコンプライアンスというフレーズを彷彿とさせるコメントだ。そのベースにあるのは、部署間や経営と現場の「情報の非対称性」である。その非対称性を補うために数値が要求される。その数値は、往々にして本質を捉えたものになっていない可能性を大きくはらむ。膨大な資料が要求されるのも、メカニズムは同じだ。
社会からの要請という発火点
Cさんの話の起点には、人的資本の開示、生産性の向上といった社会からの要請が存在している。この例では株式市場からの要請だが、こうした要請はほかにもたくさんある。一つの典型が顧客からのクレームだ。情報通信企業の人材開発マネジャーであるDさんは、こう語る。
「お客さまからのクレームへの対応、再発防止策として、チェックのプロセスを追加するという形での解決方法を目指すことがよくあります。それがどんどん積み重なって自分たちの首を絞めていくということが起きています。追加されるプロセスも、品質を高める、ミスをなくす、という本来追求すべきところとは違って、『実施したことがわかる履歴を残す』とか『達成したことが確認できる』というようなプロセスが入り込んでしまう」
そして、同様のケースとして、労基署からの是正勧告への対応のエピソードを挙げてくれた。
「要は長時間労働を削減せよ、という勧告です。そのために、労働時間管理を強化しなさいという要望だったんですけど、その対策を講じることで、結果的に従業員が毎日労働時間管理に費やす工数を増やしてしまったことがあるんです」
このエピソードに類する話は、多くの企業で発生しているのではないだろうか。働き方改革への対応策でも、管理サイド、チェックサイドには意味があっても、大半の働き手にとっては単なる手間が増加しているだけ、という実態はそこかしこで生まれている。
「社会的責任の壁」
現代の日本企業には、さらにやっかいな社会からの要請が存在する。社会的潮流ともいえるこの要請が生み出している何とも悩ましい状況を語ってくれたのは、情報通信業で部門長経験のあるEさんだ。
「社会的責任の壁とでもいえばいいでしょうか。私たちの業界に限らないことですが、この20年で求められることがものすごい勢いで増えてきた。インターネット、SNS、情報セキュリティ、個人情報、内部統制、ガバナンス、開示、SDGs、サプライチェーンに対する説明責任……こんなキーワード、キーフレーズがどんどん出てきた。おまけに、うちはグループ会社だから、社会的な要請に対する対応が、親会社からノーロジックでどんどん下りてくる。だから、社会要請テーマの実装のサイクルがあちこちでパラレルに動いている」
「本部長クラスや部長クラスが、そういうテーマを推進する役割に追われているんです。そして、不確実性が上がれば上がるほど、定型度が下がれば下がるほどその役割が重いというか大きい。だから、こうしたテーマへの取り組みについては、プレイングマネジャーならぬプレイング本部長とでもいうような状態。まるっとコーディネートしてやりきることが求められるし、そこを何とかうまいことやる人が評価されている」
「これが常態化しているんですよね。いわば麻痺している状態です。ブルシット・ジョブが生まれる構造をしっかり埋め込んでしまった形になっている」
Eさんが示している本部長、部長は、グレーバーが提示したブルシット・ジョブ5類型の一つである「タスクマスター(他人に仕事を割り当てるためだけに存在し、ブルシット・ジョブを作り出す仕事)」と重なる。しかし、社会的責任という外圧がとてつもない力となっていてその対応に追われ、そのためにブルシット・ジョブが生まれても目をつぶらざるを得ない、という姿は、グレーバーが想定していた“悪者”のような姿とはずいぶん異なるものだろう。
功名心×プロセスエクセレンスの欠落
様々な社会からの要請という、いわば「外圧」のような存在を起点とし、縦割り、サイロ化、あるいは過度な分業がもたらす組織内の硬直化、機能不全という「苗床」によって、次々とブルシット・ジョブが生み出されていく……5名の方々の話からは、そんな明確な絵姿が浮かび上がる。このストーリーラインを、さらに解像度を高めて探索していきたい。だが、こうしたストーリーラインに乗らない話もある。その中でも何とも気になる話を、一つだけ紹介しておきたい。
それは、Eさんが提示した「外圧に振り回され、致し方なくブルシット・ジョブを生み出してしまっている本部長・部長」とは違う形のタスクマスターの存在だ。発言の主であるDさんは、功名心というキーワードを掲げて、次のような話をしてくれた。
「自分の権威をリーズナブルな形で示したいと思うリーダーからブルシット・ジョブが生まれることがあると思います。本当に必要かどうかはわからないけれど、本人のパフォーマンスや威光につながる仕事って、たくさんある気がして。功名心からそれっぽくパフォーマンスする人のほうが一見高い成果を出している人に見えてしまう、という傾向もあると思います」
大きく頷ける話だ。筆者は、実はこうした現象が、成果主義人事の浸透とともに日本企業にはびこるようになったと感じている。また、ここで掲げられているリーダーとは、部門長や部長などの上位職階に限らない。成果主義という言葉は鳴りを潜めたが、MBO(Management By Objectives=目標管理)の仕組みは多くの会社に組み込まれている。この仕組みが、「功名心からそれっぽくパフォーマンスする人」を量産しているのではないか、という懸念をかねてより強く抱いている。
しかし、本人の功名心だけでは、必要性が疑問視されるようなレベルのものが公式な仕事になってしまうことはないだろう。それを仕事とすることを承認してしまう上席者・マネジャーがいて、初めてそれが公式に担当業務としてオーソライズされるのだ。別の言い方をすれば、そのような“目利きの力のないマネジャー”が、日本企業にはたくさんいる、ということだ。外資系企業に働き、日本企業に出向した経験を持つXさんから、こんな話を聞いたことがある。
「(今勤めている会社は)プロセスエクセレンスを高めることが最上位にあるんですね。ビジネスプロセスを作っていく上でそれっておかしくない?とかそんなことして本当にそういうふうになるの?っていうところをみんなが見抜ける力を高め合って過ごしている。でも、出向した日本企業はそうじゃなかった。ハロー効果で相手の印象で物事を決め付けてしまったり施策の実効性を見抜けなかったりするマネジャーがたくさんいる。論理性とか物事を定義してそれってどういうプロセスで出すのかをきちんと説明できるのとは全然違った振る舞いが必要だったんです」
日本企業の収益性は、欧米企業に比して著しく低いと指摘されて久しい。彼我の差を示す明確なデータもある。その要因として、リスクを取らない、ローリスクローリターンな姿勢が挙げられる。もちろんそういう側面はあるだろうが、それだけでは説明がつかない、もっと根源的な組織課題があるとかねてより思っていた。Xさんの話を聞いて、これこそがその要因なのではないかと感じた。プロセスエクセレンスを高めるという意識などなく、膨大な無駄、無意味を垂れ流すことに何の問題も感じていないような人材が評価され、マネジメントポジションを占めていたとすれば、その企業の収益性が高まるはずなどない。このストーリーラインも、さらに深く掘り下げていきたい。
5名という限られた人数、機縁法という偏りのあるサンプルから得られたこうした情報をもって、日本の大企業ホワイトカラーの実態を論ずることはできない。もっと大切なピースやストーリーラインがきっとあるだろう。この領域は、今回の研究テーマの本丸でもある。引き続き探索していく。
次回のコラムでは、国家公務員にスポットを当てる。自身も元国家公務員である橋本賢二研究員のレポートに期待していただきたい。

豊田 義博
リクルートワークス研究所 特任研究員/ライフシフト・ジャパン 取締役CRO/一般社団法人エン・ジニアス 代表理事 1983年リクルート入社。数百社におよぶ企業の新卒採用戦略、広報計画業務に制作ディレクターとして長く従事。その後、『就職ジャーナル』『リクルートブック』『Works』編集長を歴任。1999年リクルートワークス研究所設立と同時に着任、人材マーケット予測、若年キャリアなどの研究活動に従事。現在は、個人の就業行動や志向・価値観の変化などを探索しつつ、若手からシニアに至るまでのキャリア支援に研究者 & 実践者として携わるパラレルワーカー。 著書に『実践! 50歳からのライフシフト術』(共著 NHK出版)、『なぜ若手社員は「指示待ち」を選ぶのか?』(PHPビジネス新書)、『若手社員が育たない。』『就活エリートの迷走』(以上ちくま新書)、『「上司」不要論。』(東洋経済新報社)、『新卒無業。』(共著 東洋経済新報社)などがある。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ