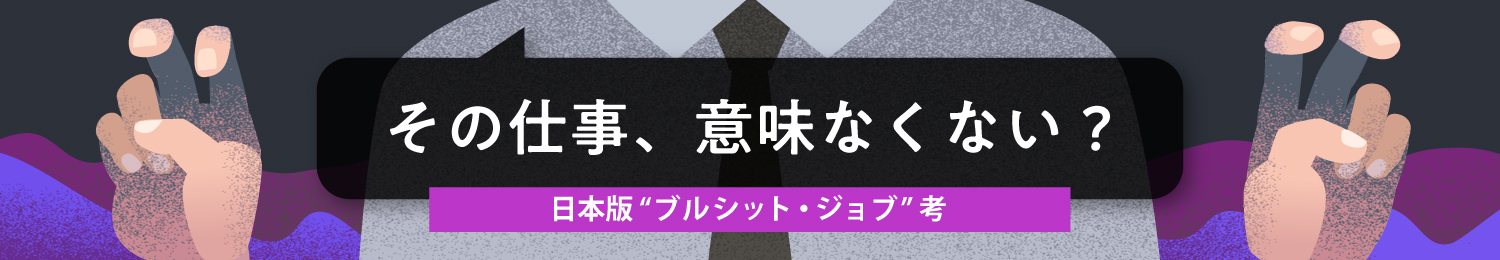
“無意味な仕事”は、なぜ生まれ、増殖してしまうのか?~日本版“ブルシット・ジョブ”研究プロジェクト発足~
仕事に手応えが得られず、後ろ向きになっている人は今も増えているのだろうか。若年を中心とした離職が増えているという声をよく耳にするが、実態はどうなのだろうか。そうした状況を改善しようと、企業サイドも様々な対応策を講じ、初任給の上昇、職場の心理的安全性への配慮などの手段が講じられているいるようだが、その効果は上がっているだろうか。もっと大切なものを見過ごしてはいないだろうか。多くの人が担当している仕事が、実は“無意味な仕事”と化していて、とても前向きに取り組めるようなものではない、といったことが起きていはいないだろうか……
どうやら、そんなとんでもないことが現実に起きているようなのだ。それも至る処で。「働く」を長年にわたって研究してきた身としては、看過できるものではない。この、あまりに悩ましく研究の俎上に載せるのも難しそうなテーマを、あえて研究してみようと決めた。本稿はその決意表明だ。
エンゲージメントスコアが低い本当の理由は?
人的資本経営というブームに乗ってエンゲージメントサーベイがこれだけ広く普及したことで、広く人口に膾炙することになったエンゲージメントという言葉。「婚約」「誓約」「約束」「契約」等の意味と並んで、「従事(没頭)している」という意味を持っている。従業員を対象に企業が行うエンゲージメントサーベイでの意味合いは、この語義から来ているものであり、「従業員と企業との深いつながりを持った関係性」という意味合いで用いられている。
そのエンゲージメントスコア、日本は世界的に見てとても低いものであることが、以前から指摘されている。エンゲージメントという概念を80年にもわたって探索し、構造化し、グローバルにその実態をリサーチしているギャラップ社の「日本の職場の現状(2024年版)」(※1)によれば、日本では、仕事に対してエンゲージメントを持っている従業員はわずか6%で、香港、エ ジ プトとともに世界で最も低い水準であり、東アジア平均(18%)や世界平均(23%)を大きく下回っている。また、世界平均のスコアはここ十数年にわたって徐々に上昇しているが、日本のスコアは低迷したままである。
ギャラップ社が定義する従業員エンゲージメントの尺度構成概念は、Q12®(※2)として広く知られている。以下が、その日本語訳である。
Gallup Q12®
Q01.私は仕事の上で、自分が何を期待されているかがわかっている。
Q02.私は自分がきちんと仕事をするために必要なリソースや設備を持っている。
Q03.私は仕事をする上で、自分の最も得意なことをする機会が毎日ある。
Q04.この1週間で、良い仕事をしていることを褒められたり、認められたりした。
Q05.上司あるいは職場の誰かが、自分を一人の人間として気遣ってくれていると感じる。
Q06.仕事上で、自分の成長を後押ししてくれる人がいる。
Q07.仕事上で、自分の意見が取り入れられているように思われる。
Q08.会社が掲げているミッションや目的は、自分の仕事が重要なものであると感じさせてくれる。
Q09.私の同僚は、質の高い仕事をするよう真剣に取り組んでいる。
Q10.仕事上で最高の友人と呼べる人がいる。
Q11.この半年の間に、職場の誰かが私の仕事の成長度合について話してくれたことがある。
Q12.私はこの1年の間に、仕事上で学び、成長する機会を持った。
「Q10.仕事上で最高の友人と呼べる人がいる」という質問は、やや過剰な条件設定に思えるが、それ以外の質問は、エンゲージメントという概念の核心を射抜いたものといっていいだろう。だが、同時に、ごくごく当たり前のことを問うていると見ることもできる。こうした質問に対する前向きな回答の比率が低いという状況は深く憂慮すべきものだ。
この12問を問い直し、職場のあり方を見直すことにはもちろん大きな価値がある。だが、この質問群には、かねてから若干の違和感を抱いていた。この質問群の大半は、職場における人のつながりに焦点が置かれている。マネジャーや同僚がどのように接しているかを問う質問が9問を占めている。その他の質問のキーフレーズは「必要なリソースや設備」「最も得意なこと」「学び、成長する機会」と、仕事に臨む上での環境やそこから得られるものを問うている。だが、回答者自身が託されている、あるいは担っている仕事そのものについての問いは一つもない。従業員エンゲージメントという概念には、その要素は含まないと定義されているのだろうと理解した上で、でも、こう思うのだ。「託されている仕事そのものに手応えを感じていなければ、このスコアが高く出るはずがない」と。
モチベーションを高める5つの特性 欠損しているのはどれか?
私は、かねてから「社会変化に伴う“一人ひとりに託される仕事の変容”が、人々の仕事に向かう意欲を低落させているのではないか」(※3)と考えている。
仕事そのものへの手応えを表す先行研究として、よく知られるものに、職務特性理論がある。モチベーション研究の系譜にあるもので、ハックマン・オルダムの理論がよく知られている。以下の5つの特性が、モチベーションを高めるための中核となる重要な特性であるとされている。
ハックマン・オルダムの職務特性モデル(※4)
- 技能多様性=職務遂行に必要な技能のバラエティ
- タスク完結性=業務全体への関与度
- タスク重要性=職務の意義・価値の認識
- 自律性=職務遂行の自己裁量度
- フィードバック=結果・成果の反響
若手社会人の仕事実態研究に携わる中で、このうちのいくつかの項目が、かつてに比べて大きく毀損されているという実態が明らかになった。その背景として挙げられるのが、仕事の細分化・仕組み化である。社会のニーズの高度化、複雑化に合わせて、業務全体は高度化、複雑化し、一つの案件に関わる人数も劇的に増えていく。そうした変化に対応し、実効性を高めていくために、分業が進んでいく。かつては関わっている人すべてと対面でやり取りしながら進めていた製品プロジェクトが、気が付くと、桁がひとつもふたつも違うような陣容となり、業務の全体像などわかるべくもないような体制になっていく。
そうした環境変化によって真っ先に損なわれるのは「タスク完結性」だ。始めから終わりまでの全体を理解した上で仕事に関わるということが難しくなってしまっている。全体像が見えなければ、自分で計画を立てたり目標設定したり、自分のやり方で進めようとする「自律性」にも支障をきたすだろう。そして、全体が見えないことで、自身がなした仕事の結果、成果についての「フィードバック」も毀損する。
「タスク完結性」「自律性」「フィードバック」が欠損すれば、仕事に臨む姿勢が受け身になるのも当然だ。外界から隔離され、情報が遮断されているなものである。担当している仕事がいかに意義・価値の高いものであったとしても、そうと認識することはできないだろう。その仕事にエンゲージ=従事(没頭)することなどできはしないだろう。
だから、ジョブ・クラフティング(社員が自分自身の仕事を主体的に捉え直し、やりがいを感じられるように、仕事の範囲や内容、関係性を変化させていく手法)というアプローチには注目し、期待していたし、この言葉が日本に流通する以前から、そうした施策の必要性を、マネジメントサイドにも個人サイドにも説いていた。
しかし、それは「タスク重要性」が担保されていればの話だ。担当している仕事の意義・価値をなかなか実感できないとしても、その仕事の先には顧客が、社会があるという前提において、だ。そして、上記の探索を行い、発信していた2010年代中盤には、それはある程度は担保されているという感触があった。だが、仕事の大元であり、最後の砦とでもいうべき「タスク重要性」が毀損していたら……そもそもの仕事が、意義も価値もない“無意味な仕事”ばかりであったなら話はまったく変わってくる。そして、そのような状況が、実はじわりじわりと広がっている。“無意味な仕事”が次々に生まれ、増殖しているのだ。
書籍『ブルシット・ジョブ』がもたらした衝撃
『ブルシット・ジョブークソどうでもいい仕事の理論』(デヴィッド・グレーバー, 2020, 岩波書店) は、まさに“話はまったく変わってくる”という悩ましい現実を突きつけるものだった。
「膨大な数の人間が、本当は必要ないと内心考え続けている業務の遂行に、その就業時間のすべてを費やしている」
「まるで何者かが、私たちすべてを働かせ続けるために、無意味な仕事を世の中にでっち上げているかのようなのだ」
「私たちが目の当たりにしてきたのは、『サービス』部門というよりは管理部門の膨張である。そのことは、金融サービス部門やテレマーケティングといった新しい産業丸ごとの創出や、企業法務や学校管理・健康管理、人材管理、広報といった諸部門の前例なき拡張によって示されている」
「こうした状況によってもたらされる道徳的・精神的な被害は深刻なものだ。それは、私たちの集団的な魂(コレクティブ・ソウル)を毀損している傷なのである。けれども、そのことについて語っている人間は、事実上、ひとりもいない」
この書籍の冒頭に再掲されている小論には、以上のような過激なコメントが並んでいる。
そして、その小論で提示された仮説を検証するためにイギリスで行った世論調査では、「あなたの仕事は、世の中に意味のある貢献をしていますか?」という問いに、37%の人がNoと回答したという。
書籍『ブルシット・ジョブ』の日本での発刊は、コロナ禍に突入して間もない時。日本人一人ひとりが「働く」と向き合い始めていた時だったこともあり、瞬く間に話題となった。お読みになった方も多いだろうし、読まれていなくてもその内容のアウトラインをご存じの方も多いことだろうが、このプロジェクトの伏線となっている書籍なので、この場でこの本の要点を簡潔に3点に絞って説明しておきたい。
-
ブルシット・ジョブの定義
被雇用者本人でさえ、その存在を正当化しがたいほど、完璧に無意味で、不必要で、有害でもある有償の雇用の形態である。とはいえ、その雇用条件の一環として、本人は、そうではないと取り繕わなければならないように感じている
-
ブルシット・ジョブ主要5類型
・取り巻き[flunkies]
誰かを偉そうにみせたり、偉そうな気分を味わわせたりするためだけに存在している仕事。
例えば、受付係、管理アシスタント、ドアアテンダント。「管理職に昇進した以上、部下をつけなければならない」と見做されて仕事もないのに雇われた人々。権威付けと序列、メンバーシップを確認するためだけにある会議体。・脅し屋[goons]
雇用主のために他人を脅したり欺いたりする要素を持ち、そのことに意味が感じられない仕事。ロビイスト、顧問弁護士、テレマーケティング業者、広報スペシャリストなど、雇用主に代わって他人を傷つけたり欺いたりするために行動する悪党。・尻ぬぐい[duct tapers]
組織の中の存在してはならない欠陥を取り繕うためだけに存在している仕事。例えば、粗雑なコードを修復するプログラマー、バッグが到着しない乗客を落ち着かせる航空会社のデスクスタッフ。・書類穴埋め人[box tickers]
組織が実際にはやっていないことを、やっていると主張するために存在している仕事。例えば、調査管理者、社内の雑誌ジャーナリスト、企業コンプライアンス担当者など。役に立たない時に何か便利なことが行われているように見せる。・タスクマスター[taskmasters]
他人に仕事を割り当てるためだけに存在し、ブルシット・ジョブを作り出す仕事。中間管理職や号令係、取り次ぎや仲介。 -
ブルシット・ジョブとシット・ジョブ
ブルシット・ジョブ=優良な労働条件であるが、無意味な仕事
シット・ジョブ=ぞんざいな報酬や処遇であるが、社会に益する仕事
新自由主義(ネオリベラリズム)という病巣
作者のデヴィッド・グレーバーは、「アメリカの人類学者、 アナキスト・アクティヴィスト」と紹介されている。2011年のウォール街を占拠せよ運動では指導的な役割を果たし、「私たちは99%だ(We are the 99%)」 のスローガンを考案したとされる。そのような姿勢が本書にも満ち満ちており、ブルシット・ジョブ増殖の大きな要因として、新自由主義(ネオリベラリズム)による改革の反動を掲げている。
新自由主義的な市場改革においては、「市場の自由化」「規制緩和」によって競争環境を整備、市場の生産性を向上させていくことと併せて「アカウンタビリティ」を高めていくことが求められるが、この一連の推進において、脅し屋や取り巻き、タスクマスター、書類穴埋め人が増えていくと指摘する。
その一例として挙げられているのが、グレーバー自身が携わっている大学教員という仕事の変質だ。シラバスや試験問題の作成を例に挙げ、経営改革が進んだ大学での手続き業務に関わる部局が増え、工数が何倍にも膨れ上がっている様を指摘する。また、アカウンタビリティ=(数量化しえないものの)数量化が、実質のある仕事のブルシット化、ブルシット部門の膨張をもたらしていると指摘する。
いずれも、大きくうなずけるものだ。新自由主義的な組織改革では、効率化や成果主義を標榜しつつ、逆に管理職や監督業務が肥大化する傾向が確かに顕著である。実際の生産やサービスに直接関与しない「管理のための管理」や、成果を数値化・監視するだけの役割が増え、現場の自律性は低下してしまう。
民間委託やアウトソーシングが進む中で、実際には不要なコンサルタントやアドバイザーが大量に雇用されるケースも増えている。彼らの仕事は、既存の業務をわざわざ複雑化させたり、意味のない提案を繰り返したりするだけの場合も多い。
また、規制緩和や民営化によって「自己責任」や「透明性」が強調される一方、それを担保するための監査・コンプライアンス部門が肥大化する。これらの部門は、しばしば実質的な生産やサービスとは無関係な書類チェックや手続きに追われ、本質的な価値を生み出さないことが多い。
独り歩きを始めたブルシット・ジョブ
しかし、多くの人たちが感じている「この仕事に、意味があるのだろうか」というもやもや、不全感の正体は、すべて新自由主義に帰結するものだろうか。そこに起因して増殖している周辺業務は間違いなく看過できないモノではあるが、“無意味な仕事”は、日本においては、もっと広範囲にわたって発生、増殖しているように思われる。そして、そのような指摘や言説も生まれている。ブルシット・ジョブという言葉はすでに独り歩きをし始め、グレーバーの意図や解釈を超えて使われている。
例えば、書籍『静かな退職という働き方』(海老原嗣生,2025,PHP新書)の中には、日本と欧米のスナック菓子メーカーの業務を比較するくだりがある。日本の大手メーカーは、年間40~50も新商品を開発しながら年間の売り上げは伸びず、その売り上げの8割以上を既存の売れ筋定番商品が占めているのに対し、欧米メーカーはほとんど新商品を出さずに売り上げを維持・成長させていると説明している。そして、日本の菓子メーカーの「壮大なる無駄」を「顧客要望と向き合う真摯な働き方が染みついている」とし、そうした働き方を「ブルシット・ジョブ(あってもなくても変わらない意味のない仕事の蔑称)の塊」と指摘している。また、そうした働き方を「やっている感を目一杯示すだけの行為」と論じ、その背後には「それが評価につながる」「何かあった時に言い訳になる」という意識があると指摘する。つまり、周辺業務ではなく本来業務そのものが“無意味な仕事”と化している、という見立てだ。
もう一つ例を挙げたい。書籍『ホワイトカラー消滅ー私たちは働き方をどう変えるべきか』(冨山和彦, 2024, NHK出版新書)には、「AI革命でホワイトカラーの仕事がブルシットジョブ化する」という見出しで始まる一文がある。ここでは、技術革新によって、機械等が人間に代わって担うことができるようになった仕事(をそのまま人間が続けていること)がブルシット・ジョブと捉えられている。それはこんなセンテンスに表れる。「現在進行中のAI革命によって、脳の置き換えが起こっている。ホワイトカラーの仕事がブルシットジョブになり、ホワイトカラーは行き場を失いつつある」。この見立ては、本家の定義から大きく飛躍しているように思われるが、ここでも指摘されているのは、本来業務についてである。
こうした捉え方の是非を、今この場では論じない。しかし、いずれも考えさせられる指摘だ。少なくとも、グレーバーの定義や視座・視界を批判的に見つめ直すことが、このテーマを掘り下げる上では欠かせない。
研究プロジェクトの意図、視界、初期仮説
改めて、私たちが、「“無意味な仕事”は、なぜ生まれ、増殖してしまうのか~日本版“ブルシット・ジョブ”研究プロジェクト~」を立ち上げた意図、視界と初期仮説をお伝えしておきたい。
「働く」にまつわる研究は、枚挙にいとまがない。それに比して、その中心にある“仕事そのもの”の実態についての研究は少ない。そして、“仕事そのもの”の中でも、その仕事がいかなる&いかほどの意味を持っているかについての実態研究は希少である。この「空白地帯」にチャレンジしたい。
グレーバーの定義や議論においては、ブルシット・ジョブを、個別のジョブやタスクではなく「有償の雇用の形態」つまりはポスト、ポジションと捉えているが、仔細に中身を見ると個別のジョブやタスクの話が随所に出てくる。本研究では、ポスト、ポジションという単位ではなく、ジョブ単位、タスク単位で捉えていくこととする。
主たる研究対象は、経営管理、事務、営業、設計・開発などのホワイトカラー職場に置くものとする。シット・ジョブと括られているエッセンシャルワーカーの職場にもブルシット・ジョブが蔓延っているという指摘もあり、ブルシット・ジョブを「優良な労働条件」のもとに生まれていると言い切ることはできないようだ。だが、その発生源は、エッセンシャルワークを提供する組織のホワイトカラー職場だと思われる。
“無意味”を議論する上では、“意味”の定義が必要になる。仕事の意味に関するレビュー論文(浦田, 2021)(※5)によれば、仕事の意味は以下の4つに大別される。
- 仕事の個人的意味
- 仕事の関係的意味
- 仕事の社会的・普遍的意味
- 仕事の宗教的/スピリチュアル的な意味
本研究においては、③仕事の社会的・普遍的意味の有無を問うものとする。日本においては、③が希薄であっても、①②あるいは④が得られることをもって、仕事に意味を見出し、自らを納得させてしまうような傾向があると感じている。なお、これまで探索されてきている「無駄な仕事」という観点(多すぎる会議、余計な資料作り、などなど)と“無意味な仕事”は、重なる部分もあるかもしれないが、似て非なるものと捉えている。
研究のゴールは、いうまでもないが、“無意味な仕事”をなくしていくことにある。そのためには、実態を探索し、“無意味な仕事”を体系的に整理し、その発生、増殖のメカニズムを解き明かしたい。だが、犯人探しをするつもりはない。“無意味な仕事”の大半は、悪意から生まれているのではないからだ。誰の目にも“無意味な仕事”であるとは言い切れない、意味があることを否定はできないところから“無意味な仕事”が生まれている、という悩ましさがあるのではないか、という初期仮説を置いている。この仮説をもとに、以下の仮定義を置いて、探索を進めていく。
【“無意味な仕事”仮定義】
帰属集団の一員であり続けるために、コミットせざるを得ない、
社会的意味があることを表向きには否定することはないが、
それを形にしても、社会的意味が極めて乏しいことが予見される仕事
次回からは、初期的な活動から見えてきた「景色」を共有したい。大企業、公務員、大学教員それぞれの実情を、機縁法インタビューを通して探索した結果をレポートしていきたい。
(※1)以下からダウンロードすることができる https://advise.gallup.com/state-of-japanese-workplace-report
(※2)https://www.gallup.com/cliftonstrengths/ja/509474/ギャラップ-q12-従業員-エンゲージメント.aspx
(※3)豊田義博,2007,『「上司」不要論。』東洋経済新報社。豊田義博,2011,「キャンパスライフに埋め込まれた学習」『Works Review』vol.6,8-21。豊田義博,2015,『若手社員が育たない。』ちくま新書。
(※4)Hackman, J. R. & Oldham, G. R. (1975). Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied Psychology, 60(2), 159–170.
(※5)浦田悠, 2021, 「仕事の意味に関する研究の現状と課題―人生の意味の心理学の立場から」(『日本労働研究雑誌』No.7365, 65-76。)

豊田 義博
リクルートワークス研究所 特任研究員/ライフシフト・ジャパン 取締役CRO/一般社団法人エン・ジニアス 代表理事 1983年リクルート入社。数百社におよぶ企業の新卒採用戦略、広報計画業務に制作ディレクターとして長く従事。その後、『就職ジャーナル』『リクルートブック』『Works』編集長を歴任。1999年リクルートワークス研究所設立と同時に着任、人材マーケット予測、若年キャリアなどの研究活動に従事。現在は、個人の就業行動や志向・価値観の変化などを探索しつつ、若手からシニアに至るまでのキャリア支援に研究者 & 実践者として携わるパラレルワーカー。 著書に『実践! 50歳からのライフシフト術』(共著 NHK出版)、『なぜ若手社員は「指示待ち」を選ぶのか?』(PHPビジネス新書)、『若手社員が育たない。』『就活エリートの迷走』(以上ちくま新書)、『「上司」不要論。』(東洋経済新報社)、『新卒無業。』(共著 東洋経済新報社)などがある。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ