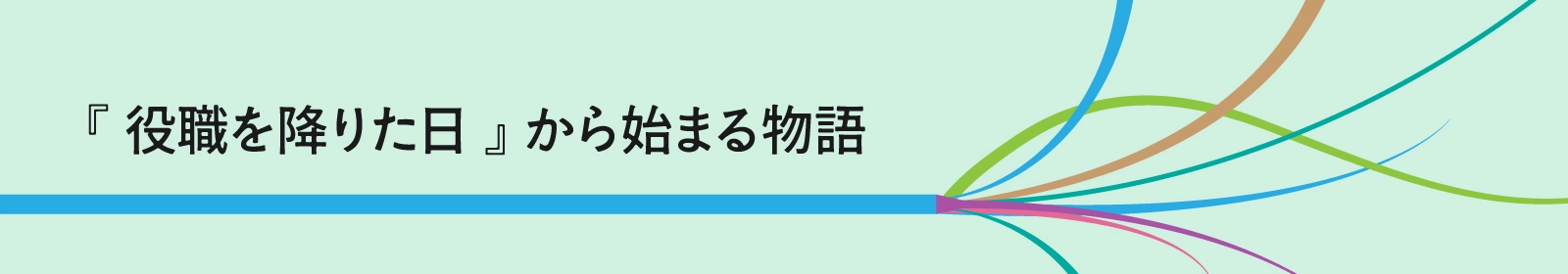
ポストオフの現実。給与、家族、そして心と体の健康
はじめに
「ポストオフ」——役職を降りる、あるいは管理業務から外れるというキャリアの転換点は、給与やキャリアパスだけでなく、家族関係、そして個人の心と体の健康にまで深く影響を及ぼす現象である。多くのビジネスパーソンが経験するこの大きな変化は、当事者にとってどのような現実をもたらすのであろうか。
前回のコラムでは、当事者たちが肩書を失った後に経験するアイデンティティの再構築の旅路を追った。今回は、その内面的な変化が、より具体的な生活の現実にどのように結びついていくのかを明らかにする。インタビューで語られたのは、経済的な厳しさ、家族との関係性の変化、そして心身の不調と回復という、生々しくも切実な物語であった。本稿では、ポストオフを経験した人々の生の声に耳を傾け、彼らが給与の変動や家族との対話、ワークライフバランスの変化、そしてそれらのトレードオフにどう向き合ったのかを探求する。
1.パートナーとの会話:「給料下がるけどいい?」
ポストオフが告げられた際、給与の変動は多くの当事者にとって大きな懸念事項となる。特に家族を持つ場合、ポストオフの決断に際して多くの人が配偶者に相談している。「給料下がるけどいい?」という問いに対し、「別に構わない」「やりたいように転職すれば」 と、パートナーからの理解を得られたという声が多く聞かれた。特に、子供が独立し、住宅ローンを完済したシニア層にとっては、家族の理解がポストオフという選択を後押しする重要な要素となっている。
一方で、会社の制度によっては、給与への影響が少ないケースもある。ある会社の専門職制度では、「基本給のグレードとして管理職から外れたから、イコールどんと下がるという仕組みじゃない」ため、ダメージが比較的小さい。また、自らポストオフを申し出た別の男性は、「年収は今のままでいいからその分売ってくれということになった」 という。しかし、これは給与が維持される代わりに、一般職でありながら管理職レベルの目標値を課されるという、新たなプレッシャーを生むことにもなる。
ある管理部門に勤務していたミドル男性は、子供の独立と住宅ローンの完済を機に、自らポストオフを希望したという。彼はこの決断に至る経緯を、「これ以上、仕事中心の人生を送りたくないという思いがあった。収入が多少下がったとしても、これからは夫婦で楽しむ時間的な余裕が生まれる。そうであるならば、無理に働き続けるよりも、残りの20年、30年を振り返った時に後悔しないよう、もっと自分自身に投資する方が良いと考えた」と説明している。この決断に際しては、パートナーに「給料下がるけどいい?」と相談し、妻からは「別に構わない」という言葉があった。
同様に、以前経営コンサルティング会社の営業所長を務めていたミドル男性は、ポストオフにより「給料が200万円以上落ちた」と語る。厳しい給与水準の変化があったものの、「妻がいたし、ちょうど子供も生まれた直後ぐらいだったので、妻とはよく話をした。もちろん給料的に厳しい中でずいぶん支えてくれた。キャリアについても、やりたいように転職すればという感じでは言ってくれていたので。家計のやりくりも含め、支えてくれていたのは妻だと思う」と、パートナーの大きな支えがあったことを明かしている。
別の繊維素材系企業で課長職であった40代の男性も、クライアントとの関係性が失われたことを理由にポストオフを告げられ、「給与が何百万円単位で落ちた。こんなに落ちるんだというのが自分の中で、ちょっとショックだった。そのあと、下がった分を戻すとなると何年かかるのかを自分の中で計算し始め、少し環境を変えたいという気持ちが徐々に芽生え始めた」と、経済的な衝撃が転職のきっかけになったと振り返っている。彼は転職について恋人にも相談していた。
また、金融業の営業所で課長職であったシニア男性は、家族の介護が必要になったため、自ら課長職を降りる決断をした。給与は「大幅に下がった」ものの、家族の状況を鑑み、「会社には申し訳ないが、自分が生きていく上で仕事が一番ということは、やはりない。家族があって、その次が仕事。自分のやり方と生き方としては、家族が一番で、それに合わせる形で仕事を選ぶ」と、家族優先の価値観を強調している。
IT系企業の部門長であった60代男性は、60歳でポストオフとなり、年俸が約3割減ったものの、「ノルマから解放された安堵感というのが、割と鮮明にあった。だから3割ぐらい年俸が減っても、苦しさから逃れられたのであれば意外とバランスが取れているのではと感じた」と、経済的な影響と心の余裕のバランスを語っている。また、「私の場合には子供が3人いるけれども、もうみんな学校を卒業して家を建てていた。子供にはもうあまり費用がかからないし、夫婦2人の世帯になったので、お金が足りない、生活費が足りないということの心配はなかった」と、ライフステージの変化が経済的な不安を軽減したことも示唆している。
2.「人間らしい時間」を取り戻す:ワークライフバランスの変化
ポストオフは、仕事とプライベートのバランスを大きく見直す機会となる。重圧から解放され、自分や家族のための時間を確保できるようになることで、心身の健康や新たな活動への意欲が生まれるケースも少なくない。
ある繊維素材系企業の元課長であった男性は、タスクの減少により早く帰宅できるようになり、これまでより寄り道や外食が増え、「プレッシャーから解放され、良い意味で自分の中に余裕が生まれた」と語る。また、課長から係長となった40代の男性は、ワークライフバランスが「仕事8割、プライベート2割」から「5対5」へと変化したことで、英語やITパスポート、生成AI関連の学習といった自己投資に時間を割いている。
さらに、転職により以前の「ブラック」な働き方から劇的に変化した経営コンサルティング会社の元営業所長は、子供や家族と過ごす時間、プライベートの時間が「圧倒的に増えた」と実感している。IT系企業の部門長であった60代男性は、プレッシャーからの解放が心身の健康に良い影響を与え、妻との旅行が増えるなどプライベートを充実させている。
その他にも、上場企業の執行役員であった60代男性は退社時間が早まり、40年ぶりに学生時代の趣味であった吹奏楽を再開した。化学メーカーの研究開発チームリーダーであった60代男性は、帰宅時間が早まったことで単身赴任先で自炊を始めるなど、生活習慣の変化が見られた。専門商社の元課長職であった男性も労働時間が短縮され、「すごく健康的な日々を取り戻した」と語り、英会話も始めたという。建設業の元総務課長であった50代男性は、精神的な解放感を語り、残業を一切せず、DXの勉強にも興味を持つようになった。ある組織の局長職であった50代男性も、仕事量が減り時間ができたことで、家庭菜園やマラソン観戦といった趣味を始め、生活が「どんどん広がっている」と感じている。
これらの経験は、ポストオフが個人の人生に新たな「人間らしい時間」をもたらし、心身の健康を回復させ、多様な活動への道を開く転機となり得ることを示している。
3.給与と心身の健康とのトレードオフ
ポストオフは、多くの当事者にとって給与減少という経済的影響を伴う現実である。しかし、この給与減少は、時に心身の健康やプライベートの充実といった、金銭では測れない価値との「トレードオフ」として受け入れられている傾向が見られる。当事者の多くは、この変化を前向きな自己投資や新たな人生設計の機会と捉えている。
経済的報酬が減少する一方で、ポストオフをより本質的な幸福のための投資と捉える見方も多く存在する。例えば、年俸が減少したIT系企業の部門長は、金銭的損失よりもノルマからの解放という精神的安堵を重視した。また、家族の介護を理由に課長職を降りた金融業の男性は、給与が大幅に下がっても、家族優先の価値観に基づいた選択であると割り切っている。
さらに、コロナ禍での過大な責任と精神的負担からポストオフを申し出た飲食チェーン役員の男性は、年収が約200万円下がることを承知しつつも、「あのまんまやってたら恐らく精神科医にかかるような状態に追い込まれてたんじゃないかな」と語り、自身を守ることを優先した。建設業の総務課長であった男性も、給料が下がっても家族を養うのに十分であるため、「自分が元気でいることの方が大事」と、精神的な解放感を享受している。
このように、ポストオフ時には給与が減少する人が多いが、当事者の多くはこれを、ストレスからの解放、心身の健康の回復、家族との時間の確保、そして自己の価値観に合致した働き方の実現といった、より本質的な幸福のための投資と捉え、給与面などのネガティブな要素とともにポジティブな要素もあるということも含めて総合的に受け入れている。
まとめ:物語の第3章——人生のバランスシートを再計算する
ポストオフの現実は、キャリアという一面的な視点だけでは捉えきれない。それは、給与という「資産」の変動、家族という「資本」との関係性の変化、そして心身の健康という「損益」の分岐点を伴う、まさに「人生のバランスシート」を再計算するような出来事である。ポストオフは、給与の変動や家族との対話を通じて、個人の生活に現実的な影響を与える。しかし、多くの当事者にとって、それは単なる「左遷」や「後退」ではなく、重圧からの「解放」であり、自分自身の時間や価値観を再構築する「新たな始まり」となる傾向が見られる。長時間労働から解放され、趣味や自己啓発に時間を割くようになったり、家族との関係を深めたりと、それぞれの方法で「自分らしい時間」を取り戻し、心身の健康を優先する傾向がある。ポストオフは、個々人が自分にとって本当に大切なものを見つめ直し、人生をより豊かにするための貴重な機会となり得るのである。

坂本 貴志
一橋大学国際公共政策大学院公共経済専攻修了後、厚生労働省入省。社会保障制度の企画立案業務などに従事した後、内閣府にて官庁エコノミストとして「月例経済報告」の作成や「経済財政白書」の執筆に取り組む。三菱総合研究所にて海外経済担当のエコノミストを務めた後、2017年10月よりリクルートワークス研究所に参画。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ