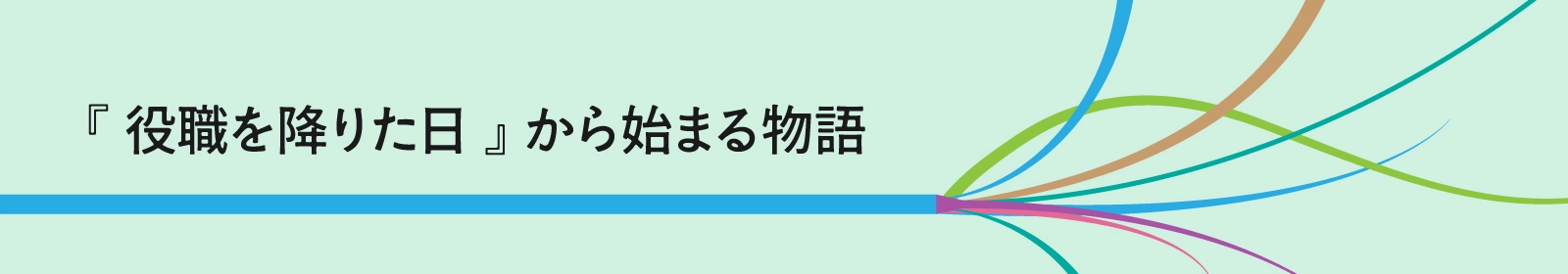
ポストオフの不信はなぜ?「いつ・なぜ・これから」の分からなさ
はじめに
これまでのコラムでは、ポストオフを経験した当事者の「受け止め方」や「その後の向き合い方」に着目してきた。ポストオフは、アイデンティティの再構築や人間関係の変化、さらには心身の健康に至るまで、個人の人生を広範囲にわたって揺るがす大きな出来事である。インタビューで聞かれた当事者たちの語りには、会社に対する不信や疑問、戸惑いといった感情が色濃く含まれている。なぜ、ポストオフはこれほどまでに悩ましいのだろうか。その背景には、当事者から見て「会社のポストオフの仕組みも運用も、あまりに分かりにくい」という深刻な問題がある。
本稿では、これまでのコラムとは視点を変え、当事者と組織との関係に着目する。当事者の不信感は、貢献意欲の低下や離職につながる組織的なリスクである。インタビューで語られた様々な「分からなさ」を解き明かしながら、人事制度としてのポストオフの不信感を生み出してしまう3つの要因と、信頼関係を再構築するための打ち手を考えていきたい。
1.「いつ」が分からない
ポストオフが会社への不信感を生む1つ目の要因は、行われるタイミングが分からないことにある。この予見可能性の欠如は、会社主導の場合も、自己申告の場合も、深刻な不信感の温床となる。
① 突然の通告(会社主導の場合)
会社主導のポストオフは、当事者にとって青天の霹靂として訪れることがある。製造業の本部長だったシニア男性は、「急でしたね。社長からの評価も悪くないのに、突然呼ばれて」と、その衝撃を語る。教育業の局長だったシニア男性も、「突然でした。呼ばれた時は、昇格の話だと思っていたので、それはショックでしたね」と打ち明ける。彼らのように、何の心当たりもなく唐突に告げられたポストオフは、当事者の心に深い傷を残す。会社への貢献を自負しているほど、その衝撃は大きくなる。
たとえ自身のパフォーマンスに心当たりがあったとしても、通告の唐突さは当事者の心を揺さぶる。営業所長だったミドル男性は、「電話来た時点で異動かなっていうのは分かっていました。本社に新設される部門への異動で期待は一応伝えられましたが、ほぼ左遷だなと捉えながら聞いていました」と語り、当時の会社に強い不満を抱いていたと振り返る。
これらの語りに共通するのは、会社主導のポストオフが、当事者の心の準備を許さない形で、予期しない時に、一方的に行われているという事実である。
② 希望の先延ばし(自己申告の場合)
自己申告によるポストオフであっても、会社の対応次第では、予期できない展開となることがある。事業開発の部長だったシニア男性は、自分が管理職に向いていないと感じていたので、上司にポストオフの希望を伝えたが、「あと1年だけはやってくれ」と言われ、実際に外れることができたのは1年半後だった。営業管理の課長だったミドル男性は、プレイヤーへの転向を希望していたが、「自分の後任を入れないと替われない」と言われ、2年かけて後任を育てた末にようやく異動がかなった。
もちろん、後任の調整など、会社側の事情も理解できる。しかし、当事者の希望がいつ実現するのか分からないまま年単位の時間を要することは、大きな精神的負担となる。自らの意思表示が尊重されていないという感覚は、徐々に会社への不信感に変わっていく。
2.「なぜ」が分からない
ポストオフが会社への不信感を生む2つ目の要因は、その理由が分からないことだ。明確な説明がないままにポストオフを告げられても、当事者は納得できず、組織への不信感を抱いてしまう。
インタビューでは、会社主導の場合に、ポストオフの背景や理由が十分に説明されないケースが多く語られた。特に深刻なのは、役員候補と目されていたシニア男性の事例だ。彼はライバルであった人物から直接ポストオフを告げられたが、明確な理由は一切説明されず、ただ「すまん。おまえを守れなかった」と告げられただけだった。さらに、人事部長からは「余計なことはしないでくれ」と釘を刺され、彼は今なおその理不尽な経験に苦しんでいる。
会社主導の場合だけでなく、自己申告によるポストオフでも、納得感を得られないケースはある。休職と復職を繰り返していたミドル男性は、限界を感じてポストオフを申し出た。しかし、会社から提示されたのは自分の想定よりも低いポストだった。「理由も聞きにくかったので、甘んじて今の立場を受け入れてます」と彼は語る。今となっては結果的に良かったと振り返るが、自ら申し出た手前、会社の提案に疑問を感じても、それを口に出すことが難しいという葛藤があった。
納得できる理由について丁寧な説明がされない限り、ポストオフは「厄介払い」や「処分」といったネガティブなメッセージとして受け取られかねない。それは、当事者の心に深い溝を残し、前向きな意欲を失わせてしまう。
3.「これから」が分からない
ポストオフが会社への不信感を生む最後の要因は、ポストオフ後の期待が分からないことだ。これは、周囲との関わりからも影響を受けて、当事者を悩ませる要因となる。
① 役割の不在
ポストオフ後の役割が不明確だと、当事者は仕事へのモチベーションの維持に苦労してしまう。教育業の局長だったシニア男性は、会社主導のポストオフ後に同じ部署の次長となって、今まで自分が仕切っていた仕事ができなくなる息苦しさを感じた。さらに、後任の局長への配慮から、自分の立ち位置や周囲との関わり方が分からない状況に陥った。彼は、1年以上もの間、「自分は何をしたらいいのだろう」と戸惑い続けたという。会社に貢献したい意欲があっても、その機会がなければ発揮できない。彼は、ポストオフについて、「能力を最後までフルに出力させないようになっている。それは会社にとってもマイナスなのではないか」と疑問を投げかける。
② 社内の偏見
ポストオフに対する社内のネガティブなイメージは、当事者を孤立させてしまう。営業所長だったミドル男性は「いわゆるラインから外れた人という社内認知がある」と語る。このため、異動先のスタッフ部門で、自分の仕事ぶりが社内表彰されても、外れた人と見られているのではないかと気になったという。「あまりしゃべりたくなかったので、結構、隅っこに座ってました」と当時の心境を振り返る。
こうした「役割の不在」と「社内の偏見」は、当事者のモチベーションを蝕み、組織にとっても損失となりかねない。だからこそ、ポストオフの後も会社に貢献してもらうのであれば、ポストに応じた役割の設計や期待の表明が必要ではないだろうか。
4.分からなさを乗り越えて信頼関係の再構築へ
インタビューから浮き彫りになったのは、ポストオフの制度やその運用における「分からなさ」が当事者を深く傷つけ、組織との間に不信感を生んでいるという現実であった。「いつ」「なぜ」「これから」の分からなさは、当事者を不安と孤独に陥れ、組織への不信感につながっている。
意外なことに、インタビューでは「ポストオフの仕組みが明文化されていなかった」「自ら降りることはできないと思っていた」と語る経験者も少なくなかった。制度が見えない、届いていない、使い方が分からない。これでは、健全な関係を構築することは望めない。
ポストオフを、人と組織が新たな関係を築くための機会として捉え直すのであれば、その第一歩は、この「分からなさ」を解消することにある。ポストオフの可能性や基準、手続きを制度として明確化し、誰もがアクセスできるようにオープンにすることである。そして、一人ひとりの当事者と向き合って納得感のある状態をつくってから、新たな役割を共に創り出していくプロセスを大事にすることが必要だ。
会社こそが、まずポストオフという現実と真摯に向き合うべきである。
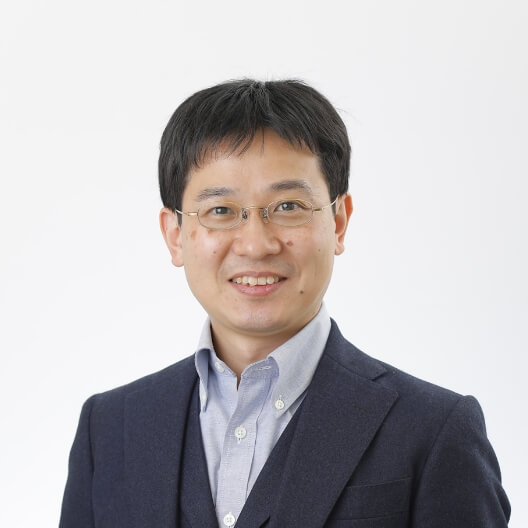
橋本 賢二
2007年人事院採用。国家公務員採用試験や人事院勧告に関する施策などの担当を経て、2015年から2018年まで経済産業省にて人生100年時代の社会人基礎力の作成、キャリア教育や働き方改革の推進などに関する施策などを担当。2018年から人事院にて国家公務員全体の採用に関する施策の企画・実施を担当。2022年11月より現職。
2022年3月法政大学大学院キャリアデザイン学研究科修了。修士(キャリアデザイン学)


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ