
裁判例から紐解くポストオフ【前編】 ―大前提となる根拠の整備―
企業がポストオフを行うとき、従業員からの納得が得られず、労働審判や裁判にまで発展するケースがある。一度、関係がこじれてしまうと、裁判費用や心労など、従業員と企業の双方にとって大きな負担となる。
本コラムでは、ポストオフにつきまとう「分からなさ(不確実性)」に着目する。これらがもたらす「従業員と企業のすれ違い」を裁判例から紐解き、「争点化を防ぐためのポイント」を2回に分けて解説したい。前編となる今回は、ポストオフ制度の前提となる就業規則に関する問題を整理する。
それは、「正当な権限」か「権利の濫用」か
企業には、従業員との労働契約に基づいて、誰をどこに配置するかなどを決める「人事権」が認められている(荒木, 2022)。しかし、その権限は無条件に行使できるものではない。裁量の範囲を逸脱したり、社会的な妥当性を欠いたりする場合には、「権利の濫用」として違法と判断されることもある。特に、基本給や手当の額が下がるなどの従業員に不利益が生じる人事権の行使には、それを行使するのに相当な理由が必要になる。
それにもかかわらず、降格や役職定年といったポストオフの当事者からは、「自分が知らないところで自分のポストについて重要な決定が下されていた」との声が聞かれた。従業員の職業人生や生活基盤に直結するポストオフが不意打ちのように運用されれば、当事者はやる気を失い、結果として企業の競争力は低下してしまう。ポストオフを、人と組織があらたな関係を築くための機会として捉え直すためには、こうした不透明さを解消し、当事者の納得を得られる運用が不可欠だ。
では、透明性と納得性のあるポストオフ制度を導入するために、企業は何を整えるべきか。そのヒントを裁判例から解き明かす。
「ポスト」と「給与」は分けて考えるーポストオフの根拠の定め方
そもそもポストオフが、「いつ、どのような場合に適用され、適用されるとどうなるのか」が明確でなければ、従業員は不安に陥り、企業への不信感を募らせる火種となりかねない。この点、“引き下げ”に関してどの程度の制度設計が必要であるかについて、裁判例では、「役職(ポスト)」の引き下げと「資格や等級(給与)」の引き下げとを分けて考えている。
① 役職や職位を引き下げる
いわゆる「部長から課長へ」といった役職や職位を引き下げるものについては、企業の人事権として比較的広い裁量が認められている。たとえば、飲酒運転による免許停止処分を受けるなど管理職としての適格性を欠くことを理由に、部長から一般職へ5段階の降格を行った事例において、裁判所は、就業規則に根拠がなくても、企業による人事権の行使として裁量的に判断できるとした(星電社事件・神戸地判平3・3・14)。つまり、役職や職位の引き下げだけであれば、必ずしも根拠となる規定がなくても行うことができる(注1)。
② 職能資格や職務等級を下げる
これに対して、職能資格や等級の引き下げは、多くの場合、賃金の減額を伴うので、注意が必要だ。職能給の場合には、職務遂行能力の引き下げという本来予定されていない措置を行うこととなる。また、職務給の場合には、職務の変更によって賃金が減額することになる。裁判例では、いずれの場合でも、就業規則や労働契約上の明確な根拠が必要としている(職能給については、アーク証券事件・東京地判平成8・12・11、職務給については、Chubb損害保険事件・東京地判平成29・5・31)。したがって、賃金の減額などを伴うポストオフを導入するためには、就業規則にその根拠を明記することが必須の条件となる。
なお、根拠を明記するにあたっては、ジョブグレード等ごとの具体的な金額幅や、必要な能力、期待される役割基準等をも記載し、従業員に示すことが適当である(CFJ合同会社事件・大阪地判平成25・2・1)。
「根拠」があればいいわけではないー制度導入自体の合理性
では、就業規則を変更して根拠を明記すれば、賃金の減額を伴うポストオフは可能になるのだろうか。答えは、否である。なぜなら、ポストオフ制度のように従業員に不利益になる制度の新設にあたっては、その内容が全従業員に適用されるものとして有効と言えるのかが問題となるからである。そもそも変更された内容が法的に合理的なものでなければ、根拠として有効なものではなくなってしまう。
賃金や労働時間などの労働条件について、従業員にとって不利益を及ぼす可能性がある制度に変更することは、「労働条件の不利益変更」にあたる。このような不利益変更が全従業員に適用されるものとして有効なものとなるためには、変更が合理的である必要があり、それは、労働契約法第10条に基づいて、以下の要素を総合的に考慮して判断される。
- 従業員の受ける不利益の程度
- 労働条件の変更の必要性
- 変更後の就業規則の内容の相当性
- 労働組合等との交渉の状況
- その他の就業規則の変更に係る事情
裁判例に着目すると、これらの要素への対応が不十分として、制度の変更が無効とされたケースがある。
① 下げ幅の妥当性
賃金の減額を伴う役職定年制の導入の効力が争点となった最高裁の判例では、経営上の必要性や専任職を設けることの合理性は認めた一方で、賃金が40~50%減額される著しいものであり、代償措置も不十分であるとして、無効と判断している(みちのく銀行事件・最判平成12・9・7)。この判例は、制度の変更によって従業員に賃金減額の不利益が生じる場合には、激変緩和措置などの経過措置を設けることが不可欠であることを示唆している。
② 十分な周知や協議
制度の中身だけではなく、変更のプロセスも重要になる。賃金の減額を伴う職群制度の導入において、具体的な金額や算定根拠が周知されていなかった事例では、労働者への周知手続きが不十分として効力が否定された(NTT西日本事件・大阪高判平成16・5・19)(注2)。また、特定の年齢層について2割超に及ぶ賃金減額を行う変更において、職場会の意見聴取や代議員会の決議によって組合大会の決議に代替した事例では、手続き違反として無効としている(中根製作所事件・東京高判平成12・7・26)(注3)。賃金の減額を伴うポストオフ制度の導入に際しては、従業員に対して制度の具体的な内容を明確に説明し、変更のための手続きを誠実に尽くすプロセスが重要になる。
③ 同意の取得範囲・明示的な同意
全員の同意を得ずに、就業規則の変更により一斉に制度変更を行う場合であっても、不利益を受ける従業員の同意がどの程度取り付けられているかは重要になる。先述の最高裁の判例では、就業規則の変更にあたり従業員の約7割が組織する労働組合の同意を得ていても、不利益の程度や内容から大きな考慮要素とならない旨を判示している(みちのく銀行事件・最判平成12・9・7)。不利益の程度や内容によっては、多数従業員の同意だけでなく不利益を被る従業員の同意も必要になる。また、不利益変更について反対意見を述べなかったことが争点となった事例では、消極的な態度は黙示の同意として認められなかった。同意が認められるのは、不利益性について十分に認識した上で、自由な意思に基づいて同意の意思を表明した場合に限るとしている(熊本信用金庫事件・熊本地判平成26・1・24)。不利益を伴う就業規則の変更では、不利益を受ける従業員からの同意をできる限り得るように努めなければならない。
制度導入はあらたな関係構築の好機
そもそも、就業規則の変更にあたって不利益変更の合理性が認められるか否かは、不透明性が高く、事前の見通しを立てることは法律の実務家にとっても難しい(白石, 2021)。企業に求められるのは、法的なリスクを回避することだけではない。従業員が受ける不利益の程度や内容に配慮した制度を設計し、可能な限りの丁寧な説明と適法な手続きを経て、従業員の「納得」を得ようとする姿勢である。この納得を得る観点から重要になるポイントは、「労働条件の変更の必要性」にある。「なぜポストオフを導入するのか」、その背景や制度の考え方をしっかりと説明しなければ、従業員が企業に抱くのは「分からなさ」から生じる不信感である。丁寧な説明とは、一方的な通告ではない。企業こそが、従業員が抱く「分からなさ」に真摯に向き合い、「分からなさ」を解消する努力をしなければならない。
制度というハードが整っても、その次には、制度をどう運用するのかというソフトの課題に向き合わなければならない(後編へ続く)。
法律監修:弁護士 白石紘一(東京八丁堀法律事務所)
参考書籍
荒木尚志(2022)『労働法 第5版』有斐閣
白石紘一編著(2021)『弁護士・社労士・人事担当者による労働条件不利益変更の判断と実務』新日本法規
注1:就業規則等に降格の根拠規定が不要なのは、従業員の役職や職位の変更は労働契約に含まれている権限だと考えられているためである。ただし、企業がその権限を行使することについては、権利濫用にあたらないかが問題となる。いずれにしても、トラブル防止の観点からは、根拠となる規定を明記しておくことが望ましい。
注2:平成16年当時は、労働契約法が制定されておらず、裁判例において、変更後の就業規則を労働者に周知することが求められていた。現在では、労働契約法第10条において、不利益変更に際しては変更後の就業規則を従業員に周知することが手続要件として明記されている。
注3:この事案では、労働協約を変更する際に、職場会での意見聴取と代議員会の議決によって、組合大会の決議に代替する運用をしていたことから、争点となった約2割の賃金減額についても同様の手続きで協議を済ませた。この点について、裁判所は、労働者に対する不利益が極めて大きい労働条件の不利益変更を内容とする労働協約の締結は、組合大会の付議事項とするべきとして、たとえ組合大会で報告事項として承認されたとしても、追認があったと評価できないとしている。
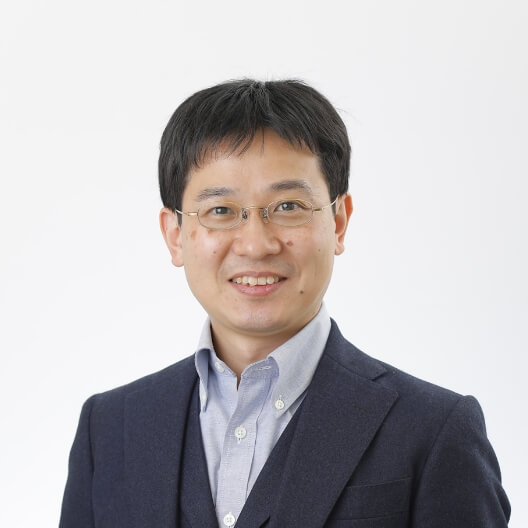
橋本 賢二
2007年人事院採用。国家公務員採用試験や人事院勧告に関する施策などの担当を経て、2015年から2018年まで経済産業省にて人生100年時代の社会人基礎力の作成、キャリア教育や働き方改革の推進などに関する施策などを担当。2018年から人事院にて国家公務員全体の採用に関する施策の企画・実施を担当。2022年11月より現職。
2022年3月法政大学大学院キャリアデザイン学研究科修了。修士(キャリアデザイン学)


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

