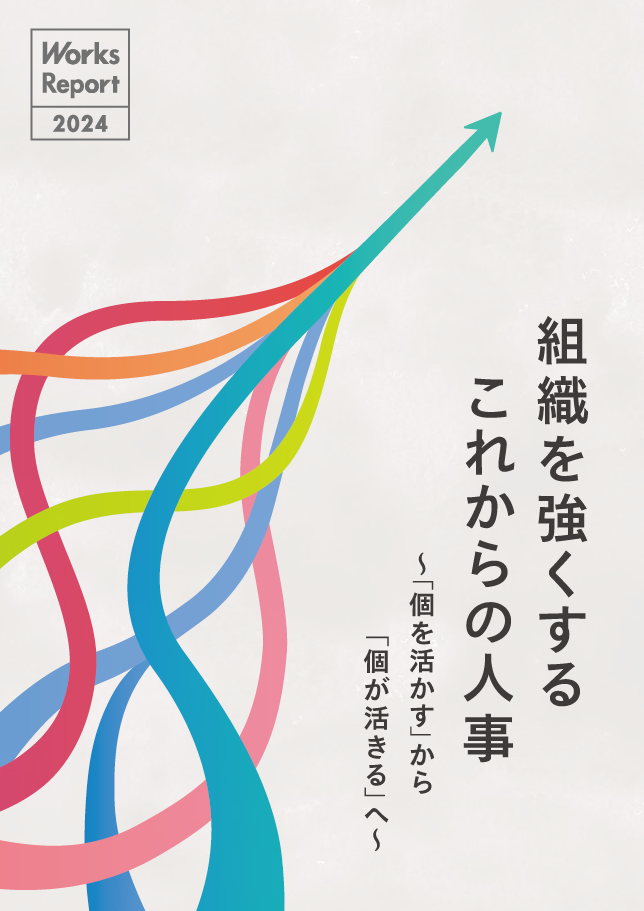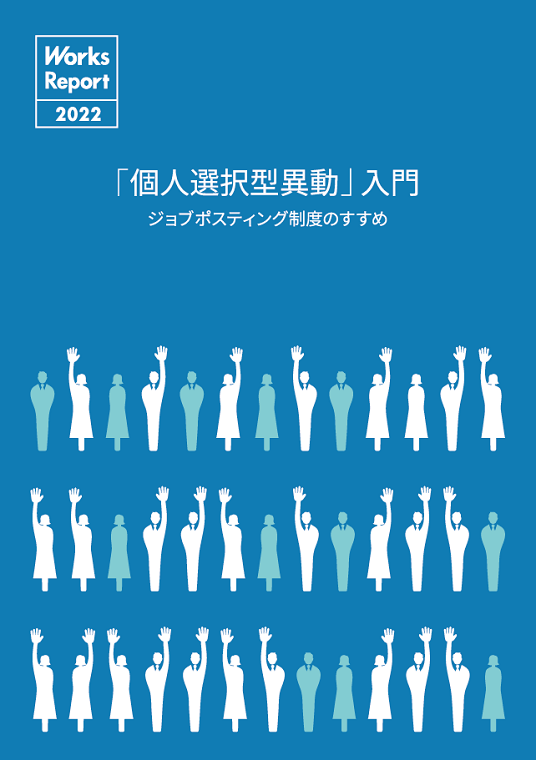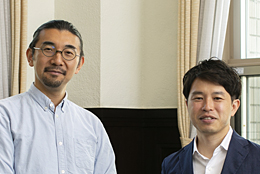ポストオフをキャリアの“オン”と捉え直す
かつて日本企業において、ポストオフとは定年制度と一体化した慣習的運用のもとで、55歳や60歳といった節目での役職退任を意味していた。そこには「役職定年」あるいは「処遇変更」といった制度的文脈が強く、個人の能力や意思とは切り離された一律的な運用が主流であった。しかし現在、この一律的・年齢依存的なポストオフのあり方は、時代とのズレを露呈しつつある。
実際、少子高齢化と人材獲得競争の激化が進む中で、「70歳までの就労機会の確保(現状では努力義務)」や「年齢に依存しない人材活用」といったミドル・シニア層に対する社会的要請が高まっている。あわせて、ジョブ型と称する人事制度の導入をはじめ、雇用・人事構造の再設計が進む中で、課題として浮上しているのがポストオフの問題である。
ポストオフとは何か
これまでポストオフという用語は多義的に用いられてきた。たとえば、定年制度(※1)、役職定年制度(※2)、役職の任期制(※3)、降格(※4)、あるいは管理職ラインから外れ部下がいなくなる状態を指すことである。また昨今、ネットニュースなどで目にするポストオフは、本プロジェクトの視界から見ると限定的に捉えているように映る。たとえば、「一律の年齢(50歳以上)」での実施、ポストオフ後も「正社員」として勤務し続けるといった限定された雇用区分への移行、さらには「会社命令」によって一方的に行われるポストオフなどがその例である。しかし、実際には雇用形態を変更して働くケースや自主的にポストオフを希望するケースもある。つまり、これらの例はポストオフの一側面に過ぎず、ポストオフの実態やその影響を十分に捉えることは難しい。こうした背景を踏まえ、本プロジェクトでは、ポストオフをより広義に捉え直し、その実態を確認していく。本プロジェクトにおけるポストオフとは、課長、部長、役員など、一定の管理職ポジションに就いている者が、その役職から外れることを指す。ここで言う管理職とは、単に職位としての肩書きを持つだけでなく、実際に複数の部下をマネジメントする責任を担っている状態を含意している。
ポストオフには、企業側の判断によって役職を離れるケースと、本人の意思に基づいてポストを退くケースの双方が含まれる。したがって、年齢や在任期間といった形式的要件のみならず、パフォーマンスや組織方針、自律的なキャリア選択といった多様な要因がポストオフの契機となり得る。なお、異動のすべてがポストオフに該当するわけではない。たとえば、ある部署の部長から別部署の部長へと異動するような横方向のポジション移動や、同一部門内で同職種のまま役割を変えるといったケースは、ポストオフには含まれない。一方で、たとえばA部署の部長が、部下を持たない担当部長や専門職ポストに異動する場合などは、ポストオフに該当すると解釈される。
このように、本プロジェクトでは、ポストオフを「役職から外れる」という制度的・表層的な変化にとどめず、ポストオフという制度の設計や運用の実態、柔軟なポストの選択や配置転換のあり方、さらにはそれに伴う評価・処遇の仕組みを含めて、それらが人と組織の関係性や個人のキャリアのあり方にどのような影響を及ぼすのかという観点から捉え直すことを目的としている。
ポストオフの問題点
現在のポストオフにおける最大の課題は、「ポストを外れること」の社会的背景を踏まえた意味づけが不十分な点にある。また、依然としてポストを外れることは、降格・左遷・失敗といった否定的なイメージが根強く残っている点にあろう。このような言葉が今なおポストオフに含まれている限り、たとえ本人の意思やキャリアビジョンに基づいた移行であっても、それは「退くこと」として語られ、評価されにくいのが現状である。
だが、こうした認識こそが組織の代謝を停滞させている一因でもある。企業としてもこのままでは、適所適材の柔軟な配置を進めることができない。その結果、「管理職になること」が避けられる風潮も広まり、後進の登用や育成も滞る。このようにポストオフは、個人のチャレンジする意欲やキャリアオーナーシップを抑制し組織にとっては新陳代謝が滞るという問題を招いている。
こうした現状を前に、今、我々が取り組むべき課題は、ポストオフの「制度」や「運用・手続き」に加えて、ポストオフがもたらす「人と組織の関係性の変容」に着目し、そこにあらたなるキャリアの起点を見出すことである。キャリアの終わりではなく、あらたなステージの始まり、すなわち単なるポストの“オフ”ではなく、キャリアの“オン”としてのポストオフ。これは、ポストを一時的に外れることで働きがいや再成長の機会を得る中継点であり、企業にとっては人材の再配置や後進育成を促す戦略的な流動化装置となり得る。
再設計の起点としてのポストオフ
しかし、こうしたあらたなポストオフの実装には、まだいくつかの障壁が横たわっている。第1に、評価と処遇の整合性の問題である。ポストを外れた際に報酬をどう調整するか、その設計が本人にとって納得感あるものでなければ、制度の正当性は維持できない。第2に、現場におけるコミュニケーションの負荷である。誰が、どのようにして、ポストオフを伝えるのか。その対話の質が、制度の印象や実効性を大きく左右する。第3に、制度導入の目的と運用の実態の乖離である。制度が「人材の代謝」や「公正性の担保」を目的として掲げていても、実態が年齢や組織都合に基づく画一的運用では、本質的な改革にはなり得ない。今、求められているのは、ポストオフそのものを社会的に肯定し直すことだ。そのためには、ポストが上がる、下がるという垂直的な思考から、変わる、戻るといった水平的・循環的なキャリアの捉え方へと転換していく必要がある。そして第4に、ポストオフ後のあらたな仕事への期待が、本人に十分に伝えられていない点が挙げられる。なぜそのジョブにアサインしたのか、これまでの経験を踏まえてその職務において何を期待しているのかといったコミュニケーションが不可欠である。
ただし、ここで十分に注意を払うべき重要な点がある。それは、ポストオフという仕組みを各企業がどのように位置づけ、いかなる方針と意図のもとで人事施策として活用しているのかという点である。
現在、ポストオフの導入状況は企業によって大きく異なっており、すでに制度として運用している企業もあれば、制度設計を検討段階にとどめている企業、あるいは現時点で導入を見送っている企業も存在する。また、導入済みの企業においても、運用方法や制度の趣旨、活用の方針には多様性が見られ、年齢を基準とした一律的な役職離任の制度として設計されている場合もあれば、パフォーマンスや役割適性を基準とした柔軟なポジション移行の仕組みとして捉えられている場合もある。このように、制度の設計や運用方法が多様である一方で、すべての企業に共通して浮かび上がる本質的な課題が存在する。それは、ポストオフという役職変更のプロセスを通じて、人と組織の関係性が大きく変化しており、そしてその変化が必ずしも上手く機能していない、という実態である。
具体的には、役割の移行や責任の変化に伴って、対象者のモチベーションが著しく低下したり、キャリアの見通しを見失ったりするケースが少なくなく、結果としてその人材の持つスキルや知識、知見といった能力が十分に発揮されないまま、組織内に埋もれてしまうという状況が生じている。制度が導入されたにもかかわらず、実質的には「外された」「価値を失った」といったネガティブな捉え方が払拭されず、ポストオフが企業と個人の関係を弱体化させる契機となってしまっているようにも見受けられる。
このような現状は、企業と個人の双方から見ても看過できない問題である。人材獲得競争の激化、定年延長といった社会的要請、そして変化の激しい経営環境の中で、組織内におけるポストの硬直性や人的資源の滞留は、企業にとっては持続的成長機会を損なうリスクとなり、個人にとってはキャリアの可能性を閉ざす障壁となり得る。
したがって、今、各企業に求められているのは、ポストオフという制度を単なる人員調整の手段としてではなく、いかにして人と組織の関係を再設計するための機会として活用していくのかという視点である。そして個人にとっても、ポストオフはキャリアを見つめ直し、あらたなキャリアに向けて自ら進化させる転機とする。
あらたなポストオフの議論へ
本プロジェクトが掲げる「人と組織のあらたな関係性」という視点は、まさにこの転換の先にある。ポストオフを単に降格と捉えるのではなく “再設計の起点”とすること。ポストオフを経験した人材が再び挑戦し、何度でも活躍できる組織であること。そのようなあらたな人事設計と組織文化が、持続可能な企業成長を支えていくのではないか。
ポストオフという現象は、単なる制度運用の問題ではない。それは、企業が「どのように人を育て、活かし、送り出すか」、その人事戦略のあり方そのものを示している。我々は今、その問いに向き合う転換点に立っている。
(※1)会社が定めた年齢に労働者が達したときに、労働契約を終了させる制度
(※2)ポストに定年を設け、役職者の年齢が設定した年齢に達した際に、ポストから離れる制度
(※3)役職への就任年数を限定して一定期間で改選することを前提に業績を厳しく管理し、任期末に役職としての適性を審査し、再任、昇進、降職、他のポストへのなどを行う制度
(※4)組織内での役職や職位を下げること

千野 翔平
大手情報通信会社を経て、2012年4月株式会社リクルートエージェント(現 株式会社リクルート)入社。中途斡旋事業のキャリアアドバイザー、アセスメント事業の開発・研究に従事。その後、株式会社リクルートマネジメントソリューションズに出向し、人事領域のコンサルタントを経て、2019年4月より現職。
2018年3月中央大学大学院 戦略経営研究科戦略経営専攻(経営修士)修了。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ