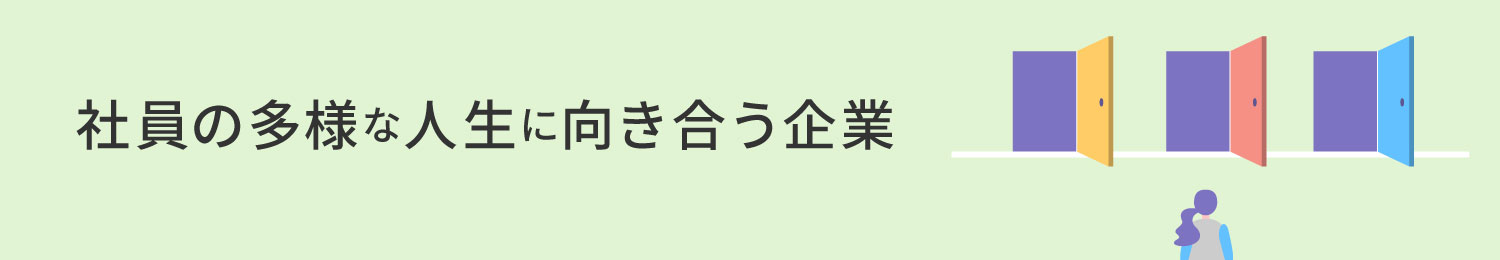
人生楽しむことで仕事も「自分らしく」活躍を 社員の家庭生活や趣味を後押し

インテリア用品の製造・販売などを手掛ける友安製作所は、社員が家庭生活や趣味など仕事以外の人生を楽しめるよう後押しをすることで、職場でも「自分らしさ」を活かして活躍してもらおうとしている。ブランドデザイン部ブランドコミュニケーション課の松本明莉氏に、具体的な施策や成果などを聞いた。
個人の価値観やライフスタイルを、仕事に入れ込む
-社員の仕事以外の活動をサポートするようになった経緯を教えてください。
2004年に現社長の友安啓則が後継者として入社し、事業の柱をねじや線材加工などの製造から、インテリア用品の製造販売へとシフトさせたことがきっかけです。社長は米国生活が長く、現地の人がライフスタイルに合わせて家づくりを楽しむ様子を見ていました。しかし当時の日本の住宅は、規格化された部分が多くDIYもあまり普及していませんでした。そこで暮らしを楽しむ文化を日本に広めたいと考え、インテリアの領域に乗り出しました。今は、「世界中の人々の人生に彩りを。」というヴィジョンを掲げています。これに照らして、従業員にも充実した人生を送ることで、仕事でもライフスタイルや価値観といった「彩り」を活かして活躍してもらおうとしています。またコーポレートスローガンの「生きるをあそぶ」も、人生と仕事の両方に自分らしさを入れ込む余地、つまり「あそび」を持ってほしい、という思いを込めています。
-仕事で「あそび」の部分を持たせすぎると、社員が甘えてしまいませんか。
確かに「あそび」が大きすぎると、社員と会社が違う方向を向いてしまったり、経験の浅い社員が何をしていいか分からなくなってしまったりするかもしれません。ですから会社への理解が深まるのに合わせて段階的に「あそび」を持たせ、会社と社員の目線をそろえるようにしています。同時に「全社員デザイナー宣言」を打ち出し、自分から課題と解決策を見つけて主体的に行動するよう社員に求めています。決められたこと以外のテーマに取り組む「あそび」の部分は、主体的に動く際にはむしろ不可欠です。
また当社の社員は、国籍などのバックグラウンドが多様なため、全社員が守るべき行動規範として10項目からなる「TOMOYASU WAY OF LIFE」を定め、採用や人事評価に活用しています。ただこれも「Be PRODUCTIVE-スピード感を持って生産性の向上を」と「Be CREATIVE-他にはない唯一無二な商品・サービスを」など、一見相反する項目をあえて並べ、どう解釈して何に重きを置くかをある程度、本人に委ねています。
シニア層もSNSを積極活用 社長が「挑戦」のカルチャーを牽引
-社長は就任後、組織をどのように変えていったのでしょうか。
社長が入社したとき、従業員は5人ほどでしたが、20年ほどで約150人に増えました。組織を変えるというより、成長に合わせてゼロから作ってきた形です。
まず、経営層の考えを共有するため年1回、全従業員を集めて「全体会議」を開いています。また全社員がカタカナの「ビジネスネーム」で呼び合うルールも作って、上下関係にとらわれずに意見を言い合える風土を醸成しようとしています。
2016年からは、従業員同士の投票で良い仕事をした人を表彰するTOMOYASU Awardも始めました。投票のベースになるのは、SNSに公開された全社員の日報です。日報にコメントしたり、「いいね」したりするなかで、違う部署の人の考えや業務内容を把握し、優れた仕事や努力をたたえられるようになります。日報には、育休中の社員などが、休んでいる間も会社の動きを知ることができるというメリットもあります。
SNSの導入当初は、「毎日日報を書くのは大変そう」「SNSはあまり使わないから不安がある」「書いても周りの人が、見たり反応したりしてくれないのではないか」といった声もありましたが、始めてみると、抱いていた不安は杞憂だったそうで、全社的にもコメントし合う雰囲気が自然に広がりました。現社長が新しい施策や事業に挑戦し続けて、「まずやってみる」というカルチャーを牽引してきた面もあると思います。
フラットな組織が採用に好影響 声を上げれば組織は変わる
-ビジネスネームを使うことに、どんな効果があるのでしょう。
例えば、私はカレーが好きで、スパイスに由来して「クミン」という名前で呼ばれています。ビジネスネームがあるだけで、話しかけたり意見を言ったりすることの心理的なハードルが下がります。新入社員も、入社当日から先輩や上司をビジネスネームで呼ぶことで、疎外感を持たずに社員の輪に入れるようになりますし、異なる部署の人への親近感も持ちやすくなります。さん付けや役職呼びは禁止で、みんな本名をほとんど知らないほどビジネスネームが浸透しています。
-フラットで柔軟な組織風土は、採用にも良い影響を与えているのではないでしょうか。
3年ほど前に新卒採用を始めたのですが、求人は大手媒体などには掲載せず、身近なコミュニティーで募集しています。それでも数人の募集に毎回、約50人の応募があります。会社の知名度を高めることにハードルはありますが、知ってもらいさえすれば第1志望に選ばれることが多く、内定辞退者も新卒採用者の離職も今のところいません。初任給は大手などに比べれば見劣りしますが、雰囲気の良さや、若手でも大きな仕事をアサインされやすいことが好感を持たれているようです。当社は良くも悪くも、入社直後から「戦力」として仕事をしてもらうので、新人は苦労もあるでしょうが、やりがいも感じていると思います。
また新入社員には、半年かけて会社に対して何らかの提案を考えるという課題を出しています。提案は経営陣に発表し、組織に必要だと判断されれば実現もします。こうした取り組みによって、「声を上げれば組織は変わる」という意識を育てようとしています。
家族を大切にする空気を醸成 フレックスや交流の場づくりで
-育児など家庭生活を大切にするための、具体的な取り組みを教えてください。
産休、育休のほか、社員個人で始業時刻などを決められるフレックス制を導入しています。職場にも、社員が保育園の送り迎えのため1時間前倒しで出社して早く帰宅したり、逆に遅く出てきたりすることに寛容な空気があります。さらに毎年、全従業員と家族が交流する場として、バーベキュー大会も開いています。会社としても、社員が増えて会場が手狭になると、社屋を改装して会場を作ったほど、この会を大事にしています。当日は大人だけでなく、子どもたちも楽しめるよう風船や射的の屋台も設けられます。
家族を大切にする文化が醸成されたのは、社長が3代目で家族への思いが強いことも一因だと思います。社長は幼い頃、先代(現会長)に会社に連れてこられると、いつもにぎやかで楽しい雰囲気を感じたそうです。当初は後を継ぐつもりはなかったけれど、先代が体調を崩したとき、こうした記憶がよみがえり父親を助けたいと思ったと話していました。
-育児などのために仕事を抜ける社員が多いと、カバーする人の負担が高まりませんか。
事前に休みなどの日程を共有するので、大きなしわ寄せを受けたという話はあまり聞きません。日報を通じて互いの仕事が見えるので、ある部署が忙しいと他の部署の人が自然と手伝いに入ることも多いです。さらに社内のシステムは全て内製化しているので、デジタル化による効率化、自動化も進めやすく、その結果残業も抑えられています。
-社員の仕事以外の人生を、会社としてどう捉えていますか。
組織として社員の人生を応援したいと考えていますし、さまざまな経験が社員の新しいアイデアや発想につながり、事業にポジティブな影響を与えることも期待しています。実際に趣味や社外活動を大切にしている社員は非常に多いですし、同じ趣味を持つ人同士で集まることも多く、社員同士もお互いの趣味や社外活動を認め合う空気があります。
当社は規模が大きくないこともあり、特別な制度を設けて社外活動を企業成長に取り込むという段階には至っていないかもしれません。ただ休みを取りやすく勤務時間を柔軟に決められる、残業が少ないといった部分で、結果的に社員が人生を楽しむことは、後押しできていると思います。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

