
HRテック進化の5年――AIと共存する採用の未来

本調査(Solution Stack 調査)では、米国の人材採用コンサルティング会社CareerXroads協力の下、米国大手企業7社へのオンラインインタビューを実施した。同社共同代表のジェリー・クリスピン氏は、長年にわたり人材獲得分野、HRテクノロジー分野に携わる米国の第一人者である。同氏への個別インタビューでは、有識者の立場から、HRテクノロジーの進化や採用の未来について語っていただいた。
▼インタビュー(ダイジェスト)
【ポイント】
- ソーシングツールの成熟と統合:ソーシングツールはピークに達しつつあり、大手ベンダーは採用マーケティング機能などを統合したより包括的なソリューションの提供を開始している。
- アセスメントのパラダイムシフト:求められるスキルは常に変化し続けている。評価の焦点は従来の「スキル」保有の有無から、候補者の「学習能力」や「モチベーション」へと移行すると予測される。
- AIによる面接プロセスの革新:面接支援に特化したAIツールが台頭し、採用プロセスは劇的に変化している。これにより、リクルーターの業務負荷が大幅に軽減されるだけでなく、候補者に対してより公平な評価とフィードバックを提供することが可能となる。
HRテック5年間の進化:AIが採用領域へ
――2019年に実施した「Tech Stack(テックスタック)調査」から5年が経過しました。HRテック領域ではどのようなトレンドや変化がありましたか。
この5年間で、HRテックの主役はビッグデータからAIへと劇的にシフトし、今や採用領域全体を席巻しています。
候補者は既にAIを巧みに活用しており、ChatGPTでジョブディスクリプションに合わせて履歴書を最適化したり、Microsoft Copilotで面接の練習を行ったりするようになりました。
一方で、企業側も2025年に入りAIツールの導入をさらに進めていますが、その多くはAI利用に関する明確な方針をまだ確立できていないのが実情です。
ソーシングはツールの自動化・多機能化が進む
――採用の各ステージにおいて、HRテクノロジーはどのように変化しているのでしょう。まず、ソーシング領域はいかがでしょうか。
ソーシングの領域では自動化が著しく進展し、多くの企業でソーサー(候補者を探す専門職)の数を削減する動きが見られます。個人的な見解ですが、ソーシングツールは既に成熟期に達したと考えています。
hireEZやSeekOutといった主要ベンダーの間では、合併や提携が活発化しており、かつては単一機能だったツールが、より多機能で包括的なソリューションへと進化しています。
採用マーケティングの成長により、ターゲット層がより明確に
――ソーシングに特化していたプラットフォームが、ほかの領域にも機能を拡大しているということでしょうか。
そのとおりです。たとえば、BeameryやPhenomのような大手ベンダーは、従来のソーシング機能に加え、採用ブランディングや採用マーケティングと連携した統合型ツールを提供し始めています。これにより、企業はより的確な候補者層にアプローチできるようになりました。
この5年で採用業務の専門分化が進みましたが、特に採用マーケティングは、HRテクノロジーによって大きく成長した分野の一つであり、エンゲージメント向上において目覚ましい成果を上げています。
この領域には採用担当者だけでなく、マーケティング部門出身の人材が流入しており、彼らの専門知識が採用キャンペーンの戦略立案に生かされています。
自動化によって「候補者を見つける」ことの難度が下がった今、成功の鍵は「いかにして候補者を引きつけ、エンゲージメントするか」という点にあり、これが今後の差別化要因となるでしょう。
AI面接が採用プロセスを大きく変える
――スクリーニングや面接におけるAI活用は、今後どのように進むでしょうか。
チャットボットによる初期対応など、スクリーニング段階でのAI活用は既に実用化されており、今後さらに進むでしょう。
私が特に大きな変化が起こると予測しているのは、「採用ファネルの上流」、つまり応募から初期選考までのプロセスです。多くの企業では、一つの求人に数百人の応募がありながらその95%は不採用となり、候補者に対して簡単な通知のみ、あるいはまったくフィードバックがないことも少なくありません。
私は2030年ごろまでには、求人に興味を示した求職者全員の初期選考はAIが行い、公平で偏りのない体験と、パーソナライズされたフィードバックを提供できるようになると予測しています。人間のリクルーターが全応募書類に目を通すのは物理的に不可能ですが、AIならば候補者の経歴にかかわらず、職務要件に基づいた客観的かつ公平な評価が可能です。
たとえば、AI面接官が応募者にヒアリングして質問を深掘りしたり、全員に同じ形式でインタビューを行ってその内容を記録してくれたりするのです。そのデータを基に人間のリクルーターが最終判断を行えば、より客観的な採用プロセスが実現するでしょう。
これを実践できている企業はまだ全体の1〜2%にすぎませんが、技術的には実現可能なレベルに達しており、これこそが採用における大きな変革だと考えています。
――候補者の中には、AIによる面接に抵抗感を抱く人も多いと聞きます。
たとえば、AI面接では、若い人や年配の人、女性など、候補者が話しやすいと感じるアバターを選択できるため、候補者はリラックスして本来の能力を発揮しやすくなるという利点があります。
しかし最大の懸念点は、AIの学習データの偏りです。つまりそのAIが企業独自のデータで学習されたものなのか、あるいはより広範な一般データで学習されたものなのかという、AIの判断根拠がわかりにくいという課題があります。
AI活用の透明性確保に向けた取り組み
――企業やベンダーは、AI活用の透明性を示すためにどのような対策を講じているのでしょうか。
自社で使っているAIについて、学習データの偏りがないかなど、適正性や説明可能性について監査を行うのがその一例です。
しかし、自社のAIアルゴリズムが第三者による監査を受け、どの程度バイアスを軽減できているかを示せる企業やベンダーは、現時点ではごく少数です。多くの企業においてAI監査の具体的な手法や基準はまだ確立されておらず、透明性の確保は依然として課題になっています。
また、候補者によるAI活用に関しては、たとえばFox Communicationsが、面接においてAIを使用してよい範囲と使用が禁止される範囲を事前に明示し、もし規定に反してAIを使用していることが判明した場合は、選考を通過できないとポリシーで明確に伝えるといった事例があります。
アセスメントの焦点が「スキル」から「学習能力」へ
――米国では、スキルベース採用が注目されています。アセスメントツールのトレンドをどう見ていますか。
スキルアセスメントの領域は非常に多様化しています。従来のコーディングテストやシミュレーション型アセスメントに加え、AIを用いて候補者の潜在的なスキルを予測するツールも登場しています。
たとえば、GemやLinkedInがスキル領域に参入したり、SeekOutやhireEZなどソーシング関連のベンダーは、AIによるスキル分類を活用して人材を検索したりしています。
しかし、求められるスキルは常に変化しており、今日の必須スキルが明日には陳腐化する可能性も十分にあります。
スキルベース採用への注目は高まっていますが、スキルの定義や評価方法には依然として多くの課題が残されています。
こうした背景から、私は今後数年でアセスメントの評価軸が特定の「スキル」保有の有無から、新たな知識やスキルを習得する「学習能力」へとシフトしていくと予測しています。
——どのようなスキルを持っているかではなく、新しいスキルをどれだけ早く習得できるかが重要になるということですね。
はい、そのとおりです。これまでは候補者の学歴を学習能力の1つとして評価していましたが、それが必ずしも実務能力を保証するものではありませんでした。
AIの普及によって、知識のコモディティ化が進んでおり、ChatGPTに聞けば誰でも容易に答えを得られる時代になりました。職務内容が絶えず変化し続ける環境では、「何を知っているか」ということ以上に、生成AIに対して「いかに的確な問いを立てられるか」、そして「ツールをいかに効率的に使いこなせるか」といった能力が重要になるでしょう。
たとえば、AIを用いて候補者が新しい業務を習得するスピードを測定できるアセスメントが開発されれば、おそらく80%程度の職務で従来の経験や資格に依存しない、より本質的なマッチングが可能になると考えています。
候補者の「モチベーション」や「意思決定」を支援するアセスメント
――特に注目しているアセスメントツールはありますか。
Plumです。このツールは、候補者のモチベーションに焦点を当てており、スキルの有無だけでなく「その仕事に対しどれだけ情熱を注げるか」というポテンシャルを可視化します。たとえば、同程度のスキルを持つ候補者が複数いた場合は、より意欲的な人を特定することができます。
さらに、今後は候補者自身のためのアセスメントが登場すると予測しています。これは、候補者が「自分はこの仕事ができるか」ではなく「本当にこの仕事をやりたいか」という内面的な動機に基づいて、意思決定するのを支援するツールです。
これまでの採用は、意思決定が企業側に偏りがちでしたが、企業理念や価値観の適合性を双方向で測定することで、入社後の定着率やエンゲージメントの向上に大きく貢献するはずです。
今後の注目トレンドは「統合型ツール」と「面接支援ツール」
――特に注目しているHRテクノロジーのトレンドや製品はありますか。
注目しているトレンドは2つあります。1つ目は、エコシステムの中でほかのHRツールとシームレスに連携できる「統合型」のツールです。
多くの大企業が導入しているWorkdayは基幹システムとして大きな成功を収めましたが、採用の各プロセスにおいては、Paradox、 Beamery、Phenom、Eightfoldといった専門ツールが連携し、機能を補完しています。
2つ目は、2024年から2025年にかけて顕著になっているリクルーター向けの「面接支援ツール」です。
面接支援ツールは、AIが面接前に候補者の情報を要約したり、面接中に質問の適切性や時間配分についてリアルタイムでアドバイスしたりします。面接後には会話内容を自動で要約し、職務要件に基づいてスコアリングすることも可能です。
これは、リクルーターの業務を根底から変える、次世代の採用ツールだと確信しています。
AIとの共存が、リクルーターの仕事に「人間味」を取り戻す
――AIツールの活用が進むなかで、リクルーターの仕事はどのように変化していくと考えますか。
現在、多くの候補者が採用プロセスに対して不満や失望を感じています。これはリクルーター個人の問題だけでなく、時間的な制約や企業の方針により、候補者一人ひとりに十分な情報提供やフィードバックができていないという構造的な課題に起因します。
私の願いは、すべての候補者が公平な選考機会と、成長につながるフィードバックを得られるようになることです。
テクノロジーは、単に生産性を上げるための道具ではありません。採用プロセスそのものを抜本的に改善し、リクルーターの仕事に新たな価値をもたらします。
つまり、採用におけるAIの活用は「人間性の排除」ではなく、むしろリクルーターが事務的な作業から解放され、候補者との対話や、より高度で人間的な判断に集中するための大きな転機となるでしょう。
インタビュアー=杉田真樹
TEXT=泊真樹子
【CareerXroads(キャリアクロスローズ)企業概要】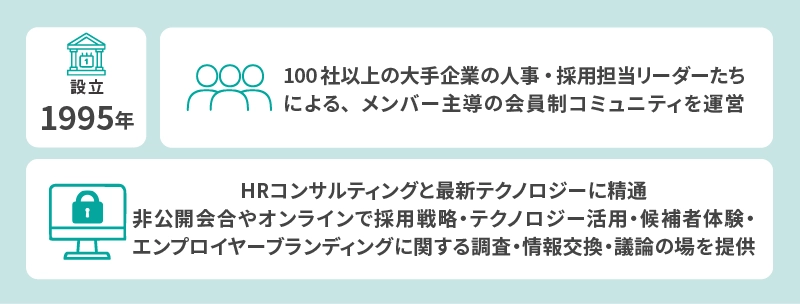
採用関連テクノロジーの概要
hireEZ
ソーシング、応募者のレビュー、再発掘、社内人材とのマッチング機能を備える採用管理プラットフォームである。2025年4月には、AIが採用業務を支援する「EZ Agent」を発表した。
SeekOut
AIでネット上の人材データを収集するタレント検索プラットフォームである。「People Insights」機能により、職種ごとの人材分布、学歴、出身大学、企業属性などを分析できる。
Beamery
採用、人材管理、要員計画を支援するタレントインテリジェンスプラットフォームである。「Talent CRM」は、職種や居住地に基づいて特定の候補者層に新着求人を即時自動配信できるほか、ニュースレターを定期配信する機能も備えている。
Phenom
候補者、従業員、リクルーター、マネジャー向けに多様な機能を提供するタレントエクスペリエンス管理プラットフォームである。採用業務では、ソーシング、CRM(採用候補者管理システム)、キャリアサイトのCMS(コンテンツ管理システム)、SMS機能などを搭載している。
Gem
CRM、ATS(応募者追跡システム)、ソーシング、面接スケジューリング、分析を統合したプラットフォームである。LinkedInやメールなど複数の情報源から候補者データを集約・管理する。自動タグ付けを行い、イベント案内などのメールを配信する。開封率やイベント登録数などのKPIの可視化が可能である。
LinkedIn
世界10億人以上のユーザーを抱える、ビジネス特化型のSNSである。2025年5月時点で掲載求人件数は1500万件超。リクルーティングプラットフォームとしても活用され、候補者の検索、連絡、管理を一元的に行える「LinkedIn Recruiter」などのソリューションを提供する。同年4月には、AIがプロフィール情報から潜在能力を推定し、候補者を推薦する機能も追加されている。
Plum
性格、問題解決力、社交知性を測定するオンラインアセスメントである 。社風との適合度や潜在的なリーダーシップ力も評価可能である。
Workday
HCM(人事管理システム)、財務、業務管理を統合したクラウド型プラットフォームである。従業員管理からタレントマネジメントまでを一元管理し、リアルタイムでのデータ分析を可能にする。「Workday Recruiting」 を通じ、候補者との円滑なコミュニケーションを実現する。
Paradox
採用業務に特化したチャットボットのプロバイダーである。AIアシスタント「Olivia」が、求職者からの問い合わせに自動応答し、経験年数や希望の職種、資格の有無などを質問してスクリーニングを行う。
Eightfold
10億人以上の経歴と100万以上のスキルデータを基盤とするタレントインテリジェンスプラットフォームである。AIが応募者を自動解析する機能に加えて、CRMと連携してメールやSMSを一斉配信することも可能である。
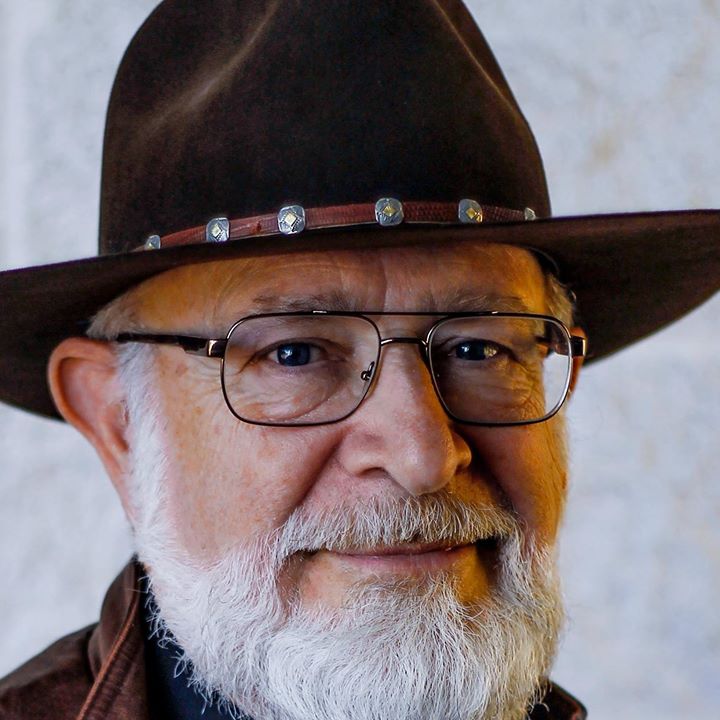
ジェリー・クリスピン氏
CareerXroads(CXR)の共同創設者および共同代表を務め、長年にわたり人材獲得分野に携わる。自らを「生涯学習者(life-long student)」と称し、候補者体験の向上に情熱を注ぎ、採用に関わるすべての人のためのよりよいプロセスを追求し続ける、米国のHR領域の第一人者。50年にわたるキャリアには、コンサルティング、採用マーケティング、フォーチュン100企業での幹部採用や人事ディレクターなどが含まれる。近年の訪問国・地域には、シンガポール、東ヨーロッパ、日本、キューバ、イスラエル、ベトナムなどがあり、CHROや採用リーダーたちによるグローバル代表団を率いて、世界各国の関係者に雇用や採用プラクティスなどに関するインタビューを積極的に行っている。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ