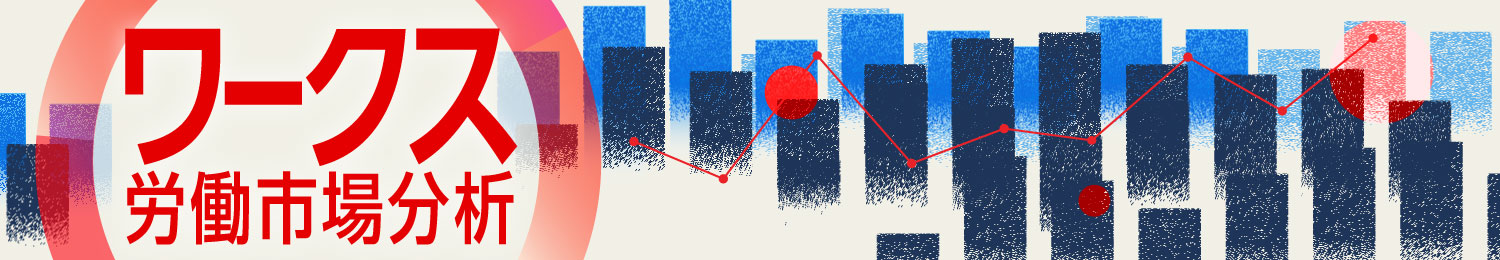
なぜ精神障害労災が増えているのか?
20年で約8倍
厚生労働省の統計によれば、20年前、2004年は年間425件だった精神障害による労働災害(決定件数ベース。以下同様)は、2023年には2,583件、2024年では3,494件に達した(図表1)。20年間で約8倍の水準に達し、2018年から毎年過去最高を更新している。これは、単なる労災件数の増加というより、職場における健康管理の構造が変化していることを如実に示している。
まず、性別構成に明確な変化がある。統計で遡ることができる2014年には精神障害による労災決定件数のうち35.3%が女性であった。しかし女性比率はその後ほぼ一貫して上昇傾向にあり、2024年に51.1%と初めて過半を占めた。2014年以前の統計はないものの、この傾向からは精神障害による労災は長らく男性が多数を占めていた可能性を示唆する。その構造が逆転したことの背景にはもちろん女性就業者数の増加があり、その裏側で「(後述する)女性の就業者が多い対人サービス職種における負荷増大」「育児・介護との二重負担」といった構造的な不均衡が、精神的負荷を押し上げている可能性を無視できない。
また、注目すべきは、この増加が特定の業職種に偏在している点にある。業種別では「医療・福祉」が比較可能な2009年→2024年で精神障害による労災決定件数が8.8倍となっている。なお、「医療・福祉」の脳・心臓疾患による労災決定件数は同期間に1.0倍である。
「教育・学習支援業」の精神障害による労災は5.9倍、「宿泊業,飲食サービス業」は4.2倍である。対人サービスを担う産業で増加が目立っている。背景には、慢性的な人手不足と、過剰なサービス要求、感情労働の肥大化があるだろう(精神障害への理解が促されたことも指摘できる)。それが支援の少なさと結びつくことでメンタルリスクに転化していると考えられる。
職種別の内訳もまた、この傾向を裏づける。増加率が高いのは「運搬・清掃・包装等従事者」で6.8倍、「サービス職業従事者」5.0倍、「その他の職種(上記以外の職種)」4.2倍である(職種は項目を合わせるため2010年と2024年の比較)。他方、「事務従事者」は2.6倍と比較的伸び率が低い(図表2)。なお、精神障害による労災と脳・心臓疾患による労災のそれぞれの増加率を比較すると、業種ではほとんど無相関だが、職種では強い相関(係数=.59)を持っており、労災発生は業種ではなく職種の違いに依存していることがわかる。
また、年齢別に見ると、2009年に39歳以下で6割近くを占めていた状況が変化していることがわかる。2024年の構成比では40代が最多の28.0%、続いて30代23.5%、50代22.3%、29歳以下が計21.4%、60歳以上4.8%である。20代は決して無視できないが、それ以上に過去と比較すると、ミドル層である40〜50代の比重が高まっている点が重要だ。40-59歳の精神障害による労災決定件数の構成比は2009年の40.4%から2024年には50.3%へと高まっている(図表3)。もちろん、就業者の年齢構成が変化している(50歳前後の就業者が増加している)ことは影響している。しかし合わせて検証すべきは、働き方改革が物理的な労働環境(労働時間、休暇)を改善した一方で、役割の過重化・分断・職場における孤立という新たなリスクが顕在化していないかという点であろう。
近年の精神障害による労災の増加は、制度的な対応や産業医療体制の整備のみならず、現場での業務設計や人間関係のあり方そのものを問い直す契機となっている。労働時間の抑制に加え、対人負荷・役割集中・心理的孤立といった「見えにくい負荷」への眼差しを日本社会が持てるかどうかが、今後の労働現場の健全性を決定するだろう。
図表1 精神障害による労災の状況
出典:厚生労働省,「過労死等の労災補償状況」各年結果より
図表2 労災決定件数の増加率(職種別)(2010年→2024年、2010年を1とする)
出典:厚生労働省,「過労死等の労災補償状況」各年結果より
縦軸:精神障害による労災決定件数増加倍率、横軸:脳・心臓疾患による労災決定件数増加倍率
図表3 労災決定件数の年齢構成の推移
出典:厚生労働省,「過労死等の労災補償状況」各年結果より

古屋 星斗
2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。
2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ