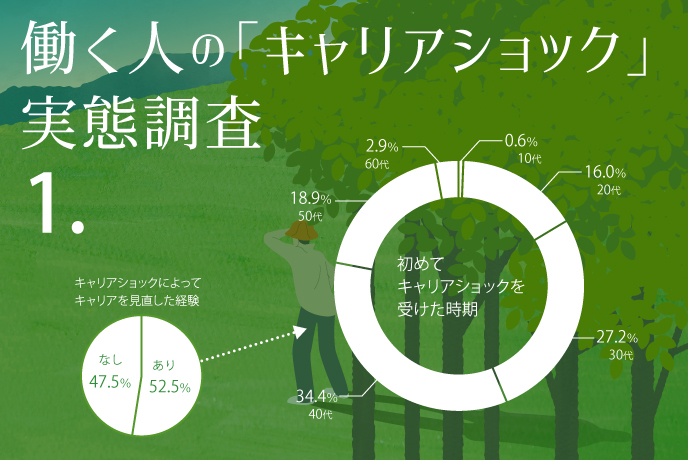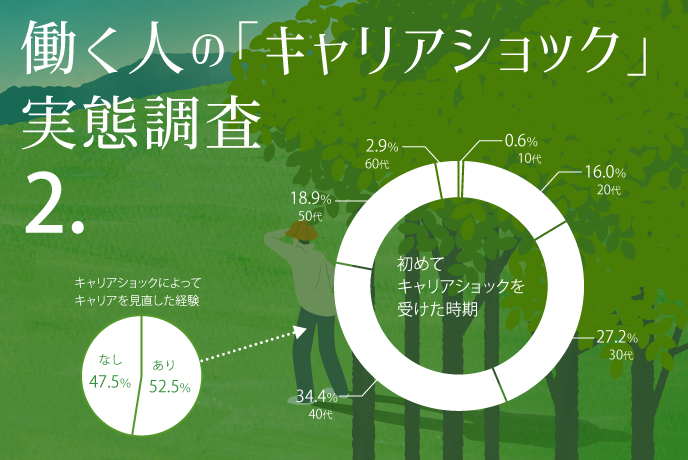「会社はきっと見ていてくれる」――その期待が崩れる時
日本の企業で働く多くの人は、「会社を信じて頑張れば、きっと報われる」と考えて日々仕事に取り組んでいるのではないでしょうか。「真面目に働いていれば、上司や会社がちゃんと見ていてくれるはずだ」――そんな期待が、働くモチベーションになっていることもあるでしょう。しかし、その期待が崩れる時があります。
「キャリアショックのきっかけは「仕事」に多く潜んでいる」の中で見てきたように、では、アンケートの回答者が「キャリアショック」と感じた出来事についての分類をご紹介しました。その中で、会社が関わるものとしては、「雇用・経営の変化」「キャリア上の地位変化」「業務内容・役割の変化」などが挙げられます。こうした変化は、社員自身が望んだものではなく、会社側の判断で起こったケースがほとんどです。社員の立場からすれば、「会社に裏切られた」と感じるような出来事かもしれません。信じていた会社から思いがけない対応を受けた時、人は大きなショックを受けます。それは、単なる業務の変化ではなく、働く前提となっていた会社との信頼関係を揺るがす深刻な問題だからです。
アンケートには、下記のような声が見られました。
-
入社から8年にわたり勤務していた営業所で一番の実績を出し貢献したにもかかわらず、左遷的な異動を命じられた。
-
病気、手術の後に復職してすぐから、今までより過酷なシフトにされた。配慮のかけらもなく、まるで辞めてほしいというメッセージにすら感じた。
といった不本意な異動に関する記述や、
-
すべてを犠牲にして仕事にうちこみ10年働いてきた会社から、2週間後にクビ=退職を告げられた。退職金もなく、失業保険も出なかった。
-
会社の経営が傾き、入社5年目で再就職しやすいという理由でいきなり1カ月後に辞めてくれと言われた。
-
勤務評価はよかったにもかかわらず突然解雇された。
といった、解雇に関わる記述が数多く見られます。
「暗黙の期待」が生む、見えない約束――“心理的契約”とは?
企業で働いていると、「頑張れば認めてもらえる」「会社は自分を守ってくれるはず」といった期待を自然と持つようになります。しかし、その期待が裏切られることもあります。このような時、多くの人が強い怒りや失望を感じます。なぜなら、「会社はそんなことをするはずがない」と、心の中で会社に対して「暗黙の期待」を持っているからです。このような「会社に対する期待と自分が果たすべき義務についての信念」のことを、経営学では「心理的契約」(Psychological Contract; Rousseau, 1989)と呼びます。心理的契約とは、法的な契約とは違い、社員が会社に対して一方的に抱く期待と義務を意味します。
人は、会社が明確に約束しなくとも、過去の経験や上司・同僚の言葉などから「この会社は成果を出せば昇進させてくれるはずだ」「上司は自分の努力をちゃんと見てくれているはずだ」と自分なりの期待を形成します。そのため、会社がその期待に応えてくれなかった時、「裏切られた」と感じ、大きなショックを受けます。こうした心理的契約の違反の認知は、その後のキャリアのあり方に大きな影響を与える出来事であり、キャリアショックの中でも特に重要なタイプの1つです。
「会社に裏切られた」と感じた時、人はどう変わるのか
会社への期待が裏切られた時、「会社への愛着が急に冷める」「会社のために頑張ろうという気持ちがなくなる」「会社を辞める決意をする」など、人の態度や行動は大きく変わります。こうした変化は、ただの不満ではなく、深い失望や怒りにより引き起こされるものです。
心理的契約には、大きく分けて「取引的契約」と「関係的契約」の2つのタイプがあります。「取引的契約」は、給与と労働力といった経済的な交換が中心で、契約期間は短期的といった特徴を持ちます。一方、「関係的契約」は、契約内容は曖昧で、長期的な信頼や忠誠心といった感情的な側面が強いものです。メンバーシップ型雇用が多い日本企業における心理的契約は、この関係的契約に近い側面を持つといえるでしょう。
関係的契約は、感情や信頼に基づいているため、それが裏切られた時のショックはより深刻になりがちです。それに伴う態度や行動の変化も大きいことが知られています。関係的契約は、会社と社員の間に長い時間をかけて築かれた信頼関係のようなものであり、社員は信頼を前提に、「自分も会社のために頑張るのが当然」と思って働いている場合があるからです。
会社に信頼を裏切られたと感じ、もう信頼関係は成り立たないと判断した瞬間、社員の態度や行動は大きく変わります。それまで「当然の義務」として果たしていた行動――残業、後輩の指導、会社の方針への協力など――を一気に放棄してしまうことがあるからです。関係的契約は、目に見えない約束だからこそ、破られた時の反動も大きくなります。信頼があるからこそ頑張れる。逆に、信頼がなくなれば、頑張る理由も消えてしまうのです。
「裏切り」が「キャリアショック」に変わる瞬間
社員が心理的契約の違反を感じたとしても、それがすぐにキャリアショックに直結するわけではありません。重要なのは、社員がその違反に対して怒りや裏切り感といった強い感情を抱き、「心理的契約の破棄」という段階に至るかどうかです。
この「心理的契約の破棄」に至るかどうかは、以下の4つの要因によって左右されます。
- 違反の評価
違反の内容が重大で、本人への影響が大きいほど、心理的契約の破棄に進みやすくなります。例えば、専門職として入社した人が、一般職への異動を命じられたようなケースです。 - 責任の所在
違反と認識された行為の責任の所在が、会社の上層部に属するほど、破棄に至る可能性が高まります。結果をコントロールできる立場にありながら、それを果たさなかったことへの憤りが強くなるためです。 - 公平性の判断
一方で、自分の身に起こったことが、類似した状況では誰でもが経験せざるを得ない出来事であったと判断できる場合、あるいは、不服申し立てなど本人の意向を伝える環境が整えられている場合、心理的契約の破棄に進むリスクは低くなります。 - 組織文化との整合性
同様に、違反の内容とそれに伴う結果がその会社の組織文化に照らして、「許容されるもの」とみなされる場合、心理的契約の破棄には至りにくくなります。客観的には不公平であっても、組織にそうした行為が蔓延しており、メンバーがあまり気にしない状況であれば、心理的契約の破棄は起こりにくいと考えられます。
なぜ、同じ出来事でもショックを受ける人と、そうでない人がいるのか?
心理的契約の違反が引き起こすキャリアショックのユニークな点は、個人差が非常に大きいことです。一見似たような出来事であっても、ある人にとってはキャリアショックとなり、別の人にとってはそうならないことがあるのです。これは、心理的契約の内容が人によって大きく異なるためだと考えられます。社員の会社に対する期待は、個々人のそれまでの経験や日々の出来事の解釈によって、長年にわたり形成されるため、画一的ではないからです。そのため、こうしたキャリアショックを正しく理解するには「その人が会社にどのような期待を持っていたのか」「その期待がどのような経緯で形成されたのか」について深く掘り下げる必要があります。
自律的なキャリア形成のきっかけとしてのキャリアショック
心理的契約の違反は、短期的にはネガティブな経験ですが、長期的に見るとどうでしょうか。これまでのキャリアショック研究では、短期的にはネガティブな経験であっても、それがきっかけとなって、本当にやりたかった仕事の発見など、自律的なキャリア形成につながるポジティブな経験になる場合があることが知られています。
つまり、心理的契約の違反を経験することは一時的には苦しい出来事ですが、それが契機となって本人のキャリア発達につながる場合があるのです。背景には、ある重要なプロセスがあります。それは、会社との信頼関係を前提に描いていた自己概念やキャリアの見通しが一旦崩れることで、自分のキャリアを深く問い直すようになるということです。この内省の過程で、それまで意識していなかった選択肢や可能性に目が向くようになり、「本当にやりたいことは何か」「自分の強みや価値はどこにあるのか」といった根本的な問いに向き合うようになります。
「キャリアショックはなぜ起こるか」でも、将来の社長候補として入社してもらうという約束が履行されず、不本意な思いで退職したが、その出来事がきっかけで、新しいものを生み出したいという本当の欲求に気づけたという事例を紹介しましたが、キャリアショックは単なる挫折ではなく、会社に依存しない自律的で前向きなキャリア形成のきっかけになることがあるのです。
まとめ
心理的契約とは、社員が会社に対して抱く「暗黙の期待や義務」のことです。会社が明示的に約束したわけではなくても、社員は「会社はこうしてくれるはず」という信頼のもとで頑張っているため、不本意な異動や不公平な扱いなど、会社により「約束を破られた」と感じられる出来事に遭遇すると、大きなショックを受けて、それまでの態度や行動を一変させることがあります。こうしたタイプのキャリアショックを理解する上で、「心理的契約の違反」という視点は非常に有益です。
このタイプのキャリアショックは個人差が大きいのが特徴です。その人がどのような期待を会社に抱いていたかを理解することが、適切なサポートのヒントになるでしょう。心理的契約の違反がもたらすキャリアショックは、必ずしもネガティブな側面だけではありません。確かに、短期的には辛く、失望や怒りを伴うような経験ですが、それが自分のキャリアを見つめ直し、新たな道を切り開くチャンスにつながることもあるのです。例えば、本当にやりたい仕事は何かをあらためて考える、自分の価値や強みを再認識する、会社に依存しないキャリアの可能性に気づく、などです。心理的契約の違反とキャリアショックの関係への理解が、キャリアショックを前向きな変化につなげる一助となることを心から願っています。
(参考文献)
Morrison, E. W. and Robinson, S. L. (1997) . When employees feel betrayed: A model of how psychological contract violation develops. Academy of Management Review, 22(1), 226-256.
Robinson, S. L. and Rousseau, D. M. (1994) . Violating the psychological contract: Not the exception but the norm. Journal of Organizational Behavior, 15(3), 245-259.
Rousseau,D.M.(1989). Psychological and Implied Contracts in Organizations. Employee Responsibilities and Rights Journal, 2,121-139.

北村 雅昭氏
大手前大学経営学部・教授。博士(経営管理)。専門は組織行動論、キャリア論。最近の研究テーマは、持続可能なキャリア、キャリアショック、インクルーシブ・リーダーシップなど。著書に「持続可能なキャリア―不確実性の時代を生き抜くヒント―」(大学教育出版)。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ