
「無意味な仕事」からチームと自分を守る
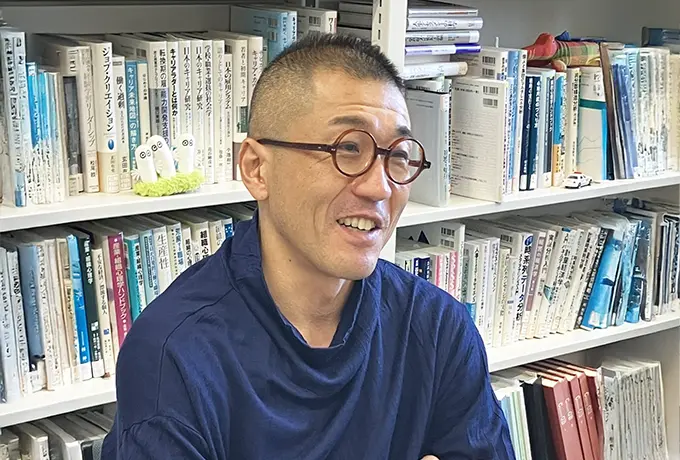
立教大学経営学部教授 中原淳氏
増殖する「無意味な仕事」に抗うことはできるのだろうか。「無意味な仕事」を生み出す組織の構造や心理からチームと自分を守るための具体的な生存戦略について、人材開発や組織開発研究の第一人者である立教大学経営学部教授の中原淳氏に話を伺った。
なぜ、「無意味な仕事」は増殖し続けるのか
濱中:多くの現場で、「無意味な仕事」がなくならず、むしろ増えていると感じるのはなぜでしょうか。
中原:無意味な仕事というのは、「明日なくなったとしても誰も困らない仕事」や「どれだけ頑張っても誰からも感謝されない仕事」だと捉えられます。言い換えると、「届け先がない仕事」ですね。そして、このような仕事は、何も手を打たずにいると、勝手に増えてしまう構造があります。
例えば、マネジャーの仕事についても、雑多な仕事がどんどん放り込まれていくといったことが現場では見られます。それは、マネジャーの仕事の、そもそもの「役割の曖昧さ」ゆえのことです。こうした性質を「役割曖昧性(role ambiguity)」といいます。
マネジメントの定義として最も有名な「Getting Things Done Through Others(他者を通じて事を成し遂げる)」という言葉がありますが、ここには「何をやる人なのか」という具体的な役割が書かれていません。どんな役割を果たすべきか、ということは、定義されていないのです。定義されていないものには、雑多な仕事が投げられていきます。
一方で、会社や社会が無意味な仕事を生み出している側面もあります。社会的な「アカウンタビリティ(説明責任)」の要請に応えていくことがそれに当たります。自分たちの活動を書面で「クオリフィケーション(正当化)」するために、膨大な書類仕事を作り出してしまいます。本来の目的よりもアリバイを作るような「リコグニション(承認)」を得ることが目的化してしまいます。
さらに、職場が「多元的無知」に陥っていて、仕事が整理されないこともあります。多元的無知とは「全員が望んでいないのに、誰も言い出せないがゆえに、誰も望まない行動をみんなで継続してしまうこと」です。かつては必要だった習慣も、今となっては誰もが「無駄だ」「やめたい」と思っている。しかし、「やめろ」という一言が言えない。これは、組織全体が「アンラーン(学習棄却)不全」に陥っている状態といえます。
「ねばならない」の呪縛
濱中:なぜ、誰も「やめよう」と言い出せないのでしょうか。
中原:過去の成功体験への固着もありますが、大きな理由として挙げられるのは、マネジャー自身や経営者が抱いている「ねばならない」という発想です。「変革をしなければならない」「新しいことをしなければならない」「自分は優秀でなければならない」「部下には聞いてはいけない」など、様々な「ねばならない」に囚われていることがあります。こうした思い込みが、現場の実情を無視した不要な仕事を生み出してしまいます。
さらに、上層部への過剰な忖度も起こります。役員がポロッと漏らした感想を部下が指示だと勝手に解釈して仕事にしてしまうのです。言った本人は忘れてしまって「なんでこれ持ってきたの?」みたいなことも起こるのですが、それだけ、マネジャーや役員は強い影響力を持っています。その影響力に気付かない場合、ふいに発した一言によって、現場に忖度が生まれ、ブルシット・ジョブを生み出すのです。
こうした「ねばならない」という発想の厄介な点は、瀕死に至るような危機的状況に直面しない限り、自分がその発想に囚われていることを自覚しにくい点にあります。本人の精神的疲弊や、部下の反発、メンバーの離職といった事態が顕在化して初めて、「ねばならない」という前提そのものが誤っていたのではないかと認識される場合が多いのです。また、人事部門から示されるエンゲージメントサーベイの結果が、気付きの契機となることもあります。
このような状況に陥ることを避けるためには、例えば、最初にマネジャーになる入口で、マネジャーが陥りやすい罠みたいなものをきちんと教えるなどの取り組みが必要です。
チームを守る「お掃除」と「実験」
濱中:「罠」の問題をクリアできたとしても、現場での関わり方次第で状況は悪化します。マネジャーがまず意識すべき点はどこにあるのでしょうか。
中原:新任マネジャーが最初にすべきことは、何かを変えることではありません。まずは、不要なことをやめ、現場の負担を軽くすることです。新しいことに取り組む時は、同時に何かを外さなければ、仕事量は増える一方です。
新しいことをやろうと思っていても、それを急がずに1年待つ。やる前に、みんなの困りごとを真摯に聞きながら、その原因となっている仕事をやめる「お掃除」をすることで、メンバーから情緒的な信頼が得られます。
そこで、私は「やめる会議」を推奨しています。実際に、自らその会議を提案し、現場で立ち会うといった取り組みも行ってきました。若い人を5~6人集めて、自分の周りにある違和感やモヤモヤ、やらなくても誰も困らない仕事について聞いてみる。そうすると、たくさん出てきます。まずは、それを「知る」ことが第一歩です。そして、実際にやめる時には、「実験」と称して始めてみることが有効です。いきなり廃止しようとするとハレーションが生じてしまうので、絶対に変えるとは言いきりません。実験であれば、実験記録を残しながら、既成事実を積み上げていきます。仮にうまくいかなくても、失敗ではなく「データが得られた」ことになりますし、撤退できるように期間限定にしながら、都合が良ければそのまま続けていくこともできます。
ここで重要になるのがAIとの付き合い方です。AIは業務を効率化するという点では、「お掃除」に非常に向いています。例えば、手作業でデータを集計するような業務は、AIに任せることで容易に効率化することができます。ただ、気を付けなければならないのは、「AIを使うこと」が「自己目的化」すると、「AIを使う」という不要な仕事も生まれてしまうので、注意が必要です。
また同時に、どこまでAIに任せるべきかという線引きの問題も生じます。というのも、こうした下積み的な業務をすべてAIに委ねてしまうと、若手がデータの構造を理解したり、業務に必要な基礎的な思考力や判断力を身に付けたりする機会が失われてしまう恐れがあるからです。その意味で、AIの活用は単なる効率化の問題にとどまらず、人材育成のあり方そのものを問い直す問題でもあります。育成については、これまでとは異なる新しいパラダイムが求められているといえるでしょう。
個人を守る「いたしません」と「乗りつつ、白ける」
濱中:無意味な仕事から身を守るために、個人にできることはありますか。
中原:私は、個人が、あらゆる業務や役割において高い水準を維持することは不可能であると考えています。何かを成し遂げたいのなら、やらない何か、を決めることです。したがって、すべてを引き受けるのではなく、意識的に線を引くことが必要になります。有名な医療ドラマの名台詞のように、「いたしません」と言うことです。自分でなくてもできることに対しては、はっきり「No」と拒否する。これを徹底しないと、際限なく「いたす」ことになってしまいます。
とはいえ、会社に勤めているホワイトカラーであれば、「言われたことはきちんとやる」マインドセットの人たちが多く、「やらなければならない」と思っている人たちも多くいるので、どうしても自分の立場では断りきれない場合もあります。その時は、「乗りつつ、白ける」という態度で向き合うことをお勧めします。すでに乗ってしまっていて、しがらみのように逃れることができない状況であれば、表面上はその仕事に乗りつつ、心の中ではうまく距離を置いて白けることが有効です。
また、会社という一つの組織にすべてを預けることは、高いリスクになります。例えば、入社した会社で配属された部署が、将来的な衰退が見えているテクノロジーを扱う部署だったとします。この場合、本人の努力とは無関係に、会社都合の配属先でテクノロジーごと自分のキャリアも沈んでしまうことが起こりかねません。そこで、会社に自分の運命を委ねすぎないように、「二足三足のわらじ」を履くことも必要ですし、そうした複数の居場所を持つことで、「乗りつつ白ける」ための精神的な余裕が生まれます。
聞き手:濱中淳子
執筆:橋本賢二


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ