
「無意味な仕事」が増殖する構造と抗い方
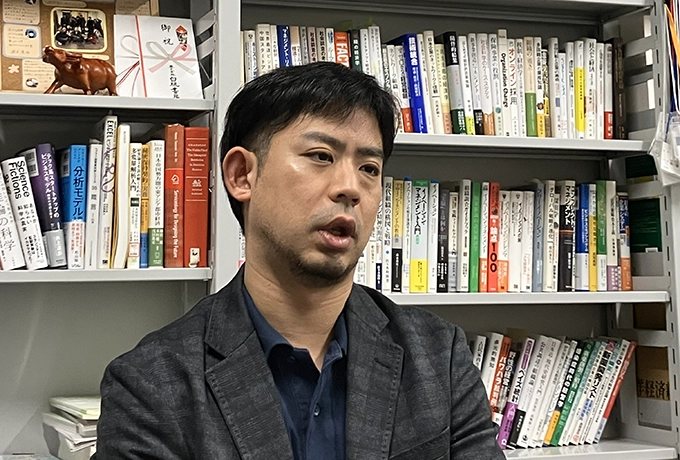
東京大学大学院経済学研究科講師 舟津昌平氏
目標を達成するために合理的に設計されているはずの組織で、なぜ、「無意味な仕事」は増殖し続けるのか。その背後には、仕事を手放せない組織や誰も「やめよう」と言い出せない組織の力学が潜んでいる。無意味な仕事が作り出されてしまう構造から抜け出すために、組織や個人にできることは何か。組織論の気鋭である東京大学講師の舟津昌平氏に話を伺った。
増殖する「無意味な仕事」の正体
橋本:なぜ、従業員が意味を感じられない仕事が増殖してしまうのでしょうか。
舟津:意味のない仕事の発生源は、大きく二つ考えられます。一つは、「本当は必要な仕事だが、本人が意味を見出せていないケース」です。組織の中では本当に必要な仕事で、何らかの意味があっても、本人が意味を見出せていない状態です。これは、上司が意味を教えることで解決することもありますが、意味づけは人によって異なるので、説明されても本人は腹落ちしないという「ズレ」は生じてしまいます。もう一つは、「本当に意味がない仕事」で、かつては必要だった業務が形骸化して、再構築(リストラクチャリング)されずに残っている状態です。中身を読まれることのない書類の作成なども含まれるでしょう。しかし、「意味がないから」といってその仕事をなくすことは簡単ではありません。
仕事を作り、手放せない組織の構造
橋本:仕事の再構築ができないのは、どうしてなのでしょうか。
舟津:そもそも仕事(ジョブ)は、常にあるとは限らず、短い一定期間で、時間とともに現れたり消えたりするものです。仕事が発生する度に人をアサインして、終われば解散するのは理想的ですが、現実には困難です。仕事は柔軟に変化する一方で、組織や人はそれほど柔軟に対応できません。この仕事と組織が相反する関係を持もつ中で仕事の配分を最適化することに難しさがあります。「メンバーシップ型」のように常に使える人が何人かいる状態にして、その人たちを仕事に充てることにはその点で一定の合理性があります。
ただ結果としてほとんどの組織では先に「人」がいて、その人に何か仕事を与えなければならないという力学が働いて仕事を作ります。例えば、自営業であれば、「仕事が終わったから、今日は終わり」と終業しても許されるでしょう。ところが会社組織であれば「今日は終わったから帰っていいよ」とはなかなかならず、現実には「職場にいなければならない」という強迫観念が生じます。本来、仕事には濃淡があるので柔軟に対応できることが望ましいのですが、仕事が少ないときでも「仕事を与えないといけない」という発想が生まれてしまい、これが、要らない仕事を生み出す一因になっています。
また、このようにして生まれたり残ったりする無意味な仕事によって、「本当に困っている人たちはあまりいないように見みえる」という問題もあります。意味がないと思いながら仕事を続けても、組織に与えている影響は見えづらいので、結果としてその状況が肯定されてしまいます。無意味な仕事には、問題として認識されづらいという特性があります。組織全体で見れば無駄を生み出し、ボトルネックになっていても、個人のレベルでは異を唱えるインセンティブがなく、受け入れてもそれほど困らないのが実情ではないでしょうか。これは無意味な仕事が組織の全体最適を阻害する根深い要因です。
誰も「やめよう」と言えない構造
橋本:無意味な仕事を増殖させてしまう組織の構造に対して、「やめよう」と言えないのはなぜなのでしょうか。
舟津:組織としては意味のある仕事を優先し、意味のない仕事は排除するべきですが、現実ではそう簡単にはできません。仕事全体を再構築して人材をアサインし直すことには、大きな労力がいります。しかも、再構築を実行できる人は、権限上も能力的にも普通は社内にあまり存在しません。
仕事の最適配分や再構築は、組織が大きくなると難しさが増します。さらに組織規模が拡大すると、セクショナリズムが生じ、組織内のグループが小さく狭くなっていくことも起こりがちです。自分が属している小さなグループしか信頼できなくなってしまうと、聖域のようなものが生まれて、上司やグループの外から口を挟みにくい場ができてしまいます。このように、本来の組織的な分業が成り立たなくなってしまうのです。
また、ほとんどすべ全ての管理職は、上司でありながら部下です。つまり上司の顔を見ている。管理職に実質的な権限がないようなケースでは、管理職の判断で意味のない仕事をやめる決断ができなくなります。歴史の長い会社では、経路依存性によって仕事に手がつけられない状態になっていることもあります。株式会社ならば会社のトップは株主を見ていることもあり、結局は誰かが言っていることを受動的に聞かざるを得ず、会社における自己決定権がますます後退していきます。同僚、上司、外部ステークホルダーの相互監視の中なかで、ルールを見直す権限があっても、実際に行使することが許されない状況が作られます。このため、仕事の配分や分担を管理するはずの管理職は、1on1など組織のメンテナンス(人間的配慮)ばかり任され、仕事の見直しが役割として認識されなくなってしまいます。
管理職ですら権限がないので、現実的には、ほとんどの労働者に仕事を変える権限はありません。異を唱えたところで仕事を選べないのであれば、「やるしかない」となってしまいます。言い換えれば、「誰かに何か言われるかもしれない」という感覚に陥って、リスクを取れなくなっています。「減点されないこと」が大事になるので、言われたことをやっていれば基本的に減点にはならず、現状肯定に走りやすくなります。そのような状況で無意味な仕事を減らせるわけがありません。
無意味な仕事は、組織やグループの外、場合によっては上司も外部と見みなせば、同時に「外に見せるための仕事」になっていることも多いはずです。中の人にとって意味のある仕事になっておらず、外向けであるがゆえに、中の人たちからは手出しができず、やめる決断がさらに難しくなってしまいます。
「管理しない」という処方箋
橋本:外向けの仕事をなくすために、組織にできることはありますか。
舟津:無意味な仕事は、野放しにした結果ではなく、何かを必死に管理しようとした結果として生まれています。ここから得られる一つのヒントは、「管理しようとしないこと」にあるのではないでしょうか。
昔は、日本企業の強さはミドルにあると言われて、世界から注目されていました。しかし、バブル崩壊後にアメリカ的なトップこそ大事という論調に変わって、相対的にミドルの重要性が後退しました。現在では、プレイングマネジャー化で仕事が集中する問題が生じて、ミドルはますます経営層と現場との間で板挟みになっています。この背景には、ミドルが主体性や自由裁量を認められない存在になってバランスを欠いていることが挙げられます。
トップが決められるのは全体最適の大きな枠組みであって、枠組みと現場の結節点としてミドルが重要な仕事を担っていることは間違いありません。現場のミドルは小さな組織のトップであり、決められることはたくさんあります。ミドルこそ大事な仕事であり、組織における重要性を認めて、待遇や裁量を改善することが必要です。これは、丸投げと紙一重とも受け止められますが、トップが「ミドルが決めていい(責任はトップが持つ)」と示すことも、非常に重要な意思決定です。ここで過度に管理を強めようとすると、細やかな最適化がなされず、意味の薄い仕事が増える危険があります。
この、管理せずに現場の裁量でバランスを取とるメカニズムは、かつての日本企業には備わっていたと言いわれます。伝統的に日本企業は「バランス分化」という自律的な調整機能を備えた組織構造を有していました。どのような組織でも、仕事を分化すると、その人たち特有の文化が出てきて、敵対することもあります。ところが日本企業には、公式に決められたわけではないけれど自由裁量で仕事をする遊軍のような人が必ずいて、その人が部署を超えた調整役を担って分化した組織のバランスを取とってきました。
このような動きは、「余白」によって生まれます。余白は多義的で、例えば、「売り上げ立ててから発言しろ」みたいなものに対して、「まあ、いいこと言っているから聞いてみよう」と受け入れてみるのも余白です。余白はマネジメント可能ですが、一時的な効率性を失うこともあります。それなりの腹をくくってコストを払う覚悟がなければ実現できません。
個人の生存戦略
橋本:組織に生まれてしまう無意味な仕事に対して、個人ができることはありますか。
舟津:仕事に対して自分自身で何か意味を加えていかないと、基本的に仕事は楽しくなりません。仕事自体はそんなに意味に溢れていないという見方をとれば、労働者側が主体的に意味を見出していかない限り仕事に意味など生まれません。
また、本来の組織にとっての意味を忘れてしまっている部分もきっとあるので、それを青臭く語ることを恐れないことも大事です。「世の中のためになる」とかですね。一方で、青臭さとは真逆の「この仕事は意味がない」と言ってしまう態度が、結果として仕事から意味を失わせてしまっていることもあります。もちろん、仕事への向き合い方に関係なく、無意味な仕事は構造的に存在しています。しかし、自分自身の仕事への態度が、無意味な仕事がうまれる構造に加担してしまっている可能性もあります。無意味な仕事から自分自身を守るためには、「意味のある仕事を無意味な仕事に変えてしまっているのは、自分自身の仕事への態度かもしれない」という可能性にも自覚的であるべきです。
聞き手、執筆:橋本賢二


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ