
霞が関に見る「部分最適」の罠
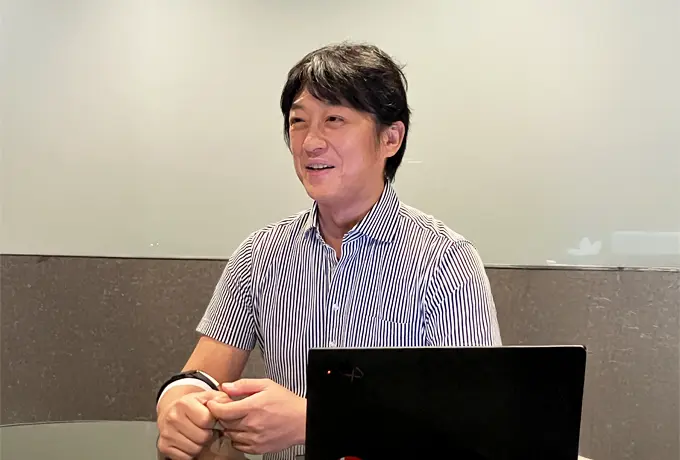
慶應義塾大学准教授 吉井弘和氏
形式的で融通が利かない仕事ぶりを表す「お役所仕事」の背後には、きっと無意味な仕事があふれていそうだ。しかし、こうした仕事は行政だけで生まれているものではない。行政の事例を探ることは、「部分最適」に陥りがちな組織が打開策を考えるためのヒントとなるかもしれない。そこで、戦略コンサルティング会社や霞が関での勤務を経て、現在は官民の境界を越えて活躍しようとする人材の支援もしている慶應義塾大学准教授の吉井弘和氏と対談した。
行政組織に似てきた民間企業
橋本:トップダウンでやらざるを得ない仕事に、現場レベルでは疑問を感じてしまうことがあります。こうした仕事は、行政に限らず生まれてしまいますが、やはり行政は特殊なのでしょうか。
吉井:民間と行政の本質的な違いは、価値の多元性にあります。民間は企業価値やパーパスを絶対的な価値としながら、経済合理性で判断をしやすいのが特徴です。一方で、行政組織は価値が多元的で、経済合理性だけで判断できない事柄が多くあります。
また、行政ではコンプライアンスやミスに対する意識が民間以上に強いです。1万回に1回のミスでも、民間であれば謝罪で済むかもしれませんが、行政の場合は大きく炎上してしまうこともあります。オペレーションにミスがあると、国民からの信頼を失い、私権を制限する正当性を揺るがしかねません。
しかし、民間が行政と似てきた側面もあります。近年は、企業においてもディフェンス的な意味合いで社会からの要請に応えることが増えました。
橋本:民間が行政に似てきているというのは面白い考え方ですね。民間でも社会的責任がより問われるようになっています。
吉井:サプライチェーンでの人権問題や環境配慮など、企業にとって炎上リスクは無視できないものになりました。かつては、公共組織にしか求められなかったようなことが、民間企業にも求められるようになり、両者が似てきました。その出発点は、単一のわかりやすい価値を追求できた時代から、多元的な価値を尊重する時代に変化したことにあると考えています。
完璧さを追い求める先
橋本:日本の行政組織では、皆が忙しそうに働いていますが、実はあまり意味がない仕事やポジションのための仕事が生まれているという可能性はないでしょうか。
吉井:意味があるかのように、自分たちで意味づけしていることはありそうです。職員は配属された以上は、その仕事を達成しなければならないと考えて、新たに仕事を作ってしまう側面はあります。例えば、補助金の検査業務では、合理的に考えれば抽出調査でも十分なものであっても、不正を見逃すわけにはいかないという意識から、全数調査にこだわってしまうことが起こります。
橋本:人件費や時間に対するコスト意識の低さが、新たな仕事を作っているのかもしれませんね。
吉井:その根底には、行政は国民に対して強制的に権利を制限しうるという、民間とは異なる特殊な関係があります。企業であれば、業界には競合がいて、その中で顧客が自分にとってベストな会社や商品を選択します。他方で行政は唯一無二だからこそ、強制的に国民の選択肢を奪ってしまいかねません。この点への意識が行きすぎると、手段が目的化してしまうことがあります。例えば、霞が関文学とも言われるわかりにくい文章を書くことは、様々なステークホルダーの想いを反映した結果を代筆しているだけだと説明できてしまいます。さらに行きすぎると、自分たちが後で追及されないように、都合よく解釈の幅を持たせることもできます。こうした事情が、コスト意識よりもリスク回避を優先させてしまいがちな構造はあるかと思います。
橋本:言い訳をしやすい構造がありますね。
吉井:しかし、逆説的に、独占状態にあることで言い訳が許されない構造も抱えています。行政の仕事には比較対象がないので、「この程度のミスで済んでいる」という主張が通用しません。そのために、リスクに過剰になり、リターンを追求する行動が生まれにくいという面もあります。
庭先だけを綺麗にする部分最適
橋本:民間企業でもリスクは極限まで低減できるように努めていますが、リスクへの過剰さという点で、民間と行政は異なるのでしょうか。
吉井:違うと思います。例えば、過去の話にはなりますが、勤怠管理のために、出退勤表、パソコンのログ、押印する出勤簿と3つの手段を併用することは、民間企業では考えられないでしょう。このようになる背景には、まず、業務改善への投資の難しさがあります。一つのシステムにまとめてもわかりやすい効果は生まれず、予算を確保したり、関係者と調整をしたりすることには時間がかかってしまいます。また、単年度予算の考え方なので、機動的な対応も難しいです。さらに、多少の労働時間を削減しても、国の予算全体に対して事務費が占める割合はわずかです。労働時間削減も含めたコスト削減が企業価値に直結するビジネスとは大きな違いです。ほかにも、競合他社がいないため全体的なコスト水準の高低が判然としないこともあります。その結果、オペレーションの改善に積極的に取り組みたいというインセンティブが働きにくい構造があります。
橋本:日本組織の場合、特に、オペレーションへの意識やコンセプチュアルな発想が弱いという指摘もあります。この指摘は役所にも当てはまりそうですね。
吉井:職員は真面目に自分の仕事をしようと考えているので、自分が果たさなければならない仕事に影響が及ぶことには、反対してしまうことがあります。自分に与えられたミッションを超えて、組織全体のミッションを考える思考様式が根付いていないように感じる時は多々あります。本来は省庁や局課の前に国家公務員であるはずなのですが、自分の持ち場である庭先だけを綺麗にしておくように、所属している課の人間として考える習性が強くなっています。
長期の政策と短期の人事異動
橋本:政策を国民に届けることを考えれば、オペレーションこそ重要です。しかし、行政ではオペレーションへの意識が希薄になりがちです。なぜ、オペレーションが軽視されてしまうのでしょうか。
吉井:官僚になる人は、そもそも政策を作りたいと思って仕事をしている人たちです。しかし、1年から2年の頻繁な人事異動の中では、自分が関われる期間が限られているので、どうしても目の前の課題を優先してしまいます。そのために、オペレーションへの関心が持てなくなってしまうのではないでしょうか。
政策を届けるための時間軸は長く、イメージが湧きにくいです。例えば、法律改正では、2年くらいの仕込みを経て国会での審議に至り、可決後も施行準備に2年くらいかけてようやく世の中に出ます。実際に使われ始めても、最初は利用率も低く、浸透してインパクトが出るまでには10年単位の時間がかかります。すぐに成果が出せないので、最後のリアルなインパクトまで責任を持つことにやりがいを見出すのは難しいです。その結果として、法改正の実現など、自分が担当している仕事の中間指標を目指すようになっています。
橋本:政策実現の長い時間軸に対して、担当として関われる時間は短い。そのために、責任が細かく分割され、全体を意識することが難しくなっていますね。
吉井:民間企業の事業はもっと短いサイクルで成果を出します。人事部主導の人事ローテーションがある企業でも人事異動のサイクルは5年程度と比較的長いので、最初からオペレーションまでを見据えて取り組めます。行政の頻繁な人事異動の理由としては、癒着防止が挙げられます。ただ、抜き打ち検査するなど癒着防止のための手段はほかにもありますし、今となっては見直しの余地が多々あるのではないでしょうか。
橋本:最後まで責任を持ちたいという職員がいれば、その人に任せるという人事の柔軟性があってもいいですね。
吉井:そのような希望を持つ人材も確かにいますし、やって損をする話ではないですよね。行政では国の地方機関や市町村、独立行政法人なども含めて数百万人単位で事業を動かしており、その関係性としても市町村は国の下部組織ではなく独立した存在という特殊性があります。このような規模の大きさや関係の複雑性を乗り越える上でも、関わる時間の長さは重要な視点だと思います。
数百人のトップと向き合う
橋本:もう一つの行政の特徴として、意思決定の機関が国会などの外部にある点が挙げられます。これは、特有の問題を生じさせているのではないでしょうか。
吉井:民間企業であれば、企業価値やパーパスという共通言語で、従業員と取締役の対話が成り立ちます。一方で、行政の場合は、党や議員の間で重視する価値観がまったく違っているために、対話を成り立たせることが難しいケースがあります。ここでも、価値の多元性が影響してきます。
橋本:それぞれの議員には議員としての合理性があり、社会的な視座から要請をします。一方で行政の現場では、現場の感覚や価値観で動いているので、それらの論理が衝突してしまうこともありますね。
吉井:そこが面白い点でもあります。行政にとって議員はトップダウンで指示をしてくるような存在として思われがちですが、実はボトムアップの側面もあります。官僚よりも国民や現場の声に接しているので、制度の細かなところまで知っていることがあります。民間企業でいえばたくさんの顧客と接しているトップのような存在です。そのような議員が何百人もいて、それぞれの議員が信じている価値が異なっているので、行政としては、多くの議員の意見を聞き、調整しながら仕事をせざるを得ません。
橋本:そのような構造は、日本だけに見られる特徴なのでしょうか。
吉井:イギリスでは、議会の審議の日程を政府でコントロールできるなど、首相に権限が集中しています。このため、イギリスの官僚は政権中枢を見ながら仕事をする意識が強いです。一方で、日本の場合は権限が個々の議員に分散していて、それぞれの議員の価値観が異なるので、その間を調整していくような仕事になります。そのために、やや感覚的な表現になりますが、行政組織では施策の内容を企画している時間が5%くらいで、残りの時間は根回しや納得してもらうための説明、施策の細部の調整などに費やすことになりがちです。
橋本:政治的な動きの中で意味のなさを感じてしまう仕事も、見方を変えれば意味があるのだとすれば、行政には意味のない仕事は存在しないのでしょうか。
吉井:想像力の問題なのだと考えます。例えば、議員が地元で使うスピーチの原稿を書くことも、かつての行政ではよく行われてきました。それも、回りまわって政策を実現するためにやっていると考えれば意味を持ちます。しかし、線引きが曖昧なままに行きすぎてしまえば、職員の過重労働につながります。では、過重労働に対して、政策の円滑な実現という効果が妥当なのかというと、リンゴとオレンジを比べるようなもので議論はかみ合いません。ですので、議員が地元で使うスピーチの原稿については、費用対効果ではなく、制度論的にあるべき姿なのかという議論で整理する必要があります。また、スピーチを書くことが学びにつながるという発想もありえますが、1日6時間働いた後の2時間と1日12時間働いた後の2時間では、学びに対する捉え方も異なります。
全体最適に向けた打ち手
橋本:行政にも似たヒエラルキー構造を持つ組織において、より意味がある仕事に向き合えるようにしていくためには、どのような打ち手が考えられますか。
吉井:現場で起きていることを見える化して、価値につながる作業なのか否かをわかるようにすることです。しかし、その副作用として、数値化は指標を選ぶことが別の価値の切り捨てにつながり、選んだ価値の間の優先順位も決めなければいけません。だからこそ、量的に表れないものに対して質的にアラートを出すような仕組みも必要です。
橋本:確かに、見える化はとても大切ですね。しかし、数値化することに過剰にこだわったり数値化するだけで満足してしまったりする危険もあります。だからこそ、同時に組織の中に議論ができるような土壌を作らないと、判断基準が部分最適に向かってしまいますね。
吉井:そのためにも、全体最適に向けたインセンティブの設計が重要です。どのような組織でも解決に向けたすべての資源を持っている人はいません。トップは現場の情報を持たなければなりませんし、現場は組織全体のことを考えるような設計にしなければ、どうしても部分最適に陥ってしまいます。部分最適に陥りそうなところに、全体に対する視野を持ってもらうための仕組みが必要で、現場を知らずに意思決定しかねないところには、情報を流通させなければなりません。
聞き手、執筆:橋本賢二


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ