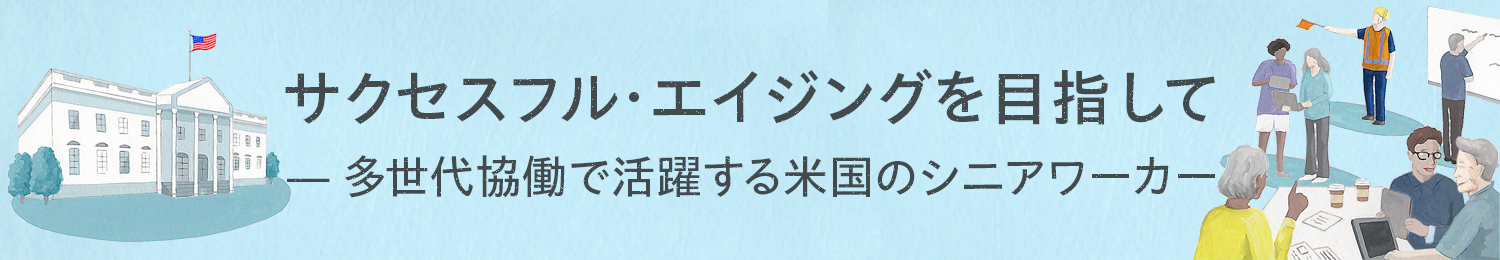
ジェロントロジーから幸福な老後を考える

ジェロントロジーとは
ジェロントロジー(Gerontology)とは、ロシアの動物学者エリ・メチ二コフ(Élie Metchnikoff)氏が1903年に提唱した概念である。日本語では「老年学」あるいは「老人学」と訳されることが多い。メチニコフ氏は、老化の生物学的側面を研究し、この分野の基礎を築いた。その後、ジェロントロジーは、生物学的、臨床的、心理的、社会学的、法的、経済的、政治的など、加齢に関するあらゆる側面を探究する学問へと発展した(※1)。
米国では1945年に設立されたGerontological Society of Americaが、ジェロントロジーに関する学際的な研究と情報発信を行っている(※2)。
ジェロントロジーと類似する分野にジェリアトリック(Geriatrics)がある。これは老衰や老化に伴う医学的問題の診断、管理、予防を扱う医学の一分野である(※3)。
両分野とも、近年の人口動態の変化やベビーブーマー世代の高齢化、平均寿命の延伸などを背景に注目を集めており、研究が活発化している。
米国のジェロントロジー研究では、一般的に65~74歳を前期高齢者、75~84歳を中期高齢者、85歳以上を後期高齢者と分類し、老年期に特有の疾患や年齢層ごとの傾向についての調査が進められている。
サクセスフル・エイジングという考え方
「サクセスフル・エイジング」という概念は、1997年に医師のジョン・ウォリス・ロウ(John Wallis Rowe)氏と心理学者ロバート・ルイス・カーン(Robert Louis Kahn)氏が共著で出版した文献「サクセスフル・エイジング」に端を発するものである。老化という誰もが避けられない現象を、いかに円滑に乗り越えるかという普遍的テーマに取り組んだ同書は、ジェロントロジー分野において大きな注目を集めるとともに、ジェロントロジーの考え方を社会に広める契機となった(※4)。
同書によると、サクセスフル・エイジングには3つの不可欠な構成要素が存在する。1つは疾病や障害からの解放、1つは高い認知機能と身体機能の維持、もう1つは日常生活への積極的な関与である。また、これらを少し言い換え、長寿、生活の質、社会貢献の3要素とする見解も存在する(※5)。
サクセスフル・エイジングのモデル
サクセスフル・エイジングには、医学、心理学、社会学、倫理学など多様な分野からのアプローチがあり、それぞれの専門性に基づいたモデルが構築されている。
たとえば、心理学におけるモデルでは、①自己受容、②満足のいく対人関係、③自律性(自立して行動を自己制御できる能力)、④環境制御、⑤人生の目的、⑥人間的成長という6つの要素を軸に、心理的幸福に基づくモデルが提案されている(※6)。
一方、社会学的アプローチでは、高齢者を活動から引退させようとする社会的風潮を否定し、中高年と同様に活動を継続することをサクセスフル・エイジングと定義している(※7)。
サクセスフル・エイジングとワーク・ライフ・バランス
多くの人は、学校卒業後に就職し、数十年にわたって働き続ける。人生において仕事に費やす時間と労力の割合は非常に大きく、それが老化に影響を与えることは否定できない。世界的に見ても、仕事と老化の関係性を深く掘り下げた調査研究は少なく、職場環境や業務内容がサクセスフル・エイジングにどのように関与するのかについては、現時点では明確な結論が出ていない。
しかし、ワーク・ライフ・バランスがサクセスフル・エイジングに大きな影響を与えることは明らかであり、ウガンダの医療分野を対象とした研究調査では、適切な就業時間、在宅勤務、産前産後休暇や育児休暇など、仕事と生活の調和を図る職場慣行に加え、退職前のセミリタイアメントに関するカウンセリングやガイダンスが、サクセスフル・エイジングに寄与するという結果が示されている(※8)。
また、週に35時間未満で就労する高齢者は、働いていない高齢者や週に35時間以上働く高齢者に比べて抑うつ症状を経験する可能性が低く、インフォーマルな社会参加レベルが低い高齢者よりも、社会参加レベルが高い高齢者のほうが、抑うつ症状を経験する可能性が低いという調査結果も存在する(※9)。これらの知見から、高齢者の抑うつ症状のリスクを最小限に抑えるためには、最適な労働時間と社会参加の程度を維持する必要があると指摘されている(※10)。つまり、高齢者が充実した生活を送るためには、ワーク・ライフ・バランスと積極的な社会参加が重要であり、それがサクセスフル・エイジングを可能にすると考えられる。
サクセスフル・エイジングからプロダクティブ・エイジングへ
老化へのアプローチとしては、サクセスフル・エイジングに加えて、プロダクティブ・エイジングという考え方が存在する。プロダクティブ・エイジングは、高齢者による経済的成果やサービスの提供に焦点を当てた概念であり(※11)、技術やスキル、人的ネットワーク、ボランティア精神などを活用し、経済・産業社会や地域社会に対して自律的に貢献することを目的としている(※12)。
プロダクティブ・エイジングに関する研究は、現時点ではそれほど進展していないものの、リタイアメント後の就労、産業活動、農作業、ボランティアなどの生産的な慣行を含むこの考え方(※13)は、年金や社会保障の受給資格を得た後も、なお活発に生活を送りたいと考える現代のシニア層の行動様式に適合していると考えられる。
そのような「プロダクティブ」な生き方を志向する人々を、ウェルビーイングの観点から配慮を行いつつ、人的資源として有効に活用することが、「サクセスフル」な老後の実現につながるのではないかと示唆される。
(※1)National Research Council (US) Committee on Chemical Toxicology and Aging, “Aging in Today's Environment” (1987)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK218728/ (last visited August 4, 2025)
(※2)Gerontological Society of America Website. https://www.geron.org/ (last visited August 4, 2025)
(※3)前掲注1
(※4)J.W. Rowe and R.L. Kahn, “Successful Aging” (1997) PMID: 9279031
(※5)柴田博「サクセスフル・エイジングの条件」日本老年医学会雑誌39巻2号(2002年)https://www.jstage.jst.go.jp/article/geriatrics1964/39/2/39_2_152/_pdf (last visited August 4, 2025)
(※6)Waddell C, Van Doorn G, Power G, Statham D, “From Successful Ageing to Ageing Well: A Narrative Review” The Gerontologist, Vol. 65(1), Issue 1 (2024) https://academic.oup.com/gerontologist/article/65/1/gnae109/7733290 (last visited August 18, 2025)
(※7)長寿科学振興財団「サクセスフル・エイジングとは」健康長寿ネット(2022年)
https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/tyojyu-shakai/successful.html (last visited August 18, 2025)
(※8)Kibedi, H., Nakasiita, K., Kakinda, A., P’Olak, K., & Muwonge, C., “Influence of Work-Life Balance and Work Engagement on Successful Aging at Work in Uganda Health Sector” East African Journal of Health and Science, 8(1), 46-61 (2025)
https://doi.org/10.37284/eajhs.8.1.2614 (last visited August 18, 2025)
(※9)Kim YM, Jang SN, Cho SI., “Working Hours, Social Engagement, and Depressive Symptoms: An Extended Work-Life Balance for Older Adults” BMC Public Health 23, 2442 (2023)
https://doi.org/10.1186/s12889-023-17072-x (last visited August 18, 2025)
(※10)前掲注9
(※11)Lin K, Ning Y, Mumtaz A, Li H, “Exploring the Relationships Between Four Aging Ideals: A Bibliometric Study” Front Public Health (2022) PMID: 35127615
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35127615/ (last visited August 18, 2025)
(※12)平田潤「『長寿大国=日本』Well Beingと3つのエイジング」世界経済評論インパクトNo. 3573(2024年)
http://www.world-economic-review.jp/impact/article3573.html (last visited August 18, 2025)
(※13)前掲注11

ケイコ オカ
2001年大阪大学大学院法学研究科博士課程修了。専門は労働法。同年4月よりリクルートワークス研究所の客員研究員として入所。労働者派遣法の国際比較や欧米諸国の労働市場政策を研究する。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ