
深夜3時の打合せが示す国会審議の構造的問題
1.深夜の打合せは「異常」なのか
あなたがランチを食べていると、上司から明日の株主総会で使う質疑応答資料の作成を命じられ、「打合せは午前3時からだ」と言われたらどう感じるだろうか。
2025年11月7日、高市総理大臣は予算委員会の準備のため打合せを午前3時から官邸で行ったことが話題となった。この一件は、「官僚の働き方改革に逆行する」と国会でも指摘された。もちろん、この国を揺るがすような大災害や大事故などの突発的な危機に対応するためであれば、時間に関わりなく総理や関係省庁は対応しなければならない。
しかし、予算委員会は突発的な出来事ではない。開催があらかじめ決まっている「予定された審議」であるにもかかわらず、なぜ、準備が直前の深夜から早朝にかけて行われるのか。
ビジネス界では、会議を充実させるためにアジェンダを事前に共有し、十分な準備時間を確保した上で臨むのが通常であろう。予定された審議に対して深夜対応が必要になること自体が、仕組みの不備を示している。この非効率の裏には、国会審議という仕組みそのものに根深い構造の問題がある。
2.開催日が直前に決まる非効率
今回の一件について、質問通告を原因とする指摘がある。質問通告とは、予算委員会で質問する議員が何を質問するかをあらかじめ連絡する国会の慣行であり、政府側が答弁準備をするための時間を確保し、国会審議を円滑に進めることを目的としている。
この質問通告は、1999年9月に与野党が「質疑者は原則として前々日の正午までに質問の趣旨等について通告する」と申し合わせたことが元になっている。2014年5月には「充実した質疑と、国家公務員の過剰な残業是正等を行うため、すみやかな質問通告に努める」と努力目標に変更され、2025年6月の通常国会でも与野党が確認している。つまり、現在の国会において、前々日の正午までというルールは存在せず、各党の内規に委ねられている。
実際に問題となった7日の審議に関して、同日に行われた木原稔官房長官の記者会見では、質問通告が出そろったのは前日の6日昼であり、前日6日夜に総理が公務を終えた時点で答弁書ができあがっていなかったことを明らかにしている。
質問通告が遅くなった背景には、委員会の開催日の決定が遅れたことがある。立憲民主党の枝野幸男氏がX(旧Twitter)への投稿で明かした経緯によれば、今回の予算委員会は、「質疑時間や与野党間の配分比率、それを踏まえた会派ごとの持ち時間などが事実上決まったのが2日前の5日(水)の正午前後で、正式決定は6日(木)の正午前後」であったという。
この時系列をビジネスに置き換えれば、株主総会の詳細が事実上決まった前々日の正午から、質問者が質問を考えると共に、応答者も資料を作り始めるようなものだ。
質問通告をめぐる問題の本質は、そもそも委員会の日程に加えて、「どのような議題で、何時間の委員会を開くのか」という要項も、直前まで決まらないことにある。
3.準備不足が招く審議の形骸化
なぜ、委員会の開催要項を直前まで決められないのか。
国会は国会法によって会期という営業期間が決まっており、さらに法案を次期に持ち越すことができない(「会期不継続の原則」会期中に議決されなかった法案は原則として廃案となる)。この短い営業期間内に全ての案件を詰め込まなければならないため、日程が過密になり、短い時間で何を優先するかという日程自体が、与野党の政治的駆け引き(日程闘争)の対象となってしまう(大山, 2025)。
こうした審議時間の欠如は、審議の質を下げている。法案の議事録を分析した研究(幸田, 2023)によれば、
- 審議の大半を占める政策に関する質疑がかみ合った議論となっていない
- 解釈に関する質疑は政府解釈を明確化する質疑が少ない
- 最も重要な法文(条文)に関する質疑(法案を修正するための論議)はほとんど行われていない
ことが明らかになっている。つまり、現在の国会では、政策の中身が深められず、条文の修正も議論されないまま形式的な質疑が繰り返されている。
想像してみてほしい。タイトな日程のなかで質問と答えがすれ違い、意見が対立したままに時間だけが過ぎていく会議。準備不足でアジェンダが揺らぎ、ビジネスに置き換えれば契約書にあたる法案の条文確認や修正ができない会議。
もし、同じような会議運営が毎日のように会社で行われていたら、その会社の生産性は大きく損なわれるだろう。私たちの税金で運営され、税金の使い道を検討する国会には、議論の質を高める構造改革が必要だ。
4.真の解決策は日程確定のルール
この問題を解決するために、「国会を通年化すれば時間が確保できる」という案がある。しかし、これは国会法が関係する話であり、即効性がない。もっとすぐにできる現実的な解決策は、委員会開催日を質問通告のルールよりも早く確定させることだ。
例えば、「委員会開催日は、少なくとも開催日の3営業日前までに、議題と時間を確定させる」というルールを設ける。たったこれだけでも、質問側(野党)と答弁側(政府・官僚)の双方に、最低限の準備時間を設けることができる。
もちろん、これは、日程闘争という野党にとって伝統的な交渉カードを一部手放すことを意味する。
しかし、国民にとってより重要なことは何か。十分な準備時間で政府の矛盾を突く「質の高い質疑」を用意するほうが、よほど建設的で、国民の支持も得られるのではないか。すれ違いの対立ではなく、お互い妥協点を見出しながらより多くの人の支持を得られるように、政策の方向性や法案の変更を実現することこそ国会に期待されている役割ではないだろうか。
開催日程の早期確定ルールを設けて、お互いに準備時間を確保することで、議論の焦点が明確になり、より実質的な議論が可能になる。これこそが、午前3時の非効率な打合せを過去のものにする第一歩だ。
これは、官僚の働き方改革になるだけでなく、政府も答弁の準備に十分な時間を確保できる。そして何より、準備万全の与野党が臨む「質の高い質疑」が、私たちの税金の使い道を左右することになる。
拙速な会議が企業の生産性を下げるように、拙速な国会審議は議論の質を下げる。今、必要なのは「委員会の開催日程を早期に決めるルール」だ。
参考文献
大山礼子(2025)『国会改革の「失われた30年」』信山社出版
幸田雅治(2023)「法案審議の実態分析と制度的基盤に関する研究」科学研究費助成事業研究成果報告書
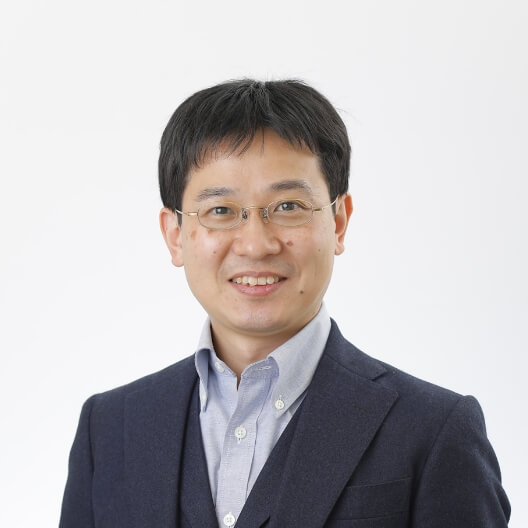
橋本 賢二
2007年人事院採用。国家公務員採用試験や人事院勧告に関する施策などの担当を経て、2015年から2018年まで経済産業省にて人生100年時代の社会人基礎力の作成、キャリア教育や働き方改革の推進などに関する施策などを担当。2018年から人事院にて国家公務員全体の採用に関する施策の企画・実施を担当。2022年11月より現職。
2022年3月法政大学大学院キャリアデザイン学研究科修了。修士(キャリアデザイン学)


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ