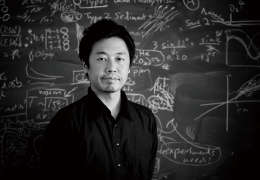Macro Scope
脳を持たない粘菌が集団行動する秘密

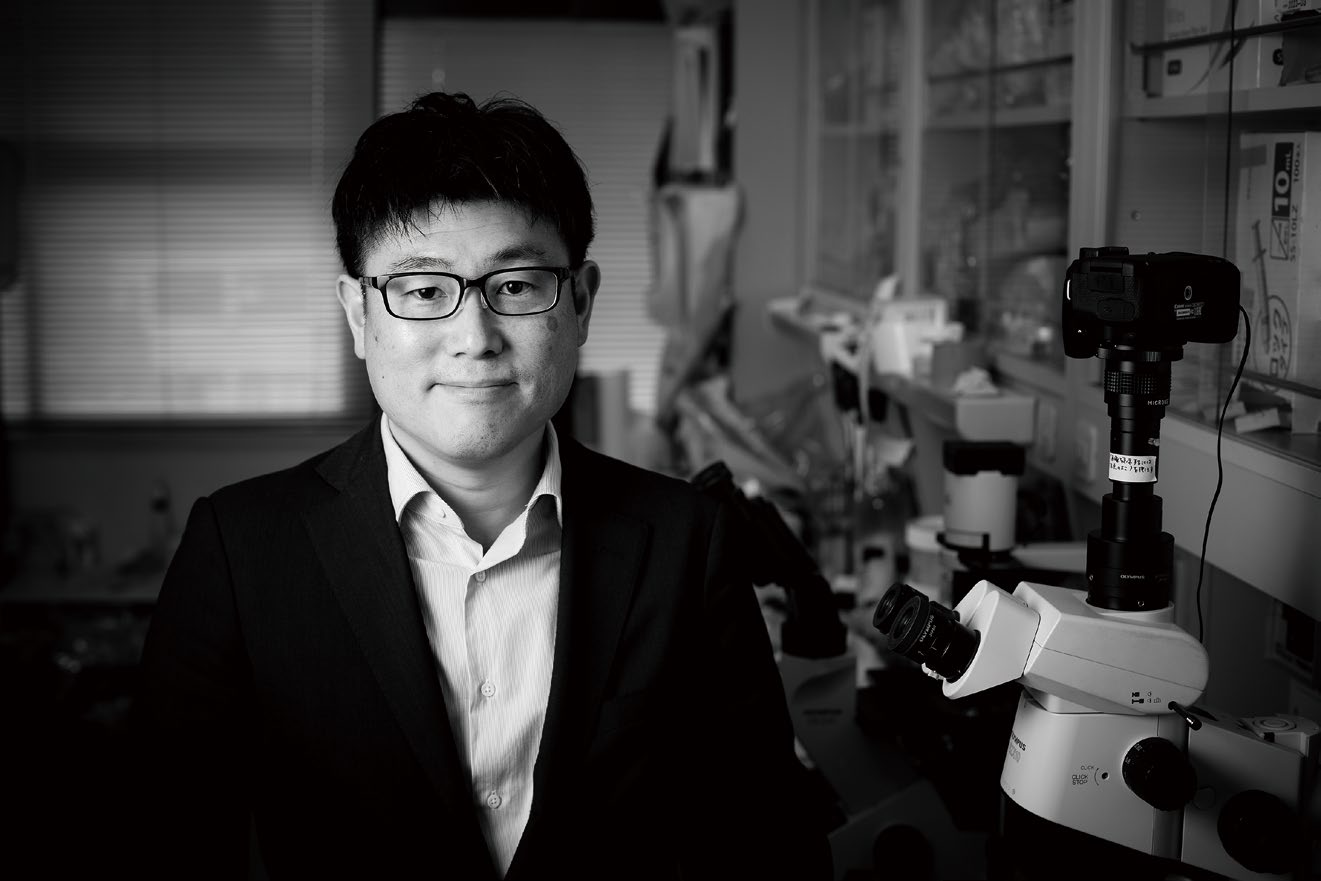 生物物理学者 澤井 哲氏
生物物理学者 澤井 哲氏
Sawai Satoshi 早稲田大学理工学部応用物理学科卒業、同大学院修士課程修了、東北大学大学院博士課程修了。博士(情報科学)。プリンストン大学分子生物学部博士研究員、科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業・総括実施型研究(ERATO)複雑系生命プロジェクトグループリーダー、東京大学大学院総合文化研究科准教授などを経て、2018年より東京大学大学院総合文化研究科教授。2012年文部科学大臣表彰若手科学者賞受賞。
粘菌という、その名に「菌」とつきながらも菌類ではない不思議な生き物がいる。脳を持たない単細胞生物であるにもかかわらず、環境に応じて集合体になったり、役割分担したりするその動きを組織の集団行動になぞらえる人事の人々もいる。そんな粘菌を見つめ、研究し続ける澤井哲氏に、粘菌とはどのような生物なのか、なぜ集団行動を取れるのかを聞いた。
― まず、粘菌というものがどのような生物なのか教えてください。
粘菌とは、移動するという動物的な性質を持ちつつも、胞子によって繁殖する植物的な性質をもあわせ持つ生物です。菌というと、カビなどの真菌を思い浮かべますが、そうした菌類とはまったく別物です。
そして粘菌には、真正粘菌と細胞性粘菌という大きく分けて2つの種があります。両方とも単細胞生物なのですが、真正粘菌は多くの細胞が集まって融合し、多核の大きな細胞になることがあります。単細胞でありながら幅1メートルものアメーバになることもある変形菌は、真正粘菌の一種です。
一方の細胞性粘菌は、多くの細胞が集合する性質を同様に持ちますが、融合はせず、一つひとつの個体が維持されたまま集団を形成します。この細胞性粘菌が、私の研究の主対象です。
― 生物学上、粘菌はどのように分類されるのですか。
真核生物の分類は動物界・植物界・菌界の3つがよく知られていますが、それとは別にアメーバ界があることがわかってきました。粘菌は、このアメーバ界に分類されます。
アメーバの特徴は、這い回って、自由自在に膜を変形させながら、外物を取り込んで栄養にすることができること。細胞性粘菌も、一つひとつの細胞が自由自在に膜を変形させて動き回ります。
私たちヒトを含め動物の体内にもアメーバ様の動きをする細胞が存在します。がん細胞や、そうした異物を排除しようとする白血球などの免疫細胞が代表的です。
“飢餓状態”になると集団を形成する
― 単細胞の生物が集団を形成する、ということがとても不思議に思えます。どのようなメカニズムなのでしょうか。
細胞性粘菌は、栄養が十分にある環境では単細胞アメーバとして存在しています。それが集合体となって変幻自在に動き回るようになるのですが、集合するきっかけを作るのは“飢餓状態”です。粘菌が存在する環境に栄養が少なくなると、集団となって子実体(しじつたい)を作るのです。子実体とは、胞子を形成し放出するための“キノコ”のような形態です。子実体となって次世代につながるクローンである胞子を放出するのです。これが、いわば集団を形成する “目的”です。集団を形成する具体的なメカニズムはというと、飢餓状態になったとき、細胞性粘菌が放出するサイクリックAMP(以下、cAMP)という物質がそのカギとなります。
cAMPは、ほかの粘菌に集合を促すシグナルであり、このシグナルを受け取った周囲の粘菌は自分自身も同じくcAMPを周囲に放出します。数百から数万もの細胞のcAMPの放出がそろって、波打つように集合し、子実体を形成するのです。この様子を顕微鏡で観察すると、きれいな渦巻き状の動きが見られます。それはあたかも、サッカースタジアムで観客がウェーブを起こすような、規則正しい動きの連鎖です。
指揮するリーダーはいない “たまたま”動き出す
― 気になるのは“誰”がcAMPを出し始めるのか、ということです。
サッカースタジアムのウェーブになぞらえて考えてみましょう。ウェーブが起こるときには、当然起点があります。起点は、リーダーシップを発揮した誰かの場合もありますが、もしかすると、最初に立ち上がった人が単にトイレに行きたかっただけかもしれません。
実は、集合を開始するときに最初にcAMPを出す粘菌は、あらかじめリーダーとしての性質が備わっているわけではなく、“たまたま”そうなりやすい状況だっただけのようなのです。
いくつかの粘菌がcAMPをたまたま放出することでランダムに動き出します。周囲の粘菌もcAMPを放出し、じわじわと付近のcAMP濃度が高くなると、それがさらにほかの粘菌の興奮を誘発し、最終的には集団内のすべての粘菌が動き出し、それが規則的な振動となって現れます。多くの細胞が集合して塊となり、最終的にはそれが子実体を形成します。
― 集合して何かを形成する姿は、まるで人間の組体操のようですね。たまたまcAMPを放出するとのことですが、そうする粘菌とそうでない粘菌の差は何なのでしょう。
細胞は、遺伝学的に同じであっても、それぞれ個性がありつつ機能的です。これが無機質な人工物にはない面白いところです。粘菌の場合、個性の1つは、cAMPを受け取る受容体やそれを合成する酵素の量です。受容体がcAMPを受け取るとさらに受容体が作られ、より多くのcAMPを受け取るというポジティブフィードバック構造があって、どんどん活性化します。
一方、受容体が少ない粘菌は刺激に反応せず、ポジティブフィードバック構造に入っていかないので不活性のままになりがちです。なぜこうした違いが生まれるか、はっきりしていませんが、それまでの栄養状態や、細胞周期の位置の違い、つまり細胞の育ちなどの違いによるようです。
― 人に影響を受けて成長するタイプと、同じことを言われてもまったく反応しないタイプがいる。人間の世界にもよく似ています。両者では、数年後の成長に著しく差が出ます。
種の存続のために自己犠牲を払う利他的行動
― ほかにも、粘菌に個性はあるのでしょうか。
子実体を形成するとき、胞子になる粘菌と、柄え になる粘菌があります。あらかじめどちらになるのか遺伝子に組み込まれているわけでもなく、指揮するリーダーが決めているわけでもない。集団のなかで、おのずと決まるのです。柄になる粘菌、柄細胞は集団全体の20~25%を占めますが、最終的に自身は胞子塊を支える構造となって死んでしまいます。進化のセオリーに照らせば合理的ではないこのような利他的行動がなぜ出てくるのか、まだよくわかっていません。
ただ、確かなことは、飢餓状態という環境のもと、子孫を残していくために、リーダー不在でも細胞同士で集団的な秩序形成を起こし、周囲に影響を与え、あるものは胞子へ、あるものは柄となる自律分散的な分業の仕組みが、細胞性粘菌には仕込まれているということです。

厳しいルールがあってこその自律分散
― 企業の世界では、自律分散型の組織を作りたい、とよくいわれるのですが、粘菌から学べることはあるでしょうか。
僕には、人間界のことはよくわかりません(笑)。ただ、素人の発想でいうならば、会社のような組織で自律分散的な分業の仕組みを作るのはかなり難しいと思うのです。
細胞性粘菌の集団内では、個々の細胞の動きを規定する厳密なルールがあることが、私たちの研究からわかってきています。ヒトの体の細胞もそうで、一部の例外を除いては、それぞれの細胞は組織や器官での役割、振る舞いが決まっています。がん細胞はまさに動物の体のなかで勝手に増えて動き回る細胞ですが、これを捕まえて、駆逐するための免疫細胞が働いています。個々の細胞に自由を与えると大変なことになるため、そのルールに従っていないものをはじく仕組みもあるのです。
細胞性粘菌の場合、柄細胞は自己犠牲を伴う利他的な行動をしますが、それは胞子細胞が自分のクローンであることが担保されてこそ。双子の兄弟である細胞が胞子になってくれる限りは、自分は死んだとしても遺伝学的には自らの子孫を残すことになります。ところが、同種でも遠い親戚の胞子だと、ただ乗りされて自分の遺伝子は残せないことになります。実際、1つの粘菌の集団に野外から採取してきた別の粘菌を混ぜると、それを排除する仕組みがあります。表面上は細胞同士が仲良く集団の利益を追求しているように見えますが、実はこのような厳しい制限、ルールのなかでの行動なのです。
― ルールで行動と役割を限定された範囲での自由であり、それぞれが複雑な意思を持たないからこそ、自律分散的な構造が生まれるのですね。
数十億年にわたって熾烈な生き残り競争を繰り返すことによって形成された生物の営みの1つが、細胞の集団化、多細胞化です。生き残れる生殖系列(胞子)と、それを支える体細胞(柄細胞)とが役割分担するからこそ、単独では生き残りにくい環境を克服してきたのです。しかし、集団としての生き残り戦略は、個々の細胞にとっては葛藤をもたらすもので、個々の細胞の自由度は大きく制限されます。そうした制限があるからこそ、我々が目にする多細胞世界の美しく豊かで多様な営みが実現しているのかもしれません。
Text=入倉由理子 Photo=刑部友康 Illustration=内田文武
After Interview
澤井氏が研究対象にする細胞性粘菌は、これを集団でやってのける。集団行動をするのも本当に不思議だが、もっと面白いのは、集団のなかでの役割分担が自然に行われる点だ。澤井氏は「種を残すというシンプルな目的のなかであればこそ、粘菌は自律分散的に動く」と言う。
私たち組織人は時に“自律分散型の組織”を夢想するが、前提となる“シンプルな目的”が難しい。企業の利益目標は、多様で複雑な思考を持つ人間の共通目的にはなり得ないからだ。だからといってすべての役割や行動様式をルールで決めるのではつまらない。人間ならではの知恵を絞って、自律分散的な集団に少しでも近づきたいところだ。
聞き手=石原直子(本誌編集長)


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ