Macro Scope
地球外生命はいる。そのとき、私たちは。

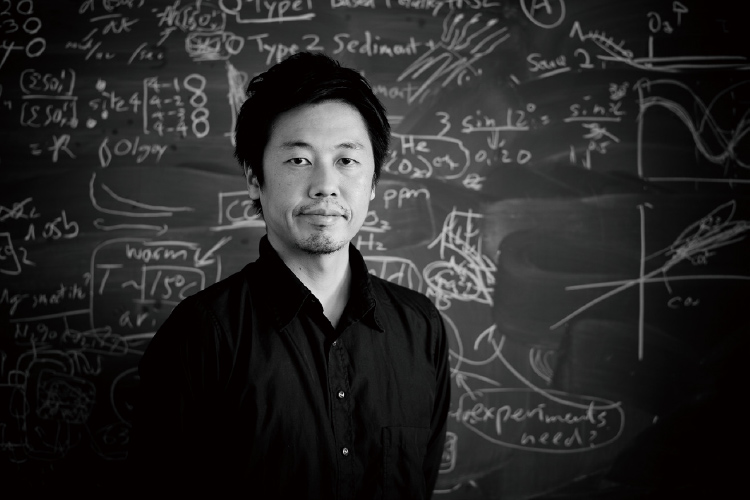 アストロバイオロジー研究者 関根康人氏
アストロバイオロジー研究者 関根康人氏
Sekine Yasuhito 東京大学理学部卒業、同大学院理学系研究科博士課程修了。東京大学准教授などを経て、2018年より東京工業大学地球生命研究所教授。土星の衛星タイタンの大気や海の起源、土星の衛星エンセラダスにおける生命存在の可能性など、宇宙における生命を育む環境の研究に従事。2009年度日本惑星科学会最優秀研究者賞、2016年度文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞。著書に『土星の衛星タイタンに生命がいる!』(小学館新書)がある。
人類にとっての課題が増え続ける現代にこそ、私たちには地球市民としての視座と行動が求められている。本連載では、人を作る人事に携わる人々が高い視座を獲得するために、人事や社会科学を超えた森羅万象について触れる機会を提供したい。第1回目はアストロバイオロジー、宇宙の生命科学である。東京工業大学の関根康人教授に宇宙に生命体は存在するのかを伺った。
― まず伺いたいのは、地球外に生命はいるのかということです。
当然いるはず、というのが現状の回答です。地球生命が生きていくためには、"液体の水"、自分の体を作る"有機物"、そして生命活動に不可欠な"エネルギー"の存在する環境が必要です。地球上でこれら3要素がある環境には、必ず生命が存在しています。実は、最近の太陽系探査によって、これら生命に必要な3要素が、地球以外にも存在することがわかってきました。今のところ誰も生命そのものをそこに確認したわけではありません。しかし、環境が生命の存否を決めているのであれば、生命を育む環境は地球特有のものではなく、地球外に生命がいることも否定できないのです。従来は、探査機が送ってくるデータから、3要素のうちの"液体の水"の存否を推測することが精一杯でした。ところが、この状況は最近10年で大きく変化したのです。
火星に生命がいるか
20年以内に決着するだろう
― どのように変化したのですか。
"液体の水"以外の"有機物"、"エネルギー"も地球外に存在している、またはあったことが実証されました。たとえば火星。火星は太陽系探査が始まる前の望遠鏡観測の時代から、液体の水や生命の存在が期待された惑星でした。しかし、1960年代の短時間での近接通過による火星探査の結果、マイナス60度という気温と大気圧の低さが判明し、液体の水や生命の存在は絶望視されました。ところが、1970年以降に探査機が火星の周回軌道から長期間観測し続けたところ、水が流れることでできる河川や三角州のような地形の痕跡が発見されました。現在は寒冷な火星にも、約40億年前には活発な火山活動があり、"液体の水"が存在したのです。
現在、火星生命の探索に大きな進展をもたらしているのは、2012年に到着した探査車キュリオシティです。キュリオシティは、約40億年前に湖だったクレータの底に着陸し、湖の泥のなかに複雑な"有機物"を発見しています。さらに、微生物が食べて"エネルギー"を得ることができる鉱物やガスも湖に存在していたことを明らかにしています。つまり、かつての火星は、地球と同じ生命を育む3要素を備えた惑星だったのです。当時の火星に生命はいたのか。現在も生命はどこかで生き延びているのか。それらを確かめるには、地球にサンプル(試料)を持ち帰って詳細な分析をする必要があります。
― サンプルリターンは、古くはアポロが月から、最近では日本の探査機「はやぶさ」が小惑星イトカワからなど、既に実績がありますね。
確かに月や小天体からサンプルを持ち帰った実績はありますが、地球や月を飛び出しほかの惑星からサンプルを持ち帰った例はありません。2020年代後半には、無人探査機による火星からのサンプルリターンが計画されています。2030年代後半には、火星に人が降り立つ有人火星探査も検討され始めています。2020年代には、月での有人探査を再開する予定ですが、月はいわば火星に行くための練習です。そこでの経験を有人火星探査に活かそうとしています。これらは、国レベルの研究ですが、民間での研究も加速度的に進んでいます。僕は、20年以内にサンプルリターンは実現し、火星に生命がいるかどうか決着がつくだろうと思います。

太陽系の惑星や衛星は多様性に満ちている
― 関根先生ご自身は、どのような研究をされているのでしょうか。
もともとは地球生命の起源に関する研究をしていました。地球にどのように生命が生まれたのか、その誕生前夜の環境を明らかにして、ほかの星でもそれが起き得るのか、宇宙における生命の普遍性を探求したいと思っていました。この10年で太陽系探査が進み、私自身の研究対象も、地球外天体の環境へ、そして地球外生命そのものへとシフトしつつあります。火星以外でも、生命の存在への期待が高まっているんです。
― 私も含めて、多くの人は太陽系の地球軌道より内側は暑すぎて、外側は寒すぎて生命が存在するには適さないと思っています。
かつては研究者の多くもそう考えていました。ところが探査が進めば進むほど、それほど単純ではないことがわかってきたのです。たとえば、木星や土星を周る衛星たちは、太陽から遠く太陽光エネルギーが小さいため、低温の氷の天体であろうと考えられていました。実際、木星の衛星エウロパや土星の衛星エンセラダスを宇宙から見ると、巨大な雪玉のようです。しかし、これらの天体の内部は熱で暖められ、氷の下には"液体の水"からなる地下海ができています。エンセラダスの地下海には、"有機物"や温泉のような地熱"エネルギー"も存在します。さらに、土星の衛星タイタンは、地球と同様に窒素がメインの大気を持っています。大気には数%のメタンも含まれ、活発な化学反応で複雑な"有機物"がたえず生成されています。また、地表には"液体のメタン"の海が広がり、そこには太陽光エネルギーも降り注いでいます。地球とは異なる太陽系の予想外な場所にも、生命が存在する可能性が高まってきたのです。
― 温暖で酸素や水などを必要とする私たちの生きる環境とは、様相が異なりますね。
タイタンのようにメタンに覆われた星では、メタンを使った光合成によって有機物やエネルギーを作るシステムがあることも考えられます。エンセラダスの地下海には海底温泉がありますが、地球にも同様の海底熱水噴出孔と呼ばれる温泉環境があります。そこに生存する微生物に似た生命がエンセラダスにもいるかもしれません。地球外生命が私たち人間と同じような環境を好み、酸素を使って生きているとは限りません。
― 夢が広がりますね。
問題は、気の長い研究だということです(笑)。火星に行くのに1年、木星には5年、天王星にいたっては10年以上かかります。私はJUICE(*)という日欧共同の木星氷衛星探査プロジェクトに参加していますが、探査機を2022年に打ち上げ、木星にたどり着くのは2029年です。惑星探査とは、林業みたいなもので、植えた苗が木になるのを、自分では見られないかもしれません。
(*)JUICE: ESA(欧州宇宙機関)が主導し、欧州各国、日本などが参加する大型木星氷衛星探査計画。
知的生命と出合えないことが語りかけるのは
― それでも研究を続けるモチベーションは何でしょうか。
宇宙の研究が、文化への貢献につながると思うから、でしょうか。かつて地動説が世界を大きく変えたように、地球外生命の発見は宇宙観、生命観、文明観を変えると思うのです。たとえば、酸素は私たちには欠くことのできないものですが、酸素が苦手な地球生命にとっては、水素やメタンの多い環境が生存に好適だったりします。さらに広い宇宙のなかでは私たちは生命の一形態でしかないかもしれません。私たちが唯一無二の存在ではないと証明することで、人類は同じ「地球生命」として一体感を持てるかもしれません。
― もう1つ、ぜひ伺いたいことがあります。知的生命は地球人のほかにいるのでしょうか。
私たちの銀河系には、恒星が3000億程度あります。その恒星が有する惑星のなかで、地球と瓜二つの星は数十億程度あるでしょう。そして銀河系のような銀河は宇宙に無数にある......。地球が知的生命の存在する唯一の星だとは考えにくいですね。ただし、知的生命を発見できるかというと難しい。隣の恒星に行くのも現在の技術では困難です。ほかの惑星に住む知的生命が発する、電波や光などのシグナルを探すというのが現実的でしょう。
私たちの文明社会の歴史は、宇宙の歴史から見るととても短い時間にすぎませんが、既にその存続が危ぶまれています。もし、私たちが、ほかの星の文明が発するシグナルを発見できないのであれば、それはほかに文明が存在しないためではなく、かつて文明があったが既に滅びてしまったため、つまり文明は普遍的に短命で終わるものだと解釈するのが妥当でしょう。
文明は、「もっとよくなりたい」という欲によって生まれ、発展します。しかし、同時にその欲はエネルギーを使いすぎたり、資源を奪い合ったりして争いを必然的に引き起こします。文明が持続するには、滅亡する前に「ちょうどよく生きていく」という革命的なマインドセットの転換が必要です。そういう転換ができた生命を、本当の知的生命と呼ぶのであれば、私たちはまだまだ知的生命ではありません。私たちの文明を存続させるために何ができるのかと、宇宙に生命を探す研究を通じて問いかけていきたいのです。
Text=入倉由理子 Photo=刑部友康 Illustration=内田文武
After Interview
昨今の企業組織では“ダイバーシティ”が叫ばれ、異なる背景や考え方を持つ人々の協働を促そうと多大な努力がなされている。だが、宇宙的な視座で見れば、我々地球上の生命、しかも、そのなかの一形態にすぎない“人類”の内部における差や違いなど、大したことではない。理解し合うのも、お互いを尊重するのも、難しいことがあろうか。そんなふうに考えたほうがダイバーシティ&インクルージョンはよほど速く進むかもしれない。
聞き手=石原直子(本誌編集長)


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ