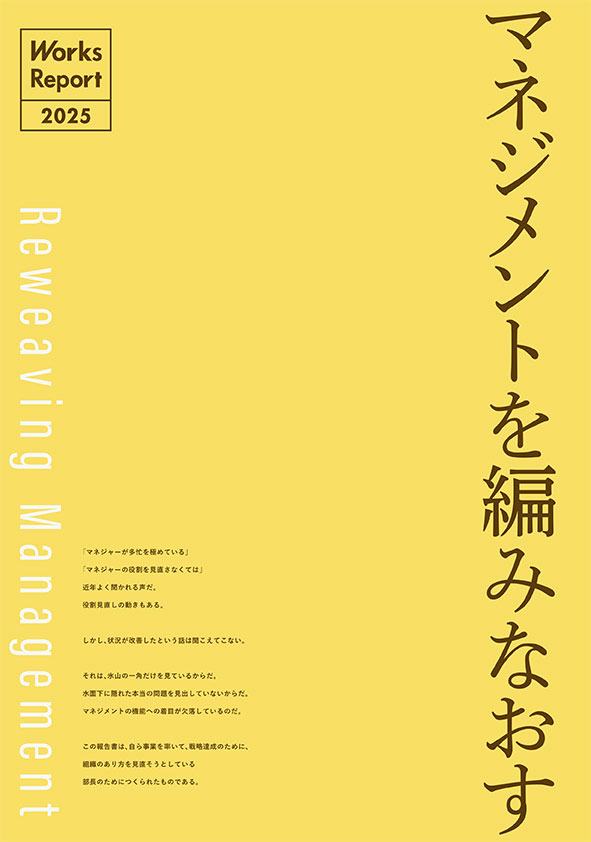【パネルディスカッション】~事業戦略からマネジメントの機能を見直す(ゆめみ、丸井グループ)

本記事は、2025年4月24日に開催された「Works Symposium 部長のためのマネジメント再考 ~事業戦略からマネジメントの機能を見直す~」の内容をもとに構成しています。
まずは試して失敗を繰り返し、そこから知見を得てマネジメントの機能を変えよ
リクルートワークス研究所 研究員・千野翔平(以下、千野):今回のシンポジウムにおける私たちのメッセージは、「マネジメントを“機能”の視点から見直してみよう」というものです。しかし、今回ご参加いただいた企業の皆さまのうち、実に78.7%が、まだマネジメントの機能の見直しに着手されていないという現状が明らかになりました。
そこでこのパネルディスカッションでは、2つの議論をしたいと考えています。1つ目は、事業戦略からマネジメントを編みなおすというのはどういうことだろう、ということ。そして2つ目が、マネジメント機能を見直すにはどうすべきか、ということです。
まずはゆめみ取締役CHROの太田さんに伺いたいのですが、事業戦略からマネジメントの機能を見直すことで、御社にはどんな気づきがありましたか。
ゆめみ 取締役CHRO・太田昂志氏(以下、太田):まずは、試してみることが大事なのだと知りました。
我々がいるデジタル業界は変化がとても激しく、戦略を立ててもすぐに陳腐化してしまいます。例えば生成AIを活用する領域では、半年に1回ぐらいはモデルが変わり続けていますから、じっくりと戦略を立てても有効性はさほどありません。それよりも実行することが重要で、そこで何度も失敗して多くを学んだからこそ、当社はこれまで何とかやってこられたという側面があります。
試行錯誤しながら何度も失敗をし、その過程で、事業戦略とマネジメント機能を作り上げることが大切だと考えます。それが今、我々が確信を持ってお伝えできることです。
千野:なるほど。企業を取り巻く環境の変化が激しいなかでは、じっくりと計画を立てるのではなく、まずはやってみて知見を蓄えることが重要というわけですね。
ところで太田さんは、事業戦略とマネジメントのどちらを先に変えるべきだとお考えですか。

太田:まずは事業戦略を固め、それから組織の変革に着手する順序が正しいと思います。
ゆめみの組織は非常にユニークなので、時には「ティール組織にしたいからこの事業をやっているの?」と誤解されることがあります。しかし、我々はあくまで、事業戦略を有効に実現するためにティールという形態を取っているだけです。まずは、事業戦略より最上位のパーパスとかミッション、ビジョン、バリューが最優先。次いで事業戦略を作り、それらを実現するための組織を整備するという基本の流れを、我々は忠実に守っています。
千野:わかりました。
次に、丸井グループ人事部長の原田さんに伺います。丸井グループでは、月賦販売の消滅、家具からファッションへ事業戦略が変わっていくなかで、マネジメントの機能の見直しにはどのように取り組まれたのでしょうか。
丸井グループ 人事部長・原田信也氏(以下、原田):きっかけは経営危機でした。上場以来初の赤字決算を2回も経験して、いつ潰れたり買収されてもおかしくない状況でしたので、変わらざるを得なかったのです。それでマネジメントの機能も含めて、あらゆるものを見直したのですが、そのときの従業員社員には心理的抵抗がありましたね。特に成功体験を持っていた先輩たちの世代には、昔のやり方を変えることで、それまで頑張ってきたキャリアを否定されたような感覚があったのでしょう。
一方、停滞期に入社した私たちの世代には、別の抵抗感がありました。それは、先が見えないなか、ここまで変えても大丈夫なのかというものです。例えば、丸井のブランドで売っていた丸井のカードを「エポスカード」と名前を変えたとき、本当に成長できるのだろうかと不安に感じました。
千野:世代によって中身に違いはあっても、多くの従業員が抵抗感を持っていたのですね。

原田:そうなんです。そうしたこともあり、当時の丸井グループは変化を恐れ、従来のやり方を手放すのが難しい組織だったと言えます。経営危機の時期に入社した若手は、自社のビジネスモデルに不満や疑問を感じていたはずです。もう服が売れない時代に変わったのに、会社はいつまでも、服をクレジットカードでご購入いただくビジネスにしがみついている、と。当時の若手は先輩たちに対し、過去の成功体験があるゆえ変化に背を向けているのか、あるいは変化を恐れているのだろうと見なしていたのではないでしょうか。
そうしたなか、変化を恐れない組織マネジメントを追求し、トップダウン、上意下達ではなく「支援するマネジメント」に切り替えた結果、当社は転換に成功したのです。
それから10年経ち、当社はいろんな仕組みを導入して高い評価をいただいています。それは単に、当社が変わらざるを得ない状況にいち早く追い込まれたからにすぎません。しかし、VUCAの時代になってあらゆる企業が変化を迫られている今、当社のやり方は他社の参考になるかもしれないと考えています。もちろん、それぞれの企業で事業戦略やコアコンピタンスが違いますから、それぞれが頑張って自社なりの解を導き出さなければならないとは思いますね。
事業ごとに異なっていた人事制度を、丸井グループ全体で統一
千野:続いて、2つ目のテーマである「マネジメントの機能を見直すにはどうすべきか」について議論したいと思います。
先ほど原田さんから、上意下達から支援型のマネジメントへの切り替えというお話が出ていました。マネジメントを支援型に変えた際に、どのような順序で進めたのか教えていただけますか。
原田:まずは、変化を恐れず、前向きに楽しめる組織を作るという目的を最優先事項だと位置づけました。その上で、組織の在り方や企業風土、評価制度などあらゆる取り組みを同時並行で進めたのです。
太田:丸井グループではいろいろな領域で多角化をされていますよね。ファッションやカード事業などの事業ごとに組織の作り方は違うと思うのですが、それぞれのマネジメントスタイルも違うのでしょうか。
原田:以前の当社では、事業ごとにマネジメントスタイルが大きく異なっていました。それぞれの業界に合った評価基準や価値観、考え方などを多く取り入れていたのです。それを、丸井グループ全体で統一された制度、マネジメントスタイル、評価基準にそろえていきました。
その一環として行ったのが、ベテラン社員であっても他部門への異動を積極的に進める「グループ間職種変更」という取り組みです。例えば、私が人事部に異動してから今年で5年目ですが、60人くらい在籍している当社の人事部の中で、私は3~4番目に人事経験が長い状況です。言葉は悪いですが、当社はある意味で素人集団のような組織をあえて作ったのです。グループ間職種変更には、劇薬のような側面があります。しかし、変化を恐れる社風を払拭し、全社のマネジメントスタイルをそろえるためには効果的だったのかもしれません。
太田:例えば、それまでアパレル部門で小売を担当していた人がクレジットカード部門に異動すると、かなり苦戦するんじゃないかと思うのです。その点、現場の皆さんはどう感じていたのでしょうか。
原田:もちろん苦戦する面もあるのですが、一方で、前の職場での経験が役立つケースもあります。
丸井グループでは数種類のクレジットカードを発行していますが、その中に、年会費無料のゴールドカードである「エポスゴールドカード」があります。一般的なゴールドカードは年収や社会的地位などの高い人に発行されるものですが、エポスカードは少し違います。長くご利用いただいて信用力が積み上がった方には、年収や地位などにかかわらずゴールドカードを発行するのです。こうした発想が生まれる背景には、店舗でお客様と実際に接してきた経験が活きていると考えています。
金融業界には、ものごとを論理的に考える「左脳型」の人が多いと感じます。おそらくこのタイプの方には、長年お付き合いのあるお客様にゴールドカードを発行する発想が浮かばないでしょう。一方、小売業で経験を積んだ人にはお客様に寄り添う共感力を磨いてきた人が多く、その能力や経験を活かして、新たな金融サービスを生み出したわけです。
職種変更によって、個人は成長のチャンスをつかめますし、企業としてもイノベーションの源泉として役立てられると考えています。
太田:確かに。よくわかりました。
権限を分散させる際には「権威性」をも分散させる工夫が不可欠
原田:あと、事業を変えるには、イノベーションを起こす必要があります。そのため丸井グループは、事業戦略を策定し、異動を積極的に行って業界の常識にとらわれない人間を生み出そうとしているのですが、異動先の部門でのスキルや経験が足りず評価が以前より落ちるという弊害もよく起こりました。そのため当時は、多くの方が異動を嫌がっていたのです。
そこで、評価からスキル給のような仕組みを排除し、ポータブルスキルだけで評価する制度をテスト導入しました。こうすることで、努力すればその部門での経験年数にかかわらず高く評価されると従業員に理解してもらえ、以前より異動にチャレンジする人が増えました。それで今は、この仕組みを正式導入しています。
太田:ありがとうございます。
原田さんのお話を伺って改めて感じたのは、人だけ異動させて状況を変えようとしてもうまくいかないということです。丸井グループのように、評価制度や報酬制度、そしてマネジメントなどを全て変え、その上で人を動かさなければ、イノベーションも起こせないのでしょうね。

千野:同感です。
最後に太田さんに伺いたいのですが、ゆめみでマネジメントの機能を見直すなかで、どんな課題があったのでしょうか。
太田:本当にたくさん課題があったので、全部つまびらかにお話しすると時間がなくなってしまいます(笑)。1つだけ共有すると、「権限分散をしても権威性は残る」という問題でした。権限と権威は別物だというのはとても重要な事実なのですが、それを認識している企業はさほど多くないかもしれません。
例えば、それまで部長が持っていた権限を課長などに分散化したとします。それでも結果的には、課長は部長の顔色をうかがって、「この人がこう言っているのだから、こうやろう」とものごとを決めてしまいます。組織の構造は変わったのに、その本質は変わっていないわけです。
千野:なるほど。そうした課題はどう乗り越えればいいのでしょうか。
太田:ゆめみでは、代表取締役権限を全員に付与することで、限りなくフラットな組織に変えました。これによって「権限がないからできません」という言い訳はできない状態になりました。ただ、権限は分散できても、権威を分散するのは事実上、不可能です。なぜなら、権威は人と人との関係性から自然に生まれるものだからです。例えば年齢や経験、これまでの実績など、権威はさまざまな要素が積み重なって形成されます。だからこそ、権威をいかに特定の人に偏らせないかという工夫が大事になってきます。そこで導入した制度の一つがC.xO制度です。C.xO、つまり「チーフ〇〇オフィサー」という形の肩書きで、C.xOはその領域のあるべき姿について第一声を上げる火付け役を期待されます。○○切り込み隊長とか、○○特命担当という感じです。こうして役割を作り直すことで、まずはこの人の話を聞いてくれと権威付けを行ったのです。
権限を分散させるとき、本来は権威性も分散しなければなりません。ただ、権威性というものは突然獲得できるものではなく、普段から積み上がって認識されるものです。したがって、権限を分散したなかでも、あえて役割を明示化することによって、もともと持っていた人の権威性を分散化する動きもやらなければなりません。これはマネジメントの変革を進めるなかで、我々が経験を通じて気づいたポイントでした。
千野:確かにそれは、大きな気づきでしたね。
今回は太田さんと原田さんのお二人から、たくさんの学びをいただきました。会場にいる皆さまにも、ぜひ参考にしていただければと思います。

執筆:白谷輝英


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ