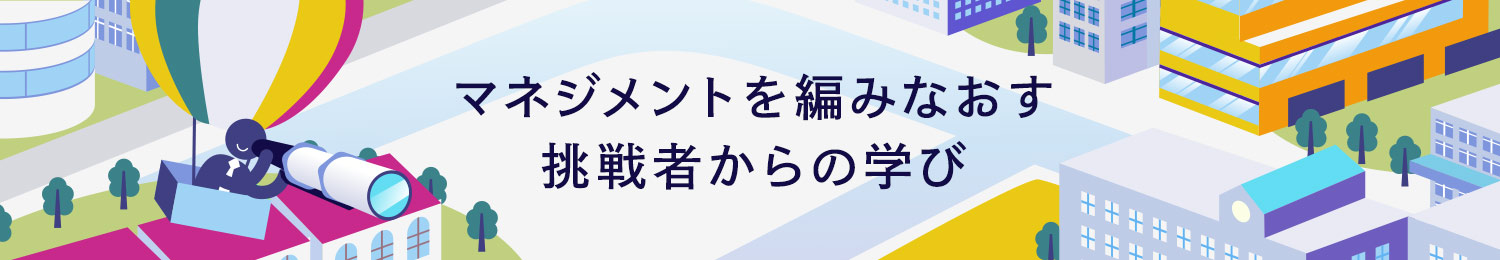
周囲に裁量を与え、期待する。その力をうまくまとめて大きな成果を得る

京都橘高校サッカー部監督・米澤一成氏
米澤一成氏は日本体育大学サッカー部時代にオランダ人監督と出会ったのを機に、サッカー指導者の道を歩み始めた。大学卒業後は世田谷学園高校と近畿大学工業高等専門学校で指導者としてキャリアを積み、2001年に創部されたばかりの京都橘高校サッカー部で監督に就任。2012年には全国高校サッカー選手権大会準優勝に輝くなどの実績を残し、高い指導力を評価されている。そんな米澤氏が大事にしているのは、コーチなど周囲の人に任せることだと語る。
監督の役割は「指導」から「マネジメント」にシフト
――高校サッカー界に長く携わってきた米澤さんから見て、監督に期待される役割は変わっていると感じますか。
以前は、サッカー戦術や練習指導などの「職人的要素」を求められることが多かったです。また、選手をスカウトしたり、チームで育った高校生を大学サッカー部に進学させたりする「商売人的要素」や、選手を上手に指導する「政治家的要素」も重要でした。それに比べると今は、多くの人に心地よく働いてもらい、彼らを束ねる「マネージャー的要素」がより求められるようになったと感じています。現場でのトレーニングは職人的要素に優れたコーチに任せ、それ以外の部分は商売人的要素や政治家的要素が得意な人に担ってもらう。そして監督は、スタッフや選手をオーガナイズする立場になるというわけです。
――なるほど。ちなみに京都橘高校サッカー部には、何人くらいの部員とスタッフが所属しているのでしょうか。
部員数は今、75人くらいです。一方のスタッフ陣は、コーチが6人とトレーナーが2人 、それに私を加えた9人います。練習メニューの作成などは各コーチに任せ、私は週1回開かれるオンラインミーティングで報告を受けて、必要があれば修正意見を挙げます。特に私は「ビッグピクチャー」を描いてある程度の方向性を示し、コーチ陣と相談しながら練習メニューをチューニングするやり方を採っています。
――コーチ陣に細かい指示を与えないのはなぜですか。
私があまりに細かく指示すると、若いコーチたちもやる気が出ないでしょう。それに、私が指示した練習メニューを選手にやらせるより、自分で創意工夫し、私や同僚と煮詰めたメニューを実行する方が勉強になるはずだと思うからです。
――そうしたやり方は以前から行っていましたか。
いいえ、昔は全ての選手に私が考えた練習メニューをやらせていました。でも2010年頃からはコーチに大きな裁量を与え、例えば、セカンドチームはコーチが自由に指導するスタイルを取り入れました。
――創部直後の時期と、2012年に全国高校サッカー選手権大会で準優勝を果たした頃とでは、マネジメント手法は変わっていたのですね。そのきっかけは何だったのでしょうか。
入部する生徒の量と質が変わったことが、きっかけだったかもしれません。創部直後の部員数は12人だったのですが、チームが良い成績を残して知名度が上がると入部希望者が増えました。また、やっているサッカーが知れ渡るにつれ、「京都橘のサッカー」をやりたいと考える生徒も多くなったのです。そういう生徒たちを満足させるには、より高度な指導をしなければなりません。また、試合に出られない選手を少なくするためには、セカンドチームを作ってコーチに面倒を見てもらう必要もあります。そうした事情があり、一定の領域をコーチに任せるようになったわけです。

個の得意分野で勝負させ、良い組み合わせを見つけてチーム力を高める
――米澤さんの著書『組織の中で個を生かす 京都橘イズム』を読んだのですが、選手のプレーはもちろん、全人格を見ている様子が印象的でした。
人に興味があるからでしょうね。私は体育教員として授業も行いますし、クラスも担任していることから、自分のクラスの生徒はよく見ているつもりです。クラス運営では、書道部の女子生徒に頼んで、大きな紙にクラス目標を筆で書いてもらいました。教室に張り出してみると、皆から「すごい!」と大評判になったのです。そうやって、いろいろな子どもにヒーロー・ヒロインになってもらい、それをきっかけに成長してほしいという思いは常に持っています。
――生徒としては、自分をきちんと見てくれる人がいるのは励みになりますね。一方で、サッカーではなかなか結果を出せない選手もいると思います。そういう人への働きかけで大切にしているのはどんなことですか。
声をかけるタイミングです。悩んでいる生徒にいちいちアドバイスを与えるのは教えすぎで、生徒を枠にはめ込む危険性があります。彼らは成長中ですから、苦労し、自力で殻を破ることで才能を開花できるのです。心がけているのは、「必要なアドバイスを必要なときに、必要な分だけ」ということですね。
一方、コーチに対してはかなり教えています。彼らは大人ですから、私の意見を受け入れてもいいし、気づきを得て別の道を探ってもらってもいい。そうして彼らのタイミングで一生懸命アプローチしているのを見て、適切にジャッジするのが、監督としての私の役目です。
――米澤さんは選手の個性を大切にされているのですね。一方でサッカーというゲームでは、チームという組織の中に個を組み込みながら勝つ必要があり、そこが難しいですよね。
私は基本的に、選手の得意分野を活かす方針です。例えば小柄だがスピードがある選手を、常に相手ディフェンダーを背負うようなポジションに置いたら力を発揮できません。そういう選手は接触プレーが少ないサイドに配置して、スピードという武器を存分に活用させるべきなのです。もちろん苦手分野を減らす指導はするのですが、それより、得意分野で勝負させる方がいい。そして、彼らの力を最大化できる組み合わせを考えるのが、監督の仕事です。その上で、チーム全員に共通認識を持たせることも大切です。こういう配置になったら、誰がどこに動いてどうプレッシャーをかけるかなどの決まり事を、チーム全体に浸透させます。
――個を活かし、さらにチーム全体で共通認識を持たせるために、どういった仕組みがあるのでしょうか。具体例を教えてください。
「ユニット活動」が代表格です。京都橘高校サッカー部では全部員が、統括グループ(キャプテン、副キャプテン、マネージャーが参加)、テクニカルスタディグループ(サッカー技術の向上を目指す)、審判グループ、フィジカルグループ(筋トレなどの研究を行う)、メディカルグループ(テーピングなどトレーナー技能の研究を行う)、そして地域貢献グループという6ユニットのいずれかに入っています。ファーストチーム、セカンドチームといった序列とは異なる軸で生徒たちを交流させることで、互いに助け合う良い関係づくりができています。

多くの人から協力を得るためキャッチーな言葉でブランディング
――生徒一人ひとりに寄り添い、上手にチームとしてまとめる米澤さんの指導は、どうやって出来上がったのでしょうか。
やはり、これまでの人生で出会った方々からの影響ですね。中でも、サッカーに関わった方からの影響は大きかったです。日体大サッカー部の3、4年次に指導していただいたオランダ人監督のアーリー・スカンスさんはまさに恩師と呼ぶべき存在なのですが、それ以外にもたくさんの人にいろいろなものを与えていただきました。今後は私自身が次世代の指導者に、上の世代からいただいたものを伝えていきたいですね。
ですから京都橘の選手やコーチも、私の影響だけを受けて育つのでは面白くないと思っています。私以外のさまざまな先人から影響を受け、それらを咀嚼した上で、次の時代を作ってほしいのです。京都橘高校サッカー部は今年から、「えんじ色のパイオニアになれ」というキャッチフレーズを打ち出しています。これも、自分たちの力で新しい時代を切り開いてほしいという思いを込めて作りました。
――「えんじ色のパイオニア」というのはいいキャッチフレーズですね。米澤さんは「ダッチフットボール」(強豪国オランダが生み出した、選手がポジションを次々と変えながらボールを保持し続けるサッカーを指す)というコンセプトも打ち出されていますが、言葉の力で人を引きつけるのが上手だとも感じました。
ありがとうございます。基本的に、私一人でできることには限界があるのです。コーチを含めた周りの人の力を借りなければ、大きな成果は得られません。それで、わかりやすいキャッチフレーズを使ってブランディングするやり方を採用するようになりました。例えば有望な中学生を勧誘するときは、「うちのチームではダッチフットボールをやってんねん」と伝えることで、相手の興味を引いています。
――ブランディングと言えば、京都橘高校サッカー部では2014年から企業スポンサーを集めていますね。選手のユニフォームにもスポンサーの名前が入っています。
高校生が参加しているJリーグのユースチームなどでは、ユニフォームにスポンサー名が入っているのが当たり前でした。それで、高校のユニフォームにスポンサー名が入っていてもいいだろうと考え、規定をしっかり確認した上で実行したわけです。とはいえ、前例がない取り組みだったので、物品やサービスのみ受け取っています。例えばANA(全日本空輸)からは、チームが遠征する際に支援をいただいていました。
スポンサーがつくメリットは、移動や用具の支援だけではありません。選手がプライドを持てることも大きいのです。企業の看板を背負うことでプレーにも気合いが入りますし、普段でも、「変な言動をすると企業に迷惑をかけてしまう」と考えるようになります。生徒たちが、大人に一歩近づくのを助けてくれるわけですね。もちろん、サッカーで勝つことは大切にしていますが、いろいろな人・企業の力を借りながら生徒を立派に育てるのも、私の重要な役割なのです。
――よくわかりました。最後に、個性を組織の中で活かしたいと考えている企業人にアドバイスをいただけますか。
人に任せることですかね。若い頃の私は、何でも自分でやらなければ気が済まないタイプの人間でした。でも指導を長く続けるうちに、周りの人をたくさん巻き込む方が、大きな成果を出せると気づいたのです。やりがいを持たせて人を成長させ、その力を上手にまとめる。その方が大きな成果につながると、私は思っています。
〈企業組織への示唆〉
米澤氏によれば、監督の役割は「指導」から「マネジメント」にシフトしているという。新たな監督としての役割を発揮していくためには、周囲の人々に裁量を与え、彼らの能力を最大限に引き出し、組織の成果を高めなければならない。米澤氏のインタビューからは監督役割に応えるための転換点が明らかになる。それは、従来の上からの指示ではなく、一人ひとりの生徒が自主的にやりがいのある目標を持つことを促し、創造性ややる気を引き出すアプローチである。さらに、チームの方向性をあらかじめ示し、分かりやすい言葉や刺さりやすい言葉を通じて、全員の意識を一つにまとめていくことが、チームを同じ方向に導く重要な工夫となる。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ