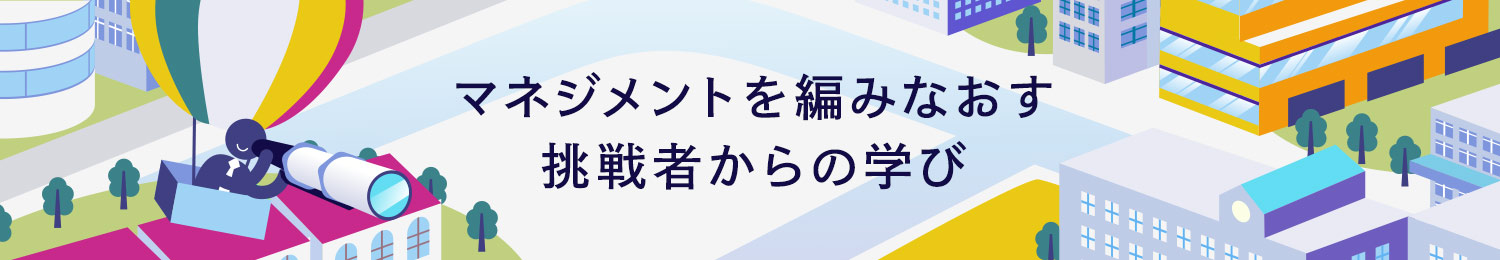
生徒のオーナーシップを奪わない

FC今治高等学校里山校校長・辻 正太氏
愛媛県今治市で2024年4月に新設されたFC今治高等学校里山校は、サッカー元日本代表監督の岡田武史氏が学園長を務め、独自性が高く実践重視のカリキュラムで注目されている。同校の初代校長である辻 正太氏は進学校だった私立中高一貫校で教師を務めた後、青森県弘前市に移住して幅広い人々に学びの場を提供する取り組みを行っていたが、岡田武史氏との出会いを機に、FC今治高等学校里山校の校長を引き受けた。彼はどのようなやり方で、生徒たちの力を伸ばしているのだろうか。
民間経験とスピード感で改革を進める校長が求められている
―― 高校の校長先生に期待される役割は、昔と今とで変わっていると感じていますか。
これは私の勝手な先入観かもしれませんが、特に昔の公立高校の校長には、一般的に「上がりの仕事」というイメージがありました。名誉職とまでは言いませんが、長く頑張ってきた教員をねぎらう最後のご褒美という側面が多少あったのです。ですから、任期の間にゴリゴリ学校改革を進めようとするタイプは少数派で、ほとんどの人は「3年間おとなしくしておこう」という発想になりがちだったのではないかと思います。
これに対し、今は思い切った改革に乗り出す校長に注目が集まっています。例えば、元横浜創英中学・高等学校のカリスマ校長として知られ、現在は本校のエグゼクティブコーチもされている工藤勇一先生がその典型です。他にもさまざまな「民間人校長」がスポットライトを浴びているのは、教育現場を変えるリーダーシップが校長に求められているという背景があるからかもしれません。
――こうした流れは、社会ニーズの変化を受けたものでしょうか。
その可能性はあります。私自身は今、学校で教えようとしていることと、社会で求められていることがどんどん乖離していると感じています。2011年に米デューク大学のキャシー・デビッドソン教授が「今年アメリカの小学校に入学した子どもたちの65%は、大学卒業時に今は存在していない職業に就く」と話していましたが、そうした変化する世の中に適応できる力を、今の学校では教えていません。私も含め大半の教員が大学卒業後、民間を経験せずに教職に就いているのは原因の1つでしょう。それで、いろいろな人を巻き込む力を持ち、民間の感覚を持ち込んでスピード感豊かに学校改革に取り組む民間人校長が注目されているのではないでしょうか。
また、今は少子化で高校生が減っています。本校も、昨年入学した1期生は34人でした。こうした状況では、何らかの特徴を打ち出して生徒に選んでもらうしかないですから、定年まで生き延びればいいと考える校長ではダメ。改革の旗を先頭に立って振れる人でなければ務まらないのだろうな、という気がします。
――辻さんもそうした改革の先導者のお一人だと思いますが、FC今治高等学校里山校ではどんな取り組みをされているのでしょうか。
本校では教員を「コーチ」と呼んでいるのですが、まずはコーチと生徒をフラットな関係にするよう徹底しています。生徒は私を「ショウちゃん」と呼びますし、学園長の岡田さんは「岡ちゃん」。教員が教え、生徒が教わるという従来の関係とは異なり、互いに学び合うことを大切にしているのです。
どんな子どもも小さい頃は何にでもなれると思っているものですが、高校生になる頃には自信や自己肯定感が低くなってしまう。これは明らかに、日本の教育の問題点です。こうした状況を変えるには学校という小さな社会で成功体験を積んでもらうのが一番で、それには、生徒のオーナーシップをできるだけ奪わないことが必要なのです。それが、フラットな関係を徹底する理由です。
本校の教員は生徒に対し、ああしろ、こうしろと指示したりしません。その代わり、「どうしたの? 君はどうしたいの? 先生に何かできることある?」という質問をひたすら繰り返します。これも、生徒の自主性を伸ばすためです。本校の校則は「命の危機にかかわるようなことをしない」「物を壊したり人を傷つけたりしない」「他者の成長と学びの機会を妨げたりしない」という3つだけで、それ以外は何をやってもいいと生徒には伝えています。後は生徒たちがそのつど勝手に、学校生活やクラス運営をスムーズにするためのルールを決めているのです。また、本校の生徒は寮生活を選ぶことも可能ですが、そこでもやはり、生徒が作った自治会により、自分たちで決断、行動しています。

不要な助け船を出さず「子どもが自然に育つ力」を伸ばせ
――生徒の自主性を大切にするのは素晴らしいと思う半面、大人としては、生徒が躓きそうなときはつい助けてしまいそうですね。
そうですよね。ですから、開校直後でコーチが本校のやり方に慣れていなかった時期は、困っている生徒を見てつい助け船を出した人もいました。そうした姿を見て私は、全力で「行っちゃダメ!」と止めていたものです。そのうちコーチたちも理解してくれ、2カ月後くらいには止める必要など一切なくなりました。
――コーチだけでなく、生徒側にも戸惑いがあったのではないでしょうか。
おっしゃるとおりです。特に入学したばかりの1年生は戸惑っていたと思います。本校の生徒はほぼ全員が寮に入っているのですが、4~5月頃は彼らからよく、寮生活に関する要望を受けたものです。彼らとしても、高校1年生という若さで初めて親元を離れたわけですから、不安になるのは当然です。ただ、いくら相談されても、我々は「そうなんだ。それで、君はどうしたいの?」としか答えませんでした。そのうち生徒の方も、自分たちが動かなければ事態は何も変わらないと気づきはじめます。そして入学から半年くらいまで経った頃には、「こういう計画を立てていて、ここまで準備しているんだけど、ここがどうしても自力では解決できない。どうしたらいいですか」という聞き方をするようになってきました。
生徒側の発案で、3月に1年生だけで運動会をやることになりました。現時点で2週間前ですが、我々は今のところ、生徒から具体的な内容は何も聞かされていません。生徒ではなく担当の教員にそれとなく状況を聞いてみたのですが、どうやら責任者役の生徒がいっぱいいっぱいになっているようでした。普通の学校なら、教員から「大丈夫か? そろそろこう動いたらいいんじゃないか?」などと声をかけるのが一般的だと思いますが、本校はそんなことはしません。もちろん、運動会は失敗する可能性があります。岡田さんは常々、「子どもたちは育つ力を持っているのだから、大人はそれを邪魔するな」と言っています。私たちはその考えを学校現場に落とし込んでいるのです。
――2024年7月に中学3年生向けの学校説明会を開いたと報道されていましたね。あのイベントも、生徒発の企画だったのでしょうか。
そうです。生徒が企画から参加者の案内、プレゼンテーションなど全てをこなしました。指示命令系統がない、究極の自律分散型組織というべき状態だったのですが、それでもイベントがきちんと実施できたのは感慨深かったですね。生徒たちが自らの役割を自覚し、正解のない世界で信念を持って目標に立ち向かって行動する「キャプテンシップ」を持てたからこそ、イベントが成立したのです。
岡田さんはよく、「リーダーのいない国がダメなのではなく、リーダーを求める国民がいる国がダメなのだ」ともおっしゃいます。あのイベントでも、リーダーに委ねるのではなく、全員が自分の頭で考え続ける生徒の姿を見ることができました。

短期的な結果より、生徒が長期的に成長できることを目指す
――生徒の中にはFC今治高等学校里山校に合っていて、学校を使い倒せる人もいるでしょう。一方、中にはそうでないタイプの生徒もいるかもしれませんね。
確かに。高校生活の3年間で大きく花開く生徒もいるでしょうが、3年間モヤモヤし続ける生徒も出てくると思います。ただ、3年間で必ず結果を出さなければならないと考えるのは、学校側のエゴなのではないでしょうか。3年間モヤモヤしていても、そのときの経験が10年後に役立ち、突然成長する人だっているかもしれません。私たちは生徒の未来のため、「心が動くような種」を蒔き続けることが役割ではないかと、今は考えています。
岡田さんは、サッカー監督の経験を踏まえ「選手を人間として認めていると伝え続けることが大事」だとも、よく話されます。サッカーチームでは、ずっと試合に起用されない選手もいます。でも、そんな選手にきちんと目配りをして、時には褒めたり、何気ない世間話をしたりする。そうして存在を認めることで、人の心は救われるというのです。ですから我々も、生徒に何か気になることがあれば声をかけています。また、悩みを抱えている生徒に対しては、生徒がコーチを選んでマンツーマンで話せる「お茶会」という、いわゆる1on1の場を用意しています。
――FC今治高等学校里山校では、コーチにどのような素養を求めるのでしょうか。
1つ大切にしているのは、コーチにもチャレンジし続けてもらうことです。ですから、採用面接時に「今の学校では~があまりうまくいかないのですが、ここならやりたいことがやれそうだと思って応募しました」と話す方はお断りし、「今の学校では~のチャレンジをしていて、ここに来たら~というチャレンジをしてみたいです」という方を採用しました。また、コーチには学内だけでなく、学外でもチャレンジしてもらいたいですね。執筆や講演など何でもいいので、いろいろな活動をしてほしいと期待しています。コーチが自分自身をアップデートしている姿を見れば、生徒たちにも刺激になるはずです。
――生徒の「育つ力」を徹底して伸ばそうとする方針は、本当に素晴らしいですね。
本校では、想定外・板挟み・修羅場という3つの言葉を大切にしています。一般的な学校では、これらから生徒をできるだけ遠ざけようとしますが、それを続けていると、不測の事態が起きたときに生徒は対応できなくなってしまいます。
今の教育現場では、生徒や保護者を「お客様」と捉えるケースが増えています。これに対し、本校が目指しているのはそれとは真逆の方向です。時に生徒が厳しい状況に陥っても、余計な手は貸さない。自分たちで考えて決断し、自分たちで行動させる。それが、生徒の成長につながると信じているのです。
〈企業への示唆〉
生徒のオーナーシップを重視する姿勢は、組織内での自主性と責任感を育む上で重要である。FC今治高等学校里山校では、先生をコーチと呼ぶなど、コーチと生徒の関係をフラットに保ち、生徒が自らルールを決め、行動するように取り組んでいる。このプロセスでは、コーチが教えすぎないことが重要である。過度な指示は生徒の自主性を損なう恐れがある。この考えは、企業においても社員が自分の役割に対してオーナーシップを持つことを促進する。また、挑戦を続ける文化を育むことで、失敗を恐れずに成長を目指す環境が整い、企業全体の競争力を向上させるのである。
聞き手:千野翔平
執筆:白谷輝英


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ