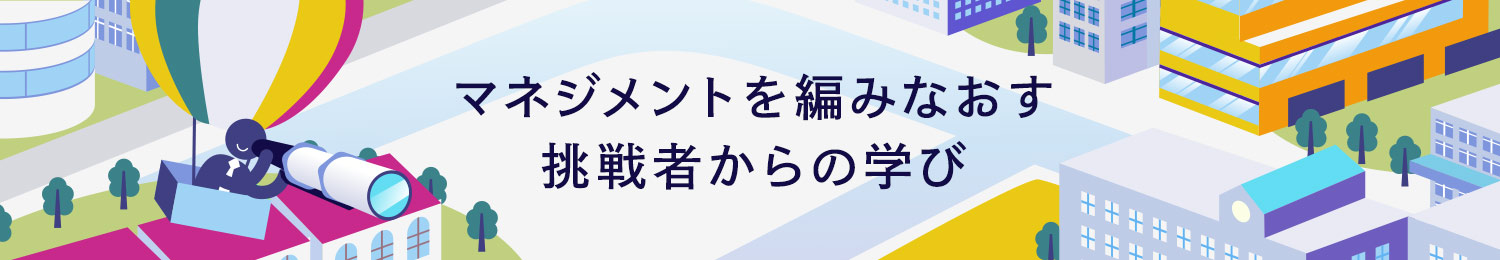
バイアスをなくして個人とフラットに向き合う
 ビジャレアルCF・佐伯夕利子氏
ビジャレアルCF・佐伯夕利子氏
佐伯夕利子氏は1992年春スペインに渡り、サッカーの指導者ライセンスを取得してスペイン3部リーグ所属チームなどの監督を歴任。2008年からはビジャレアルCFに加わり、ビジャレアル・レディースAチーム監督や育成強化責任者などを務めた。その後はJリーグ理事(2022年退任)やWEリーグ理事として日本サッカーを支え、現在はビジャレアルCFに復帰。そんな経歴を持つ佐伯氏はスペインのサッカー最前線で、一人ひとりに向き合う指導の重要性を肌で感じてきた。
スペイン社会の民主化がサッカークラブにも影響
――佐伯さんは今、ビジャレアルCFでどんなお仕事をされているのですか。
もともとのバックグラウンドは指導者ですが、現在は、本来の業務である経営領域で、選手の補強や契約締結業務といった幅広い業務をおこないながら、指導者の成長支援を続けるなど領域をまたいで兼務しています。
――最近のビジネス界では、リーダーに期待される役割が変わっています。サッカー界にも、指導について何か変化は起きていますか。
変わってきたと思います。スペインに限って言えば、その背景にあるのは社会の変化ではないでしょうか。かつてのスペインは16世紀から300年にも渡りカトリック教会が大きな権力をふるった国ですし、19世紀は絶対王政から立憲制に移行する過程で内戦が続きました。また。ミゲル・プリモ・デ・リベラ将軍のクーデターによる権力掌握、フランコ総統による独裁政権など、つまりは強い権威が民衆を支配する構造でした。それが民主化とともに、教育現場も民主的な在り方に変わりました。
ビジャレアルCFはトップチームから育成カテゴリー、女子チームまでのさまざまなチームから成り立っていて、それらに関わる指導者は全部で120人くらいいます。そのうち3分の1くらいは、教員や元教員、教育学部の学生といった教育関係者です。彼らの中に「社会が変わったのだから、教育も権威主義的なやり方から脱するべきだ」と感じる人が増え、その流れがクラブにも波及してきています。
改革の道のりは、決して平坦ではありませんでした。私が指導していた女子チームの場合、5人くらいのスタッフと22人の選手が長時間にわたって濃い関係を結ぶわけですが、そこは想像以上の閉鎖空間です。「遅刻しない」といった基本的な約束事から、「ロッカールームで起きたことは絶対に口外しない」などたくさんのルールがあり、がんじがらめになっているヒエラルキー社会だったのですね。そこで民主的なやり方を導入するためには、組織の解きほぐしが必要でした。まずは、スタッフ陣のミーティングを丸いテーブルで行うなどの取り組みを行うことで、ピラミッド型組織からの脱却を図りました。そうして「監督が上、選手が下」という意識を取り去ってから、個人にフォーカスし、選手個々の意見や思考、感情を尊重するやり方に切り替えたのです。
――そうした動きはビジャレアルCFに限ったものですか。
いいえ、そんなことはありません。私たちが指導改革に挑み始めたのは10年ちょっと前で、当時は物珍しげに見られていたものでした。しかし今では、レアル・ソシエダやアスレティック・ビルバオ、RCDマジョルカといった他クラブも、私たちと似通った育成方針を採用するようになっています。

指導時の言葉の主語を指導者から選手に変えることの重要性
――佐伯さんがスペインで学んだやり方は、いわば「アスリート起点」の指導法と言えそうですね。それを学んだ際に、乗り越えるべき障壁はありましたか。
最大の障壁は「エゴ」でした。己の利益ばかりを考える「エゴイズム」よりもっと広い、「自我」という意味のエゴです。例えば練習で選手を指導している時などに、私は周囲の人から「それは君のエゴだよね」と言われたことがあります。声をかける際の主語が選手ではなく、自分になっていると指摘されたのです。
当時の私には、私が選手に教えるのだという意識がありました。そして選手に対し、「チームのために頑張ろう」などと伝えていたのです。でも、チームというものは実にぼんやりした概念です。そこには20人以上のメンバーがいて、それぞれが個性を持ち、悩みを抱えています。そうした人たちを「チーム」とひとくくりにするのは乱暴で、もっと一人ひとりに向き合わなければならないとよく指摘されました。私たちのクラブには、「フットボールをヒューマナイズしようぜ!(人間味のあるようにする)」という合い言葉もあるのです。
――「主語が選手ではなく、自分になっている」と指摘された件ですが、そこから佐伯さんは選手へのアプローチをどう変えたのですか。
それまでは、「指導者である私が選手に教える」という形で言葉をかけていました。「主語を選手に変換してその一文を言い換えたらどうなる?」といった作業を丁寧に繰り返し行いました。そうして主語が指導者から選手に変わると、私たちの行動・アプローチも変わっていきました。
――異なる感情を抱き、異なる状況に置かれた選手に向き合い、それぞれに合った指導を行うやり方は、本当に素敵だと感じます。ただ、それは簡単なことではありませんよね。佐伯さんはどうやって、その技術を磨いたのでしょうか。
一つの例としては、自分の胸にアクションカメラとピンマイクをつけ、選手の表情や会話を記録する取り組みをしました。後で映像を見返して、「この選手は私と話をするとき、目線をそらしがちだな。発言したくないというメッセージなのだろうか?」などと分析していったのです。また、私がどの選手に何回声をかけたかなどの状況をサイコロジストにチェックしてもらい、そこから指導法について自省することも行いました。例えばある日の練習で、A選手には20回、B選手には3回声をかけたとします。それだけで、私はB選手よりA選手の方を潜在的に気に入っていると認識できるわけです。こういう「自らの本音」を突きつけられたのは、私にとって大きな気づきでしたね。
――なるほど。ただ、バイアスをなくして個人とフラットに向き合うのは素晴らしいと思う一方で、トップダウンで部下に言うことを聞かせる方が楽で効率的だと考える上司もいるでしょう。
そうかもしれません。ただ長い目で見れば、個人としっかり向き合うマネジメントの方が豊かだと、私は考えています。
メキシコの代表選手・現在メキシコ代表監督、2014年には日本代表監督を務めたハビエル・アギーレさんという名将がいます。彼がRCDマジョルカの監督を務めていた頃の記者会見で、ずっとベンチを温めていた選手が「僕たちのチームでは、出場機会が多い選手も、僕のようにそうでない選手も皆がハッピー。こうした状態を作り上げられる監督は、僕のキャリアの中で初めてだ」と話していました。これを聞いたとき、私は深く納得したものです。選手にとって一番悔しいのは試合に出られないことで、ベンチに長く置かれている選手は監督に反発するのが普通です。ところがアギーレさんは、どの選手にもきちんと時間を割き、正対し、真摯に向き合い対話を重ねられるそうです。だから選手の側も納得し、ベンチにいながらチームに貢献できる道を模索するようになるのです。
――そうやってチーム全体の士気を高め、成果を出すのが、本物のチームマネジメントなのかもしれませんね。
そうですね。そしてあの記者会見での選手の言葉は、指導者にとって最大の褒め言葉だっただろうと、私は考えています。
指導改革には決定権を持つ世代とのすり合わせも大切
――佐伯さんはビジャレアルCFで経営側の立場でもいらっしゃいますが、クラブ全体の指導理念が変革された際に、どうやって指導者に浸透させたのでしょうか。
それまで指導者の実力を測る物差しは、数字でした。優勝回数が多く、高い勝率を残した指導者が優秀と見なされていたのです。でも、こうした考え方はもうやめる、今後は選手をどれだけ成長させたかという点にフォーカスして評価すると、全指導者に伝えました。

――それは思い切りましたね。反発したり、疑問を感じたりした人はいましたか。
いましたね。当時は、「優勝して当たり前の戦力を持つチームが2位で終わっても、私の職は危なくならないのですか」と、多くの指導者に質問されたものです。クラブの中核的なポジションで、経営陣と指導者をつなぐ役割も果たす「ダイレクター」は、もちろんそれでOKだと答えました。ただ、経営陣の合意がきちんと取れていないと、そこでトラブルが起こりがちです。
実際、ビジャレアルCFでもそうした問題が発生したケースがありました。あるカテゴリーのチームに選手教育に長けた指導者がいたのですが、ある年のチーム成績がクラブの期待に達せず、解任されてしまったのです。ダイレクターや指導者仲間は彼の指導者としての実力をよく知っていましたから、皆で一斉に抗議しました。スペインの人たちには、正義を守るために一斉に立ち上がる習慣が身に付いているのです。そうして話し合いをした結果、経営陣は過ちを認め、その指導者をもう一度戻してくれたことがありました。
――事態が良い方向に収まって良かったですね。
そうですね。現場を変えていくのは、もちろん大変です。そして、決定権を持ち、昔ながらの考え方を持つ世代の人の理解を得ていくのも、同様に大変です。私たちのクラブではうまくいきましたが、それがどの組織でも実現できるかと言えば、それはわかりません。
ただ、スペインサッカーのプリメーラ・ディビシオン(第1部)に所属するトップ20クラブのうち、私が知る限り、私たちを含めた4つのクラブは、個人にフォーカスする育成方針に切り替えています。また、優秀な指導者の基準も今後はどんどん変わっていくと、個人的には期待しています。
――ありがとうございます。日本の一般企業でも、スペインサッカーと同様に、個人にフォーカスするマネジメントがもっと広がるといいですね。
〈企業組織への示唆〉
佐伯氏へのインタビューによって、個人にフォーカスしたマネジメントの重要性が浮き彫りになった。特に、スポーツ界が権威主義的な指導スタイルから民主的なアプローチへの移行することが、選手の成長を促進することが示された。この指導法の核心は「選手の意見や思考、感情を尊重する」ことであり、指導者のエゴを排除することが不可欠である。また、指導者だけでなく、経営層とも一体となる必要がある。このような変革は、個々の能力を最大限に発揮させるだけでなく、チーム全体の士気を高め、成果を上げるための鍵となる。企業においても、個々の社員に向き合い、彼らの成長を支援するマネジメントスタイルが求められる時代が到来している。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ