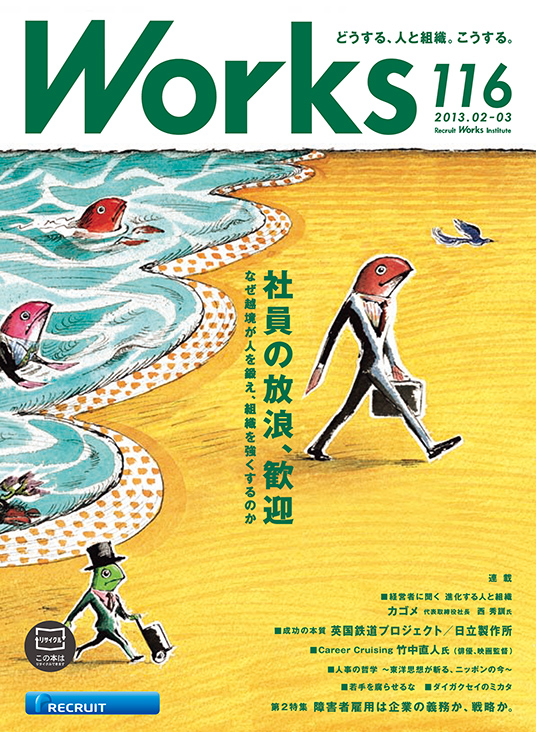支援が必要な人材を受け入れるほどに 組織は強くなり成長する
福岡市に本社を置く警備会社ATUホールディングスは、常時雇用者51人のうち過半数が障害者である。さらに、多様な人材を積極的に採用し、モチベーション高く安定的に働ける環境づくりに取り組むことで、高付加価値のサービスを実現し、顧客に選ばれる企業となった。ダイバーシティの推進が企業の生産性を押し上げる理想的な関係はどのように生まれたのか。代表取締役の岩﨑氏に話を聞いた。
基礎情報 合計28人
| 精神障害-発達障害 | 12人 |
| 身体障害 | 10人 |
| 知的障害 | 6人 |
「万人が働ける会社」を追求した結果、価格競争に巻き込まれない価値が生まれる
工事現場周りの交通誘導、施設や駐車場の出入管理など、さまざまな警備サービスを手掛けるATUホールディングス。警備の契約単価は地域(福岡都市圏)の相場より15%以上も高いが、安定的な受注により高利益体質を実現している。顧客に選ばれる理由は群を抜いた安全性の高さであり、「これまで重大労災事故が一度もありません」と岩﨑氏は振り返る。

岩﨑 龍太郎氏
「とりわけ道路工事では、しばしば警備員が交差点の真ん中に立って交通誘導する光景を見かけますが、これは厳密に言うと道路交通法違反であり、車にはねられる危険性があります。しかし、多くの警備会社では現場監督の求めに応じて警備員が車道に出ているようです。一方、当社では社員の身を守るため、事前に『歩道や工事帯の中で安全に誘導したい』と顧客企業に要望するとともに、警備員の配置を提案するなどして顧客の負担軽減を図ってきました。それでも懸念がある顧客には、一度当社を利用して実際を知ってもらうため、工事にあたり近隣住民に周知するチラシ配りを請け負うなどの、付加価値サービスを提供することもあります。理解が得られるにつれ、きわめて安全な交通誘導ができるようになり、他社には模倣困難なほどの価値が生まれたのです」と続ける。
岩﨑氏いわく「他社が車道で誘導する現実を受け入れている」のは、断りにくさに加え、警備員が臨機応変にリスクを回避するから大丈夫だろう、という楽観による。「しかし障害者の場合、健常の警備員のように柔軟に対応できるとは限らず、そもそも誰であろうが危ないことをさせるわけにはいきません」と岩﨑氏は言う。障害の有無にかかわらず、当たり前に誰もが安心して働けるユニバーサル化に注力した結果、安全性の向上、ひいては事業発展につながったと言えるが、その出発点になったという意味で、同社の取り組みは障害者雇用における多くの示唆に富んでいる。
岩﨑氏はかつて別の警備会社に勤めていたが、「仕事のできる部下」が精神障害を理由に退職を迫られた出来事をきっかけに、「適性がある人が排斥されない会社」を作ろうと決意した。「社員の発達を保障し万人が働ける会社」を経営理念とするATUホールディングスを2012年に設立し、事業目的の1つに障害者雇用を掲げた。「障害のある人を雇用・育成することにより、本人の自立につながるのはもちろん、育てる人の能力も向上します。私は障害者雇用を『会社を強くするための一手』と捉えています」と語る岩﨑氏の会社では、ほぼすべての障害者が正社員で、助成金なども受けていない。育成する者のキャパシティから採用人数は絞るが、「当社以外でも働けると思われる軽度の障害の方と、重度の方が応募された場合、働くことのハードルが高い重度の方を採用しています」と言う。
採用基準はただ1つ、「自転車に乗れそうなこと」と独特である。これは「警備に関する多くの作業は、自転車を扱うより簡単にできるはず」という岩﨑氏の考えによる。車椅子や片麻痺の人を除き、応募者は自転車課題分析表に基づく8段階のチェックを受け、特段の問題がなければ採用する。面接では、支援者の有無や今までの支援計画書を確認するほか、仲間との過ごし方や体調不良時の切り抜け方など、4つの質問を行う。「人の能力や適性の見極めは実際に仕事をしてもらわないとできません。また障害のある方は自己肯定感が低く、正確な自己評価や自己PRをできる方が少ないので、面接はあくまで本人の背景を理解する場と考えています」と語る。
「目合わせ」を徹底し、業務に支障が出るリスクを把握・共有する
警備の仕事はチームを組んで行うが、現場では通常、警備員一人ひとりの距離が10m以上離れているため、1人で判断しなければならない。「時にはお客さまから『障害のある警備員を1人にするなんて危険だ』と言われることもありますが、危ない場所は誰にとっても危険です。先に述べたとおり、当社では現場のチームがあらかじめ自分たちで安全な場所に配置を決めており、たとえば重度の躁うつ病がある社員が電気通信工事で高所作業車を追走して交通警備を行うこともあります。どのような障害があっても、安全に警備できるようチームで考えているのです。そのうえで、手厚いサポートおよび情報共有の仕組みを構築しています」(岩﨑氏)
事務所には各現場を担当する管理者が常駐し、毎朝のあいさつや体調チェックをはじめ、ことあるごとに無線で連絡を取り合っている。「トラブルが起きれば無線をつなぎっぱなしにして状況を正確に把握し、適切な対応を指示します。遠隔ながら一人ひとりに寄り添っているイメージです」と岩﨑氏。またベテランの警備員が現場を頻繁に巡回し、指導員として実務を教えている。管理者、指導員とも障害者支援のサポーター(有資格者)ではなく、警備の仕事に精通しているかを重視して配置している。
さらに社員は毎日、日報を書いてシステムに上げる。日報には「寝つきが良かったか」「やる気・集中力が出たか」「不安なことはないか」といったチェック項目と自由記載欄があり、管理者は毎回コメントを返すほか、週一ペースで日報を基に定期的な面談を行う。5分程度の簡単な面談だが、これを「目合わせ」と呼んで特に重視している。「仕事を続ける自信がない」などの記載があれば、すぐに面談してケアに努めており、離職や休職を防いだケースも多い。
また、気になる情報は、現場チームのほかのメンバーにも随時共有し、リスクアセスメントを行って業務不能に陥りそうなリスクを報告させている。軽微なクレームが来そうなレベルから契約先に解除されるレベル、さらには死亡事故につながりかねない危険な兆候まで、あらゆるリスクを洗い出して対策を練り、すべての現場の安全仕様書を作成・更新して全社員に情報を周知している。「同僚の障害特性が基で発生するリスクも、情報が周知されていればお互い様の組織風土により疑心暗鬼になることなく仕事を続けられます。『目合わせ』をはじめ、こうした仕組みが整うにつれ、事故率はもとより離職率もきわめて低くなりました」と岩﨑氏は語る。
警備業界は人材の定着が難しく、入社1年目で3~5割が退職すると言われている。「しかし当社の離職率は社歴を問わず去年は1.7%でした。また、日給制が常識の業界にあって全社員が月給制であり、給与水準も地域警備員と比較して約10%高いです(※1)」(岩崎氏)。月の労働時間は155.5時間(業界平均196時間※2)、有休取得率90%、研修時間は実労働時間の6.4%と、労働環境や人材育成の水準が高い。類のない実績が評価され、2020年に人を大切にする経営学会が主催する「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞で、審査委員会特別賞を警備業では初めて受賞している。
多様な人材がいるほど、仕組みや制度が強化され生産性が向上する
人事評価制度においても障害者とほかの社員の区別はなく、係長級以上の役職にも精神疾患など障害のある社員が就いている。昇進・昇格の判断材料は、同僚・部下・上司の三者によるボトムアップ型評価に基づくもので、順に5割・3割・2割と、同僚の評価のウエイトが最も高い。「最大の評価項目は『ほかの社員をどれだけ成長させたか』であり、同じ立場の同僚の客観評価を一番重視しています。これにより管理者など健常の社員の指導力も目に見えて上がっています」と岩﨑氏は語る。併せて挙手人事制度も導入しており、本人の希望を踏まえた昇格・降格が可能である。「挙手しない権利、あるいは『一定期間評価を受けない権利』なども認めることで、多様な社員の居場所を確保しています」と岩﨑氏。
人材育成に関しては、年度ごとに一人ひとりチャレンジプランシートを作成し、目標管理を行うとともに個別対応型の社内トレーニングプログラムを実施している。「本人にやりたい業務があれば、必ずやってもらう。そのうえで解決すべき課題を発見し、時には数年単位のキャリア課題としてチャレンジプランを設定することもあります。成長スピードは人それぞれなので、焦らず、長い目で育成しています」(岩﨑氏)
このような同社の取り組みは、障害者雇用のみならず広くダイバーシティに寄与しており、事実、女性社員や女性管理職の割合も業界水準を上回っている(※3)。また、障害者手帳を持たない、いわゆる“グレーゾーン”の者や、ひきこもり経験のある者などを積極的に雇用しているのも特筆すべき点である。「なんらかのハンデがあっても、『目合わせ』『公平な人事評価制度などによる柔軟な働き方』『経営理念の下支え』を実践すれば、組織は必ず強くなり、生産性が飛躍的に高まります」と岩﨑氏は語る。その言葉は、実績に裏付けられているだけに説得力がある。さらに、最も印象に残ったのは続くひと言である。「逆説的に言うと、手厚いサポートが必要な方がいればいるほど、目合わせや制度が強固になるため、生産性が上げやすくなるのです」。障害者をはじめ多様な人材を活用することで、健常者ばかりの環境よりも会社が強くなるという指摘を重く受けとめたい。
(※1)「令和6年賃金構造基本統計調査」により、警備員の所定労働時間166H/月と所定内賃金224.3千円/月を基にすると全国の平均時給は1351.2円。「職業安定業務統計による地域指数」(2025年度)より、福岡県は95.9%。よって、福岡県の警備員における平均時給は1295.8円。ATUホールディングスにおける所定労働時間143H/月と所定内賃金203.6千円/月を基にすると、平均時給は1423.8円。よって、同社の賃金が9.9%高い
(※2)一般社団法人 全国警備業協会(平成27年)「基本問題諮問委員会調査部会(最終報告書)」
(※3)女性社員の割合は、業界平均の6.4%(警察庁生活安全局生活安全企画課「令和5年における警備業の概況」)に対し、同社では8.4%。女性管理職の割合は、全業種の2024年平均12.7%(厚生労働省「令和5年度 雇用均等基本調査」)に対し、同社では25%
TEXT=稲田真木子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ