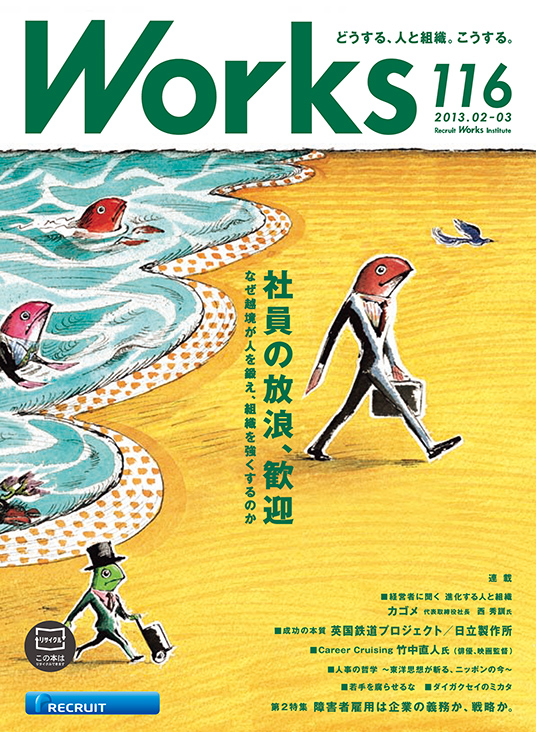革新的なビジネスモデルにより障害者を戦力化し 自ら生きる力を育む
基礎情報
| 就労支援事業所 | |
| 精神障害-発達障害 | 19人 |
| 身体障害 | 1人 |
企業勤務が難しくても支援があれば可能。就職につなげる新しい「S型」を創設
障害者総合支援法に基づく就労支援サービスには、目的や内容により「就労継続支援」「就労移行支援」「就労定着支援」の3つの制度が設けられている。そのうち就労継続支援にはA型とB型があり、A型は一般企業などで働くことに困難を抱えるものの、雇用契約に基づいて働くことが可能な人が、支援体制がある事業所と雇用契約を結んだうえで業務に従事する制度である。雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の給料が保障される。一方、B型は雇用契約を結ばずに、体調などに合わせて自分のペースで利用できる。
ところがカムラックには、独自に「S型」と呼ぶA型事業所がある。利用者と雇用契約を結び、企業から業務を請け負うまでは通常のA型と同じだが、「S型」ではその業務を1人でできるようになるまで利用者を育成し、十分なスキルが身に付くと取引先の企業に採用を提案する。いわば職業訓練機能と就労移行支援を兼ねたハイブリッド型である。業務水準や受け入れ環境の懸念から、直ちに障害者雇用に取り組むことを躊躇している企業も、この仕組みなら既に能力が保証されているから安心だ。ちなみにカムラックのS型事業所(就労継続支援A型事業所「Come Luckラボ」)が受託する業務の大半はIT系で、これまで行政機関のホームページ制作やアプリ開発などにも実績がある。通常のアウトソース先と比べても遜色ない成果を上げている(本プロジェクトのウェブ素材もカムラックで働く方がデザインしている)。
企業に採用された障害者は、安定収入を得て社会保険にも加入できる。「つまり少しの支援があれば社会で自立できる人たちを『納税する側』に移行することで、社会保障の受け手を減らし、本来もっと支援が必要な重度の障害者に行き届くようにする。これが、私たちが目指す社会のあり方です」と語るのはカムラック社長の賀村氏。雇用側にも利益をもたらす画期的な取り組みは労働行政にも高く評価され、2024年に福岡労働局が創設した、障害者の戦力化を通じて企業の人材確保を支援するスキーム「福岡モデル」に障害者戦力化先進企業として参画している。本コラムではカムラックの取り組みをひもときながら障害者の戦力化について考える。
業務委託から採用に。雇用側も利用者もウィンウィンのビジネスモデルを確立
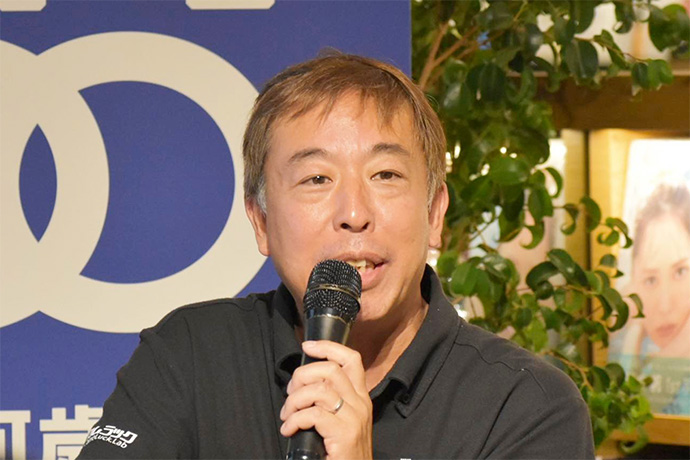 賀村 研氏
賀村 研氏
カムラックが創業したのは2013年。システム開発やウェブ制作を行うIT企業としてスタートした。当時からIT業界は人手不足だったが、「育児や介護で離職された方からの『フルタイムは無理だけど少しでも働きたい』という声は結構ありました。ベンチャーならその辺り、柔軟に対応できるだろうと。なるほど一億総活躍の時代だな、といった話をしていた流れで、障害のある人も話題に上ったのです」と賀村氏は振り返る。それまで関わりがなく、障害者が「稼げる」イメージも持てなかったが、一方で四十路を前に、社会に貢献したいという思いも芽生えていた。手始めに就労支援事業所を見つけ、データ入力などの作業を発注した。「しかし上がってきたものは、到底私たちの求める水準に達していませんでした。その際、いろいろと疑問を抱いたことから、自分たちでやってみようと決意したのです」(賀村氏)
発注者が満足する仕事を行い、雇用者を経済的に自立させる。またその中から企業に送り出す。賀村氏は当初から、こうした持続可能な仕組みづくりを考えていた。そこでまず、8時間フルタイムで働けるA型事業所を設立した。なお、多くのA型の勤務時間は4時間から6時間未満である。当初は「給与に見合う仕事をする」という点で多少の意識改革は必要だったが、業務自体は問題なく習得できた。「障害のある人は限定的な業務しかできない、というのは雇う側の先入観にすぎません。必要なのは能力を発揮できる環境を整えてあげることです」(賀村氏)
「障害があろうが、どんな仕事でもできる」と断言する賀村氏は、企業へのアプローチも独特である。「まず障害者を雇用したいという企業から依頼が来るのですが、業務内容はこちらで選びます。障害の有無に関係なく、その企業の社員が階層別、あるいは部門ごとにどんな仕事をしているか、アウトソーシング業務も含めて総合的かつ横断的に見たうえで、企業にとっても人手が要り、我々ができそうな仕事を切り出していきます。それらを1年間、当社に発注してもらうのです」
最初は企業側も半信半疑だというが、出来栄えを確認するなどのやり取りを重ねるうちに、賀村氏いわく「先入観がどんどん壊れていきます」。1年が経つ頃には「ぜひとも採用したい」と前のめりになる。「障害者雇用を達成するという観点からすると『採用』がゴールですが、企業には『採用をスタート地点として、ここからキャリアを積ませてほしい』とお願いしています。つまり優秀な新入社員を採用するのと何ら変わりません」と賀村氏。近年では平均して年に10名程度採用されている。
新しい発注業務を覚える際は、カムラックのスタッフと依頼企業の社員が教えている。「そもそもA型には国立大学や有名私大出身の人も多く、能力だけで見るとポテンシャルは高い。ただ発達障害の特性によりコミュニケーションに問題があったり、障害があることで能力を発揮する機会が与えられていなかったりするのです」と賀村氏。A型の業務にはバックオフィス系が多いため、コミュニケーション不全に関しては対面ではなくチャットでのやり取りや、リモートワークにすることでだいぶ改善されるという。採用する企業にもこうした点を伝えて理解を求め、支援環境を整えている。
優良企業を取引先に、内製業務を切り分けることにより適正価格を実現
 冨塚 康成氏
冨塚 康成氏
障害者雇用を実現するだけでなく、戦力となる人材を獲得できる――。「カムラックモデル」が評判になるにつれ企業の依頼も増加しているが、同社は取引先の選択においても「利益を上げている企業」に限定するという独自の方針を貫いている。ダンピングされがちな労働力を安売りすることなく仕事を請けるためで、事実、A型利用者の給与は最低賃金より高い。「現在は、1日6時間以上の勤務ができることが雇用の前提条件なので、週に30時間、月給にすると15万円から20万円になる」と各事業所のサービス管理責任者を束ねる冨塚氏は語る。ほか前提条件には「PCのタイピング」があるが、応募者によってはプログラミングやテストといったシステム開発業務に従事できる人もいる。「そうするとシステム開発会社が受託案件の中で下流工程を切り分けて当社に発注するようになり、そのぶん別の案件を増やすことができるわけです。元は発注先が内製でやっていたので金額もそれほど下がりません。その点でも共存と共栄のビジネスモデルが出来上がっています」(賀村氏)
仕事の確かさが周知されるに伴い、依頼される業務の幅も広がっている。軽作業も増えてきたためB型事業所を作ったが、「内製の仕事を切り出して請け負うスタイル」はA型と同じである。代表例はトラックの洗車業務で、「洗車はトラック整備の最終工程です。高収入の整備士の仕事の一部を請け負う形で受注したため、1台当たりの洗車料はほかのB型事業所が請け負う場合よりはるかに高額です」と賀村氏。最終的には洗車スタッフとしての採用を視野に「A型に行くためのB型事業所」と位置付けている。
とはいえ、同社のA型(カムラックにおける「S型」)利用者のスキルはかなり高く、移行するにはハードルが高すぎたため、間にワンクッションとして「従来の」A型支援事業所を開設している。これはB型利用者のスキルを無理なく高めるとともに、デザイナーやプログラマーとしては難しいが、定型業務は問題なくできる人材の受け皿にもなっている。新たに作った子どもを支援する放課後等デイサービスを起点に、B型からA型、企業に行くためのA型(S型)ならびに就労移行支援事業と進み、企業の就職につなげる「段階的支援体制」を確立している(図)。

出所:カムラックホームページ
障害者としてではなく、企業等の戦力として活躍する人を増やす。こうしたカムラックの取り組みは現在、全国の関係者に知られ、同社では賛同する行政機関や企業にノウハウを公開している。「うまくいく支援のあり方は、地域の特性によって異なります。当社が広く展開するというより、やはり地域に根ざした企業に取り組んでいただきたい。そのための連携や協力は惜しみません。声をかけてくだされば喜んで応援します」と冨塚氏は呼びかける。
同社が利益を上げている企業、もっといえば「業界トップ企業」との取引を重視しているのは、適正価格の確保のほかにもう1つ、大切な理由がある。「利用者の自己肯定感の向上です。当社では顧客企業に許可を得たうえで、利用者の仕事内容をご家族に伝えています。ほとんどの親御さんは『あんな有名な会社の仕事をしている』と驚き、我が子を大いに賞賛されますね。また、毎日のように当社の見学に来られる企業の皆さんも、利用者の仕事ぶりに感嘆されています。利用者の多くは、就職の失敗や人間関係の挫折などにより傷ついていますが、そんな機会を通じて次第に自信が得られ、就労意欲が高まるようです」と賀村氏は語る。さらに同社の「S型」施設の隣に、あえて放課後等デイサービスを配置し、職場見学を通して子どもたちに「将来はこんなふうに活躍できる」という、ロールモデルを示すという発想にも唸らされた。自ら生きる力を引き出す、まさに草の根の支援に多方面から取り組んでいる。
TEXT=稲田真木子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ