著者と読み直す
『ケアと編集』 白石正明
常識からの逸脱部分がそのままで輝けるように、本人を変えずに『背景』を変える
本日の1冊
『ケアと編集』 白石正明
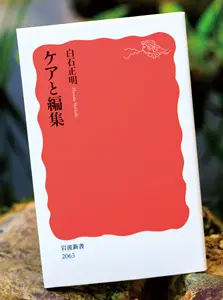 医学書院の〈ケアをひらく〉シリーズは、医療や福祉の専門家、病気や障害の当事者、哲学者、ロボット学者など多彩な著者が独自の視点から「ケア」に光を当て、大宅壮一ノンフィクション賞、新潮ドキュメント賞、小林秀雄賞、大佛次郎論壇賞など多くの賞を受賞してきた。その名編集者がケアする人たちから学んできた、人や文章の〈傾き〉が輝きに変わる編集術とは。ケアにまつわる名著のガイドとしても参考になる。(岩波書店刊)
医学書院の〈ケアをひらく〉シリーズは、医療や福祉の専門家、病気や障害の当事者、哲学者、ロボット学者など多彩な著者が独自の視点から「ケア」に光を当て、大宅壮一ノンフィクション賞、新潮ドキュメント賞、小林秀雄賞、大佛次郎論壇賞など多くの賞を受賞してきた。その名編集者がケアする人たちから学んできた、人や文章の〈傾き〉が輝きに変わる編集術とは。ケアにまつわる名著のガイドとしても参考になる。(岩波書店刊)
ALS(筋萎縮性側索硬化症)を発症した母を12年間介護した川口有美子さんの『逝かない身体』、小児科医・研究者であり脳性麻痺の当事者でもある熊谷晋一郎さんの『リハビリの夜』、哲学者・國分功一郎さんが能動でも受動でもない「中動態」と依存症を関連づけて論じた『中動態の世界』、美術やアートを専門とする美学者、伊藤亜紗さんの『どもる体』。医学書院の〈ケアをひらく〉シリーズのラインナップは実に多彩だ。医学や看護など専門領域外からも幅広い読者を惹きつけ、数々の賞に輝いてきた。
『ケアと編集』は、同シリーズの編集者、白石正明さんによる初の著書。不思議なタイトルについて白石さんは「『と』って、やっぱり便利。関係ないものを『と』で結ぶと、何かそこにあるんじゃないかと人は思うでしょ」と悪戯っぽく笑う。そう、これは謎解きの本なのだ。
ケアとは何か。白石さんはシリーズの各作品を引用しながら、思考を巡らす。執筆者との出会いや作品が出来上がっていくまでの過程もたっぷり振り返る。時に「話がどんどんズレていって、終わらなくなってしまった。こんなことでいいのか」と自らツッコミを入れるほど、思索の道はうねうねと曲がるが、当初はまったく異なる仕事に見えた「ケア」と「編集」が、実はよく似ていると最後には納得させられる。
謎解きで重要な役割を果たしているのが、北海道浦河町にある精神障害者の生活拠点「浦河べてるの家(以下、べてるの家)」のソーシャルワーカーの向谷地生良(むかいやちいくよし)さんだ。精神障害のある患者が、自分たちを苦しめている幻覚や妄想をネタにして語り合う「幻覚&妄想大会」など、べてるの家の型破りな取り組みの中心にいる人物だ。こんな話がある。
〈傾き〉を正さず 魅力にしてしまう
ある日、向谷地さんは患者女性を講演の舞台に上げ、彼女にまつわる話をして会場が盛り上がる。そこで向谷地さんは本人に語りかける。だが、数日前からまったくしゃべらなくなった彼女は無言のまま。会場の空気が緊張する。その瞬間、向谷地さんは言う。「これからまったくしゃべらない芸をします」。今度は無言が会場の笑いを誘い、彼女もニヤリと笑う。
「しゃべることがよいという普通の価値観にのっとって、しゃべれない人をしゃべれるように変えようとするのが医学です。一方で向谷地さんがやってるソーシャルワークは、しゃべらないという常識からの逸脱部分がそのままで輝けるように、本人を変えずに『背景』を変える。とすれば、編集にも医学的編集とソーシャルワーク的編集があるんじゃないか。編集者が自らが理解できるよう文章を改変するのが医学的編集。著者や原稿の〈傾き〉はそのままに、むしろ〈傾き〉を強調することによって、逆に魅力にしてしまうのがソーシャルワーク的編集。僕はそれを目指してきたのだと思います」
白石さんが向谷地さんを「編集の先生」とまで呼ぶのには理由がある。白石さんは、ある講演で向谷地さんが女子学生から「信じられる根拠がないときにはどうするんですか」と聞かれたときのエピソードを引いて、こう続ける。
「彼は、べてるの家では『信じる』をそんなにきまじめに使っていない。ヤケクソに信じるとか、口先だけで信じるとか、つまり『ちょっと信じる』でいいんだと言いました。20年以上前のことですが、僕はこの答えにすごく感動した。今の世の中では、根拠なくちょっと信じるなんて理性的じゃないように思われるでしょ? でも、まったくそうじゃない。現実の人間関係では、『あなたを信じられるエビデンスを出せ』と言った瞬間に信頼関係は崩れます。嘘でもいいから先に信じることで、お互いの間に『信』が事後的に形成されていく。つまり、向谷地さんの『ちょっと信じる』は現実を生きるうえでの最適解なんです。それに人間はずっとそうやってコミュニティをつくって生き延びてきたわけだから、人類学的な根拠だってあると思いますよ」
モノサシを変える 問いの外に出る
そして、〈ケアをひらく〉シリーズも、常識からはみ出すアナーキーな「べてる的価値観」を多くの人に知ってもらいたい、べてるの不思議さをさまざまな専門家の目から解明してほしい、という思いから生まれたのだという。
「ケアは刹那的」「自立のためには依存先を増やす」「受け身の豊かさ」「モノサシを変える」「問いの外に出る」。『ケアと編集』で出合う言葉も、アナーキーだ。「狙ったわけではないけれど、与えられた問題に答えるのに汲々としている人たちに具体的に役立つものになっているのでは」と白石さん。自立/自律せよ。能動的であれ。コスパが大事。未来のために今は我慢──。私たちが自分自身や他者にかけている現代の呪いから自由になるのにも、おすすめの1冊だ。
 Shiraishi Masaaki
Shiraishi Masaaki
中央法規出版で10年間校正に従事したのち、1996年に医学書院入社。2000年から編集者として作ってきた〈ケアをひらく〉シリーズは50冊(2025年9月現在)を数え、2019年には毎日出版文化賞を受賞。2024年3月に医学書院を定年退職。
Text=石臥薫子 Photo=今村拓馬


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ