人事は映画が教えてくれる
『A.I.』に学ぶ機械との共生における日本人の強み
非生物も自然に愛せる日本人ならではの感性に今こそ注目したい
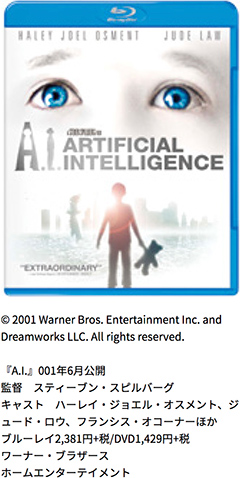 【あらすじ】舞台は近未来。ある日、子どもが不治の病で冷凍睡眠状態にあるスウィントン夫妻のもとに、夫の会社が開発した、母親を愛する機能を持つ少年型ロボット、デイビッド(ハーレイ・ジョエル・オスメント)がやってくる。妻モニカ(フランシス・オコーナー)は、最初は抵抗を感じるが、いつしか人間そっくりに作られたデイビッドを愛するようになる。しかし、実の子どもが奇跡的に回復し、家庭に戻ってくると、彼を危険な目に遭わせたことが原因となってデイビッドは捨てられてしまう。
【あらすじ】舞台は近未来。ある日、子どもが不治の病で冷凍睡眠状態にあるスウィントン夫妻のもとに、夫の会社が開発した、母親を愛する機能を持つ少年型ロボット、デイビッド(ハーレイ・ジョエル・オスメント)がやってくる。妻モニカ(フランシス・オコーナー)は、最初は抵抗を感じるが、いつしか人間そっくりに作られたデイビッドを愛するようになる。しかし、実の子どもが奇跡的に回復し、家庭に戻ってくると、彼を危険な目に遭わせたことが原因となってデイビッドは捨てられてしまう。
『A.I.』は、人を愛する機能を持った少年型ロボットのデイビッドが、息子として人間の母親の愛情を得ようとする物語です。
冒頭のシーンで、デイビッドを開発した博士に一人の女性が「ロボットから愛されるなら、人間もその愛に応える義務があるのではないか」と問いかけます。これに対して博士は何も答えなかった。つまりそれこそがこの映画のテーマです。
このテーマ設定には、キリスト教的な欧米人の世界観が色濃く反映されています。「人間とそれ以外」を峻別する彼らにとって、ロボットは愛情の対象とはならないんですね。
劇中では、それを象徴する場面がいくつも描かれます。子どもたちがデイビッドをいじめるシーン、ロボットを破壊して愉しむショーのシーンなどがそれです。また、最初に家族が食卓を囲むシーンで、デイビッドに食事は用意されません。AIがどれだけ発達しようと、彼らにとってロボットは人間より下に位置するモノにすぎません。
母親のモニカは、デイビッドを人間と思い込むことによって愛そうとします。そして、デイビッドは人間になることでモニカの愛を得ようとする。どちらの心の中にも「人間か、ロボットか」という葛藤があり、その葛藤こそがこの悲しい物語を成立させています。
2000年後、デイビッドの願いは叶います。最新技術によって1日だけ蘇った母親からの愛情を受けたデイビッドは、その愛情を胸に自分の機能を停止させます。自ら「死」を選んだデイビッドの行為は非常に人間的です。彼は「人間になる」ことで葛藤を乗り越えたのです。
このラストシーンに私は涙が止まりませんでしたが、その一方で、「日本人がAIロボットの映画を撮ったらこうはならないだろう」とも感じました。それはなぜでしょうか。
「八百万の神」の世界である日本では、万物に魂が宿ると考えられています。特別信心深い人でなくても、日本人はこの感覚をどこかで持っていますから、非生物にも愛情を注ぐことができてしまう。お掃除ロボットに名前をつけたり、自動車やバイクを恋人のように扱ったりするあの感覚です。読者のみなさんも心当たりがあるでしょう。
ですから、日本人はロボットをロボットのまま愛することができる。つまり、『A.I.』で描かれたような「人間か、ロボットか」という葛藤は起こりようがないのです。のび太たちは、ドラえもんがロボットだとわかっていて、自然に友達になっている。あれが日本人の感覚です。
これからは、今まで人間が行ってきた仕事の一部をAIロボットが担っていくようになります。販売や介護など対人サービスの領域にもAIロボットが浸透していくでしょう。
そのとき、これは私の予測ですが、欧米では、『A.I.』で描かれたように、人間がロボットを拒絶する局面が訪れる可能性が高い。拒絶(自分と違う者を拒む)→融合(違いを無視して同化しようとする)→分離(違いを認める)→統合(違う者同士が一つにまとまる)というダイバーシティのプロセスをひとしきり経る必要が生じるはずです。
 願いを叶えたデイビッドが、母親モニカと共に永遠の眠りにつくラストシーン。この悲しいストーリーは欧米的な価値観のもとでこそ成立する
願いを叶えたデイビッドが、母親モニカと共に永遠の眠りにつくラストシーン。この悲しいストーリーは欧米的な価値観のもとでこそ成立する
それに対して、日本人は、前述の理由からAIロボットを自然に受け入れることができると見ています。拒絶→融合の段階を経ず、いきなり分離の段階から機械との共生を進めていくことができる。これは、日本にとって大きなアドバンテージです。ですから、私たちは自分たちの感性に自信を持って、AI時代のモノ作りやサービス作りを徹底的に推し進めたほうがいい。
人事にとっても、AIロボットとの共生・協働は、「どんな問題が起こるかわからない」という意味で、近い将来の懸案事項かもしれません。しかし、日本人に限っては大丈夫。それが私の見立てです。
Text=伊藤敬太郎 Photo=平山諭 Illustration=信濃八太郎

野田 稔
明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科教授
Noda Minoru リクルートワークス研究所特任研究顧問。専門分野は組織論、経営戦略論、ミーティングマネジメント。
Navigator


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ