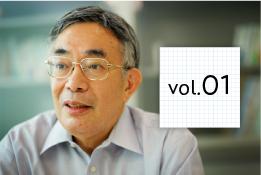人が集う場を提供する「インフラ型」組織へ 人事は会社と個人の調整役(太田肇氏)
 同志社大学政策学部
同志社大学政策学部
太田肇 教授
社員主導のキャリア形成を進めようとする時、多くの企業が個人の意思を尊重することと、組織としての最適配置をいかに両立するか、という課題に直面する。個人と企業、双方がWin-Winでいられる関係をつくるため、人事はどのような役割を果たすべきだろうか。同志社大学教授で「個人を生かす組織」を研究してきた太田肇氏に聞いた。
社外も視野に入れ、社員のキャリアを考える
大手企業を中心に、公募やジョブ型の人材マネジメントなど、社員が自律的にキャリアを構築する仕組みが広がりつつある。しかし太田氏は「細かい制度は変わっても、人事主導で社員をローテーションさせるという『骨格』が変わらない限り、効果は限定的ではないでしょうか」と疑問を投げかける。
「ジョブ型」を導入したと言っても、ポストごとの職務を定めただけで、実際には社員の多くが会社主導で異動している企業も少なくない。一方、欧米企業のジョブ型は、ポストごとに希望者を募って職務限定で採用するため、基本的に望まない配置は発生しない。さらに米国では空いたポストはほぼすべて公募で補充するが、日本ではポストを絞って募る例が多い。
また日本企業は、原則的に職務無限定で社員を雇用するため、事業再編などの際、配置転換によって社員の雇用をできる限り維持する義務が生じる。このため再編される部署の社員は、希望以外の部署へ異動せざるを得ないケースもある。
「私は欧米の制度を理想とは思いませんが、日本企業が、社員の意思によらない異動をすべてなくそうとしても、解雇規制が足かせとなり実現は難しいと思います」
大企業で「ジョブ型」が機能しているように見えるのは、グループ内に多くの事業が存在し、社員が望むキャリアを、異動によってある程度実現できるからだ。しかしこうした大企業はごく一部にすぎず、大多数の企業は、組織内で社員の希望を叶えるのには限界がある。
このため太田氏は「雇用の流動化を前提に、社外も視野に入れて社員のキャリアを考える必要がある」と強調する。
個人の意思を尊重せず組織に囲い込むような企業に、優秀な人材は集まらない。そんな組織では働き手の意欲も低下し、創造的なアイデアや挑戦も生まれなくなるだろう。フリーランスの増加といった外部要因からも、企業が組織内で部分最適を追求することに、限界が来ていることは明らかだ。
退職を企業の「得」に変える アルムナイや出戻り社員を活用
企業が、社外も含めたキャリア形成に本気で取り組むには「企業と個人、双方にとって中途退職が損にならない仕組みを整える必要があります」。
退職者については、アルムナイという形で緩やかなつながりを維持し、社外からプロジェクトベースで事業に関わってもらう。さらに社外から再び内部に「出戻る」人も歓迎するなど、組織と個人がより柔軟な関係をつくれるようにする。
「退職者が社外でもまれて成長し、在職中以上の戦力となって社外から貢献してくれる場合もある。そうなれば、中途退職はむしろ企業に恩恵をもたらします。どこからが組織の『外』で、どこからが『内』かという壁を薄くし、広い視野で損得を考えるのです」
退職者や転職者、フリーランスなど多様な人材が、社員と同じ土俵で働くようになれば、組織はピラミッド型から、人が集う場を提供するという「インフラ型」に近づく。人事の役割は、アルムナイネットワークや「出戻り」のような、企業と個人がWin-Winでいられる仕組みを整え「インフラ型」組織への移行を促すことだ。
「人事は、会社と個人の調整役を務めればいいと思っています」
人事は「ライン」から「スタッフ」へ
日本企業では従来、人事が強力な人事権を占有し、あたかも事業や経営に直接関わる「ライン」の部署であるかのように振る舞ってきた。しかしこれからは間接部門として「スタッフ」に徹するべきだと、太田氏は指摘する。
配属や仕事の割り振りには、人事権を行使するのではなく「市場原理」を働かせ、活躍している社員ほど、公募などを通じて希望の部署ややりがいのある仕事に就きやすくする。人事の役割は、フェアな公募制度を構築することや、応募に必要な情報を社員に提供すること、さらに希望が叶わなかった社員に、理由を説明して納得してもらうことなどだ。
また「かつて多くの企業で人事部員がしていたように、現場に足を運び、社員の話を聞くことも重要」とも語る。社員に対する周囲の「評判」を聞き取り、人事評価の参考にすることで、評価の納得感や公平性を高める効果も期待できる。ただそのためには、1対1でじっくり話をして、本音を引き出す必要がある。
「社員の本音には、アンケートや通り一遍のヒアリングを超える深い情報が含まれています。ただ、評価や異動などを決定する立場の人に『転職したい』などと打ち明ける社員はいません。だからこそ人事は人事権という『生殺与奪の権利』を手放す必要があるのです」
採用に関しても、白紙の人材を一括採用し、人事部主導で配属する手法は時代に合わなくなりつつある。とはいえ入社間もない若手などを中心に、社員側にも「職場に育ててほしい」という「受け身」の要望は根強く存在する。
こうした層にはキャリアの相談に応じ、選択肢を提示するなど、人事部の介入もある程度は必要だ。ただ行き過ぎにならないよう、対象を入社3年目までに絞るなどの線引きをするべきだという。
「大事なのは最終決定権が本人にあることを人事が認識し、本人にも伝えること。そして人事が本人に『社外に出る』という選択肢も、隠さず提示することです」
社員に受け身の傾向が強いのは、企業に「社員自らキャリアを築く」という選択肢がほぼ存在しなかったことの裏返しでもある。社員は、自分の意思ではキャリアをどうすることもできないとわかっていたがゆえに、考えることを放棄してしまったのだ。
「自分の望むキャリアを実現できる道が開ければ、社員はそのことに真剣に向き合うようになり、自己決定力も高まるはずです」
それぞれが社会や市場に貢献 企業と個人の「間接的統合」
人事の主導権を個人へ移すと、社員の希望は叶っても企業は全体最適を実現できず、成長が妨げられるのではないか、という懸念も生まれる。太田氏はこれに対して、「社員全員が企業と同じ方を向いて仕事をする時代は終わった」と言い切る。
「働き手の家庭の事情や価値観、稼働できる場所や時間などが多様化するなか、社員には自分なりのやり方で職場に貢献してもらい、その結果として自社も成長するのだと、企業は考えを切り替える必要があります」
経営理念への共感などにもあまりこだわらず、組織に貢献してくれそうな人材を幅広く受け入れることが、かえって成長につながる可能性もある。また欧米企業の経営理念には多くの場合、個人の尊重や豊かな生活の実現といった社員向けのメッセージも盛り込まれているが、日本企業の理念は、「顧客や社会にどのように貢献するか」という視点に偏りがちだ。このため社員が理念を自分ごととして受け止めず、表層的な理解に留まっているケースが多い。
「日本企業は理念などを通じて、『社員に何を提供できるか』をもっと明確にすべきです。それによって社員も『会社で働くことが自分にとってプラスになるなら、力を合わせて貢献しよう』と考え、自然に求心力が生まれるのです」
たとえ企業と個人の立ち位置が違っていても、社会や市場に貢献するという目的を共有することで、結果的に同じものを目指すという姿が、これからの両者の在り方だという。
「個人と企業が、社会や市場という『北極星』に向かって進み、それぞれに実績をあげてそれが評価されることで、結果的に企業利益も生み出していく。いわば市場や社会を通じて、企業と個人が間接的に統合されるのです」
聞き手:千野翔平(研究員)
執筆:有馬知子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ