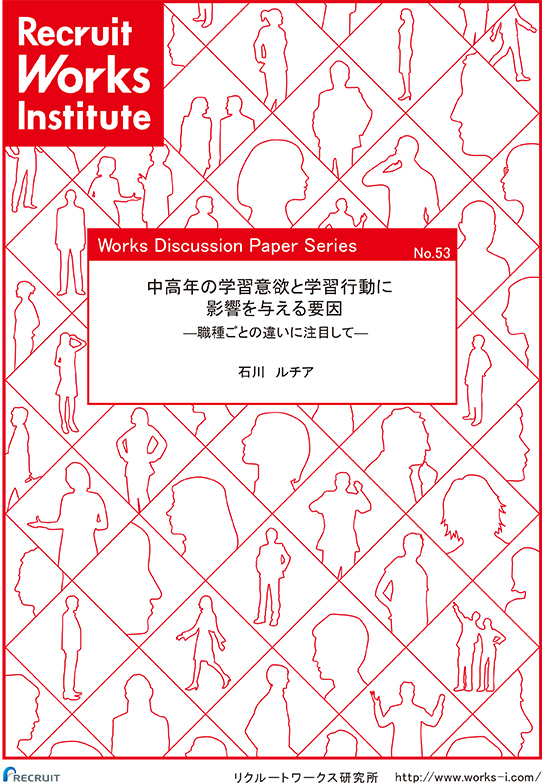プログラミングを習得しアプリ開発 60代で一から学び始めた原動力とは
服部太郎さん(男性、66歳)
流通会社勤務
服部さんは60代になって一からプログラミングを学び、2023年11月にはiOSアプリを開発、Appleの承認を得てApp Storeでリリースした。「職場で新たに導入予定のツールにも挑戦し、業務を自動化できる仕組みを開発したい」と意気込む。1パソコンユーザーが、4年間で職場の課題解決をデジタル技術で進める存在になった背景を聞いた。
「人生のリベンジ」でデジタルを学び始める
服部さんがプログラミングの勉強を始めたのは、5年前の2019年。最初は「職業人生をこのままでは終わりたくない、リベンジしたい」という思いからだった。大学院で土木工学を学び、1982年に大手ゼネコンに就職。その後流通業界に転職したが、誘いを受けて流通小売業向けクラウドサービス会社の立ち上げに参画した。しかし10年ほど経った55〜56歳の頃から、上司の言葉による嫌がらせや仕事面での冷遇などのパワハラを受けるようになり、やがて退職勧奨された後に、解雇されてしまう。幸い取引先だった今の勤務先に転職できたが、「不本意な形で会社を去ることになったのは納得できませんでした」(服部さん)。
後半生を懸けて、社会に残せるような何かを身につけたい。最もやりがいのありそうなテーマは何かと考えたとき、思い浮かんだのはデジタル技術だった。「社会をものすごいスピードで変えていくデジタル技術に純粋な好奇心を覚えました。目の前で起きている変化に、自分が関わらずに終わるのはもったいない」(服部さん)
開発した無料アプリをApp Storeでリリース 講師に教わることで学習効率が上がった
20代に勤務していた大手ゼネコン時代には、パソコンが普及する前から設計の仕事を通じて大型電算機に接していた。ただしプログラムを書く機会はなく、1ユーザーとしてソフトを使っていた。「私たちの年代は、大型電算機時代が終わった後、社員1人ひとりにパソコンが配布され、メールや文書作成といった業務は遂行できます。一連のIT技術に何とか追いついてきたので、今回もやってできないことはないだろうという思いはありました」(服部さん)
最初は独学でプログラミングを学び始めたが、参考書を見るだけでは行き詰まり、打開策が見つからないため、プログラミングスクールに入学した。「専門家に教わることで、デジタル技術の全体像や何を学ぶべきかの方向性がわかり、学習効率が格段に上がりました」(服部さん)
まず簡単なスマホアプリを作ることで基本のプログラミングを学んだ。講師からは、行き詰まったら画面のエラーメッセージをコピーしてインターネットで検索すると解決策が列挙されるといった、当たり前だが参考書には書いていないノウハウも教えてもらった。基本スキルを身につけた後は、独自のアプリ制作を始め、複数のプログラム言語やAPI、コードの履歴管理、通信プロトコル、セキュリティを守る暗号化技術など開発に必要なさまざまな技術を順番に学んだ。
最初の目標としていたApp StoreにiOSアプリをリリースして以降、現在もプログラミング言語Pythonで開発したオリジナルのAIを組み込んだ画像処理アプリを開発中である。次はさらに多くのユーザーを獲得できるようなアプリを開発することを目指している。「アプリはさまざまなノウハウを組み合わせて構築された1つの完成したシステムで、完成したときの充実感も大きく、得られる知識も非常に深くて幅広い。もっとスキルを高めて、中期的には有料でリリースできるアプリを作りたいと考えています」(服部さん)
企業のDX研修は、一方的にスキルを伝授する形が多く、プッシュ型で学びを促す、きめ細かな対応はされていない。このため「セミナーの受講後に、業務に活用したり、スキルを習得し続けるかどうかは、本人のやる気に任されている。目先の仕事で手一杯という状況では『学んだ』以上の化学反応は起きにくいでしょう」(服部さん)。
職場でも最新ツール体験に手挙げ 業務自動化に役立てたい
服部さんの勤務先ではDX推進の専門部署を設け、従業員向けにオンラインセミナーを開いている。2024年春には、最低限のプログラムコードでアプリやシステムを開発できる「Microsoft Power Platform」が導入される予定である。希望者にはこのツールを体験させるチームを設けており、服部さんも加入した。「以前からプログラミングスクールでPower Platformについて聞いていたおかげで、勤務先でのPlatform導入にアンテナが反応し、体験チームに手を挙げることにしました」(服部さん)
服部さんは現在、管理部門に所属している。アプリ開発の知識にPower Platformのスキルを上乗せすることで、予算作成や進捗管理などの業務を大幅に効率化できると考えている。「DX推進部門はシステム環境の準備や研修などの社員教育はできても、各部署固有の業務効率化やイノベーションに直接関わるのは難しい。私のような立場の人間がリードユーザーとして現場での課題解決を進める『伝道師(エバンジェリスト)』のような役割を果たせれば、新しい仕組みの導入が徐々に浸透し、ひいては仕事の形も変えられるのではないか」(服部さん)
「伝道師」となる人材は、各職場に一定数存在すべきだと考えている。デジタル技術を扱える社員に、職場内のデジタル関連業務が集中し、ほかの社員は何もわからないまま同僚に頼りきりになりがちだ。「デジタルに関心のある社員を一定数集めて知識技術やスキルを習得させ、それぞれの職場の同僚に広めていく仕組みが必要です」(服部さん)
わからないことは自分で調べる 習慣づけが大事
服部さんはスクールでの学びを通じて、デジタルツールに対するハードルが下がったこと、わからないことは自分で調べる習慣がついたことが、大きな収穫だったという。たとえば関数やマクロを使えば瞬時にできる資料作成でも、多少作業が複雑になると断念して手作業に戻る人が多い。「ネット検索で分からないことを調べない人が大半です。研修で『自分で調べる』習慣をつけさせる必要があります」(服部さん)
多くの社員がツールを使って自分の業務を自動化できるようになり、「仕事が楽になった」というメリットを享受できれば、さらに学ぶ意欲も生まれる。また「この残業は本当に必要なのか」「この技術を新製品や新サービスの提案にどう生かせるだろうか」「顧客営業や仕入先との交渉など、本来社員が担わなければならない仕事にもっと注力できるようになるのではないか」など、職場の仕事を見直す機運が高まることも期待できそうだ。
デジタル技術を身につけたシニアが、若手の仕事を楽にする
ミドルシニアの管理職も「少なくともデジタル技術に関する基礎的な知識を身につけ、職場に導入したソフトの内容は理解しておく必要がある」と、服部さんは指摘する。「DXの対象には現場作業や企業の戦術・戦略に関わる内容もあり、現場と管理職、経営幹部が欲しい情報はそれぞれ違います。たとえ開発はスキルのある若手に任せたとしても、幹部や管理職も自分が必要な情報は自分で取り出して加工できるスキルを身につけておくべきです。」(服部さん)
シニア層が技術を身につけ、業務の自動化を進めれば、最前線に立つ若手の仕事を楽にできると考えている。管理部門の自動化が一段落したら、調達や営業など他部門のツール開発をしたいという。「私が今から営業の現場に立つのは現実的ではない。でもデジタルの仕事なら、シニアでも若手と同じくらい重要な役割を担える可能性があると思います」(服部さん)
ミドルシニア以上の社員は、デジタルの進化と、それに伴う仕事の変化を乗り越えてきており、DXも対応可能な変化の1つといえる。企業側も「中高年層のリスキリングは難しい」という先入観を取り払って学習機会を提供する必要があるだろう。また、現場を経験したシニア層がデジタル化の担い手となることで、若手が本業に集中できるというメリットも指摘された。企業としても50~60代の社員に「若手を助ける。若手にはまだ負けない」と思わせる新たなやりがいを提案することで、リスキリングの目的が明確になり、促進されるのではないか。
聞き手:石川ルチア
執筆:有馬知子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ