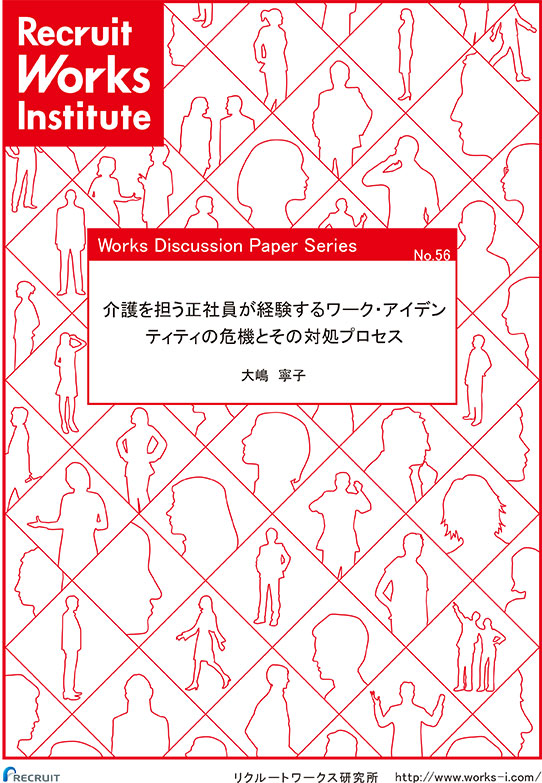「介護に寄り添う」会社の姿勢が社員との信頼関係を育てる 中外製薬・佐藤華英子氏
 中外製薬は2021年、全社員を対象とした介護と仕事の両立支援に乗り出しました。すると、導入した介護に関する実態調査、学びのツールについては、社員の約8割が受講し、企業主催の「介護相談デー」もキャンセル待ちが出るほどの盛況に。キャリアへの影響を懸念し、会社に黙って介護を担うビジネスパーソンも多い中、社員が「職場に相談してみよう」と思える土台を築けた理由を、ダイバーシティ推進室長の佐藤華英子氏に聞きました。
中外製薬は2021年、全社員を対象とした介護と仕事の両立支援に乗り出しました。すると、導入した介護に関する実態調査、学びのツールについては、社員の約8割が受講し、企業主催の「介護相談デー」もキャンセル待ちが出るほどの盛況に。キャリアへの影響を懸念し、会社に黙って介護を担うビジネスパーソンも多い中、社員が「職場に相談してみよう」と思える土台を築けた理由を、ダイバーシティ推進室長の佐藤華英子氏に聞きました。
D&Iは、非当事者を巻き込んでこそ効果を発揮
――企業として、介護支援に力を入れるという意思決定に至った背景を教えてください。
ダイバーシティに取り組み始めた10年ほど前から、介護についても問題意識はありました。2012年に介護実態調査アンケートを実施し、情報不足や知識不足といった課題に対し、各事業所でセミナーを実施、その他、介護情報専用のウェブサイトを整えたものの、当時は、育児との両立支援や女性活躍推進など、ほかに取り組むべき課題が多かったことから、中長期的な課題と判断し、優先順位の問題として、それ以上の対応は後回しになっていたのが正直なところです。
しかし近年、労働組合や各職場から具体的な困りごとの声が徐々に上がってくるようになりました。D&Iを推進していく中で、女性を含め、多様な人財がマネジャーや管理職等として活躍してもらうためには、こういった役割を担う社員の多くは介護に携わる可能性が高い世代でもあるため、介護に関する対策の必要性を感じていました。また組織運営の観点からも見過ごせないと考え、このタイミングで本格的に介護支援に取り組むことを決めました。
上位マネジメントからも、介護支援に取り組むこと自体への反論は出ませんでしたが、全社員を対象にすることについて「若手は関心を持つのか」という懸念、指摘はありました。
――なぜ若い世代も含め、全社的に施策を展開したのですか。
D&Iの施策は、特定層に実施するだけでは効果が薄いと、これまでの経験から学んでいたためです。当事者だけでなく周囲のさまざまな立場の社員を巻き込み、理解してもらうことが不可欠です。
また、介護は自分ごと化しやすいテーマでもあり、全社的なムーブメントにした方が、関心も高まりやすいと思いました。「会社のどこかで介護支援が始まったらしい」ではなく、自分にも関係し、いつ直面してもおかしくない立場として「会社が介護に力を入れ始めたね」と、社員同士が話せる環境をつくりたかったのです。
若手に関しても、水面下で関心が高まっていたからこそ、労働組合から声が上がったのだと思います。また当社はヘルスケア産業で、健康や介護といったテーマへの関心が高い若手社員が比較的多いことも、取り組みやすさにつながったのかもしれません。
――介護について、社員の抱える困りごとは具体的にどんな内容でしょうか。
一番多いのは、単身赴任や実家から遠い地域にいる間に、介護が始まったらどうすればいいのか、という声でした。ほかにも介護費用に関する不安、体力的、精神的に介護と仕事を両立できるのか分からない、介護の知識が乏しく、何から始めればよいのか、どうしていいのか分からないなど、かなり具体的な意見が出ました。「職場や会社に相談しづらい」という声もやはりあります。
また、介護を担う部下を持つ上司からも、部下に相談されてもどうすればいいのか分からない、といった声も上がりました。
当事者予備軍であり上司でもある、マネジャー層がカギに
――介護に対する基本的な考え方と、取り組みの内容を教えてください。
介護についてはケアを担う社員本人が主体的に、制度や支援機関を活用しながら、かじ取りをすることが基本ではあります。また要介護者の状態や家庭の事情はそれぞれ異なっており、期間が長期に及ぶこともあり、休業などの制度だけでは解決できない問題がたくさんあります。会社がこういった制度の整備以外に支援できることは何かを考え、セミナーや研修プログラムを通じた情報提供に乗り出しました。具体的には、まずマネジャー層にセミナーと介護実態把握を包含した学びのプログラムを実施し、必ず受講するよう呼びかけました。
――なぜマネジャー層からアプローチしたのでしょうか。
マネジャー層は、介護の担い手になりうる「当事者予備軍」世代という意味でも、介護を担う部下が現れた時、組織の体制を整え、業務を回していくという意味でも、介護支援のカギを握ると考えたからです。マネジャーにリテラシーをインプットして介護を「自分ごと化」してもらい、部下の苦労や悩みに対して、上司が部下に適切な声かけを行い、サポートができるようになれば、組織としてのマネジメント能力も高まります。
プログラムはマネジャー層の受講後、部下にあたる社員全員に展開したのですが、上司が部下に受講を勧める動きもあり、全体の受講率は8割に達しました。会社主催の「専門家による介護相談デー」には多数のキャンセル待ちが出るほどに予約がありました。上司へのアプローチから始め、一気通貫したプログラム設計による波及効果は大きかったと考えています。
――多くの企業で、社員が介護について会社に明かさず働くケースが見られます。社員が会社に相談しようと思える信頼関係を、なぜつくれたと思いますか。
まだもちろん、すべてがそのような理想的な状況になっていると思ってはいませんが、一連の取り組みを通じて「会社は介護当事者の困りごとに関心を持ち、理解しようとしている」というメッセージが社員に伝わり、安心感を生み出しつつあると思います。セミナーについても、介護当事者でない社員からも、年に1回「介護」の存在を再認識できるよいきっかけなので毎年続けてほしい、という要望も出ています。
仮に部下がマネジャーに介護支援について相談した際に、関心のない反応を返されたら「うちの職場は介護に関心がないんだな」と感じ、相談しなくなるでしょう。上司と部下双方に介護の「共通言語」を提供したことで、コミュニケーションのベースもできつつあるのではないかと感じています。今後は、全社で実施している1on1の場でも、こういった相談がよりしやすく、当たり前になってくるとよいと思いますが、こうした状況をつくっていくことが引き続きの課題だと思います。
業務量を減らしても仕事の質は落とさず、キャリアを継続
――介護を抱えるビジネスパーソンの多くは、自分のキャリアが揺らぐことに不安を抱いています。不安を解消するため、上司にはどのような心構えが必要でしょうか。
介護に限らず働き方に制約のある社員については、その先のキャリアを考えると、業務量を減らしてもアサインする仕事の質は落とさず、キャリアを継続してもらいモチベーションを維持する必要があります。当事者は「もう自分は会社に期待されていないのでは」と疑心暗鬼に陥りがちなので、上司が励ましや期待を伝える声かけをすることも大事です。
育児を抱える部下を持つマネジャーには、育児期のアサインについて考える研修を実施していますが、研修で学んだ内容は、育児にとどまらず、介護などの事情を抱えて働く部下にも応用できるものと思います。しかし実際は、当事者が対応できる業務量が減ることに不満を感じる同僚や上司もいますし、マネジメントが難しく悩んでいる上司も多いのではないかと思います。
――マネジャーに対して、今後何をすべきだと考えますか。
まず、働き方に制約のある社員の評価やキャリアについての考え方を、改めてしっかりと会社として伝えていく必要があると考えています。根本となる考え方が整理され、理解が進めば、誤解に基づく不満も解消しますし、上司によって評価の仕方がぶれることも防げるはずです。こうした取り組みの積み重ねが、部下と上司が介護や育児などについてフランクに話せる、相談できる風土へと、つながっていくことを願っています。
――新たに取り組みたいことはありますか。
介護の当事者同士がつながれるコミュニティづくりです。当社は毎月1回、ランチタイムに希望者を集めてダイバーシティのさまざまなテーマについて話す会を開催しているのですが、介護がテーマの会では、当事者同士がノウハウを教え合ったり、気持ちを吐き出したりしていました。この状況を見て、当事者には介護相談窓口のようなオフィシャルな仕組みの手前で、日々の介護について語り合いたいというニーズがあると感じました。まずは社内の小規模な集まりから始め、将来的には社外も含めたネットワークをつくれれば、と思っています。
聞き手:大嶋寧子
執筆:有馬知子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ