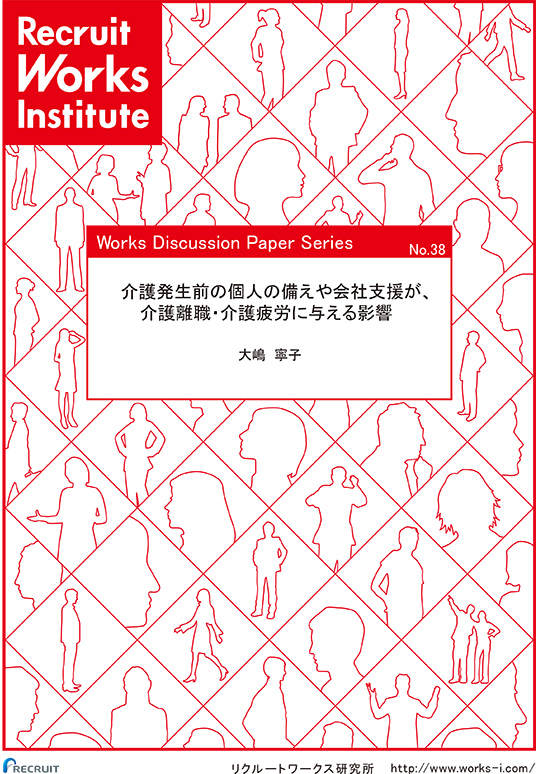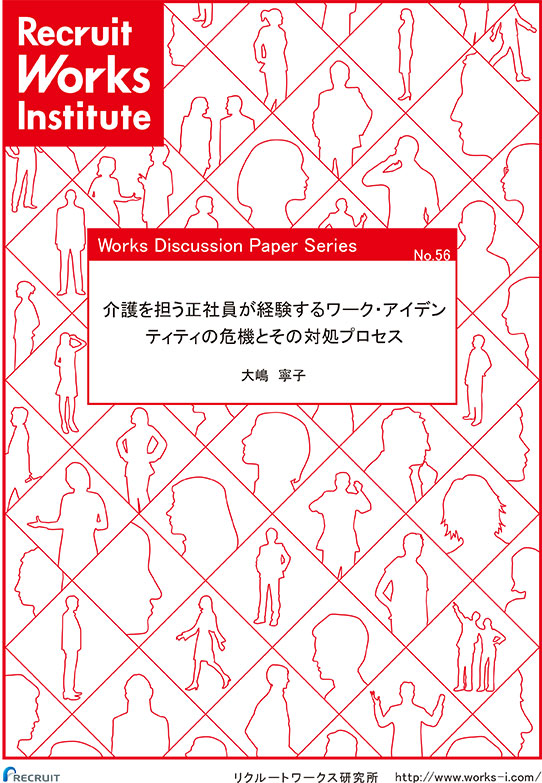介護経験で得た人間的成長を、事業に取り込む。全社員を対象に仕事と介護の両立支援策を実施 ハウス食品グループ本社・加藤淳子氏
 ハウス食品グループは2020年、全年齢の社員を対象に介護リテラシーを高める取り組みを始めました。情報不足による社員の不安を解消して両立をサポートすると同時に、介護経験に伴う当事者の人間的成長を、事業に取り込むことが狙いです。ハウス食品グループ本社ダイバーシティ推進部長の加藤淳子氏に、取り組みの経緯や課題について聞きました。
ハウス食品グループは2020年、全年齢の社員を対象に介護リテラシーを高める取り組みを始めました。情報不足による社員の不安を解消して両立をサポートすると同時に、介護経験に伴う当事者の人間的成長を、事業に取り込むことが狙いです。ハウス食品グループ本社ダイバーシティ推進部長の加藤淳子氏に、取り組みの経緯や課題について聞きました。
制約の有無による「成長機会の格差」を解消
――仕事と介護の両立支援に取り組むようになったきっかけは何ですか。
当社は2021年4月からの第七次3か年中期経営計画で、ダイバーシティの実現を通じて、個人と企業がともに成長する、という経営目標を打ち出しました。ただ、介護や育児、家族関係の悩みなどを抱えて心身ともに余裕のない人にとって、成長はハードルが高い面があります。私も親の介護をしていた時、同僚に「加藤さんはチャレンジしないの」と聞かれ、「やりたくても今はできない」と内心悔しい思いをしたことがありました。この経験もあり、人材部門で仕事をするようになって、介護を抱えても「成長機会の格差」が生まれないよう、支援の在り方を考え始めました。
また、介護は非常に大変ですが、担い手の人間的成長ももたらします。介護を担う当事者に、新規事業の創出や風土改革などさまざまな形で組織に貢献するチャンスもいずれ来るだろう、来てほしいと考えています。
――どのような支援を始めたのですか。
1年目は情報提供を通じて、社員が介護に向き合う心理的なハードルを下げることにフォーカスしました。
親が衰える姿を想像するのはつらいということもあり、多くの人は介護に直面するまで、問題を先送りにしがちです。当事者自身が、介護を突然の出来事にしてしまうのです。社員が何の知識もないまま介護に突入し、相談相手もなく孤立した結果、離職してしまう、といったケースだけはなくしたいと考えました。
介護に関する知識があれば、過剰な不安を減らすこともできるのではと考えました。
グループ各社に声をかけ、まずは5社2600人を対象に介護に備えるためのリテラシーを学ぶことができるオンラインのプログラムを導入し、情報提供を始めました。現在、国内グループ会社15社すべてが参加し4500名を対象に実施しています。
介護は年齢、性別にかかわらず誰もが担う可能性があり、実際に社内には20代の担い手もいました。同僚が当事者になった時、チームとして仕事をどう回すかというマインドも持ってもらう必要があります。そのため、受講は全年齢を対象、そしてプログラム参加は業務扱いとしました。
介護を担うのは会社ではなく自分 意識のベクトルが変わる
――社員の反応を教えてください。
導入したオンラインプログラムでは社員が設問に答えると、介護開始まで「あと〇日」とリアルな日数が示されるので「準備しなければ」という危機感が高まりました。「会社が何をしてくれるのか」ではなく「自分は何をすべきか」と、意識のベクトルも変わったと感じています。
受講者の6%に当たる89人が、実際に介護を担っていました。コメントを見ると、悩みを一人で抱え込んでいる当事者がいる一方、受講を機に「会社に相談していいと分かり、気が楽になった」という声も聞かれ、社員の安心感を高める効果もありました。
介護について知った後は、行動を促す
――2年目以降は、どのように取り組みを発展させてきたのでしょうか。
1年目に社員のリテラシーがある程度高まったので、2年目からは社員に「行動」を促すことをテーマに掲げました。講演などを通じて、介護の担い手には要介護者に安らかに過ごしてもらうための実践的な方法を伝授し、「予備軍」には早めに準備することのメリットを伝えて、備えに着手してもらおうとしています。さらに非当事者にも、介護中の同僚とどのように関わるかなどを考えてもらいます。
当事者と上司、そして私たち人材部門の担当者による三者面談も始める予定です。部下から介護について相談を受けても、直属の上司だけではどう対処していいか分からない、といったケースがあるので、私たちも面談に入り、ざっくばらんに困りごとを聞き一緒に解決策を見出したいと考えています。
――一連の施策を通じて、社員に変化は起きていますか。
メールや会話などを通じて、現場の複数の社員からポジティブな反応をもらっています。ある工場勤務の社員は「親の介護が急に始まり退職も考えたが、会社として介護支援を始めると聞いて踏みとどまった」と話してくれました。地道な取り組みを3年、6年と続けてこうした人を増やすことで、将来的に目に見えるような成果を出していければと思います。
社員の「介護リテラシー」格差の解消が課題
――今後の取り組みについて教えてください。
組織のリテラシーとして、オンラインプログラムへの回答率を、管理職で100%、国内グループ会社15社で7割に引き上げることを目指しています。社員の7割に知識があれば、残り3割も困りごとを抱えた時、横のつながりで必要な情報を得られるのではと考えています。ただ、目標の数値を押し付けるのではなく、プログラムの狙いやセルフチェックによる回答を通じて得られるさまざまなメリットなどを伝え、社員の自発的な回答を促したいと考えています。
また2020年に介護支援策を進めたことによって、プログラムへの回答者と未回答者の「リテラシー」格差が広がりつつあります。未回答者は「親はまだ元気」「仕事が忙しい」「妻が専業主婦」「実家が遠距離」などの理由で、介護と向き合うことを先送りしがちです。「おむつを替えるだけが介護ではない」「遠距離でも介護はできる」など、それぞれの家族によって介護の在り方も多様だというメッセージを伝え、彼らのマインドを変えていければと考えています。
――社員からは介護支援について、どのようなニーズがありますか。
最も多いのは、仕事と介護を両立する当事者の話を聞きたいという声です。グループ会社からも「介護のため管理職への昇進を諦めてしまう人がいるので、管理職の当事者に、具体的な仕事の回し方などを話してほしい」という要望があります。仕事も介護もチームプレーなので、当事者の話には連携の在り方など、仕事の生産性を高めるヒントも多いはずです。私たちも介護を通じて働き方が変わった、仕事の上で新しいアイデアを得たといった声を、積極的に発信したいと考えています。
本人がキャリアの舵を取り、国と会社の制度をうまく活用する
――仕事と介護の両立では、誰がキーマンになるべきでしょうか。
本人が旗を持つことが、一番大事だと思います。もちろん上司や職場の理解も大事ですが、経験のない第三者には分からないことも多く、できることにも限りがあります。当事者が自分でキャリアの舵を取り、上司や人事、会社、国の制度をうまく活用してほしいです。
――ご自身は、介護経験を通じて、どのような糧を得られましたか。
テレワークやフレックスの制度もなく、会社に出勤し所定労働時間をしっかり働くという時代でもありました。介護中は、親を家に残して涙をこらえながら出勤し、終業のベルと同時にダッシュで職場を出てヘルパーさんと交代する生活でした。最も大変だった時期でも、上司にすら最低限の情報しか共有しませんでしたし、「会社を辞めるしかない」と思いつめたこともありました。
一方、同僚との会話やランチで気分が変わって仕事に集中できることも多く、介護以外の居場所を持っていることのありがたさも感じたものです。また私は元来、ケアも仕事も一人で抱え込むたちでしたが、介護を通じて、医療や介護・福祉の専門家、同じ要介護の家族を持つ方、近所の方など多くの人に助けてもらいました。これによって負担を手放せるようになったことは、私にとってとても貴重な経験となりました。さらに今は、両立支援という経験を生かせる仕事にも携われています。社員にも「助けを求めていい」というメッセージを伝え、介護があっても働くことを諦めないでいられる組織をつくっていきたいと思います。
聞き手:大嶋寧子
執筆:有馬知子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ