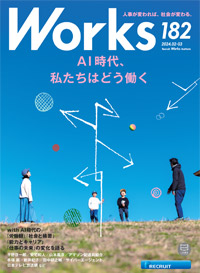理想の社会とは。その探求が哲学とAI、経済学の往還に

駒澤大学 経済学部 准教授
井上智洋氏
早稲田大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。博士(経済学)。2015年より駒澤大学経済学部で教鞭を執り、2017年より同大学准教授。専門はマクロ経済学、貨幣経済理論、成長理論。著書に『純粋機械化経済』『人工知能と経済の未来』『ヘリコプターマネー』ほか。
マクロ経済学の専門家として、AIが経済に与える影響について早くから論じてきた井上智洋氏。高校時代は哲学に傾倒し、大学ではAIを研究、エンジニアを経て学問の道に進んだという。そこに通底するのは、よりよい社会を目指す思いだと語る井上氏に、自身の知的探求の軌跡と、AI時代を生き抜くための学びのあり方についてうかがった。
大学時代はコンピュータサイエンスを専攻。卒業してシステムエンジニアとして働いた後、大学院に入学して経済学の道に進みました。端から見るとわかりにくいかもしれませんが、私の関心は一貫しています。小中学生のころから漠然と、「人間とは何か」「理想の社会とは何か」といった問いについてずっと考えてきました。
もっとも、子ども時代に、何か大きな社会との摩擦を経験したというわけではありません。活字の本は大して読まないけれど、『○○のひみつ』といった子ども向けの学習マンガシリーズが大好きで、平穏無事に暮らしていました。
ただ、当時から社会を俯瞰する癖があり、世の中の常識にはまったく染まらない子どもでした。例えば私の通った小学校では、連帯責任を求められることがよくありました。給食の配膳中に一人でも私語をしたら最初から配膳をやり直し、全員が一言もしゃべらず姿勢を正して給食を食べ終えなくてはいけなかった。子ども心に、何かおかしいなと疑問を抱いたことを覚えています。
多くの人が周囲に合わせて行動する中、私は何をするにも自分で考えて自分の理屈で行動する、少し頭でっかちなところがありました。先生に対しても、親に対しても、おかしいと思うことは「おかしい」と反論するので、「それは屁理屈だ」などと言われることも多かった。大人からすれば、扱いにくい子どもだったと思います。
これは私の生来の性質なのですが、後に知ったところでは、私の祖父は戦前、革命的思想の持ち主だったようです。祖父が持っていた社会改革に関する本が家に残っており、私も手に取ったことがあります。もしかしたら理想の社会を探求する祖父の気質を受け継いだ面もあるのかもしれません。
特にその思いが強くなったのは高校時代です。きっかけは部活動での挫折でした。理不尽なしごきが横行する中で心身ともにダメージを負って、なんとかやめることができましたが、生きているとうまくいかないことがあるという事実に直面しました。他者との齟齬、社会との摩擦のようなものを感じ、そこから哲学に傾倒していきます。ニーチェやバタイユをはじめ、国内外の古典文学や歴史書、政治思想書まで読み耽りました。実は大学進学でも、最初は文学部に行こうかと思っていたくらいです。
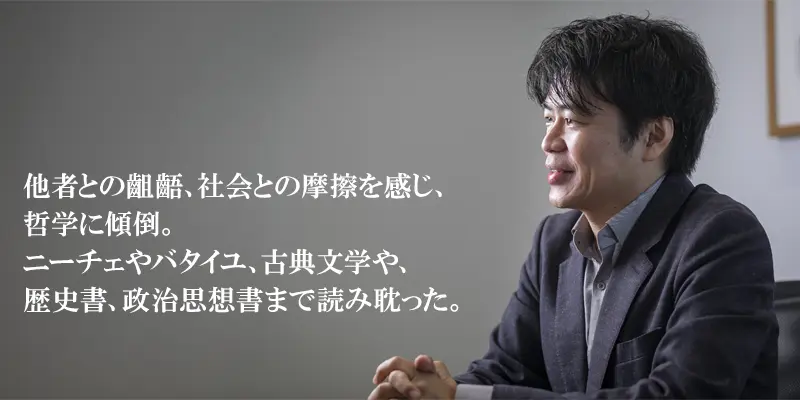
デフレ不況と技術的失業への興味が大学院進学へと導く
最終的には、環境情報学部という学部を選んでコンピュータサイエンスを専攻しました。、友達から「これからの時代はコンピュータだ」と説得されたからです。コンピュータサイエンスの中に人工知能という分野があることを知り、自分に合っているのではないかと思いました。多くのAI研究者の夢は、人間と似たようなものを作ることですが、そのためには「人間とは何か」がわかっていなければなりません。哲学的探求としても面白いのではないかと感じ、AIに関するゼミに入りました。
ただ、当時のAIは人間の知的能力とはほど遠いもので、論じられていることと実際にできることとの間には、大きな隔たりがありました。実際にやってみて「何か違うな」と思ったのも事実です。今はその隔たりはかなり縮まってきていますが、私の学生時代はちょうど第2次AIブームの後で、むしろAIは時代遅れと言われていました。
卒業後は、IT企業に就職してシステムエンジニアになりましたが、そこでもまた転機がありました。私は経理システムを作っていたのですが、「このシステムが完成したら経理担当者が失職してしまうのではないか」という疑問を抱きはじめたのです。さらに、当時はデフレ不況の真っただ中であり、「なぜこの不況は解決できないのか」と考えていくうちに、経済学に出合いました。仕事の傍ら経済学の勉強をはじめ、デフレ不況と技術的失業というテーマをさらに深掘りしたいという思いが強くなり、会社を辞めて大学院に進学したのです。
小学校で強要された連帯責任や運動部での厳しい上下関係などの経験を経て、私はいわゆる「リバタリアニズム」に近い考えを持つようになりました。その考えというのは、再分配を否定するということではなく、個人の行動を他者に強制されるような社会は望ましくないということです。
私が今、ベーシックインカムを提唱しているのも、貧困を無くしたいからというだけではありません。生きるためには働かなくてはならず、その中では不本意なことも受け入れざるを得ないのが現実です。現実的に個人の自由な選択を実現するには、ベーシックインカムのような生活の基盤を固める必要があるのではないか。今はAIの進歩によって、そうした理想の社会が実現する可能性も高まっていると考えています。つまり私にとって経済学は、理想の社会を探求する営みのなかにあるものなのです。
AI時代こそ現場に足を運び、人の話を聞く
特定の思想やイデオロギーに囚われると、それに合わせて事実認識を歪めてしまう危険も感じています。特にアカデミズムの世界に身を置いていると痛感しますが、真に科学的な態度とは、特定の学派に依らず、フリースタイルの立場で何が正しいかを探求していくことではないでしょうか。
例えば、教科書に書いてあることを錦の御旗のように持ち出す学者は少なくありません。しかし、私はむしろそれを疑うのが学者の役割だろうと思っています。私自身は、教科書に書かれていることも鵜呑みにしないように努め、自分で一つひとつ確認して、納得できなかったらこれは間違いだと堂々と批判します。ときに敵を作る行為かもしれませんが、まったく気にしていません。その根底には、子どもの頃と同じく、純粋に何が正しいのか知りたいという思いがあります。だから常に、なるべく俯瞰して物事を見るように心がけています。
それと同時に、AI時代に入って強く思うのは、経験することの大切さです。AIは大量の知識を俯瞰する能力に優れています。それこそ神のような目を持っていて、相談すれば世の中の最大公約数的な意見をすぐに教えてくれます。たまにおかしなことも言いますが、95%くらいは納得のいく返事が出てきて、何時間でも丁寧に教えてくれるので、私もよくAIと議論をします。自分の考えを深めたり検証したり、思考の壁打ち相手としてAIを活用しています。
しかし、AIには「人間としての体験」がありません。様々な情報を伝えてくれても、その基になる体験を表現したのは、あくまでも人間です。AIの学習データからは印象派やキュビズムなどの新しい絵画は生まれなかったというニュースがありました。やはり新奇性のあるアイデアや独創的な芸術は、まだ人間でなければ生み出せないのかもしれません。
結局、人間が「元ネタ」を作り、その集合知として今のAIがあるのです。もし人間がオリジンを作ることをやめてしまえば、AIのネタも枯渇してしまう。AI時代だからこそ、現場での経験や個人の感情に基づいた新しいアイデアを生み出す人間が、ますます重要になるでしょう。
これは私自身への自戒も込めて言うのですが、人文社会科学系の学者は、冷房の効いた部屋で本や論文を読んでいるだけではいけないということです。もっと現場に足を運び、人々の話を聞き、それを自分の言葉で発信していくことが大切だと思います。
それもあって最近は、知識を得るのにも五感を使うことを意識しています。身体化されない知識は、ただの暗記にすぎず、教養にはなりません。室内にいる時も、知識をより身体化できるよう、活字を読むだけでなく、戦争に関する動画を見たり、耳で古典文学の朗読音声を聞いたりするなど工夫しています。
私はもともと知ることと考えることが好きで、今でも毎日寝る前にテーマを決めて、考えながら寝ているくらいです。だから知的探求をしていること自体が楽しいのですが、自分の知識欲を充足させるだけにとどまらず、それが日本や世界をよい方向に導くことに繋がればと考えています。子どものころから追い続けてきた「理想の社会」の実現に、少しでも貢献できればうれしいですね。
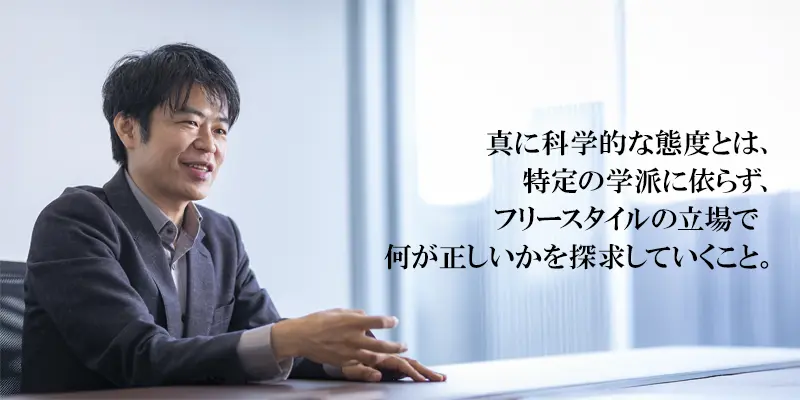
TEXT=瀬戸友子 PHOTO=刑部友康


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ