
企業のなかで育む「Human Co-becoming」(中島隆博氏)
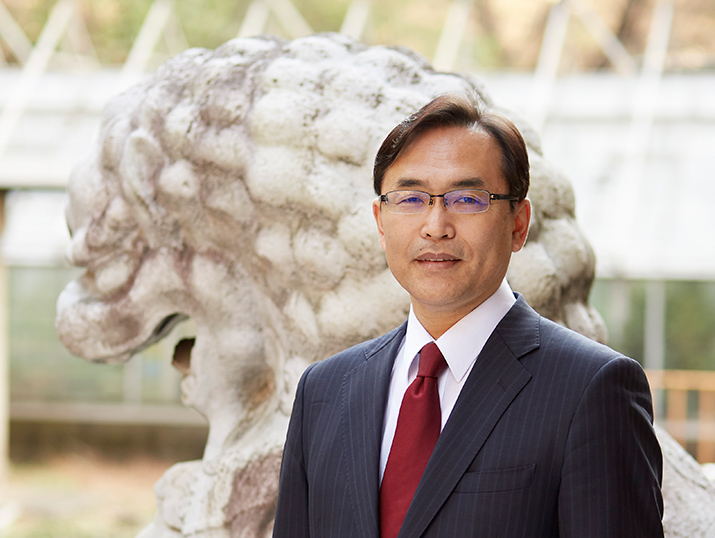 東京大学教授 中島隆博氏
東京大学教授 中島隆博氏
人事の未来をどのように考えるのか。その最初の手掛かりを哲学に求めた。人が集う集合体である企業のなかで、人事には何ができるのか。他者と共に歩む「Human Co-becoming」を提唱する、東京大学東洋文化研究所の所長である中島隆博氏に聞いた。
共に人間的になる
――最初に、先生が提唱されている「Human Co-becoming」について、どのような概念なのか教えてください。
中島 私は、ずっと中国哲学をやってきて、従来の西洋中心の哲学史観をひっくり返したいと思っていました。西洋中心の哲学ゲームのルールを変えていくためには、それを構成しているいくつかの概念を変えないといけません。西洋哲学の根本概念はいくつかあって、その一丁目一番地が「存在」という概念なのですが、ものすごく違和感がありました。存在のなかで最も存在としてふさわしいのが神でしたが、近代では神に代わって人間が中心になり、まるで神のように人間を扱うようになります。
英語で人間を「human-being」と表すことに象徴されるように、人間を存在という概念でつかむと、どうしても人間中心の考え方になってしまいます。しかも、存在は本質とセットで使われます。そうすると本質を明らかにすることでよしとする、本質主義的な思考からも逃れられなくなります。
それに対して、例えば生成becomingから見たらどうかという考えが、もともと中国哲学にはありましたし、現代ヨーロッパの哲学からも出てきました。とりわけ中国哲学では、人間というのは不完全なものだと捉えて、何とか生成して変化していくことでより人間的になっていくことが必要だと考えてきました。しかも、人間が人間的になっていく時に、自力で頑張るのではなくて、誰かと共にとか、何かと共にしか人間的になっていけない。ここに1つの洞察があると思って、「Human Co-becoming」という言葉をつくりました。
――誰かと共に、何かと共にという考え方は、昔からあったのですね。
中島 「Human Co-becoming」は、古代中国の「仁」という概念の翻訳語でもあります。『論語』において孔子が新しい概念として盛んに提案しているものですが、実は、きちんとした定義がありません。弟子たちが孔子に向かって「仁」とは何ですかと問うと、それぞれの弟子に応じた答え方をして全く定義がない。ところが、これはとても新しい人間のつかまえ方でした。
古代中国では、君臣関係というヒエラルキーのなかで人間関係がつくられていましたが、孔子は全く違う人間の関わり方を考えたのです。孔子の周りには若者が集いましたが、見様によっては、国から国を渡り歩く不穏な集団だったかもしれません。しかし、それは何か熱い議論がなされる空間であり、ある種の新しい言説や概念が生まれてくる、発見的な空間でもありました。そこでの人間関係を、範例的に「仁」という言葉で表したのだろうと思います。「仁」は「人」に「二」と表しますが、1人では実現できないものです。当然、誰かとの関係においてしか仁はありえません。
1人で人間的になるのは本当に難しく、共にしかなれません。Human becomingという表現はすでに使われていたので、そこに、私はあえて「Co」をつけて、人間を他者と共に人間的になりゆくものとして捉えれば、全然違う世界が見えてくるのではないかと考えました。
企業での経験が人を変容させて社会を豊かにする
――企業も誰かと共に何かをなす場だと考えれば、企業はHuman Co-becomingを実現する場となりうるのでしょうか。
中島 企業においても、最終的には人間の深い変容を価値としていくことがとても大事になると思っています。人間に本当に大事なことは、その人の経験が深まっていくこと、そして新しい言葉を獲得してそれを定義することです。何でもいいのですが、自分がいろんな知覚を通じて何か物事を経験し、その経験の組織化をいい方向に持っていくことがとても大事です。経験によって、これまでのボキャブラリーとは違うものを、違う構文で話すようになっていく。それが人間にとっての価値であり、一番深いHuman Co-becomingです。そういう価値を実現することが極めて重要です。
この価値は、企業のなかの人間関係によって同時に生じさせないといけません。企業のなかでも、経験を通じて新たな言葉と構文を獲得することで、人間が深く変容していくプロセスを、社員たちと共にやっていく。そこから出てきたアイデアがお客さんに反映されていく。そのような仕組みを生み出すことがとても大事です。このHuman Co-becomingという考え方は、人間の今日的な価値の問題とも深く関わっているのです。
――人との関わりだけでなく、社会や地球との関わりも考えなければならないということでしょうか。
中島 企業も社会を構成している重要なメンバーです。そして、企業はいろいろなインパクトを地球にも与えています。それをしっかりと反省して、自覚できている企業が勢いを持つようになります。消費者は消費という選択によって豊かな人生を送ることを目的としているので、消費者が賢くなればなるほど、しっかりと考えて、自分たちの生きる意味を与えてくれる企業を選ぶようになります。そうではない企業は選ばれません。そういう循環が絶対に生じると思っているので、企業の在り方が変わらないといけません。
社会はマーケットとそれ以外で構成されていますが、実はマーケット以外の部分がかなり大きいので、企業活動はマーケットだけではなく、マーケットの外にも向かっていかなければなりません。マーケットの外は価格でなく、本当の価値が問われます。そこにアクセスする時、人間を深く変容させていくことを価値として認めるような企業活動にならないといけない。これは、企業だけではなく、教育やパブリックセクターでも同じです。人の変容はモノの生産や消費とは全く違うプロセスです。一人ひとりが変容していくことが、私たちの社会が豊かになることにつながります。
豊かさとは望む力が花開くこと
――企業は一人ひとりの変容をどのように支援することが望ましいのでしょうか。
中島 私は、豊かさとは一人ひとりが花開くように繁栄していく在り方だと考えており、それが実現できる社会が望ましいと思っています。その時に誤解してはいけないことは、「人間が有している能力を開発する」という考え方です。能力はできるという次元で人間をつかまえるもので、開発はそのできることを増やそうという発想です。しかし、本当に人間にとって大事なことは、できるという次元ではなく、望むとか、希望するとかの次元です。そういう望む力が花開いていくことが、より大事なのではないでしょうか。それによって、人が深く変容する経験そのものを得ていくのだと思います。
旅をしてメンターに出会うとか、仲間を募って対話をすることで、はじめて変容する瞬間が訪れます。もちろん、どんなに力のあるメンターに出会っても、タイミングやその人との相性が悪ければ無理です。ある種の偶然でもありますが、いいタイミングは必要です。様々な機会を通じてそういったチャンスを準備することが極めて重要で、それは企業も同じです。変容できるチャンスをどれだけ準備して提供できているかが、これからの企業を選ぶ基準となり、企業の死活問題となるくらいに大事なことだと思っています。
――個人に変容を求めることは、タフな個人を強いるようにも聞こえてしまいます。
中島 旅をして動くことは、精神的な辺境に身を置くことで、危険もありますが、人と人とが真に出会うことで、新しい知や新しいチャンスが必ず生まれてきます。それは「タフな個人」ではなく、「弱い連帯」を求めることです。企業に求められるのは、そうした精神的な辺境に向かうリスクをどう低減し、そこでのチャンスをどう生かすかをサポートすることです。たとえば、ある企業が若い人にどんどん新しい問いにチャレンジさせ、育てているとしましょう。そうなれば、自分の能力の開発にとどまらず、他者との「弱い連帯」が十二分に発揮できるその企業に行きたいと思う若者は増えるはずです。うまくいけば、望む力までも身につけられるかもしれないからです。定量的な数字で自分たちの実態を示すだけではなく、その先のもっと質の高い情報を整理して表現できる企業が出てきてほしいと思います。
今は、望んだとしても、それが叶わない人、そこで負ける人を生み出す仕組みになっていて、それを競争といって誤魔化しています。人は単一ではなく、複数の望みを持ちます。1つの望みが果たされなくても、他の望みまで果たされなくなるわけではありません。1つが駄目でも、他のものが実現していけばいい。それが他者との「弱い連帯」のレッスンを通じて、1個実現した、2個実現したと増えていけば、だんだんと望み方が上手になっていきます。企業でも、競争という言葉で望みを断ち切って、望めない人を作り上げていくことはやめた方がいいように思います。
測ることのできる能力は能力の一部で、しかも、そんなに大して重要ではない場合もあります。本当に必要な力は望む力です。その人がどれだけ他者と共に多様な経験をしてきて考えてきたのか、自分の言葉でそれを表現しようと努力してきたのか、それを測ればいいのではないでしょうか。
望む力を育む
――自分が何を望むのかが重要になりそうですが、何が望む力に結びついていくのでしょうか。
中島 望む力も自分でただ頑張るだけでは得られません。人間が社会的な動物であるというのは重要なことで、シェア、共有しているという意識がとても大事になります。人の意識は、自分ではない誰かと共にしか育てられません。だから、その人に頑張れと言うのではなくて、その人の経験が深まるような良いセッティングを、社会や企業が準備することが絶対に大事です。これに尽きます。これが本当の価値を生んでいるので、ここにエネルギーを大きく割くべきです。
自分は見守られていないと思うと、孤独になって変な方向に落ちていきます。いろいろな責めを個人に帰することはやめた方がいい。見守る目があると、人はいい方向に進みます。見守ってくれる目があるということを、一人一人が理解していることが一番大事です。社会でも企業でも学校でも、その人を見守ることによって人は伸びていくという考え方をした方がいいのではないでしょうか。
――人の経験が深まる良いセッティングとは、どのような状況を目指せばいいのでしょうか。
中島 これまでの良さというのは、名詞形で考えがちでした。良さという本質がきっとあると考えてしまうのですが、それは本質主義的な思考の罠なので、違うアプローチが必要です。
良いというのは形容詞で悪くないですが、本当は副詞なのではないかとすら思います。良く生きる、というような名詞的な本質に還元できない副詞的な在り方、人が関与し合ってはじめて生じるような状況、みんながそこにいると非常に居心地がいいし、ぴったりしている、うまくやっている、という感覚を持てる状況です。そうすると人はリラックスできて挑戦ができます。しかも、その心地良さというのは、ただリラックスするというのだけではなくて、そこに大事なことが何かあるということはわかるけれども、そこに近づくためには努力をしないと近づけない。この感覚を持てるかどうかです。
企業であれば、様々なメニューを提供して自分に合ったところで頑張ることができるチャンスをセッティングできるかどうか。これが人事では特に大事なのではないでしょうか。
聞き手・執筆 橋本賢二(研究員)


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

